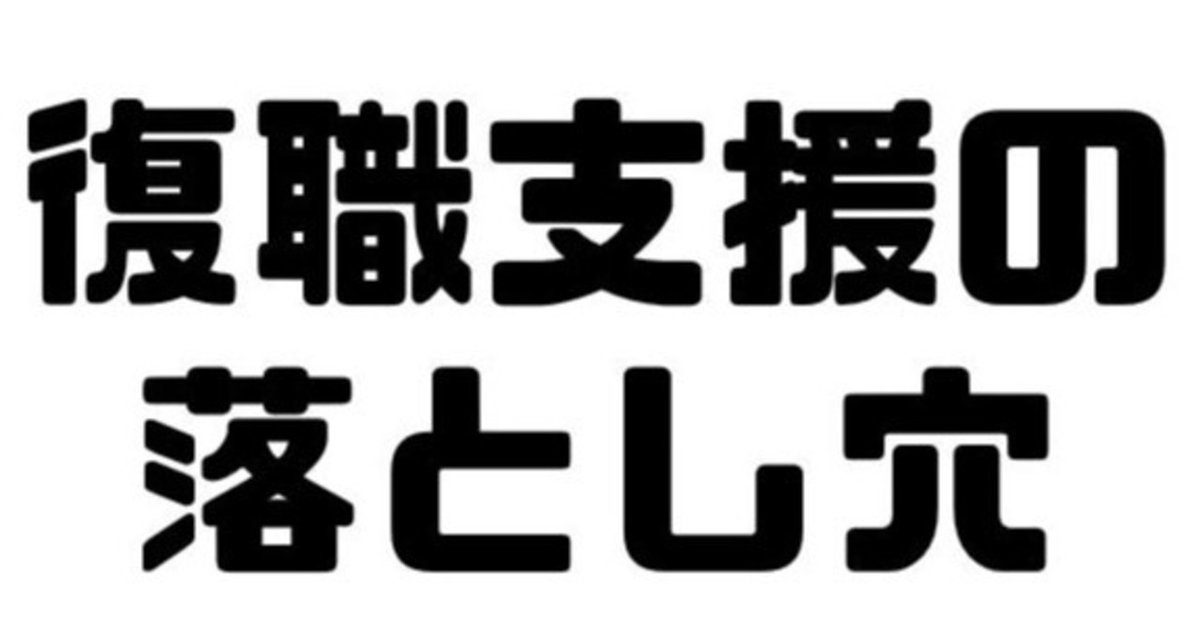
38.復職支援の落とし穴

産業保健活動におけるメンタルヘルス不調者への対応は、とても重要な課題となっていますし、事業所から産業医に対する期待としても大きいと言えます。そして、その中心となるのが、労働者の職場復帰支援です。基本的には、厚生労働省から出された「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(以下、手引き)にその対応の概要は解説されています。しかし、実際にはこの手引きを参照しても復職支援は容易ではありません。本記事では、復職支援に潜む落とし穴をご説明します。
主治医意見通りの落とし穴
主治医から復職が可能という診断書が発行されたとしても、それは就業能力を担保するものではありません。手引きにおいては以下のようなことが示されており、主治医の意見は、あくまで日常生活レベルの判断であり、必ずしも就業レベルの判断ではないと言えます。(「主治医連携の落とし穴」も参照)
主治医による診断は、日所生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見を述べることが重要です。
産業保健職は、主治医の診断書を鵜吞みにすることなく、その他の様々な情報を収集し、適切な判断する必要があり、復職が難しいと判断したときには、堂々とその意見を出す必要があります。
なお、森本氏は著書の中で産業医判断の適格性について、面談の事実や判断根拠となる具体的な事実があるかどうかが重要だと述べています。
復職不可の落とし穴
「産業医は就業を制限する存在?という落とし穴」でも言及していますが、産業医の本質的な役割は、復職を認めるか・拒否するかを判断するような役割ではありません。あくまで判断の主体は企業にあり、産業医は助言する立場です。産業医としての「復職不可」という表現は、言い換えれば、現在の健康状態では求められる労務提供が行えない可能性が高いこと、就労を行うことで健康状態が著しく悪化する(=安全配慮義務違反に関わる)こと、就労を行うことで自他の安全が危ぶまれること(例:運転していて事故で他者を巻き込む)、といったことになります。働き方と健康状態がミスマッチしていることを助言しているだけです。どんな健康状態であっても働ける可能性は常にあり、働き方を変えれば働けるという助言にもなりえます。産業医としての視点は、どういう点に配慮すれば、どのような職場環境にすればその健康状態で働けるのか?というものです。
(参照:「産業医が決定してしまう落とし穴」・「産業医の「復職不可」について考えてみる 〜いわゆる、主治医と産業医の意見が異なる場合〜」)
休職満了の落とし穴
通常では、休職期間中に傷病が回復すれば復職となり、回復せずに休職期間が満了すればそのまま退職となってしまいます。休職期間満了ギリギリで産業医面談をすることもあり、産業医が復職不可と判断すれば、そのまま退職になってしまう可能性もあるため、産業医としても非常に悩ましい判断を迫られることになります。しかし、そもそも休職期間満了は、即座に退職とするものなのでしょうか?これは過去の判例などから、必ずしもそうとは言えません。産業保健法務に詳しい令杜若経営法律事務所の向井蘭氏(弁護士)は、以下のように、休職満了であっても、即座に退職措置とするのではなく、配置可能性を探ることや、短期間の復帰準備時間を提供することが求められることもある、としています。
治癒の基本的な基準は、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したとき」だが、裁判所は、その状態に達しないからといって、直ちに会社が労務の提供の受領を拒絶して良いとは考えてこなかった。かなり前の裁判例も、使用者は、「治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり、かつ、その程度が、今後の完治の見込みや、復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して、解雇を正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証することを要する」としていたし、最高裁は、労働者が職種等を特定せずに労働契約を締結した場合、「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして…配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」として、従前とは異なる業務への配置可能性を探るべきことを述べ、本人からの申し出を前提に、労使双方の事情を踏まえて、休職前と異なる業務への配置可能性を探るべきことを明言した。その後の裁判例の蓄積もあり9)、現在のところ、①休職前の業務に復帰できるか、②その業務に比較的短期間で復帰できるか、③本人が申し出た休職前の業務以外の業務について、労使間で配置の調整ができる場合のいずれかに、復職を認めるべきという判例の考え方(判例法理)が確立してきている。もっとも、労働者側は、あくまで債務の本旨に従った履行を果たす義務があるので、たとえば総合職社員ならそれに見合ったコミュニケーションをとれるなど、その契約の内容に照らして、本来的な業務を遂行できる能力が確認される必要があると述べる判例も出てきている。
休職満了になるような場合においても、復職・就労継続を支援する立場である産業医は、病状の見込みや復帰可能性を検討し、最後まで復職できる道を模索する必要があります。企業側から「産業医が復職不可と言ったから戻れません」と産業医を盾に使われてしまうケースや、労働者側からも、「産業医によって復職を妨害された」と捉えられてしまうケースもあります。産業医としての立場を明確にして復職判断に臨むように注意してください。
職場環境改善なき職場復帰の落とし穴
「人を仕事に適合させるという落とし穴」でも言及している通り、職場側に休職に至った体調悪化の原因がある場合には、人を仕事に適合させるよりも仕事を人に適合させるために、職場環境改善を行う必要があります。例えばパワーハラスメントを行うような上司が原因であった場合には、そのパワーハラスメントの方を解決するべきです。また、長時間に及ぶ残業が原因であれば、その残業の改善がなければ、その労働者の再発可能性が高まるばかりでなく、他にも同じように体調を崩してしまう労働者が発生してしまいます。
以下のツイートも参照ください。
企業のメンタルヘルス対策は、休職した従業員が、原職復帰をすることを繰り返すことで、徐々に進んでいくと思う。休職した従業員が辞めてしまったり、配置転換して復職するばかりだと、メンタルヘルス対策は進みにくい。それは、休職の問題解決に向き合うことをしていないから。
— ガチ産業医🥊🐯🥊HPVワクチン3回接種済・コロナワクチン3回接種済 (@fightingSANGYOI) January 23, 2022
業務起因性の落とし穴
休職の原因の体調不良が、業務に起因していないか、業務上疾病に認定される可能性がないか、という点は常に検討する必要があります。業務上疾病として認定された場合には、休職・退職の取り扱いや、職場環境改善や就業上の配慮事項も大きく変わってきます。そして、多くの労働訴訟で争われるように、業務上の負傷・疾病による療養期間中の解雇制限が労働基準法19条1項に定められていますので、もし後に業務上疾病と認定された場合、休職満了による退職は無効とされます。(例:東芝事件など)(参照:業務上疾病の認定等(厚生労働省))
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
休職支援の落とし穴
産業保健職が行うのは、「復職支援」であって、「休職支援」ではありません。そのため、休職中に産業保健職が支援することには注意点が多く潜んでいます。企業によっては、休職中の支援を産業保健職が担うこともあると思いますが、以下の点を十分に理解した上で対応する必要があります。
①主治医とダブルスタンダードを生んでしまう懸念があること
産業保健職は治療・回復を支援する立場ではありません。休職中は主治医の治療に専念することが重要です。くれぐれも主治医の治療方針を否定することや、産業医の治療を押し付けることはしないようにしましょう。
(参照:「臨床医マインドの落とし穴」「臨床マインドからの脱却」)
②体調を悪化させる懸念があること
休職中というのは言葉通り、治療に専念する期間です。そのため休職中に産業保健職が介入することによって悪化させる懸念がないとは限りません。仕事のことや、体調悪化の原因を思い出させるようなこともあるかもしれません。そもそも企業側の人とやり取りをするのも辛いという方もいるかもしれません。企業によっては、定期面談と称して事業所に来てもらうというやり方をとってところもあるようですが、特に体調が悪い時期に事業所に来させるのは、体調悪化の懸念があるので望ましくないと思います。また、休職中に関与することがリハビリだと言う方もいるかもしれませんが、それは主治医が復職できると判断してから段階での話になろうかと思われます。
(参照:「産業保健活動の侵襲性を考える」
③復職を急かす懸念があること
休職中の方の多くは、「早く復職したい」という焦りの気持ちを大なり小なり持っているでしょう。産業保健職側にその意図がなくとも、休職中に「復職の意欲が出てきましたか」「そろそろ復職できそうでしょうか」という問いかけをすること自体が、復職を急かしてしまう懸念があるでしょう。休職中の関与自体がそのような作用をもたらしかねないことにも留意が必要だと思います。
④支援しすぎの懸念があること
支援という行為自体が、自己保健義務・治療意欲・自律した健康管理を阻害しかねません。産業保健職に言う通りにリハビリをするといった支援は、結局のところ本人のためにならないこともあるでしょう。復職後もずっと支援できるわけではありません。また、産業保健職の言う通りに努力してきたのに復職に失敗した場合には、その責任の矛先を産業保健職に向けられる懸念もあります。復職するかしないか、できるかできないかということも本来は当事者自身の責任で行うべきでしょう(=自己保健義務)。支援しすぎることは、その方が自分の足で立って歩くようになることを阻害しうることを支援者は知らなければなりません。
⑤感情移入の懸念があること
休職中の弱っている労働者をずっと寄り添って支援し続けることは、本人の感情移入しすぎることで労働者側に味方をしすぎた判断をする懸念があります(患者への感情移入に近い)。これは、疾病性に引っ張られないことや、あくまで独立・公平な立場で「復職支援」を行う必要があります。また、労働者側も、自分が弱っている時からずっと寄り添って支援してくれたのにも関わらず、突然冷たいことを言われたとショックを受ける懸念もあります。
もちろん、これらのデメリットを理解し、上司や人事担当者と役割分担をした上で、産業保健職が休職中に連絡をとることもあり得るでしょう(さらには産業医ではなく、看護職が連絡をとるという役割分担もありえるでしょう)。特に、休職中の労働者が上司や人事と不信感を抱いている場合です。しかし、役割や目的を整理せずに、なんとなく休職中に関与するということは避けた方が望ましいと思います(上司や人事から、なんとなく仕事を振られるというケースも多々あるようです)。
追記

このアンケートはあくまで参考程度ではありますが、休職中に連絡を取りたい方ばかりではない、ということを知っておくことはとても重要だと思います。企業側のルールとして定期的な連絡(メール、電話、面談)をとることは必要でしょうし、連絡を取りたい方もいる一方で、連絡を取ること自体がマイナスにも作用してしまう可能性があります。人事・上司側からの要望で、産業保健職が連絡をとる、という仕組みになっている企業もあろうかと思いますが、関わりすぎにはリスクもありますのでご注意ください。個人的には連絡は最低限にしたい、ということもありますし、少なくとも復帰が見え始めるまでは、文書のやり取り程度でいいのではないかと思っています。
支援しすぎの落とし穴
復職して就労を継続することを支援することが産業保健職の役割ですが、その支援の範囲にはご注意ください。あれもこれも手助けすることではなく、状況や道筋の整理が大切です。例えば、本人の気持ちを代弁しすぎたり、付き添いで受診したり、本人の気持ちに沿い過ぎるような産業医意見を出すことは、ときに支援しすぎと言えるかもしれません。前述のように休職中の支援もそれに当たるかもしれません。もちろん、体調の状況や企業文化などによって必要な支援の範囲も大きくなりますが、支援しすぎることは、本人の主体性を損なったり、産業保健職への依存を生んだり、疾病利得に繋がる可能性があることも常に念頭に置く必要があります。体調を回復し、労務提供できるように健康管理を行うこと、職場の様々なストレスに対応できるようになること(レジリエンスを高める・ストレスコーピングを身に着けるなど)は、自己保健義務であり本人の責任として行わなければならないものだと思います(参照:「疾病利得の落とし穴」)。
働くことは健康に悪い?の落とし穴
休職から職場に復帰することは、体調に悪影響なのでしょうか?たしかに職場には様々な悪化要因が潜んでいます。例えば、残業や様々なプレッシャー(業務指示、成果・ノルマ)、人間関係、ハラスメントなどです。しかし一方で、働くことには体調によい効果もあります。例えば、企業に対する帰属感、社会貢献感、経済的安定、雇用安定、生活リズム、適度な緊張、自己保健義務・治療意欲の醸成といったものです。人によって様々な価値観がありますし、家庭環境も様々です。一人一人の状況に合わせて復職判断を行う必要がありますので、就労することが必ずしも体調に悪いと誤解しないようにご注意ください。
判断基準なき復職支援
手引きには職場復帰可否の判断基準の例として以下の事項が示されています。
<判断基準の例>
・労働者が十分な意欲を示している
・通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる
・決まった勤務日、時間に就労が継続して可能である
・業務に必要な作業ができる
・作業による疲労が翌日までに十分回復する
・適切な睡眠覚醒リズムが整っている昼間に眠気がない
・業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している など
職場復帰後に、体調が悪化し、再度休職に至ることは企業にとっても労働者にとっても不幸です。そして、病気を繰り返すごとに病気が重くなったり、再発しやすくなることが報告*されていますので、休職を繰り返させないことも重要です。そのため、職場復帰を検討する際には、このような職場復帰の判断基準を設け、再休職のリスクを下げることが重要です。このような判断基準がなければ、労働者側としても職場復帰までの道のりが不明確になり、混乱してしまう懸念もあります。当たり前かもしれませんが、職場復帰の判断基準を設定し、関係者で共有することが非常に重要です。
判断基準に頼りすぎの落とし穴
このような判断基準を設けても、体調が再度悪化するリスクはゼロにならないことに注意が必要です。職場復帰を検討する際に、上司や人事担当者などから、「本当に大丈夫なんですか?」「絶対に再発しませんよね」などの声をいただくことがありますが、結局のところ最後には、戻ってみないと分からないと言えます。判断基準に頼りすぎてゼロリスクを求めてしまうと、復職判断のハードルが上がってしまいますし、労働者へのプレッシャーが強くなりすぎてしまう懸念がありますのでご注意ください。
例えば、判断基準の中の「業務に必要な作業ができる」(業務遂行能力)があり、職場復帰可否を判断する際には、業務遂行能力を評価する必要があります。しかし、業務遂行能力は、完全には評価することはできません。復職に向けて、模擬的な作業を行ったり、緊張度合いの高い作業を行ったり、リワークを行うことで、業務遂行能力を評価しますが、結局のところ最後は、「やってみないと分からない」という限界も知っておく必要があります。
*Kessing.2008, Kessing et al 2004
こちらもご参照ください。
疾病性の落とし穴
前述の職場復帰可否の判断基準の例のように、復職時に判断することは働けるかどうかであり事例性に関わる部分です。診断名や内服薬などの疾病性に関わる部分はさほど重要ではありません。しかし、未だに精神疾患に対する誤解や、通院・服薬している者は復職させられないといった誤解を持っている方は多いのが現状です。職場復帰を支援する関係者間において、疾病性に引っ張られないような配慮や、誤解を持たないようにする必要があります。
参考になる文献
科学的根拠に基づく「産業保健における復職ガイダンス 2017」Ver.4.1 20180523 日本産業衛生学会関東地方会
向井蘭, 森本英樹, 三柴丈典. 産業保健と法~産業保健を支援する法律論~ 4 産業保健に貢献できる就業規則のあり方
田中建一, 三柴丈典. 5 神奈川 SR 経営労務センター事件の教訓
その他、参考になるサイトはこちらにまとめています
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

