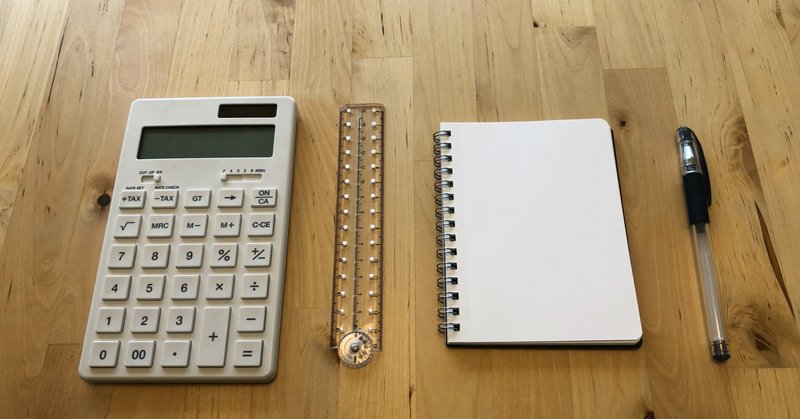
評価において大切なこと(その4)
今回は、評価の中でも特に大切な「目標管理」について考えていきます。
皆さんは、「目標管理とは何か?」と訊かれたら、どのように答えますか?
業績管理なら業績を管理すること、
情報管理なら情報を管理すること、
品質管理なら品質を管理すること、
在庫管理なら在庫を管理すること、
納期管理なら納期を管理すること、
なので
目標管理は「目標を管理すること」と考えがちですが、これは大きな間違いです。
目標管理のことを”MBO”と呼んでいる会社もあると思います。
これは、有名なドラッカーが提唱した考え方、
"Management by Objectives"の頭文字を取ったものなのです。
by とあるので、日本語に翻訳すると「目標による管理」ということになります。これを目標管理と訳してしまっていることが誤解の始まりです。
さらに、
"Management by Objectives" には続きがあるのです。
ドラッカーは
"Management by Objectives and Self-control" と残しています。
彼が言いたかったのは、「目標を管理する」でも「目標による管理」でもなく、「目標と自律によるマネジメント」なのです。
すなわち、
自ら目標を立て、その目標に向かって自律的に取り組むことで、人が人らしく働き、働く喜びと成果の両方を獲得する
ということです。
ドラッカーは著書”Management”において、次のようにも述べています。
「哲学という言葉を安易に使いたくはない。できればまったく使いたくない。大げさである。
しかし、目標と自立によるマネジメントこそ、マネジメントの哲学たるものである。」
これくらい、"Management by Objectives and Self-control" は崇高で、マネジメントにとって重要な課題なのです。
にもかかわらず、日本企業の多くでは「目標管理=評価のためのツール」と誤解され、本来の目的が果たされていないことは残念でなりません。
本稿をお読みいただいている管理者やリーダー、経営者や人事部門の方には、これをきっかけに今一度再考いただけると嬉しく思います。
では、目標管理を真の意味で活用するにはどうしたらよいでしょうか?
まずは、目標の設定です。
目標設定にあたっては、本人がワクワクしながら取り組める課題であり、達成することにより部門や会社の業績に結びつくものをテーマとして選び、本人の能力よりやや高いレベルのゴールを設定することが望ましいと言えます。
ここで、ゴールとは、「いつまでに、どのレベルまで」というように、機嫌と到達レベルが明らかになっていることが大切です。
次に、業務の遂行です。
業務遂行にあたっては、本人の自律的・主体的な取り組みに委ねることが大切です。トライ&エラーをある程度許容することも大切です。管理者やリーダーには、細かく指示するのではなく、大きな方向性の逸脱がないか、許容範囲を超えるルールや社会規範からの逸脱がないかなどを観察しつつ、必要に応じて本人をサポートするという関わり方が求められます。
最後に、評価です。
評価にあたっては、本人が自分自身の取り組み方や成果について振り返り、管理者やリーダーと確認し、次期の目標や取り組み方の設定について話し合うことが大切です。
そもそも目標管理は評価のためのツールではなく業務マネジメントのためのツールなので、「振り返りと次期に向けての話し合い」が重要です。評価の点数はその副産物くらいに考えるべきでしょう。
最も大切なのは、評価に関する面談や話し合いを通じて、「次は頑張ろう」とか「次も頑張ろう」というモードを共有することです。
このように、目標管理の仕組みを使って業務そのものを適切にマネジメントすることは非常に重要な仕事なのです。
評価において大切なこと、
その4は「目標管理の意味と目的を正しく理解して取り組む」です。
いかがでしたでしょうか?
次回は「フィードバック」について書いてみたいと思います。
株式会社F&Lアソシエイツ
代表取締役 大竹哲郎
https://www.fl-a.co.jp/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
