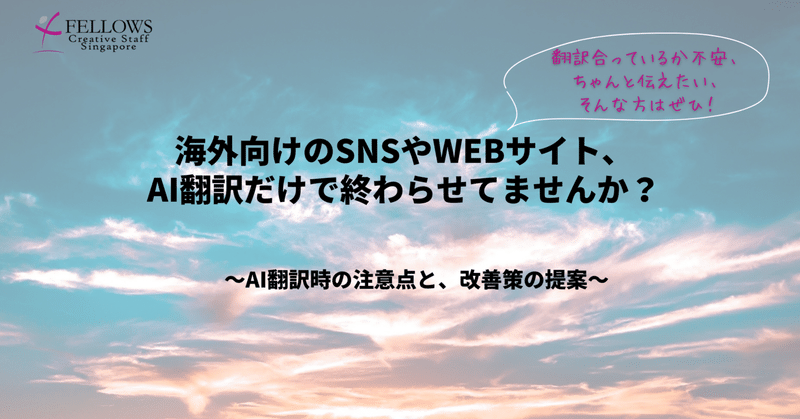
【AI翻訳の注意点と改善策について】シンガポール向けコンテンツはAI翻訳するだけでいいのだろうか
【私たちについて】
クリエイター専門のマネジメントを提供している「株式会社フェローズ」の初の海外拠点として設立された、Fellows Creative Staff Singapore(フェローズシンガポール)。
私たちは、「一者一社と熱くむきあう」ことを理念に、現地クリエイターやエキスパートと、海外進出を目指す日本企業の出会いを実現します。
東南アジアで構築してきた独自のネットワークを活用し、東南アジアのクリエイターや、各業界の専門性を持ったエキスパートを紹介しています。
また、シンガポールの優秀な人材、制作クリエイター探し、東南アジアへ進出といった「ご縁」をつないでほしいという相談は、弊社TwitterのDM、HPから受け付けています✉
弊社を活用して、シンガポールのクリエイターや人材を探したいという方は、こちらをご覧ください!
近年、シンガポール、タイ、マレーシアなど、東南アジアに進出していく企業が多い傾向にあります。
その時に、例えば、自社のWebサイトを多言語化したり、シンガポールの人に向けてSNSで発信したりと、新しいマーケティング施策をしていると思います。
その際は、ほとんどの方はAI翻訳を活用しているのではないかと思います。
AI翻訳はかなり精度が高く、正確に翻訳することができますよね。
しかし、AI翻訳の活用しても伝えたいことが正確に伝わらないこともあるので、今回はそれについて触れ、対応策についても紹介していきます。
1.AI翻訳だけで終わってませんか?
もともと、日本でのマーケティングに活用していたWebサイト、SNS、アプリ、商品、それらを例えばシンガポールやタイに向けてのコンテンツに翻訳して活用することはよくありますよね。
その際、DeepL等のAI翻訳アプリが大活躍します。英語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語に翻訳したら、そのまま現地の人に自社のサービスや商品について知ってもらうことができます。
しかし、AI翻訳を活用して、そのまま発信してしまっていいのでしょうか。
実際、AI翻訳で「正しく伝わっているのかな、変な誤解を招いていないかな」と不安に思ってる方もいるのではないでしょうか。
英語なら分かるのである程度チェックできるけど、タイ語、マレーシア語、ベトナム語となると、翻訳したものが正しいか確認のしようがないですよね。
まさに、ここが問題だと考える部分なのですが、翻訳した結果が本当に正しく伝わるのか、変な誤解を招くことはないかを改めて考えてほしいと思います。
AI翻訳による翻訳結果が、正しく伝わらなかったり、変な誤解を招いたりするとどうなるでしょうか。
実際に合った翻訳ミスの事例を2つ紹介します。
①スペイン語の誤訳による粉ミルク460万缶の回収
アメリカで起きた、スペイン語の誤訳です。
粉ミルク製造会社のミード・ジョンソン社は、粉ミルクの作り方を書いたスペイン語の製品ラベルに、誤表記があることがわかり、約460万缶を回収しました。
スペイン語の誤訳により、正確に伝わらない粉ミルクの作り方がラベルに記載され、赤ちゃんの健康被害につながる可能性があったからです。
この誤訳による健康被害はなかったそうですが、460万缶を製造し、流通させ、その後に回収したコストを考えると、莫大な損失です。
会社としての信用も落ち、ここからブランディングを改めて行うことになると、追加費用が多くかかることが想定できます。
引用元:https://www.tahoedailytribune.com/news/4-6-million-cans-of-formula-recalled-over-spanish-label-error/#:~:text=WASHINGTON%20(AP)%20%E2%80%93%20Mead%20Johnson,health%20problems%20and%20even%20death]
②広告の誤訳で1000万ドルのリブランディング
香港での広告キャッチコピーにおける誤訳です。
香港上海銀行が、「Assume nothing(先入観を持つな)」というキャッチコピーでブランディングを行っており、多言語展開するときに誤訳が発生し、「Do nothing(何もするな)」という意味で各国の言語に翻訳されたまま、発信。
結果的にリブランディングで、1000万ドルがかかってしまいました。
伝えたい内容を、正確に伝えられなかった事例です。
引用元:https://www.ft.com/content/77b58214-f6e3-11dd-8a1f-0000779fd2ac
③キャンペーンの誤訳で中国進出に悪影響
KFCは北京市場進出を検討し、「Finger Lickin’ Good」キャンペーンを中国に導入する計画を立てます。
しかし、中国語に適切に翻訳されず、「指をしゃぶるほどおいしい」というニュアンスが、「Eat Your Fingers Off(指を食べてしまえ)」という意味になってしまいました。
さらに、中国市場への適切な調査を怠っており、元のメッセージが適切に翻訳されていたとしても、意図した結果は得られなかった可能性があることがわかりました。中国の文化では、指をしゃぶるほどおいしい、という感覚がないからです。
引用元:https://www.mashed.com/747566/the-hilarious-translation-mistake-kfc-china-made-with-its-slogan/
要するに、
元の言語を翻訳した後、現地の方に、正確に伝わるようにすることが大切で、もし誤訳が発生すると、自社が金銭面、ブランディング面などで損害を被ることになったり、消費者に損害を与えたりすることになりかねないということです。
2.カギは現地クリエイターによる校正
では、そういった誤訳が起きず、伝えたい内容を、正確に伝えるためにはどうしたらいいでしょうか。
このようなとき、現地クリエイターによる確認・校正(リライト)がカギになります。
現地クリエイターにより、日本語から翻訳されたものが、その意図通りの内容になっているか、現地の文化や消費者の視点も踏まえて確認し、誤訳を招かない文に校正することができます。
先ほどの事例を用いて、現地クリエイターに校正(リライト)してもらうとどうなったか、考えてみましょう。
※1つの例として紹介しているので、ご参考までに。
①スペイン語の誤訳による粉ミルク460万缶の回収の場合の対策
もし、製造する前に、粉ミルクの作り方が正しく翻訳されていることをスペイン人クリエイターが確認して校正していれば、粉ミルクを多くの方に届けられたでしょう。それにより、回収コストもかからなかったでしょう。
②「広告の誤訳で1000万ドルのリブランディング」の場合の対策
この事例は多くの言語で展開するため、それを各現地クリエイターに校正してもらうのはかなりのコストがかかります。
この事例で校正してもらうか、してもらわないかは、担当者の判断次第ですが、校正するという選択は、リブランディングに1000万ドル払うよりも、安く済んだのは明らかです。
③「キャンペーンの誤訳で中国進出に悪影響」の場合のクリエイターによる校正
この事例は、翻訳の前に、中国の文化や市場を調査しておくことが必要でした。
中国の方に、より多くのフライドチキンを楽しんでもらうために、アメリカと同じ伝え方でいいのか、それとも中国の方向けの伝え方にした方がいいのか、中国のマーケターなどと協力して、事前に調査しておくことで対策ができたかと思います。
その上で中国で効果的なキャッチコピー、キャンペーンになっているか、中国の人材、ライターなどに校正をしてもらうとベストです。
どうでしたか?
現地クリエイターによる校正で、誤訳を招きかねない文を校正し、正しく伝わる内容で伝えることの大切さがわかったかと思います。
しかし、現地クリエイターによる校正がカギだといったのには、もう1つ理由があります。
現地クリエイターによる校正がカギとなる理由②
ただ校正するだけでなく、現地の消費者、文化を踏まえたうえで、彼らに響き、行動を促すためには、どう伝えたらいいかという部分も考慮した内容に修正できること。
つまり、もともと伝えたかった内容を他の言語で正確に伝えるだけでなく、より現地でのマーケティングとして効果的な発信が可能になるということです。(KFCの例から考えると納得できるかと思います。)
このように、現地の消費者や文化も考慮して伝えていくことを、トランスクリエイションといいます。
この記事では、日本からシンガポールへ、はたまた日本から他国にサービスを展開するときに、大切な考え方として、詳しく書いています。ぜひご覧ください。
では、実際に現地クリエイターに校正してもらうとしたら、何をする必要があるでしょうか。
これから説明していきます。
3.現地クリエイターによる校正をしてもらうには
では、現地クリエイターに校正してもらうには、どうしたらいいでしょうか。
2パターンあると思います。
1.すでにある外国語版のページ等を校正してもらう
2.日本語版を参考に、新しく外国語版ページを一緒に作る(翻訳と言ってもいいですね)
ただどちらのパターンにせよ、やるべきことは細かいことを省くと、おおまかに以下の事かと思います。
①校正(翻訳)の目的を明確にし、校正(翻訳)依頼の準備
②人材もしくはサービスを選定し、連絡をとって見積もりをする
③校正(翻訳)依頼し、作業スタート
④進捗確認と修正を繰り返したのち、納品してもらう
校正、翻訳依頼するにしても意外とやることが多いですよね。
また、適切な人材を見つけること、その人材としっかりとコミュニケーションをとることが大切になります。
ただ、現地クリエイターによる校正を行うか行わないかで、かなり変わります。
ぜひ、現地のクリエイターに校正してもらい、伝えたい内容を現地の消費者に正確に伝え、かつ彼らに響き、行動を促すように伝えていきましょう!
「ここで関連記事2つ」
①弊社による海外クリエイターによる翻訳、校正の具体的なサービス内容をこちらで紹介しています。
ぜひご覧ください。
②翻訳や校正のようなことを行っている、シンガポールのデザイナーの方にインタビューをしたので、ぜひこちらもご覧ください。
彼女は、日本企業のシンガポールでのマーケティング支援をしており、そういった人材を探しているという方は読んで損はないでしょう。(笑)
4.フェローズシンガポールを活用して探すのも1つ
もしこれから、
「自社のWebサイトを外国語に翻訳するために、現地クリエイターにお願いしたい。」
「自社の英語版Webサイトを現地クリエイターに校正してもらいたい。」
「現地の消費者に伝わるよう、SNSを運用したいが、できる人がいない。」
ただ、
・そもそもどうしたらいいの?
・人材を見つけるのにてこずっている。
・コミュニケーションがしっかりとれるかわからない。
このように思っている方は、ぜひフェローズシンガポールを活用して、現地クリエイターを探し、校正や翻訳してもらうのも1つの手段です。
もちろん、マーケティング支援会社や翻訳会社なども調べたうえで、フェローズシンガポールを1つの候補としつつ、しっかり比較検討をしたうえで選定してもらえればと思います。
「弊社による、現地クリエイターの紹介&校正について」
フェローズシンガポールでは、シンガポールをはじめ、東南アジアのクリエイターを日本企業に紹介しているのですが、イメージとしては、先ほど挙げた②③④をお手伝いさせていただく形です。
打合せをもとに、適切な人材を選定し、提案。その後、ディレクションからマネジメントまで一貫して行い、納品します。
これは1つの例ですが、お客様の希望に合わせた形で柔軟に対応していきます。
例えば!!
|パターンA
「マーケティング支援会社に頼むほどではない、翻訳結果のチェックのみをしてほしいというような小規模のプロジェクト」の場合。
弊社との打ち合わせ後、弊社が見つけた現地クリエイターと直接つながってもらい、話し合いを重ねた上で、柔軟にプロジェクトを進めていけると思います。
その際、弊社もプロジェクトが円滑に進むよう、コミュニケーションなどサポートさせていただくことも可能です。
|パターンB
「人材を見つけることだけしてほしい。その後のタイ語版Webサイト制作プロジェクトは自社でしたい。」場合。
適切な現地クリエイターの人選と契約の部分のみをわたしたちが行い、その後の実際のプロジェクトの進行は、現地クリエイターと話し合いを行いつつ、進めていってもらえます。
このように、フェローズシンガポールを活用し、校正や翻訳を行える人材とつながり、お客様に合う形でそのプロジェクトを進めていけるお手伝いが出来たらと考えています!
活用してみたい、話だけでも聞いてみたいという場合は、気軽にお問い合わせください!
弊社のTwitterや、下のサイトからもお問い合わせ可能です!
校正と翻訳をフェローズシンガポールを活用して行っていきたいという方に、具体的にイメージしてもらいやすいように、弊社活用時の詳細を資料にしました。こちらもご覧ください!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
