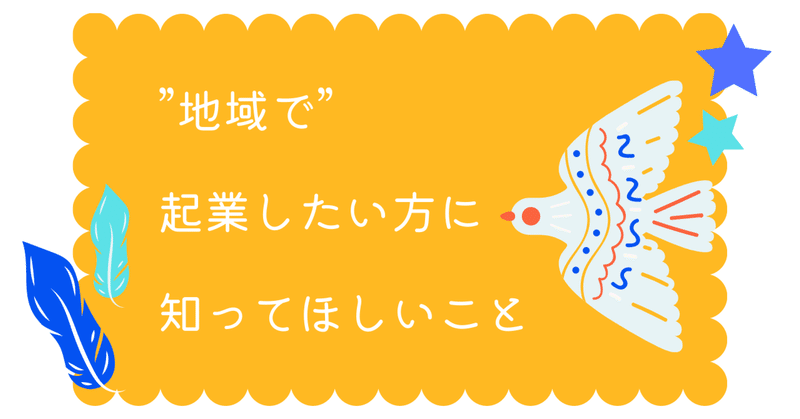
地域で起業したい!
こんにちは!えぽっくの若松です!
”働く” をアップデートするえぽっくでは、地域で起業したい!という方のサポートもしています!今日は地域で起業することについて、僕が思うことを書いていきたいと思います!気になった方はぜひ読んでみてくださいね。
■“地域で”起業する人ってどんな人?
まず、『起業する人』と聞いて、どんな人をイメージしますか?『志が高い人』と思う方もいるでしょうし、『野心家な人』と思う方もいるかもしれません。
では、『 “地域で” 起業する人』と聞いて、どんな人をイメージしますか?
僕の経験によれば、組織で3~5年程度働いて、退職を機に地域へ移住、起業、という方もいれば、家族ができたタイミングで移住、起業する方も結構います。『あまり年を重ねてからだと移住したいと思った時にハードルがあがってしまいそう(守りが強くなって挑戦がこわくなりそう)』と、30代前半くらいで決意して移住、起業する方もいる一方で、20~30年という長いキャリアを積んだ上で、新たなチャレンジをするために起業するという方も、もちろんいます。
いずれも都会で働いてきた方が多いですが、こうして考えてみると、実にさまざまな方がいますよね。大きく分けると、
①それまでの経験を糧に、新しいことに挑戦したいから新天地で起業する
②結婚などを機に自分たちがどう生きていきたいかを考えるきっかけになり、ライフステージが変わる段階で移住も含めて起業する
こんな感じです。
上記の方々に共通していえることは、『バリバリ働いて会社を大きくするぞ!』という野心家のようなイメージはあまりなく、暮らすことと働くことのバランスを取りたい人が多いことです。自然が多い環境など、『住み心地の良いところで暮らしながら働きたい』と考えられている方が多い印象です。
■その事業、お客さんの見込みは?
地域で起業する方の多くは、起業そのものが初めてです。そういった方々と接していてよく思うのは、『(起業した事業に)お客さんが本当にいるかどうか考えられているかな?』ということです。
リサーチが足らず事業が上手くいかないというケースは、起業に際してありがちなことですが、地域性という観点を入れて考えておいたほうが良いことの例を挙げます。
たとえば東京23区の人口は約968万人、面積は約627.6 km²だそうです。茨城県で人口が多い上位3市(水戸市、つくば市、日立市)の人口の合計は約68万人、面積の合計は約726.7 km²です。東京23区に比べ茨城県内3市の広さは1.15倍とあまり変わりませんが、内在する人口は東京23区の0.07倍です。
日本一人口の多い東京と比べるとわかりやすくインパクトもありますが、つまり何が言いたいかというと、地域になった途端、思った以上に商圏が小さいことに気づくと思います。
商圏という規模感、市場、地域の方の価値観…場所が変わればさまざまなことが変わります。たとえば、『人材紹介サービスを利用して、毎月人材採用に100万円かけることができる企業がどれくらいあるのか?』と考えたときに、東京ならばたくさんあるのかもしれませんが、地域で活躍する規模の小さな企業だと、ハローワークや無料で掲載できるリクルートサイトの利用が主流だったりします。
またよくあるのが、『まだ誰もやっていないサービス』を展開するのは良いのですが、『どこにもニーズがないから誰もやっていない』、『ニーズがなかったので既に撤退していた』というパターンも案外多いです。ニッチなサービスであればあるほど、地域ではより成り立ちにくいことも多々あります。商圏などを都会での経験や感覚だけで捉えるのは賢明ではありませんので、具体的にどういった事業で起業するか、既に考えがある方であっても、今一度多角的にリサーチされることをおすすめします。
逆に、地域での起業が上手くいっているなと僕が思う人は、集客の見込みがきちんとあって、その方法がきちんと確立されている人です。
たとえば過去記事にも書いていますが、やはり地域で活動するとなると人間関係の構築はとても重要なので、人間関係構築能力が高い人は、自分の商材がその地域で売れるかどうかという市場調査を、自然とできているんじゃないかと思います。僕が見る限り、営業経験がある方はこの点で強みがあるような気がしていて、お客さんと良好な人間関係をつくるのは営業の大事な仕事の一つなので、その辺りが上手な方が多い印象です。
営業経験があれば良い、というわけではもちろんなくて、お客さんと良い人間関係を作り、お客さんのニーズに合った喜ばれる物なりサービスを提供する、ということは、どんな事業であっても当然必要なことです(ちなみに僕も、会社員時代に営業職の経験はありません(笑))。
やりたいことが明確にあって起業したいという志の高い方はとくに、サービスを作り込んでしまうこともあるかと思います。それは素晴らしいことでもありますが、先走ってサービスを作り込んでしまうその前に、本当にそのサービスで集客を見込めるかどうかを吟味することも大事だと思います。そのためにも、事前のリサーチはとても重要です。
僕の場合でいうと、たとえば『就活』がテーマのイベントを開催するとき、どういった切り口で開催すれば人が集まるのか、ということをいつも意識していました。多くのイベントを開催する中でアンテナを張っていると、『女性のキャリアについて知りたい』というニーズが高いことがわかってきました。
そこで、入社して間もない方、産休を経て仕事に復帰した方、役職に就かれている方など、さまざまなライフステージにいる企業に勤める女性社員の方をお招きして座談会を開催したところ、これがとても盛況で、圧倒的に集客が上手くいきました。
イベントをいくつも作りながら、どういうテーマがいいのか、PRの文言も含め集客するためにどのような呼びかけをすればいいのかなどを、事業をやりながらリサーチし、勘所を掴んでいった良い事例だと思います。
きっちりとサービスを作り込む前に、自分が展開しようとしているサービスに対して本当にお客さんがいるのかどうかを確認し、集客できる環境や関係性を作れているか、作っていけるかどうかも、とても大事なポイントだと思います。
※専門用語で言うとPMF(プロダクト・マーケット・フィット)というのがとても大事です。参考:PMF(プロダクトマーケットフィット)とは?
■地域ならではの ”共通の財産” を使うとき
地域でビジネスをするときに、何かしらの地域資源を利用、活用することがあります。どういうことかというと、たとえば海、川、山…など、その地域の自然を利用する、などです。
細かいことをいえば個人所有の場合もありますが、基本的に自然は個人の所有物ではなく共通の財産です。その共通の財産を使うわかりやすい例が、アウトドア。『景色、眺望』という形で海を利用してカフェを開く、山でトレッキングツアーをする、などは、地域資源を利用したわかりやすいビジネスですよね。
共通の財産であれば借り入れたりするものでもありませんので、コストがかからないという利点がある一方で、このような地域資源には、管理する団体や自治会など、当然さまざまな人が関わっています。
自分の事業のために共通の財産である自然を、開発のために壊してしまうのはもっての外ですが、管理団体や地域住民、各方面の関係者と信頼関係を作り、理解を得ながら進めていかないと、多くの方が関わっている中での事業というのは上手くいきません。
特に地域外から来た方に対して警戒心がある方も少なからずいるので、『今まで自分たちが守ってきたものを壊そうとしているんじゃないか?』と誤解をされてしまうこともあります。ですので、そこはしっかりと目的を伝え、その地域にとって良いこと、喜ばれることをやろうとしていることを理解していただく必要があります。
起業すると、当初の想定と違うことが起こったり、自分がやろうとしていることがなかなか理解されなかったり、やってみたけれどお客さんがつかなかったりと…ネガティブなことも時には起こります。そんなときには、多面的な思考を持つことが、とても大事なことだと思います。
『なんで上手くいかないんだろう…』と落ち込むこともあるかもしれませんが、たとえ地域側の古い考え方だとしても、『この地域ではこういうことを大切にしているんだ』とか、『こういうバックボーンに生きてきたから、こういう価値観が根付いているんだ』のように、リフレーミング(物事を見る枠組み(フレーム)を変えて別の視点で捉え、ポジティブに解釈できる状態になること)ができれば、地域の在り方に対して納得できることも増えて、道は拓けていくと思います。
いかがでしたか?地域で起業するといろんなことが起こると思いますが、僕たちのようなサポーターも地域にはいますし、前向きに捉えていたら協力してくれる人たちとの関係ができていくと思いますので、地域で起業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
■関連記事もぜひ!
茨城県北起業型地域おこし協力隊のサポートをしています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
