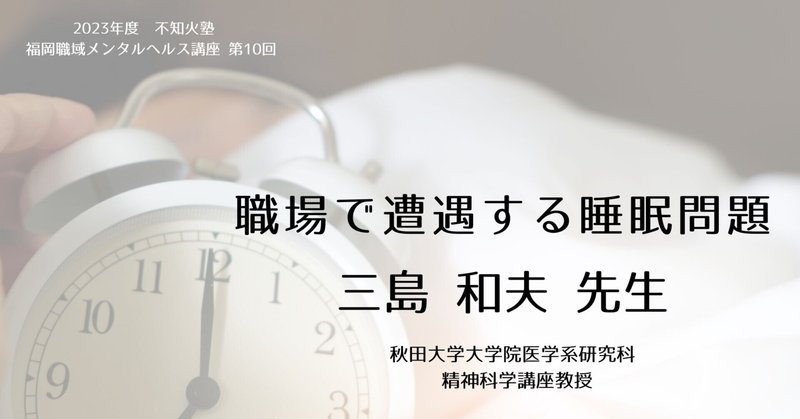
【睡眠不足が及ぼす影響】あなたの睡眠時間、足りていますか?
自分の睡眠時間に満足していますか?
おそらくNOと答える方が多いでしょう。週末に『寝だめ』をしている方もいるのではないでしょうか。
私もその一人です。『寝だめ』やシフト勤務による睡眠時間の変化は身体に影響を及ぼすことが判明しています。
不知火塾 第10回目は、秋田大学大学院医学系研究科 精神科学教授 三島 和夫先生による「職場で遭遇する睡眠問題」がテーマでした。
厚生労働省による令和5年版過労死等防止対策白書では、「睡眠」というキーワードがなんと105回も登場したそうです。
同書によると、多くの就業者に、理想と実際の睡眠時間にギャップが生じており、それが大きいほど抑うつ傾向が強くみられるとのこと。
睡眠時間の差が及ぼす影響
三島先生は、長時間労働の結果として短時間睡眠が発生しているだけではなく、メンタルヘルスの悪化が先にあり、その結果、短時間睡眠が起こる可能性を前置きされたうえで、睡眠不足の問題についてお話されます。
成人の約10%は慢性不眠を抱えているとおっしゃいました。
睡眠不足になると、怒りを抑える脳機能が弱まるそう。
わずか数日の睡眠不足においても、ネガティブな感情刺激に対する反応が強まり、抑うつ気分や不安感が高まると説明されます。
◆内的脱同調による気分変動
睡眠・社会リズムが乱れると、内的脱同調が生じるとのこと。
● 内的脱同調
:睡眠リズムとさまざまな生理機能リズム(深部体温やメラトニン・コルチゾール分泌など)の相互の調和が乱れること。
内的脱同調が大きいほど、抑うつが強まることが判明しており、睡眠・社会リズムが崩れると高確率で抑うつが出現することを指摘されます。
健康な人でも内的脱同調によって容易に気分変動が生じるという実験結果も示されました。
◆社会的ジェットラグ(社会的時差ぼけ)
平日と休日の睡眠中央時刻の差を算出するとおよその社会的ジェットラグが算出されるそうです。
● 社会的ジェットラグ
個人の生活スケジュールや社会的義務と、生体内時計や自然な生理的リズムとの不一致。日常生活の中で週末や休暇などに、平日とは異なる睡眠・覚醒スケジュールを持つことにより引き起こされる。
例えば、その差が4.5時間あるとすると、毎週末、時差が4.5時間ある中央アジアと日本を往来しているほどの負荷が心身へかかることに。
社会的ジェットラグ(社会的時差ぼけ)は、内的脱同調が引き起こされる代表的な例であり、このような乱れは気分障害や概日リズム睡眠・覚醒障害など、多くの疾患でも生じるそう。
週末の『寝だめ』でもある種の脆弱性を持っている人は臨床的に無視できない程度の抑うつ傾向が出てくるとおっしゃいます。
私自身も、病棟での夜勤で睡眠リズムの乱れを肌身をもって感じており、どうしても『寝だめ』をしてしまう傾向にあります。
振り返ると確かに、睡眠不足の時は自分でもイライラしてしまったり、落ち込んでしまったりすることも多く、腑に落ちるお話でした。
自覚できない睡眠不足
生物時計によって自然な眠気が出てくる時間帯は決定されているとのこと。
● 生物時計(生体リズム)
:毎日ほぼ定時に眠くなり、一定時間経過後に自然に覚醒する
● 恒常性維持(ホメオスタシス)
:先行する覚醒時間が長いほど睡眠時間が延長(覚醒時疲労に対する休養=寝だめ)
ただし、眠気が現れる時間帯と必要睡眠時間には個人差があるそうです。
早い時間に眠気が現れ、必要睡眠時間が短い人は楽な社会生活を送れる一方、夜型傾向が強く必要睡眠時間が長い人は社会生活を始めてからかなり苦労されるとのこと。
そのため、理想と現実の睡眠時間のギャップが生じていると話されました。
現代人の多くが、自覚できない睡眠不足を抱えている可能性を指摘されます。
電子機器など光のあるなかで生活している私たちは、平均約1時間の潜在的睡眠不足を抱えているそう。
たった1時間でも、身体には負担やストレスがかかっていると述べられます。
平均約1時間の潜在的睡眠不足を解消すると、身体の生理機能の回復がみられたとのこと。
また、日本は世界でも断トツの睡眠不足国家であり、OECD加盟諸国の平均睡眠時間が8時間25分に対し、日本は7時間22分と約1時間の差がみられると説明されます。
その主な原因は生活の夜型化だと指摘されました。
短時間睡眠の要因とリスク
働き方改革関連法案でも睡眠・休養不足の問題が論議されたそうです。
● 毎日4時間、月80時間相当の残業
⇒発症前2~6ヵ月間の過労死ライン
● 毎日4時間、月100時間相当の残業
⇒発症前1ヵ月の過労死ライン
残業時間が増えると、睡眠時間を圧迫し過労死のリスクが増加しますが、睡眠時間が5時間以下になると脳・心疾患のリスクも高まるとのこと。
勤務間インターバルが長い群ほど、睡眠時間が長く、さらに睡眠の質もよかったという研究がある一方で、労働者は勤務間インターバル内において睡眠時間よりも余暇時間を優先している状況が明らかになったと説明されます。
勤務間インターバルを設けるのは必須ですが、それだけでなく”睡眠時間を生活の固定費”として確保する必要を強調されました。
短時間睡眠は生活習慣病や血管障害の大きなリスク要因であることを述べられ、米国心臓協会の心血管系の健康状態を測定するチェックリスト(Life’s Essential 8:健康人生のための必須8項目)に『健康的な睡眠』が追加されたことに触れられます。
新しい指標では、成人は毎日7〜9時間、子どもは年齢に応じてそれ以上の睡眠をとることが推奨されているとのこと。
ある調査結果によると、睡眠に満足しているのは世界の成人では55%、日本人はわずか29%しかいなかったそうです。
労働者のメンタルヘルスと健康リスクに備えるためにも、睡眠問題に目を向けてほしいとまとめられました。
睡眠という誰しもが関わるテーマだけに、まさに自分ごとのように聞き入ってしまった内容でした。
忙しくても寝る直前まで、スマートフォンでSNSを見たり、ドラマを観たりといつのまにか寝る時間が遅くなっていることが多々あります。
心身の健康を守るためにも、睡眠時間を生活の固定費として見直していこうと考えされられる内容でした。
非常に、学びのあるお話をありがとうございました。
不知火塾の詳細はこちら
次回テーマは「AIは心の病を診ることができるか?」です。
次回案内はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
