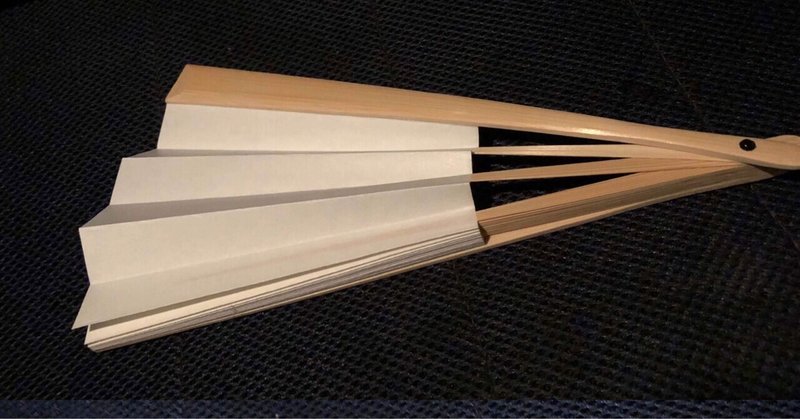
看取り人 エピソード3 看取り落語(8)
師匠の目が大きく開く。
(看取り落語?)
古典でも?創作でもなく⁉︎
しかし、そんな師匠の疑問を置いて二人の噺は始まる。
「皆様、お気づきかどうかは分かりませんが……私……」
看取り人は、いや看取り人の声を借りた茶々丸は言葉を溜める。
「猫でございます!」
淡々とした声でドヤる看取り人、もとい茶々丸に師匠は唖然とする。
「猫と言いますとニャれお気楽、ニャれのんびりして羨ましい、ニャれいつも寝てるなんて言われておりますが、こう見えて野良猫だったら餌探しに奮闘し、飼い猫だったらご飯強請るのに甘えたくないのに甘えたりと意外と忙しいのでございますにゃ」
看取り人は、茶々丸になり切っているつもりなのか、様々なところにニャやにゃで変化を加えながら話すが淡々とした口調は変わらないので違和感が強い。
これが直弟子なら手に持った扇子を投げつけて怒鳴り散らすところだが、師匠にそんな力はもうない。
それに何故か彼の話しに、言葉に怒りは湧かなかった。それどころか水のせせらぎを聞いてるような、乾いた心の隙間に染み込むような心地よさすら感じる。
「さて、そんな忙しなく生きてる猫ではございますがにゃ。人間の忙しさにはとてもとても敵いませんにゃ。勤労で勤勉。私達が猫が寝てる頃には働いて、私達が寝てる頃に帰ってくる。まあ、何とも慌ただしい生き物ですにゃ」
茶々丸は、一呼吸置くように口を開けて……閉じる。
まるで自分が喋ってるかのように。
いや、喋っているのだ。看取り人の声を借りて。
「そんな人間ではございますが働いてばかりはいられませんにゃ。心の安定を図るためにも娯楽というものが必要ですにゃ。猫に猫じゃらしがあるように人間にも沢山の娯楽がございますにゃ。食であったり、レジャーであったり、スポーツ、ゲームと多岐多様に渡りますにゃ。そんな娯楽の中でも古いものが落語となりますにゃ」
落語と言う言葉に師匠の目が震える。
茶々丸の翡翠の目が師匠にじっと見据える。
「落語というものの起源は非常に古く、発祥は江戸時代、滑稽を中心とした落ちつく"落としばなし"のことを指しておりました。その当時は様々な人、それこそ町民から住職まであの手この手と話されたものでございますがいつしか落語家と言う人間が話すようになりましたにゃ」
茶々丸は、小さく舌舐めずりをする。
「さあ、落語家と言う職業。良く耳にする名前ではございますが一筋縄でいくものではございませんにゃ。それこそ実力、才能、努力、どれだけあっても満たされることのない腕と喋り、そして私のような愛らしさがないと生きていけない世界でございますにゃ」
最後はいらんだろうと師匠は胸中で突っ込む。
茶々丸は誇らしげに目を細める。
「そんにゃ熾烈を極める猫の世界、いニャ、落語の世界でございますから生き残っているのも当然ながら鬼才、天才と呼ばれる人間たちが犇いております」
怨霊跋扈のように言うな、師匠は思わず苦笑する。
「しかし、鬼才、天才というものは言い方を変えれば奇人変人とも呼ぶことが出来ますにゃ。要は狭い特有の世界では稀有な才能を発揮しても広い世界では適用出来ない、規定と呼ばれる道を歩むことの出来ない人間のことを指しますにゃ」
看取り人の両手が茶々丸の羽織に触れる。
茶々丸が小さく唸る。
「これはそんにゃ鬼才と呼ばれた変人と、とある愛らしい猫の話しにございますにゃ」
茶々丸のピンクの羽織が脱げる。
茶々丸がふうっと唸って翡翠の目を滾らす。
本筋が始まる。
「その男が落語を始めたのは私がこの世に生を受ける前、つまりニャーン年前と言うことですにゃ」
茶々丸は、年の部分を愛らしく誤魔化しながら話し出す。
「その男、小さい頃に祖父母に連れて行ってもらった寄席で見た落語に感動し、忘れることが出来ないまま多感な時期を迎えましたにゃ。頭も素行も良くなかった男は親に請われるままに高校に入学したものの目的も見えず、酒を飲み、煙草を吸い、喧嘩を売られれば買い、腹が減れば万引きする。底辺の悪ガキがするようなことは大概やらかしましたにゃ」
底辺とはひでえ言い草だな。
これでも近隣じゃ名の知れた不良だったんだぜ。
まあ、どれだけ強がろうが褒められることじゃねえが。
「そんな素行不良な男でございますから当然、学校は見切りを付けます。親も手に負えないと諦めます。普通ならその時点で反省したり、負い目を感じるものでございますががにゃ、そこは奇人変人、逆にそれを金言、神の道標と思い、子どもの頃に夢馳せた落語の世界に飛び込む決意をしたのでございますにゃ」
忘れもしねえ。
17の時。
日曜の夕方の番組の出演者の一門が家の近くにあるって聞いてその門を叩いた。叩いて……。
「叩き出されましたにゃ」
茶々丸は、笑うように欠伸する。
出てきたのは自分の半分も満たない身長の爺さん。
それなのにその眼光と言ったら腹の減った狼よりもギラついて睨みつけてきやがった。
当時の師匠は流行りの剃り込みを入れ、衣服をだらしなく着こなし、背筋を曲げて相手を睨みつけて恐怖を煽る、そんな典型的な不良だったが爺さんはまるで怖がる様子もない。むしろゴキブリでも見るような軽蔑した目で師匠を見据えた。
これでも喧嘩負け知らずを自負していた師匠は爺さんの迫力に気圧されし、「出ていけクソガキ」の言葉一つで萎縮して、尻尾を巻くように逃げ出した。
人生で初めて心の折れた瞬間だった。
今思えばこれが鬼才と呼ばれる人間の放つ圧と呼べるものだったのだろう。
あの時はもうこのまま諦めようと思った。
しかし、一度燻ってしまった火は消えなかった。
「その日から男は何度も何度も爺さんの元に行って頼み込みましたにゃ。髪を丸め、衣服を正し、態度を改め、門の前で正座して雨の日も風の日も槍の日も頭を下げてお願いしましたにゃ。その姿はまるで餌をくれるまで離れない野良猫ように哀愁が漂っておりましたにゃ」
そりゃ流石に言い過ぎだろう……間違ってないか。
だから爺さん、大師匠も受け入れてくれたのかもな。
「男の態度と粘る姿勢に根負けした爺さんは、ついに弟子入りを認めましたにゃ。大喜びする男の声は発情したオス猫にも引けを取りませんでしたにゃ」
ちょいちょい猫表現でディスってきやがるな。
「その日から男の落語生活が始まりました。しかし、弟子入りしたからと言って直ぐに落語ができる訳ではございませんにゃ。見習い、前座、二ツ目と独り立ちするまでは人としては見られない。野良猫の方がマシなのではないかと思えるような過酷な日々が続きましたにゃ」
確かに、あの当時は師匠にでも奢って貰えなけりゃ白飯すらありつけず、角砂糖だけを舐めることだってあった。野良猫の強請る猫まんまの方が遥かにまともだった。
「しかし、その過酷な日々が、情熱が男を一歩も二歩も成長させ、前座を超え、二ツ目を抜け、ついに真打へと上り詰めましたにゃ」
師匠の胸にあの時の花火が全身で鳴り響いた時の喜びが蘇る。
やって良かった。
生きてて良かった。
アレだけ泣いたのは子どもの時以来だった。
しかし……。
「男は、真打に慣れたことを喜び、咽び泣きましたにゃ」
茶々丸が師匠の心情を読み取ったように言う。
しかし、その翡翠の目は固く、じっと師匠を見る。
「しかし、男は後にそれを後悔することになりますにゃ」
茶々丸は、口元を覆うように右の前足を持ち上げて甘噛みする。
「自分は……真打になるべきではなかった、と」
その通り。
自分は真打になるべきじゃなかった。
そうすれば……あんな悲劇は起きなかったはずだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
