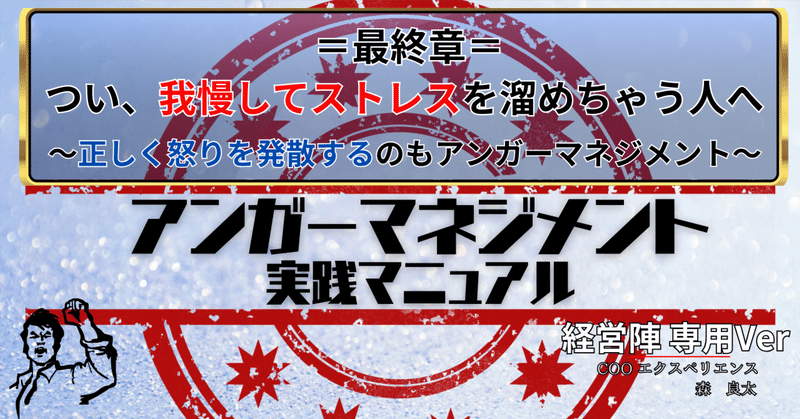
〔5〕怒りを我慢し続けるとストレスが蓄積される。【アンガーマネジメント実践マニュアル】正しく発散するのもアンガーマネジメント!
【アンガーマネジメント実践マニュアル第5章】
=つい、我慢してストレスを溜めちゃう人へ=
怒りを内に秘め、発散できない人必見!
ちょっと怒ったらすぐにパワハラと言われる。
軽く愚痴を言っただけで大袈裟な噂にされて広められる…
怒りを爆発させられる場所も減る一方…
怒りや不満を溜めることに慣れてしまって、
気がつけば、
心身に影響が出るぐらいストレス過多になっていることも。
そこで今回は、
怒りを内に抱え込むことのリスクと、
それを健康的に発散する方法に焦点を当てていきます。
怒りをうまく表現し、
コントロールすることは、
心身の安定だけでなく、
周囲と良好な関係を築くためにも重要で、
COOをはじめ、
リーダーシップを発揮するポジションの方には
欠かせないスキルになります。
セクション1: 我慢することの代償

怒りを我慢することは、
自己制御や忍耐の証とされることがあります。
しかし、
我慢が心身に及ぼす影響は計り知れません。
怒りを抑え込むことの代償には、
以下のような側面があります→
1. 心身の健康への影響
怒りを内に秘めることは、
ストレスホルモンの過剰な分泌を引き起こし、
心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。
睡眠障害、消化不良、
さらには心臓病や高血圧のリスクを
高める可能性があります。
2. 感情の蓄積
怒りを表現しないことで、
感情が蓄積し、
やがては小さな出来事にも
過剰に反応してしまうようになることも…
些細な出来事で、
暴走してしまうことにも繋がります。
※電車で少し肩がぶつかっただけで
猛烈にキレだす老害オジさんとかが
このパターンです。
老害にならないように気をつけましょう。
3. 人間関係への影響
怒りを表現しないことは、
周囲とのコミュニケーションにも影響を及ぼします。
抑え込んだ怒りは、
皮肉や冷たい態度といった形で無意識に表れ、
人間関係に亀裂を生じさせることが多々あります。
4. 自己表現の抑圧
怒りを我慢することで、
自己の感情や意見が抑圧されていきます。
これに慣れてしまうと、
自分の意見を言う場が無くなっていき、
無力感や自己肯定感が下がる要因にもなります。
5. 内面の平和の喪失
常に怒りを抑え込むことは、
内面の平和や幸福感を脅かします。
心の中で繰り返し怒りを感じることは、
自身の幸福感を奪い、
人生の質を低下させてしまいます。
怒りを我慢することは、
あらゆる場面で深刻な影響が…
そうならない為にも、
怒りを正しく発散させていきましょう。
セクション2: 感情のコントロールと怒りの解放

COOのような社長の右腕かつ
全体をマネジメントしなければいけない立場や、
管理職等のリーダーシップを求められるポジションにいると、
自分の仕事だけではなく、
周りの動きに左右されることが多いため、
怒りたくなる状況が人一倍増えます。
毎日、怒りを感じる瞬間だらけだ!
というリーダーも多いでしょう。
そこで、怒りの性質を理解し、
適切にコントロールする方法を紹介しておきます→
◇怒りの根源を理解する:
怒りは表面的な出来事に対する反応として現れますが、
その背後にはもっと深い心理的な要因が
隠されていることが多いです。
例えば、
部下のミスに対して怒る時、
それは単にミスそのものに対する怒りではなく、
自身の責任感、完璧主義、
あるいはチームに対する高い期待が原因かもしれません。
このように、
怒りの真の原因を掘り下げることで、
自分自身の内面を深く理解し、
より健全な対応を取ることが可能になります。
まずは、
「怒りを感じた瞬間に何を考えていたのか?」
「どんな感情が湧き上がっていたのか?」
を振り返ってみましょう。
それが
「信頼されていないと感じること」
や
「部下を管理しきれずにコントロールを失うことへの恐れ」
など、
深い心理的な要因が根源だと気づけるかもしれません。
さらに、
怒りの根源に気づくためには、
過去の経験やそれに対する反応を振り返ることも有効です。
子供の頃の出来事や過去の職場での経験が、
今の怒りの反応に影響を与えている可能性があります。
例えば、
幼少期に厳格な親から受けた批判が、
現在の完璧主義や批判への過敏反応に
繋がっている場合もあります。
このように自己分析を進めることで、
怒りの感情をより深く理解し、
それを健全にコントロールする方法を
見つけることが出来るようになります。
◇冷静になるための即効策《5-4-3-2-1法》:
冷静になるための即効策として、
「5-4-3-2-1法」は特に効果的です。
この方法は、
感覚を利用して怒りの状態から
脱却するのに役立ちます。
具体的には以下の手順で行います→
◎手順その一:5つのものを見る
まずは、
周囲にある5つの異なる物体を見つけます。
これは、
あなたの注意を現在の環境に集中させ、
感情的な反応から離れるのに役立ちます。
例えば、
机の上のペン、窓から見える木、
壁にかかった絵、手元の携帯電話、
足元の靴などがそれにあたります。
◎手順その二:4つのものに触れる
それから、
手の届く範囲にある4つの物体に触れてみます。
触感に集中することで、
感情を鎮めるのに役立ちます。
例えば、
机の表面の感触、椅子の布地、
キーボードのキー、
自分の衣服など。
◎手順その三:3つの音を聞く
次に、
3つの異なる音に耳を傾けます。
離れた場所からの会話の声、
エアコンの音、外からの鳥の声など、
周囲の音に意識を向けることで、
心を落ち着かせます。
◎手順その四:2つの匂いを嗅ぐ
できる限り、
周囲の2つの異なる匂いを嗅ぎます。
コーヒーの香り、
香水の匂いなど、
香りに注意を向けることで、
感情の高ぶりを鎮めます。
◎手順その五:1つの味を味わう
最後に、
何か飲食物の味を意識して味わいます。
飲み物の温かさや冷たさ、
食べ物の味わいなど、
味覚に集中することで、
現在に集中しましょう。
怒りの感情から離れるのに役立ちます。
この「5-4-3-2-1法」は、
簡単に実践できる一方で、
怒りを感じた時に心を落ち着かせ、
冷静な判断を取り戻すのに非常に効果的です。
感覚を利用することで、
怒りの感情が高まった状態から距離を置き、
自分を落ち着かせることが可能になるのです。
◇相手に建設的な言葉で怒りを伝える話術:
怒りの感情を言葉に変えることで、
冷静に伝えることができます。
例えば、
「あなたのせいでプロジェクトが遅れた!」
ではなく、
「プロジェクトの遅れについて心配しています。
どうすれば改善できると思いますか?」
と表現すると、
相手も受け入れやすくなります。
相手に建設的な言葉で怒りを伝えることは、
コミュニケーションの重要なスキルです。
特に管理職やリーダーの立場にある人にとって、
怒りを適切に表現する能力は、
チームの士気と効率を維持する為に欠かせません!
以下のステップで
怒りを建設的に伝えてみましょう。
ステップ1. 非難から解決への焦点のシフト
怒りを表現する際、
非難や批判的な言葉は避け、
問題解決に焦点を当てることが重要です。
「あなたのせいで…」
と非難するのではなく、
「この問題をどう解決できるか考えましょう」
と前向きなアプローチを取りましょう。
ステップ2. 具体的な事実に基づく
怒りの原因を具体的な事実に基づいて伝えます。
感情的な表現よりも、
具体的な事例やデータを用いることで、
相手も問題を理解しやすくなります。
ステップ3. Iメッセージの利用
「私は…と感じる」
といったIメッセージを使うことで、
自己の感情を直接的に伝えることができます。
これにより、
相手が防御的になるのを防ぎながら、
自分の感情を明確に伝えることが可能になります。
4. 解決策への協力を促す
「どうすればこの問題を改善できると思いますか?」
といった形で、
相手に解決策の提案を促します。
これにより、
協力的な雰囲気を作り出し、
共に問題を解決する姿勢を示します。
5. 聞く姿勢を保つ
相手の意見や感じていることを積極的に聞き、
理解しようとする姿勢を示すことが大切です。
これにより、
対話がより建設的なものになり、
相互の理解が深まります。
怒りを建設的に伝えることで、
相手は非難されていると感じることなく、
問題の解決に向けて一緒に取り組む意欲を
持ってくれるようになります。
このようなアプローチは、
健全な職場環境を維持し、
チームの結束力を強化する効果があります。
どんなに歩みよっても、
改善されない人も稀にいますが、
すぐにはクビにすることは難しいのが
現状という方が多いと思います。
そういう時こそ、
アンガーマネジメントです!
とにかく怒りで感情的になって、
くれぐれもパワハラで訴えられたり、
つい手を出してしまって、
傷害事件にならないように注意して下さい。
セクション3 簡単に出来るストレス解消法

日常生活に容易に取り入れられる、
ストレス解消法を
いくつか紹介するので、
参考にしてみて下さい→
◇短時間の散歩:
仕事の合間に数分間の散歩を取り入れましょう。
新鮮な空気と運動は、
ストレスホルモンを減少させ、
心身をリフレッシュさせます。
◇深呼吸の実践:
机での作業中でも、深呼吸を数回行うことで、
心が落ち着きます。
特に腹式呼吸は、緊張を和らげ、
集中力を高めるのに効果的です。
◇音楽を聴く:
好きな音楽を聴くことは、
気分をリフレッシュし、
ストレスを軽減します。
穏やかなクラシック音楽や自然の音は、
特にリラックス効果が高いとされています。
◇ストレッチ:
机の周りで簡単にできるストレッチを行うことで、
体の緊張を和らげ、
ストレスを軽減出来ます。
中でも肩や首のストレッチは、
デスクワークによる緊張を解消するのに特に効果的です。
◇水分補給:
水分を適切に補給することは、
体と心の健康を保つのに重要です。
水やハーブティーをこまめに飲むことで、
リラックスし、
集中力を維持できます。
◇短い昼寝:
昼休みに10〜20分の短い昼寝を取ることで、
脳がリフレッシュし、
午後の業務効率が向上します。
短い昼寝は、
ストレス軽減にも役立ちます。
◇趣味の時間を設ける:
日々の生活に好きな趣味の時間を取り入れることで、
ストレスを効果的に軽減できます。
絵を描く、ガーデニング、料理、写真撮影、
ゲーム、アニメやドラマ鑑賞等、
何でも良いので
リラックスできる活動を見つけましょう。
◇アロマセラピー:
アロマオイルやアロマキャンドルを使用して、
リラックスする時間を作ります。
ラベンダー、ユーカリ、ローズなどの香りは
特にリラクゼーションに効果的です。
社会的交流を持つ:
友人や家族との会話や交流は、
ストレスを減らすのに効果的です。
気軽なお茶会や電話での会話など、
人との繋がりを大切にしましょう。
ペットとのふれあい:
ペットと過ごす時間は、
ストレスを軽減するのに非常に有効です。
犬の散歩や猫との遊びは、
心を落ち着けるのに役立ちます。
※ペットが飼えない環境の方は、
猫カフェ等に行くのもOKです。
◇ガーデニング:
植物の世話をすることは、
ストレスを和らげるのに効果的です。
自然と触れ合うことで、
心が穏やかになります。
◇アートセラピー:
絵を描く、粘土をこねる、
工芸品を作るなどのアート活動は、
クリエイティブな表現を通じてストレスを解消します。
◇感謝日記をつける:
毎日、感謝することを3つ書くだけで、
肯定的な考え方が促進され、
ストレスが軽減されます。
ポジティブな思考は、
ストレスに対する耐性を高めるのに役立ちます。
出来そうなことから取り入れてみて下さい。
怒りを溜め込まないように、
自分に合った方法を見つけ、
定期的にストレスを発散しましょう。
コンクルージョン: 感情管理とストレスの克服

怒りは誰にでもある自然な感情ですが、
その扱い方が心身の健康、人間関係、
職場の環境に大きな影響を与えます。
怒りを我慢することは短期的には
平和を保つかもしれませんが、
長期的には多くの心身の問題を
引き起こす可能性があります。
怒りを適切に表現し、
コントロールすることは、
個人の幸福感を高めるだけでなく、
周囲との良好な関係を築くためにも非常に重要です。
アンガーマネジメントを活用して、
より穏やかで健康的な日常を過ごしていきましょう。
常にイライラしているリーダーの元に、
効率よく元気に働いてくれる部下が
現れることはまずありません…
反対に
マネジメントする側のポジションいる人間が
常に機嫌良くいるだけで、
組織の生産性はアップしていきます!
=========
このnoteブログ
「COOエクスペリエンス」では、
現役のCOO であり、
次世代COOの育成〜社員教育研修、
コンサルティング等に従事している
実際の経験に基づいた内容になっています。
厄介なマネジメント問題に立ち向かうための
活きた現場の知恵や戦術を、
お伝えしているので、
フォローして頂けたら嬉しいです♪
※毎週、金曜日夕方にnote更新中!
=========
今回の「COOエクスペリエンス」では、
アンガーマネジメント第5章と称して
我慢しがちな日々を送っている人という
ピンポイントの狭い話を深掘りしました。
COOをはじめ、
右腕、ナンバー2、管理職ともなると、
我慢することが増えて、
いつしか我慢することが仕事!みたいに
なってしまうこともあります。
ですが、
気づかないうちに、
肌が荒れていたり、
寝ても疲れがとれなかったり、
些細なことでイライラするようになったりと、
心身が蝕まれているものです。
自分は大丈夫!と思っているかもしれませんが、
今日をきっかけに、
自分自身を大事にして、
周りのことだけではなく、
自分のストレスを解消することも
真剣に考えてみて下さい。
あなたがいなくなると
困るんです…
無理はずっとは出来ません。
部下の機嫌、社長の機嫌、
取引先の機嫌をマネジメントすることは
大事な仕事ですが、
自分の機嫌をとることは
人生で一番大事な仕事とも言えるでしょう!
COOをはじめ、
経営者、次世代のリーダー達が
職務を果たすために少しでもお役に立てたら幸いです。
Amazon Kindleでも、
経営、マネジメントに関する知見や、
実践的なノウハウをまとめているので、
ぜひご自身の経験と結びつけてご活用ください。
※Kindle Unlimitedに登録している方は無料で読むことが出来ます。
↓↓下記をクリックして下さい↓↓
会社が立ち上がるのはCEOの力ですが、
その後、会社が伸びるかどうかはCOO次第です!
みんなの為に人柱になってあげて下さい。
職場の平和のために〜犠牲になるのがCOO /ナンバー2の役目です笑
一緒に敏腕COOへの道を歩んでいきましょう!
〔COO育成塾〜noteテキストVer〜〕
サポートはしていただかなくて良いので、もし投稿が気に入ったら《フォロー》 『スキ』して頂けると非常に嬉しいです♪
