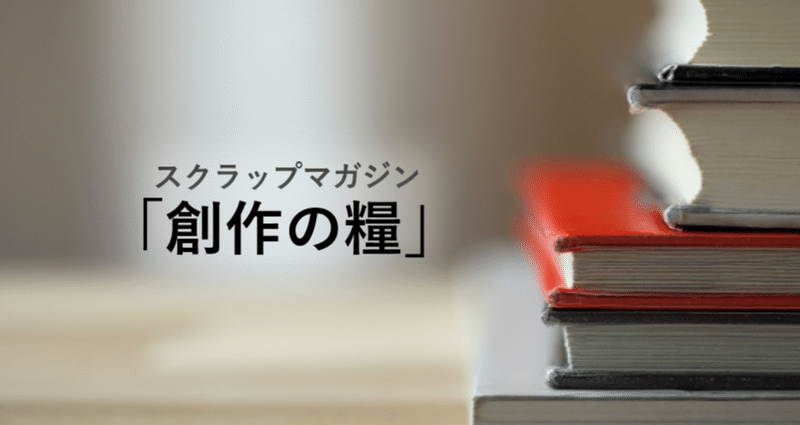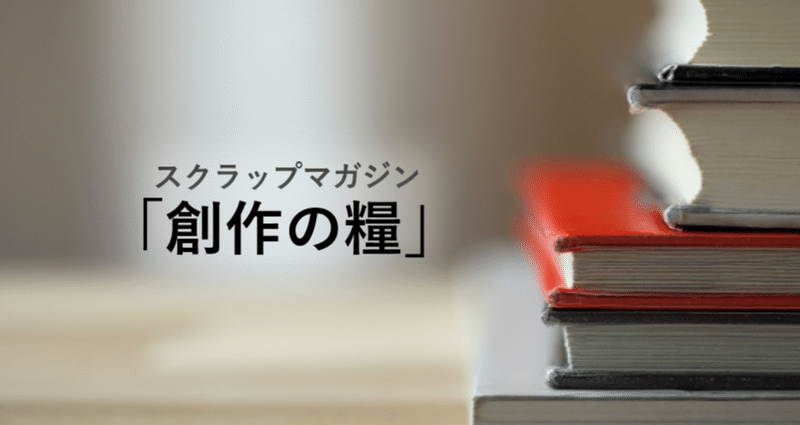俳句コンテストでの類句検知に協力
概要2021年5月に、部員の西江友里、宮本稜太、宮本大輝が、国内最大規模の俳句コンテスト「伊藤園お~いお茶新俳句大賞」の選考過程において技術支援を行いました。投稿された句のうち、既存の作品と重複するものや著しく類似するもの(類句)の検知を行いました。このコンテストは今年で32回を迎え、近年では毎年約200万件の句が投稿されています。人手で行っている類句検知の労力を軽減するのが目的です。
詳細今回は一次審査を通過した約2万句について、既存句約100万に対する類句の検知を行いま