
金曜日の随筆:江戸時代の三俳人
また運命を動かしていく金曜日がやって来ました。2021年のWK26、水無月の肆です。本日は、俳句の歴史をさらっとなぞった後、江戸時代の三俳人について纏めます。
『俳句』になったのは明治時代
『俳句』は、季語の含まれた五・七・五(十七語)の定型詩です。『俳』という字には、「こっけいなこと、おどけ。(小学館デジタル大辞泉)」という意味があり、俳句を読む人は『俳人』と呼ばれます。
俳句は近世に発展した文芸である俳諧連歌、略して俳諧から生まれた近代文芸である。
『俳句』とは「俳諧の発句」の前後を取った略語で、明治時代に正岡子規(1867/10/14-1902/9/19)が起こした「俳句革新運動」によって確立され、流布されていった呼称だということです。おそらくは、学校で習った筈ですが、全然覚えていませんでした。
ということは、『江戸時代の三俳人』と称される以下の三人が活躍した江戸時代には、『俳句』とは呼ばれていなかったことになります。
松尾芭蕉 寛永21/正保元年(1644)- 元禄7年10月12日(1694/11/28)
与謝蕪村 享保元年(1716)- 天明3年12月25日(1784/1/17)
小林一茶 宝暦13年5月5日(1763/6/15)- 文政10年11月19日(1828/1/5)
とはいえ、『俳句』として芸術に体系化されていく過程で、彼らの活動や遺した作品の数々が重要な役割を果たしたことは間違いありません。現代『俳句』の基礎を作り、有名な句を数多く残している俳諧の人(俳人)の詠んだ句について知っておこうと思います。
松尾芭蕉
松尾芭蕉は伊賀国出身です。「蕉風」という独自の作法を確立した俳句界最大の巨匠かもしれません。おそらく、一番有名な句は、野ざらし紀行から戻った1686年の春に、江戸の芭蕉庵で催した蛙の発句会で詠んだ
古池や 蛙飛びこむ 水の音
ではないかと思います。
芭蕉は、生涯、旅を愛しました。人生晩年の45歳の時には、弟子の河合曾良と共に江戸を発ち、東北から北陸を経て大垣(岐阜県)までを巡った旅の紀行文『おくのほそ道』を記しています。旅の途中で、多くの名句を残しています。
夏草や 兵どもが 夢の跡 【岩手県平泉町】
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 【山形県・立石寺】
五月雨を あつめて早し 最上川 【山形県大石田町】
荒海や 佐渡によこたふ 天河 【新潟県出雲崎町】
与謝蕪村
与謝蕪村は、大阪に生まれた江戸時代中期の俳人です。松尾芭蕉を尊敬し、衰退傾向にあった「蕉風」を立て直して、写実的で抒情性のある絵画的な作風を確立しました。「江戸俳諧の中興の祖」と呼ばれます。
個人的には、三俳人の中で最も印象が薄い人です。実際、評価が回復したのは、明治の時代になってからの正岡子規や萩原朔太郎の功績だとされます。蕪村の有名な句は、
春の海 終日(ひねもす)のたり のたりかな
菜の花や 月は東に 日は西に
あたりでしょうか。
蕪村は画家としての顔もあります。文人画(南画)を確立した、絵画の新ジャンルにあたる『俳画』を開拓した、という功績も見逃せません。
小林一茶
小林一茶は、信濃国の富農出身です。江戸の商家へ奉公に出た後、俳諧の道に入り、「一茶調」と呼ばれる独自の俳風を確立しました。明るく、ユーモラスで親しみやすい印象を与えてくれる句風は、現代でも人気があります。
小林一茶は生涯で約22,000句も詠んだ多作の人です。有名な句としては、
すずめの子 そこのけそこのけ お馬が通る
春風や 牛に引かれて 善光寺
やせ蛙(がえる) 負けるな一茶 これにあり
あたりでしょうか。一茶は晩婚で、年老いてから生まれた子どもを次々と亡くす悲哀を味わっています。陽のイメージとは裏腹に、子どもを喪った悲しみと孤独な身の上を嘆いた句も少なくありません。
今週の格言・名言《2021/6/21-27》
Failure is a required part of success.
成功のためには、失敗も必要
The mind is everything. What you think become.
心がすべてである。あなたはあなたの考えた通りになる。
ブッダ 仏教の開祖/インド
※昨日の投稿で、700日連続投稿を達成しました!
これは通過点に過ぎません。まだまだ記事投稿記録を延ばしていきます。
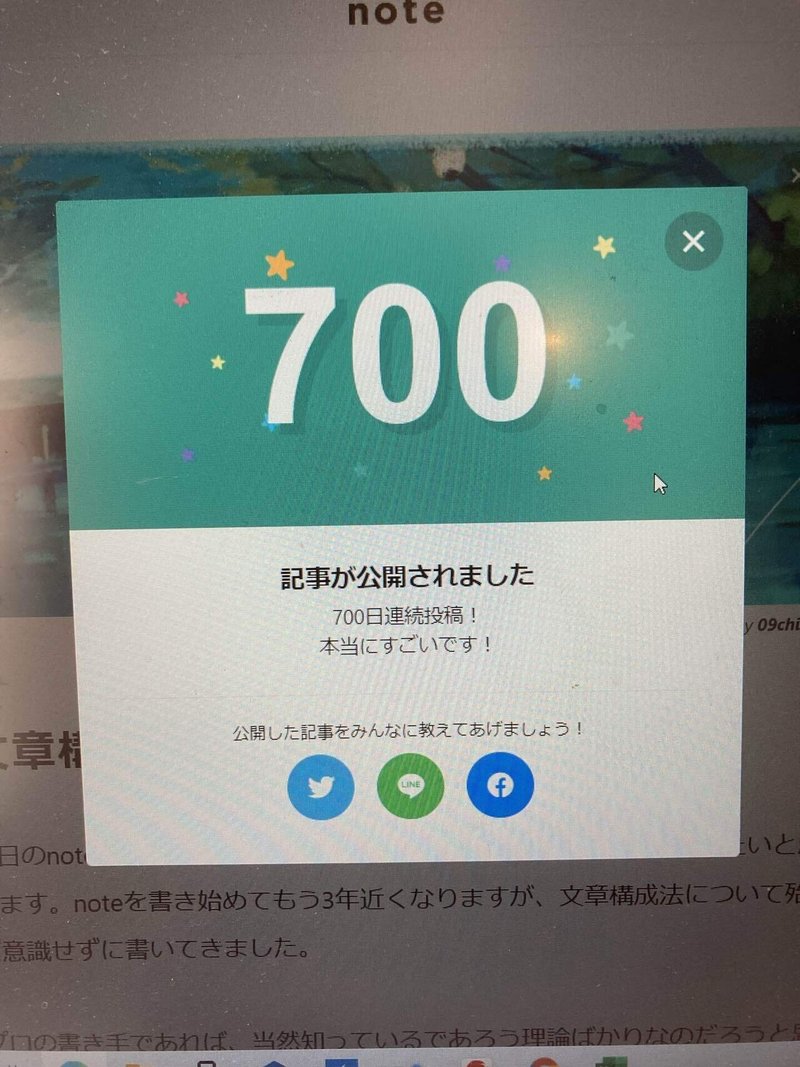
サポートして頂けると大変励みになります。自分の綴る文章が少しでも読んでいただける方の日々の潤いになれば嬉しいです。
