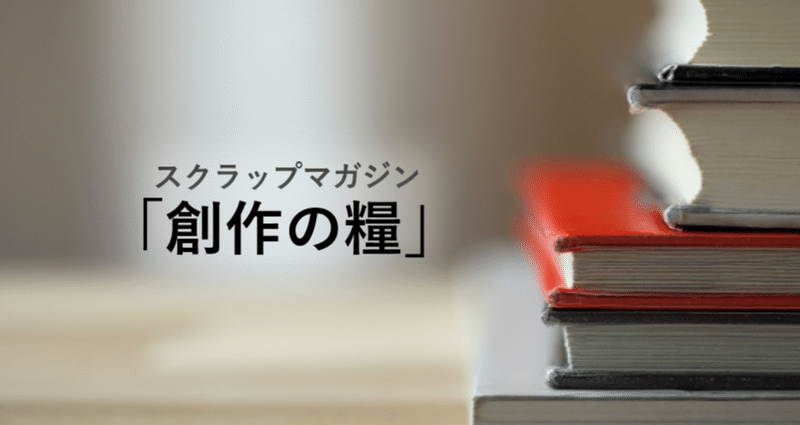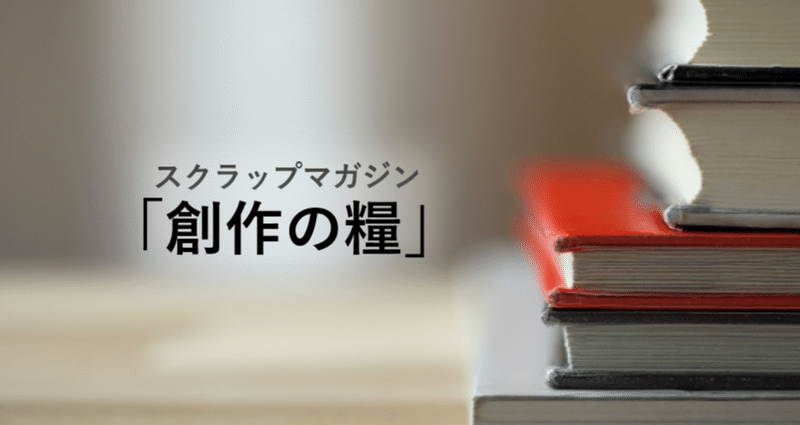なんか怒られるかと思ってたんだけど
や、なんか、まいぬ(合ってる?)さんが、人生は私を裏切ってくる。って書いてて、面白いな。と思ってメモしてたら、フォローしてくれたんだけど、俺はべつに面白い人間じゃないが。まあなんか思い出したのはモトカノで、俺ずーっとモトカノひきずってるけど、なんか結局俺、(モトカノ、)捨てたんよな。悪いとこは滅茶苦茶あって、親戚disってくるとか、田舎の家ベタ褒めするとか、トロフィーとかを見て、なんか使ってないみたいだから私にちょうだい。って言ってみたりだとか無茶苦茶で、次女なんだよなあ。俺