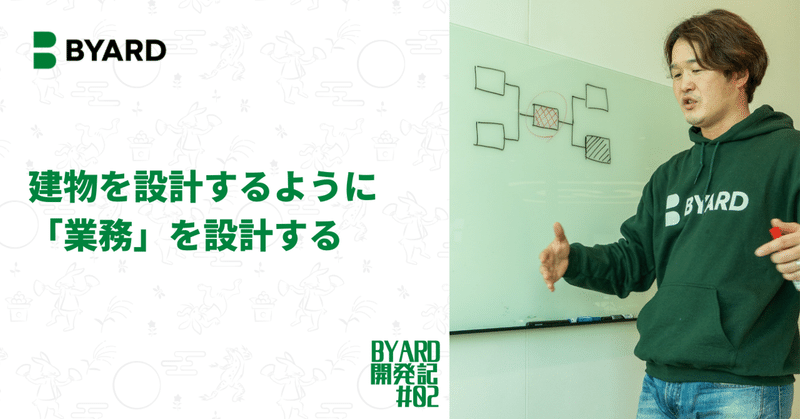
建物を設計するように「業務」を設計する|#BYARD開発記 02
第2回は、プロダクトの設計思想の根幹になっている「業務設計」の概念が生まれた背景について振り返ります。
「BYARD開発記」について ※本文はこの下からスタートです
株式会社BYARD・代表の武内俊介が、サラリーマンから税理士資格の取得を経て起業し、BYARDというプロダクトを作り上げるまでの開発ストーリー。
開発に至るまでの背景や、プロダクトの設計に込められた想い、起業・開発を通じて得た経験などをご紹介します。
(ヒアリング/執筆/撮影:藤森ユウワ)
コネクティング・ザ・ドッツ——大企業での業務フローの構築、会計の世界、そしてスタートアップ
大企業からスタートしたキャリアが、気が付いたら今はスタートアップの道を歩いている。
もちろんこれまでも、その地点ごとに志や目標は立てていました。しかしそれぞれの点は、現在をあらかじめ見すえてつないできたわけではありません。スティーブ・ジョブズが言ったとおり「点と点は後からつなぎ合わせることしかできない」のだと感じます。
***
Apple が iPhone5を発売した2012年。個人として独立するため税理士資格の取得を目指し、会計事務所へと転職していた私に、大きな転機が訪れます。
転職から3年が経ち税理士試験の3科目に合格していたものの、このまま受験勉強を続け、無事に資格を取れた場合のその先のキャリアは、この時点ではまだ十分に描ききれずにいました。
税理士に限ったことではありませんが、資格だけで食っていける時代はとうに終わっていて、税理士といえども特定分野に特化しなければ生き残っていくことは困難です。周囲には資産税や組織再編などに特化している先生方もいましたが、自分が後追いでその第一線に立てるとは思えず、何より税務の分野で尖っていくことに対して興味も湧きませんでした。
独自の強みをどうやったら見いだせるのか——悩んでいたちょうどそんなときに、起業していた大学時代の友人から「仕事を手伝って欲しい」との誘いを受けたのです。
長男が生まれ、経済的な面からも今後のキャリアを考えていたタイミングでした。もしこの誘いがなければ、きっと私は別の税理士事務所に転職してそのまま会計の世界に留まっていたでしょう。
そうではない新たな道を進むため、いったん税理士試験の勉強は中断して友人の会社を手伝うことを決意。ここから私のIT業界およびスタートアップでのキャリアがスタートしました。

入社後はセールスやWebマーケティングからはじまり、経理の知識と経験を活かしてバックオフィスへと、担当領域を広げていきました。そんな中で出会ったのがSalesforceであり、この出会いが私のキャリアにまた新たなドットを刻むことになります。
営業から会計まで社内の一通りの業務を把握しているということで導入プロジェクトに加わり、システムの構築を担当することになった私は、フロント〜バックオフィスまでの一連の業務フローと、そこでのデータの流れ方を考慮してSalesforceの構造や処理プロセスを考えていきました。私は頭の中で自然に思い描きながらやっていたのですが、周囲は「武内さんしかできないやり方だね」と言うのです。
最初は「そうなのか?」と不思議に思っていました。しかし考えてみれば業務とデータのフローを一気通貫でロジカルに組み立てることなど、普通に管理部門だけで働いていたのではめったに経験しないのではないかと気が付いたのです。
例えば「経理」の業務は、企業規模が大きくなれば請求担当、支払担当、経費精算担当……というように分業化され、そこで求められるのは「各自がより速く、より正確に“処理”すること」です。バックオフィスはコストセンターだという考え方が一般的だった時代の名残であり、致し方ないことだとも言えますが、これでは当然自分の担当を越えた「業務全体の流れ」など考える機会はありません。

大企業で、いくつもの部門をまたいで業務とデータのフローを設計したこと
会計事務所で、「会計」という裏方のフローをすみずみまで取り扱ったこと
そしてこれらの経験とITツールとを組み合わせて、業務やデータのフローを設計すること
「管理」ではなく「事業成長」のため、会社が思い切りアクセルを踏み込める土台としてから会社を支える管理部門を設計する——もしかしたら、これこそが私の独自の強みになるのではないかと、おぼろげでありながらも確かな手応えを感じたのです。
建物を設計するように「業務」を設計する
皆さんがもし注文住宅で自分の家を建てるとしたら、まずは何から始めるでしょうか。普通に考えればいきなり大工さんを呼んで建て始めるのではなく、家を「設計する」ところから始めるのではないかと思います。
会社が一つの「建物」だとすれば、壁・床・柱などの建物を構成するパーツがそれぞれの部署であり、私たちが日々行っている業務だと言えるでしょう。だとすれば、丈夫な会社の土台や、事業がスムーズに回る仕組みを作るためには、業務を設計するという考え方が必要なのではないかと私は考えています。私が「税理士」とは別に、「業務設計士®」という肩書を名乗っている理由がここにあります。

その後無事に税理士資格を取得し、もう一社別のITスタートアップを経た後に独立、「業務設計のコンサルティング」を事業とする会社を起業することになりますが、そこでいくつもの企業を支援するなかで課題も見えてきました。
業務全体を俯瞰して見る視点と、実際の現場での業務経験、そしてバックオフィスとITの幅広い知識。私はたまたま、これらのドットがつながって業務設計をなりわいとするようになりました。しかし建物を設計する建築士が難関資格であるように、業務の設計もまた、誰もが簡単にできるようなものではなかったのです。
「業務設計」を私一人の専売特許としてコンサルタントを続けるなら問題ないのですが、それでは再現性がなく事業をスケールさせることはできません。「業務設計」に必要な要素を分解して、もっと広く誰もが使える仕組みを作れないか——この発想が、BYARDというプロダクトへとつながっています。
BYARDは使い始めの起点が「業務プロセスが簡単に組み立てられる」という機能になっていますが、プロダクトとして最終的に実現したいのは「誰でも簡単に業務設計できる」という世界です。
バックオフィスはまだまだ非効率な仕事や仕組みが多く、エンジニアやセールス、マーケティングなどの世界と比べると、残念ながらだいぶ遅れていると言わざるを得ません。エンジニア組織が歳月を掛けてアジャイルやスプリントの仕組みを作り上げてきたように、営業組織がSFAの登場によって「営業のプロセスを科学する」ことが当たり前になったように、バックオフィスも、これから進化せざるを得ないはずです。
バックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作りたい——進化の途上の時代を生き、業務設計士を名乗るものとしての「使命感」のようなものを感じて、私はBYARDというプロダクトを開発しています。
「BYARD開発記」シリーズのご紹介
「BYARD開発記」は全13話のシリーズになっています。
BYARDそれ自体は、数ある業務用アプリケーションの中の一つですが、その背景にはバックオフィスの実務家として、事業の運営者として感じてきた想いや経験があり、それをプロダクトの設計に込めています。
BYARDでは、私たちと一緒にバックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作る仲間を募集しています。もし開発記をお読みいただいて、ご興味をお持ちいただけたようであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
シリーズINDEX
第1章:BYARDへとつながった背景ストーリー
第2章:起業・開発で活用した手法
第3章:BYARDのプロダクト紹介
最終章
BYARDの採用情報は、以下のページよりご確認いただけます。
また、BYARDのこと、業務設計のこと、バックオフィスのことなど、CEO・CTOと気軽に話せるカジュアル面談も実施しております。「気になるけど、いきなり採用に応募するのはな…」という方は、ぜひこちらへお気軽にお申し込みください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
