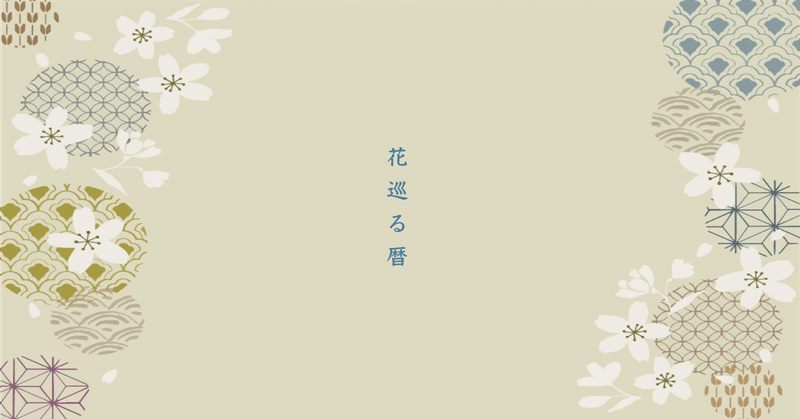
第四話 朔風花払 ―きたかぜはながはらう― (十五)
<全十九話> <一> <二> <三> <四> <五> <六> <七> <八> <九> <十> <十一> <十二> <十三> <十四> <十五> <十六> <十七> <十八> <十九>
<十五>
◇◇◇
「坊ちゃん、だめですよ」
こっそりと背後から忍び寄ろうとする気配に、まるおは前方を見据えたまま注意をした。ちぇーっ、とつまらなさそうな声が答えた。
「まるおは後ろに目でもついているの? どうして僕ってわかるんだよ」
「気配でわかりますよ。どうしたんですか。とうに寝る時間でしょう。明日の朝、起きられませんよ」
夜半過ぎの灯もない暗い中、ひたひたと足音が近づいてきて、広縁に座るまるおの横に座った。綿入れを着込み、首には手拭いを巻いているが、それでも寒そうに縮こまった。
「ちっとも眠れないんだ。まるおはずっとここで座りっぱなしだろ。寝なくて大丈夫なの?」
「わたくしどもには必要ございませんから」
「疲れない?」
「滅多にあるものではないですね。普段から、じゅうぶん休ませていただいておりますし」
「そうなんだ」
ふうん、と磐雄はあぐらをかいた姿勢で、まるおと同じように庭を眺めた。が、どこかわざとらしさが感じられ、落ち着きがない。
「これ以上、近づいてはなりませんよ。隙を見て飛び出したところで、痛いめにあうだけです」
そう言えば、磐雄は恨めしげな眼差しを佇む四天王に向けて、溜息をついた。
「ばれてたか……」
甲冑をつけた勇ましい仏の姿を一目見た時から、下の坊ちゃんが興味津々なのはまるおもわかっていた。側に寄るのも駄目だと注意はしたものの、その内こっそり見に来るだろうと思っていたが、案の定だ。こんな夜中になるとは予想外だったが。
「もうちょっと近くで見たいんだけど、だめ?」
「だめです。あそこは、ただの結界内じゃありません。表面の薄い一枚だけですが、笹の内側は言うなればお嬢さまの作られた『場』であって、お嬢さまのつけた条件が付与されております。四天王は、ご家族を寄せつけないために呼んだものです。万が一、門の内側に落ちたら危険ですからね。あれらは仏教に帰依しない者には容赦がございません。興味本位で近づかない方が身のためです」
「そうなんだ。じゃあ、なんで姉さまは呼び出せるのさ。姉さまも仏教徒じゃないじゃないか」
「信仰心はともかく、お嬢さまが使われたのは古神道と言って、神仏習合で混ざっていた頃の、昔ながらの民間のやり方ですよ。このために、この寒い中、水垢離までなさったんですから」
「仏も使役するって、陰陽道とは違うの? あれも、少しは仏教が混じってるでしょ」
「主に天台密教ですね。あと他にも色々混じっています。陰陽道は式神などをもたらしましたが、実際のところ、星見や方角、暦を読むことを主としています。それらを読んで先を占い、難を避けることが基本とされます。どちらかというと、教理よりも学問の域に入るかと。それに比べると即物的というか、実践向きですね」
「ふうん」
「その辺りの成り立ちは、政も関わるぶん複雑でございますから。わたくしどもでもよくわかっているとは言い難いものにございますよ」
「そうか……じゃあさ、僕も古神道のやり方を覚えれば、ああやって呼び出せる?」
「まあ、やってできないことはございませんね」
まるおは目を眇めて答えた。
「でも、そうすると、若さまや梟帥さまのように戦うことはできなくなりますよ。旦那さま方のように祝詞を唱えるだけで、結界を張ることもできなくなります」
「えっ、そうなの!?」
「神はまっさらであることを好まれますので。古神道を使えば、半分は仏教に浸されることになるので、神の御霊を御身に降ろすことは叶わなくなります。祀ることや願いを口にするぐらいならできますが、直にお力をお貸し頂くことは許されなくなります」
「そうなんだ……それは困るな……」
磐雄は、あからさまにがっかりしたようだった。身体を動かすことの好きな、やんちゃ盛りの下の坊ちゃんから選択肢が消えたことに、まるおは心の中で笑った。咲保には最初から選択肢がなかったが、磐雄は違う。大旦那さまに絞られるようになれば、また考えが変わるかもしれないが、木栖家の者は、皆、負けん気が強い。おそらく、大丈夫だろうと思う。
しばらく、沈黙が続いた。あまりに静かなので、寝てしまったのか、と思ったところで、ぽつり、と問いがあった。
「……姉さまたち、無事かな」
「ご無事でらっしゃいますよ」
「どうしてわかるのさ」
「あれらがまだ残っておりますから」
四天王を視線で指して答えた。
「あれらは、お嬢さまがお帰りを願うか、お亡くなりにならない限りは、あの場を動きません」
「そうなんだ。そっか……」
安心する声が答えた。
「お二人をお助けするために、猫めも動いております。こちらはお任せください。何か異変があれば、すぐに皆さまにお知らせします。風邪をひきますし、今はお休みください」
「うん、わかった」
頷きながらも、磐雄はまだ後ろ髪が引かれる様子で、なかなか立ち上がろうとしなかった。
「ねぇ、まるおは助けに行かないの? まるおだったら、門が開いている今なら、影を渡って行けるだろ」
「……わたくしは猫めほど、隠密行動には長けていませんので」
「そうなんだ」
口惜しいことに。手塩にかけて世話をしてきた咲保をはじめとする木栖家の子どもたちは、皆、まるおにとっても自分の子同様に感じている。だから、助けに行きたいのはやまやまだ。だが、今回は、足音を立てず素早く動ける猫の方が向いていて、その方が成功する確率が高い。なので、その役目は浜路に譲った。だが、やはり悔しい。
「適材適所とでも申しましょうか。今回、失敗をしてしまいましたが、わたくし共は家を守り保つことを得意としておりますので。逆に、気ままな猫めらはそちらは向きません」
「あ、へぇ、そんなのもあるんだ。ああ、でも、確かに浜路さんに、家事は似合わなさそうだよね」
まるで言い訳のようだと自分でも思う付け足しの説明に、磐雄は素直に感心したようだった。
「さようにお思いで」
「うん、掃除とかしても、花瓶とか割っていそう」
その例えは目に浮かぶようで、堪えきれず、まるおも肩を揺らして笑ってしまった。
「たしかに」
「うん、なんか頼りない感じ。その点、まるおが家にいるといないとじゃ、安心感がちがうから。父さまや母さまもそう言ってた」
じん、ときた。
「ありがとうございます」
本当に、この家の子たちは良い子ばかりだ。自慢に思う。
「さ、ここはまるおに任せて、もうお休みください」
「わかった。おやすみ」
「おやすみなさいませ」
来た時同様、ひたひたとした足音で磐雄は部屋へ戻っていった。足音を聞く限り、この短い期間に随分と下半身が安定したように感じる。少し右に傾いていた身体の均衡が、まっすぐになった。存外、熾盛家の梟帥の指導が良かったらしい。あの若者と関わりすぎるのもどうかと危惧したが、うまく回っているようだ。今後も注意は必要だろうが――。
(あと、この家の結界だな……まったく、地面から来るとは小賢しい!)
盲点を突かれた。とはいえ、その対策のために、地の気を断ってしまうと出てくる支障が大きすぎる。何もないように見える地面も、その下にはありとあらゆるさまざまな要素が含まれている。地表に生きる者たちは、その地面から立ち上る、目に見えない恩恵に浴しているからこそ、健やかに生きていられもする。
(なにか対策を考えねば……)
二度とこんなことがないようにしなければならない。
(お嬢さま……)
四天王がいる限りは死んではいない。だが、怪我をしていないとは言い切れない。辛い思いをしていないとは限らない――そういったことが、一切、わからない。そういうことも飲み込んでしまう気丈な娘だから、余計に心配になる。
(どうか、ご無事で……)
モノは祈らない。ただ願う。
まるおは重ねた足を組み替えると、背筋を伸ばし、また前方を見据えた。
◇◇◇
咲保はその身一つでは、戦う術をもたない。守る術も。生まれついての『余分』のせいで身体も鍛えようがなく、一般人より更に脆弱だ。そのため、もし、敵と遭遇してしまった場合にどう対処するか、が計画の肝でもあった。
勇ましく自ら兄を助けに行くと宣言した咲保だったが、計画を立てるにあたって、自分の身が危険に晒される可能性をいっさい考慮していなかったことに気づき、愕然とした。なんとかなるだろうと漠然と思っていただけだった。抜けているにも程がある。両親が心配する筈である。
「おんまゆらきらんていそわか! 孔雀明王ご来臨くださいませっ!」
先手、必勝。札の一枚を地面に落とし、孔雀明王印を結び呼び出した。ばさり、と音を立てて、艶やかな玉虫色の羽根が顕れた。仏像以外で孔雀を目にしたのは初めてだ。現物は雉とそう変わらないと思っていたが、まったく違った。本当に奇妙な形の羽根をしている。一本一本、葉脈のような細い羽根が連なる頂上に、突出して丸い目玉の様な柄がついていた。
(本当に出たわ……)
咲保は、声をあげて笑いたくなった。まるお達からは、咲保なら必ずできると言われていたが、本当に出てきた。背中しか見えないが、上に四本の腕をもつ菩薩も乗っている。菩薩は一言も発することなく、人の姿の玄武に斬りつけた。瞬きする間に、玄武は本来の姿に戻り、菩薩の羽根を模した剣を硬い甲羅で跳ね返す。が、すかさず別の腕が振り上げられ、柑橘が投げつけられた。辺り一面に爽やかな香りが立つが、玄武は気に入らない匂いだったらしい。首が引っ込められた。
「私の呼びかけに応えてくれるかしら……?」
事前の話し合いで、不安がる咲保にまるおは言った。
「お嬢さまの声は他の方々に比べて、普段からわたくし共にはよく響いて聞こえます。まして、『あわい』に於いては異質になる人の声はより大きく鮮明に響くため、助けを呼べば一も二もなく応えるでしょう」
「呼ぶのは明王がよおござんしょね。あれらは、元は大陸で悪神と呼ばれたモノたち。鬼と一緒ですよ。仏に帰依してこちらで新たに名を連ねたモンでござんすから、徳を積むためにも衆生を救わんと躍起になるんじゃないですか? 武に特化してござんすし、玄武なんぞが相手でも、力づくで従わせようとしますよ」
暁葉がけらけらと笑った。
「でも、明王ってたくさんいらっしゃるわよね。不動明王とか軍荼利明王とか。どなたを呼べばいいのかしら」
「その辺はお嬢さまとの相性や相手にもよりますが、暴れすぎると危険もございますので、あまり苛烈でない方がよろしいでしょう。この方などいかがでしょうか」
ばらばらと資料本をめくって、まるおは一頁を指差した。
