
【短歌表現】第三章:新種四百人一首

王朝和歌の絢爛たる世界が蘇る!
藤原定家の「小倉百人一首」。
「原色小倉百人一首」 (シグマベスト)鈴木日出男/山口慎一/依田泰(著)

「小倉百人一首―みやびとあそび―」平田澄子/新川雅朋(著)

足利義尚の「新百人一首」に続き、
丸谷才一が新たに編んだ「新々百人一首」。
「新々百人一首〈上〉」(新潮文庫)丸谷才一(著)

「新々百人一首〈下〉」(新潮文庫)丸谷才一(著)

新百人一首は、藤原定家撰の小倉百人一首に漏れた著名な歌人の歌を、勅撰和歌集から百首選定したものであり、新々百人一首は、25年の歳月をかけて、定家と義尚が選んだ二百人を敬遠せず、かつ両人の取った二百首との重複は避けて厳選した不朽の秀歌百首と、スリリングな解釈(それに付された滋味溢れる長短繁簡とりどりの注釈)を施した現代版「百人一首」であり、通読すると歌で読む「日本文学史」にもなっている優れものです(^^)
上巻は、「春」「夏」「秋」「冬」の部を、下巻は、「賀」「哀傷」「旅」「離別」「恋」「雑」「釈教」「神祇」の部を収録しています。
さて、その他の異種百人一首としては、
日本人ならこれだけは知っておいて欲しい、近代100首を、当代随一の歌人が選び、心熱くなるエッセイとともに、未来へ贈る名歌集「近代秀歌」。
「近代秀歌」(岩波新書)永田和宏(著)
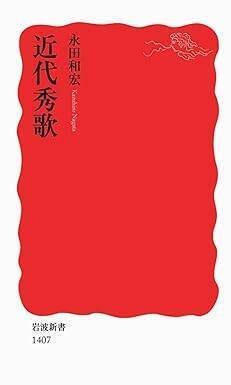
大好評を得た「近代秀歌」の続篇として、「今後100年読まれ続けて欲しい」、主として戦後の秀歌100首を編み、著者ならではの視座から、歌の現在を、そして未来を語る一冊「現代秀歌」。
「現代秀歌」(岩波新書)永田和宏(著)

明治から現代迄の100首以上の名歌を取り上げながら、人生という長い旅路の途中には、必ず節目となる瞬間が存在し、その時、たった31文字の言葉に勇気づけられたり、救われたりした自らの体験を、ふんだんに織り交ぜて綴った、心熱くなるエッセイ&短歌鑑賞入門「人生の節目で読んでほしい短歌」。
「人生の節目で読んでほしい短歌」(NHK出版新書)永田和宏(著)
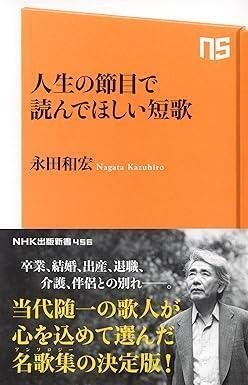
「文藝春秋」創刊90周年企画として、藤原定家が選んだ「小倉百人一首」の向こうを張って、近現代短歌の「新・百人一首」を編み、本書は、読者からの好評を受けてのその新書化「新・百人一首 近現代短歌ベスト100」。
「新・百人一首 近現代短歌ベスト100」(文春新書)岡井隆/馬場あき子/永田和宏/穂村弘(著)

百人百様の“生きた”幕末史を堪能することで、維新の別の一面が浮き彫りになる一冊「幕末百人一首」。
「幕末百人一首」(学研新書)菊地明(著)

歴史の本からは分からない、詠み人の人となりや、日本文化に深く根ざした、お茶の文化を垣間見ることができる一冊「茶の湯百人一首」。
「茶の湯百人一首」(淡交新書)筒井紘一(著)

本書は、中国人60人、日本人40人の古代から現代に及ぶ代表的な漢詩を精選し、和歌に影響を与えた漢詩文を、詩人独自の読みを附すと共に、詩句の由来や作者の経歴、時代背景などを紹介した「漢詩百首 日本語を豊かに」。
「漢詩百首 日本語を豊かに」(中公新書)高橋睦郎(著)

岡本かの子といえば、桜だけを題材にしたものすごい勢いの連作「桜百首」。
「桜」岡本かの子
これらの真・異種百人一首の向こうを張って、短歌表現を「詠んだ人」の視点と「読む」側の感覚を織り交ぜて、新or追体験させてくれる穂村弘さんが選ぶ何でもありの短歌ガチャ100の本書を真似て、
「短歌のガチャポン」穂村弘(著)

もう、なんでもありのマジカルな短歌ワールドを、とことん楽しみなが、考えさせられながら、近・現代短歌を中心に、百人一首選び(≒遊び)をしてみたので、お時間有れば、お立ち寄り下さい(^^♪
【第三章:新種四百人一首】
■序章:異種百人一首(100首)
「クラビクラと呼ばるるときを知らぬままふたつの窪みはみづを拒みぬ」
(佐藤せのか『西瓜』第六号より)
「ガラス器の無数の傷を輝かすわが亡きのちの二月のひかり」
(松野志保『われらの狩りの掟』より)
「音立てずスープのむときわがうちのみづうみふかくしづみゆくこゑ」
(菅原百合絵『たましひの薄衣』より)
「何度でもめぐる真夏のいちにちよまたカルピスの比率教えて」
(岡本真帆『水上バス浅草行き』より)
「鏡面に揺るる水銀 カデンツァのゆび砕くごと冬はゆくべし」
(金川宏『アステリズム』より)
「罪を知り海を知らないあの場所でかすかに揺れている水たまり」
(島楓果『すべてのものは優しさをもつ』より)
「重力に逆らって翔ぶ鳥の目よ 逆らふ者の美しい目よ」
(片岡絢『カノープス燃ゆ』より)
「水と塩こぼして暮らす毎日に水を買いたり祈りのごとく」
(辻聡之『あしたの孵化』より)
「庭から呼ぶ生きものの声あるような苔盛りあがる美しい冬」
(源陽子『百花蜜のかげりに』より)
「壺とわれ並びて佇てる回廊に西陽入りきてふたつ影伸ぶ」
(睦月都『Dance with the invisibles』より)
「〈青とはなにか〉この問のため失ひし半身と思ふ空の深みに」
(山中智恵子『喝食天』より)
「「とりかえしのつかない ことがしたいね」と 毛糸を玉に 巻きつつ笑う」
(穂村弘『ラインマーカーズ』より)
「「用意」から「ドン!」のあひだの永遠を生まれなかつたいのちがはしる」
(千葉優作『あるはなく』より)
「あはと消ゆる南のゆきのかろきをば降らせたやなうそなたがうへに」
(紀野恵『フムフムランドの四季』より)
「あやまちて野豚(のぶた)らのむれに入りてよりいつぴきの豚にまだ追はれゐる」
(石川信夫『シネマ』より)
「ある時は小さき花瓶の側面(かたづら)にしみじみと日の飛び去るを見つ」
(北原白秋『雲母集』より)
「うす青き朝の鏡にわが眉の包むにあまるかなしみのかげ」
(蒔田さくら子『秋の椅子』より)
「うつしみの手首にのこる春昼はるひるの輪ゴムのあとをふといとほしむ」
(小池光『サーベルと燕』より)
「うるほへる花群のごと人をりて揺れなまぬなり夏の朝を」
(高木佳子『玄牝』より)
「おだやかな眼差しかへすキリンたちいつも遠くが見えてゐるから」
「looking back at me
so calm, these giraffes
because
they can always see
such a distance」
(田中教子(翻訳:アメリア・フィールデン/小城小枝子)『乳房雲』より)
「おほかたの友ら帰りし構内に木の椅子としてわれを置きたし」
(澤村斉美『夏鴉』より)
「オルガンに灯る偽終止、頑張れば楽になるとふ属音ドミナントあはれ」
(濱松哲朗『翅ある人の音楽』より)
「きたる世も吹かれておらんコリオリの力にひずむ地球の風に」
(井辻朱美『コリオリの風』より)
「きみの指を離れた鳥がみずうみを開いていけば一枚の紙」
(平岡直子『みじかい髪も長い髪も炎』より)
「くちびるに迫る夕日のつめたさを海に告げたり海はわらふも」
(水原紫苑『さくらさねさし』より)
「クリスマス・ツリーを 飾る灯の 窓を旅びとのごとく 見てとほるなり」
(大野誠夫『薔薇祭』より)
「くれなゐを久遠に閉ざすかのごとく光をおびてゆくりんごあめ」
(門脇篤史『微風域』より)
「ゲットーの四角い窓から降る雪をみているもうすぐ永遠に留守」
(野樹かずみ『もうひとりのわたしがどこかとおくにいていまこの月をみているとおもう』より)
「こころとは見えぬ虚空の水仙の夏の没日に逃げ惑う蝶」
(正岡豊『白い箱』より)
「こんなにも ふざけたきょうが ある以上 どんなあすでも ありうるだろう」
(桝野浩一『てのりくじら』より)
「ささぶねの杭に堰かれてゆつくりと艫を捩らせ流れゆきたり」
(久保茂樹『ゆきがかり』より)
「セケン帝なる皇帝がいるらしいあの日の丸の赤の奥には」
(松木秀『Rera』より)
「そこにはだれもいないのにそこには詩人もいないのにそこにも白い」
(蝦名泰洋『ニューヨークの唇』より)
「それでいてシルクのような縦パスが前線にでる 夜明けはちかい」
(永井祐『広い世界と2や8や7』より)
「ダージリンティーにそえたる砂時計ひそかに吾のときを奪いぬ」
(野上卓『チェーホフの台詞』より)
「だいどこ、と呼ぶ祖母が立つときにだけシンクにとどく夕焼けがある」
(岡野大嗣『音楽』より)
「たくさんの空の遠さにかこまれし人さし指の秋の灯台」
(杉﨑恒夫『食卓の音楽』より)
「たましいを引きあげる手の静けさで記憶以前の場所に燃える火」
(古川順子『四月の窓』より)
「ともすればかろきねたみのきざし来る日かなかなしくものなど縫はむ」
(岡本かの子『かろきねたみ』より)
「どれほどの量の酸素に 包まれて眠るふたりか 無垢な日本で」
(小佐野彈『メタリック』より)
「なにとでも呼べる気持ちの寄せ植えにきみの名前の札をさしこむ」
(遠野サンフェイス『ビューティフルカーム』より)
「ね え見て よ この 赤 今後 見せ られる ことな いっすよ この量の 赤」
(木下龍也『玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだ』より)
「ノウミソガズガイノナカデサドウシテセカイハイミトコトバニミチテ」
(森本平『モラル』より)
「ベツレヘム。生まれてきてから知ることの遅さで届くこの遠花火」
(toron*『イマジナシオン』より)
「マッチ擦る つかのま海に 霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや」
(寺山修司『空には本』より)
「まひるまのひかり食べかけのポテトチップスに贅肉のごとき影なせり」
(西村美佐子『猫の舌』より)
「みづうみにあはくさしだすただむきのこの世にあれば桟橋と呼ぶ」
(黒田瞳『水のゆくへ』より)
「やはり<明日>も新鮮に来てわれわれはながい生活(たつき)の水底にゆく」
(三枝昻之『暦学』より)
「ゆうまぐれまだ生きている者だけが靴先を秋のひかりに濡らす」
(竹中優子『輪をつくる』より)
「わたくしの絶対とするかなしみも素甕に満たす水のごときか」
(築地正子『花綵列島』より)
「われを呼ぶ うら若きこゑよ 喉ぼとけ 桃の核ほど ひかりてゐたる」
(河野裕子『森のやうに獣のやうに』より)
「椅子に深く、この世に浅く腰かける 何かこぼれる感じがあって」
(笹川諒『水の聖歌隊』より)
「一枚の玻璃を挟みてそれを拭く男とわれと生計(たつき)ちがへり」
(今井聡『茶色い瞳』より)
「稲妻が海を巨いなる皮として打ち鳴らしたる楽の一撃」
(奥山心(NHK BS2「ニッポン全国短歌日和」 2010年10月24日放送分)より)
「雨にも眼ありて深海にジャングルに降りし記憶のその眼ずぶ濡れ」
(小島なお『サリンジャーは死んでしまった』より)
「下京区天使突抜(てんしつきぬけ) 雪晴れのさんぽはクノップフの豹をおともに」
(橘夏生『セルロイドの夜』より)
「海を見るような眼をわれに向け語れる言葉なべて詩となる」
(今井恵子『分散和音』より)
「街が海にうすくかたむく夜明けへと朝顔は千の巻き傘ひらく」
(鈴木加成太『うすがみの銀河』より)
「街をゆき 子供の傍を通るとき 蜜柑の香せり 冬がまた来る」
(木下利玄『紅玉』より)
「巻き上がる蔓に支柱の尽きたれば深さ果てなし天上の青」
(木下のりみ『真鍮色のロミオ』より)
「完璧のかたちさびしく照り映えてアル=ケ=スナンの製塩工場」
(安田茜『結晶質』より)
「簡単に生きてみるのは もう止めにするんだ 風が唸る屋上」
(山田航『水に沈む羊』より)
「逆立ちて視る風景よわたくしは芯まで熱き地球儀の脚」
(鈴木英子『鈴木英子集(淘汰の川)』より)
「襟元をすこしくづせり風入れておもふは汝(おまへ)かならず奪ふ」
(春日井建『友の書』より)
「月させば梅樹は黒きひびわれとなりてくひこむものか空間に」
(森岡貞香『白蛾』より)
「月わたる夜を思えば袋田の瀧双つ瀧赤くなりたし」
(佐佐木幸綱『アニマ』より)
「玄界灘の波濤めがけて走り出すともだちのいま生きている背中」
(鯨井可菜子『アップライト』より)
「言葉淡き地上にあれば手は常に強く握れと教えられたり」
(中沢直人『極圏の光』より)
「菜の花を摘めばこの世にあるほうの腕があなたを抱きたいという」
(山崎聡子『青い舌』より)
「坂道で鴇色となり燃え落ちる。午後、妹の髪を噛むとき」
(大橋弘『既視感製造機械』より)
「四万十に 光の粒をまきながら 川面をなでる 風の手のひら」
(俵万智『かぜのてのひら』より)
「子ども抱へし ボート難民の リアルなる渚を 思ふ冬の入口」
(馬場あき子『馬場あき子全歌集』より)
「自転車の後ろに乗ってこの街の右側だけを知っていた夏」
(鈴木晴香『夜にあやまってくれ』より)
「手套(てぶくろ)にさしいれてをりDebussyの半音に触れて生(なま)のままのゆび」
(河野美砂子『無言歌』より)
「初夏の空がどの写真にも写り込みどこかが必ず靑、海のよう」
(立花開『ひかりを渡る舟』より)
「人のかたち解かれるときにあおあおとわが魂は深呼吸せん」
(松村由利子『大女伝説』より)
「人生を やってることには なってるが あまりそういう 感じではない」
(工藤吉生『世界で一番すばらしい俺』より)
「生きるとは 死へ向かうこと 薄明は 部屋を青へと 染め上げていく」
(伊波真人『ナイトフライト』より)
「生きるとはなにか死ぬとは ハンドソープがわが手に吐きし白きたましい」
(北辻一展『無限遠点』より)
「前に出す脚が地面につくまへの、ふるはせながら人ら歩めり」
(山下翔『温泉』より)
「太陽は山上にあそぶ子供らを食べ鳥どもを食べてかくれぬ」
(松平修文『水村』より)
「地に降りて水へと戻る束の間の白きひかりを「雪」と呼び合う」
(本川克幸『羅針盤』より)
「朝おきて泡たてながら歯をみがくまだ人間のつもりで俺は」
(嵯峨直樹『神の翼』より)
「爪のない ゆびを庇って 耐える夜 「私に眠りを、絵本の夢を」」
(鳥居『キリンの子』より)
「冬木立高くそびゆる傍らに人はゆっくり時計のネジを巻く」
(清水あかね『白線のカモメ』より)
「透明な月球のごとき丸氷にバーボン注げば夏がきている」
(笹公人『終楽章』より)
「曇天のくもり聳ゆる大空に柘榴を割るは何んの力ぞ」
(浜田到『架橋』より)
「覗(のぞ)いてゐると掌(て)はだんだんに大きくなり魔もののやうに顔襲(おそ)ひくる」
(前川佐美雄『植物祭』より)
「白抜きの文字のごとあれしんしんと新緑をゆく我のこれから」
(安藤美保『水の粒子』より)
「薄明のままに明けない日のやうに卵の殻のやはらかな白」
「like the dim light
before day dawns
is
the soft whiteness
of this egg’s shell」
(紺野万里『星状六花』より)
「微生物ひきつれ弥陀はたたなづく青垣を越ゆしたしたと越ゆ」
(永井陽子『樟の木のうた』より)
「風。そしてあなたがねむる数万の夜へわたしはシーツをかける」
(笹井宏之『てんとろり』より)
「並び立つ書架にどよめく死者のこゑ樟のひかりにしずむ図書館」
(上村典子『草上のカヌー』より)
「防犯カメラは知らないだろう、僕が往きも帰りも虹を見たこと」
(千種創一『砂丘律』より)
「癒えること なきその傷が 癒えるまで 癒えるその日を 信じて生きよ」
(萩原慎一郎『滑走路』より)
「夕映えの原子炉一基にやわらかきイエローケーキが降るあさき夢」
(加藤英彦『プレシピス』より)
「葉桜の葉言葉は「待つ」三つ折りのメニューをお祈りみたいに閉じて」
(工藤玲音『水中で口笛』より)
「流灯に重なる彼の日の人間筏わが魂も乗りて行くなり」
(山口彊、Chad Diehl(訳)『And the River Flowed as a Raft of Corpses』より)
「恋ふは乞ふましろの梨の花のもと雨乞ふ巫女か白く佇ちたる」
(大沢優子『漂ふ椅子』より)
「眩むほど水かがやきぬ街を縫ふ細き流れを朝越ゆるとき」
(高野岬『海に鳴る骨』より)
■第一章:新種二百人一首(+100首)
「あの夏の数かぎりなきそしてまたたつたひとつの表情をせよ」
(小野茂樹『羊雲離散』より)
「黄昏にふるるがごとく鱗翅目ただよひゆけり死は近からむ」
(小中英之『わがからんどりえ』より)
「わがために塔を、天を突く塔を、白き光の降る廃園を」
(黒瀬珂瀾『黒耀宮』より)
「クリムトの金の絵の具のひと刷毛の一睡の夢をわれら生きたり」
(加藤孝男『十九世紀亭』より)
「晩夏光おとろへし夕 酢は立てり一本の瓶の中にて」
(葛原妙子『葡萄木立』より)
「蜜満ちてゆくガーデニア・ガーデンを等圧線は取り囲み 雨」
(錦見映理子『ガーデニア・ガーデン』より)
「おれの中の射殺魔Nは逃げてゆく街に羞(やさ)しい歌が溢れても」
(谷岡亜紀『臨界』より)
「カーテンのレースは冷えて弟がはぷすぶるぐ、とくしやみする秋」
(石川美南『砂の降る教室』より)
「十円じゃなんにも買えないよといえばひかって走り去る夏休み」
(盛田志保子『木曜日』より)
「フィルムに風をとどめて三脚はしずかに倒れる春の渚に」
(ひぐらしひなつ『きりんのうた。』より)
「透視図法の焦点となるかみしみのかなたにくらく森がにおえり」
(三枝浩樹『銀の驟雨』より)
「天使(エンジェル)の羽ならざれば温み持つ金具を外したる夕つ方」
(中澤系『uta 0001.txt』より)
「一切は烏有に帰する悦びへ火は立ち上がる逝く秋の野に」
(小笠原和幸『テネシーワルツ』より)
「抱き癖の大王イカを寝かしつけ僕を殺しに戻る細い腕」
(高柳蕗子『潮汐性母斑通信』より)
「下宿までいだく袋の底にして發火點いま過ぎたり檸檬」
(江畑實『檸檬列島』より)
「垂直線もて天頂と結ばるる夜にポロシャツをまとへるが我」
(浜田蝶二郎『からだまだ在る』より)
「文字ひとつ手紙から落ちとめどなく文字剥落し雪となり降る」
(西橋美保『漂砂鉱床』より)
「もろこしのおほき國原バーボンに古(ふ)るあめりかの霜の味はも」
(松原未知子『戀人(ラバー)のあばら』より)
「まぎれなく〈季〉うつろうと虎杖(いたどり)の群生ぬけて海にむかえり」
(西勝洋一『コクトーの声』より)
「光芒の水に折れゆく見てあれば調絃の音ほのかにきざす」
(今野寿美『花絆』より)
「集会のお知らせの壁に黄ばむ駅けむりのやうに汽車を降りれば」
(川野里子『太陽の壺』より)
「風の上に軌道はあらむひと方を指してすぎゆくひと群(むら)の星」
(資延英樹『抒情装置』より)
「目薬のつめたき雫したたれば心に開く菖蒲あやめむらさき」
(岡部桂一郎『一点鐘』より)
「星のなき空めざすごと玻璃濡れて無人エレベーター夜を昇りゆく」
(影山一男『空には鳥語』より)
「落下する骨と螢と石ころと見ているわれとモナドと神と」
(市原克敏『無限』より)
「乳母車押しゆく五月かたわらの花叢をはや過去となしつつ」
(花山多佳子『楕円の実』より)
「ざわめきは遠く聞きつつ街を出る内耳にふかき海を湛えて」
(山田消児『アンドロイドK』より)
「いま我は生(よ)のどのあたり とある日の日暮里に見し脚のなき虹」
(桑原正紀『月下の譜』より)
「純喫茶〈ミキちゃん〉出でたる路地裏に風太郎しんと尿(ゆまり)しており」
(島田修三『晴朗悲歌集』より)
「水瓶の形に水はひつそりと置かれてゐたり秋の門辺に」
(古谷智子『ガリバーの庭』より)
「いっせいに鳩が飛び立つシグナルの青あの部屋にブラウスを取りに」
(岡崎裕美子『発芽』より)
「うす霜の降りたる冷凍庫の奥の豚肉(ポーク)やさしくたたまれてある」
(阪森郁代『ナイルブルー』より)
「たすけて枝毛姉さんたすけて西川毛布のタグたすけて夜中になで回す顔」
(飯田有子『林檎貫通式』より)
「針先は蟻酸したたり濡れながらくまん蜂ひとつ空よりくだる」
(恩田英明『白銀乞食』より)
「あはあはとあはいあはひをあはせつつうたひあひゐるしやぼん玉はも」
(由季調『互に』より)
「ガーゼ切り刻みたるごと散るさくらわがてのひらのまほろばに来よ」
(杉森多佳子『忍冬(ハネーサックル)』より)
「ブイ揺れて取り残さるる夏蝶を喩となす前に君に差し上ぐ」
(棚木恒寿『天の腕』より)
「あふぎつつ泥濘ゆけば空のまほ水のきはかと思(も)ふひかりあり」
(池田はるみ『奇譚集』より)
「オカリナに口づけせしごと冷ややかに朝(あした)は白き光放てり」
(花山周子『屋上の人屋上の鳥』より)
「人生を乗せいる電車ひとすじの光の詩形そこに射しこむ」
(大滝和子『竹とヴィーナス』より)
「せんせいのおくさんなんてあこがれない/紺ソックスで包むふくらはぎ」
(野口あや子『くびすじの欠片』より)
「カフェの壁あまりに白しエンダイヴこの苦さこそわれを在らしむ」
(尾崎朗子『蝉観音』より)
「食べてゐてふと明るさに気がつきぬわが負ふ影のなかより見つむ」
(天草季紅『青墓』より)
「晴れ上がる銀河宇宙のさびしさはたましいを掛けておく釘がない」
(杉崎恒夫『パン屋のパンセ』より)
「澄むものと響きあいたるあきあかね君の頭上を群れて光れり」
(遠藤由季『アシンメトリー』より)
「粥を食みつゆさきほどの時間さへとりもどせねば粥どこへおつ」
(渡辺松男『蝶』より)
「真青なる空とびてゆくしろたへのはくてうの羽の暗き内がは」
(本田一弘『眉月集』より)
「思ひきり苦いやさうは刻み込むどれつしんぐのはるさらだなる」
(川崎あんな『エーテル』より)
「こもりぬのそこの心に虹たちてあふれゆきたり夢の青馬」
(江田浩司『まくらことばうた』より)
「よみがえるこころ、車窓を信号機のうつくしく過りゆく転瞬を」
(内山晶太『窓、その他』より)
「あくびする口ひとまはり大きくなり猫はおのれをいま脱がむとす」
(花鳥佰『しづかに逆立をする』より)
「生者死者いづれとも遠くへだたりてひとりの酒に動悸してをり」
(真中朋久『エフライムの岸』 より)
「自閉する日々にも秋の降るように惑星(ほし)は優しく地軸を傾ぐ」
(法橋ひらく『それはとても速くて永い』より)
「岸にきてきしよりほかのなにもなくとがびとのごと足をとめたり」
(吉田隼人『忘却のための試論』より)
「通らない時にもレールがあることの表面に降り濡れてゆく雨」
(相原かろ『浜竹』より)
「夏すべて壊れものなり指先に切子の波は鋭く立ちて」
(宮川聖子『水のために咲く花』より)
「ああここにも叫び続けるものがゐるほどけつつある靴紐たち」
(惟任将彦『灰色の図書館』より)
「湖の底に沈みし銀の匙魚知らざるや背に秋の光(かげ)」
(井上孝太郎『サバンナを恋う』より)
「今日もまた前回までのあらすじを生きているみたい 雨がやまない」
(鈴木美紀子『風のアンダースタディ』より)
「太陽へあなたの傘を広げれば昨日の午後の雨がにほへり」
(熊谷純『真夏のシアン』より)
「手羽先にやはり両手があることを骨にしながら濡れていく指」
(山階基『風にあたる』より)
「とある朝クリーム色の電話機に変化(へんげ)なしたり受付嬢は」
(本多真弓『猫は踏まずに』より)
「水に書く言葉に似たるこの生をマルクス=アウレリウスも生きしと想へば」
(鷺沢朱理『ラプソディーとセレナーデ』より)
「三百頭のけもののにおいが溶けだして雨は静かに南瓜を洗う」
(白井健康『オワーズから始まった。』より)
「笑つてはいけない、いけない 眉検査に前髪を切り貼りつけて来ぬ」
(桜川冴子『キットカットの声援』より)
「この街にもつと横断歩道あれ此岸に満つるかなしみのため」
(田村元『北二十二条西七丁目』より)
「キャベツ色のスカートの人立ち止まり風の匂いの飲み物選ぶ」
(竹内亮『タルト・タタンと炭酸水』より)
「ああみんな来てゐる 夜の浜辺にて火を跳べば影ひるがへりたり」
(梶原さい子『リアス / 椿』より)
「ぬばたまの黒醋醋豚を切り分けて闇さらに濃く一家團欒」
(堀田季何『惑亂』より)
「イチモンジセセリ一頭の重さあり指に止まりて羽ばたく須臾に」
(春野りりん『ここからが空』より)
「ぼろぼろと光を零してはつ夏のきゅうりを交互に囓りあう朝」
(柴田葵『母の愛、僕のラブ』より)
「変わりたいような気がする廃屋をあふれて咲いているハルジオン」
(北山あさひ『崖にて』より)
「シンクへと注ぐ流れのみなもとの傾きながら重なるうつわ」
(嶋稟太郎『羽と風鈴』より)
「ていねいな暮らしに飽きてしまったらプッチンプリンをプッチンせずに」
(水野葵以『ショート・ショート・ヘアー』より)
「少女期のしめりを帯びし手のひらに十薬の白ほのかににほふ」
(小野りす「庭」『西瓜』第八号より)
「患いて街を離れたわたくしをやさしく照らすヤコブの梯子」
(澤本佳步『カインの祈り』より)
「山鳥の骸をうづめ降る雪のきらら散らして白き扇は」
(渡邊新月「楚樹」より)
「カーブする数秒間を照らされて蕾のようにひらく左眼」
(早月くら「ハーフ・プリズム」より)
「電車から駅へとわたる一瞬にうすきひかりとして雨は降る」
(薮内亮輔「花と雨」より)
「お互ひに聞かぬ言はぬの距離ながら白露の萩に解けてゐたり」
(中西敏子『呼子』より)
「「smileの綴りはスミレとおぼえてた」どうりでそんなふうに微笑む」
(西村曜『コンビニに生まれかわってしまっても』より)
「人はみな馴れぬ齢を生きているユリカモメ飛ぶまるき曇天」
(永田紅『日輪』より)
「つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」
(在原業平『古今和歌集』巻16哀傷歌861より)
「五分ほど遅れてをれば駅ごとに日本の車掌は深く深く詫ぶ」
(齋藤寛『アルゴン』より)
「頭とは何ぞと問ふにジャコメッティ端的に応ふ胸の付け根」
(玉城徹『われら地上に』より)
「ふるさとはハッピーアイランドよどみなくイエルダろうか アカイナ マリデ」
(鈴木博太「ハッピーアイランド」『短歌研究』2012.09より)
「ふと思ふ我を見守るあたたかき心に気附かず過ぎしことあらむ」
(安立スハル『この梅生ずべし』より)
「人間はひとつの不潔なる川と靠(もた)るる窓に夕茜燃ゆ」
(阿木津英『天の鴉片』より)
「歌数首読みて心の静まれば銀のくさりを引きて灯を消す」
(田附昭二『造化』より)
「元気よくおりこうさんの返事するニュースの子ども 子どもは窮屈」
(細溝洋子『コントラバス』より)
「黙ることは騙すことではないのだと短い自分の影踏みながら」
(山本夏子「スモックの袖」/「現代短歌」2018年7月号より)
「白磁器にたまるうすら陽かなしがり方のしずかなひとに寄りゆく」
(中田明子「Ammonite」『砦』,2021.11より)
「モロヘイヤいくつあってもモロヘイヤこの夏幸せなモロヘイヤ」
(吉田奈津「短歌研究」2015年9月号より)
「水鳥のからだのなかに水平を保てる水のあり冬の空」
(永田和宏『日和』より)
「新しき黒もて黒を塗りつぶす分厚くわれの壁となるまで」
(大西民子『雲の地図』より)
「われはわれにてなお何ならむ焦がるれば夜の稲妻膝照らすなり」
(李正子『ナグネタリョン』より)
「海を過去、空をその他とおもひつつ海上飛べる鷗見てをり」
(原賀瓔子『星飼びと』より)
「地下のバー酔ひやすくして己が手に残る時間を人ら埋(う)もるる」
(篠弘『凱旋門』より)
「トンネルをいくつも抜けて会いにゆく何度も生まれ直して私は」
(藤田千鶴『貿易風(トレードウインド)』より)
「見せあうものは悲しみのたぐい黒衣きて雪野を遠く来る人に逢う」
(百々登美子『盲目木馬』より)
■第二章:新種三百人一首(+100首)
「ああ夕陽 明日のジョーの明日さえすでにはるけき昨日とならば」
(藤原龍一郎『夢見る頃を過ぎても』より)
「白き霧ながるる夜の草の園に自転車はほそきつばさ濡れたり」
(高野公彦『汽水の光』より)
「廃村を告げる活字に桃の皮ふれればにじみゆくばかり 来て」
(東直子『春原さんのリコーダー』より)
「照りかげる砂浜いそぐジャコメッティ針金の背すこしかがめて」
(加藤克巳『球体』より)
「道の端にヒールの修理待つあいだ宙ぶらりんのつまさきを持つ」
(沖ななも『衣裳哲学』より)
「蒼穹に重力あるを登攀のまつ逆さまに落ちゆくこころ」
(本多稜『蒼の重力』より)
「リバノールにじんだガーゼのようだから糸瓜の花をあなたの頬に」
(入谷いずみ『海の人形』より)
「落胆はうすかげの射す目に顕ちて煮くづれをして沈む大根」
(桝屋善成『声の伽藍』より)
「ゆふぞらにみづおとありしそののちの永きしづけさよゆうがほ咲(ひら)く」
(小島ゆかり『月光公園』より)
「水の面にはなびらはのりはなびらの運ばるるゆゑみづぞ流るる」
(喜多昭夫『夜店』より)
「風鈴を鳴らしつづける風鈴屋世界が海におおわれるまで」
(佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』より)
「ビル抱く暗き淵よりせりあがり観覧車いま光都(くわうと)を領(し)れり」
(沢田英史『異客』より)
「たましいの年はいまだおさなくてふたり手をふる異国の船に」
(里見佳保『リカ先生の夏』より)
「胸もとに水の反照うけて立つきみの四囲より啓(ひら)かるる夏」
(横山未来子『樹下のひとりの眠りのために』より)
「雑然たる日々のすきまに見えきたる光の如く年を迎うる」
(高安国世『光の春』より)
「サンチョ・パンサ思ひつつ来て何かかなしサンチョ・パンサは降る花見上ぐ」
(成瀬有『遊べ、櫻の園へ』より)
「手でぴゃっぴゃっ/たましいに水かけてやって/「すずしい」とこえ出させてやりたい」
(今橋愛『O脚の膝』より)
「口が口を食ふかなしさよ丸干しのいわし食ひたりまづあたまから」
(大松達知『フリカティブ』より)
「髪の毛のかかる視界でこの町を見ていたのびていくあいだじゅう」
(本田瑞穂『すばらしい日々』より)
「剃刀をつつみながらにみづ流れちかくの苑にねむるくちなは」
(多田零『茉莉花のために』より)
「どんぶりに桜花(あうくわ)をもりて塩ふりぬ朝焼け激しき食卓なれば」
(仙波龍英『墓地裏の花屋』より)
「象さんの鼻となりたるわが弓手(ゆんで)背には殺意の馬(め)手遊ばする」
(内藤明『壺中の空』より)
「薄き血の色のマニュキュア愉しまん誰にも気付かれないそのことも」
(十谷あとり『ありふれた空』より)
「娘の肩の蝶結びほどけばぱたぱたと蝶は逃げゆき子と秋老いぬ」
(塩野朱夏『そして彼女は眼をひらいた』より)
「モルヒネに触れたる手紙読むときに窓の湛える水仙光よ」
(山下泉『光の引用』より)
「茹で加減よろしきパスタ半分こ模様のちがふ皿に移しぬ」
(高木孝『地下水脈』より)
「天地のちとおもしろきいそうろうとこの身思えば手足鮮し」
(鹿野氷『クロス』より)
「つり革にのぞく少女の切れかけた生命線が吸ふ晩夏光」
(日置俊次『ノートルダムの椅子』より)
「手の甲に試し塗りする口紅を白い二月の封緘として」
(兵庫ユカ『七月の心臓』より)
「留守番の妻の声聞くつまらなさ辻褄合わせのメッセージ入れる」
(小塩卓哉『樹皮』より)
「われのみが内臓をもつやましさは森の日暮れの生臭きまで」
(なみの亜子『鳴』より)
「日を葬(はふ)りざぶんと蒼きゆうぐれにこの世の橋が浮かびあがりぬ」
(白瀧まゆみ『自然体流行』より)
「休日の鉄棒に来て少年が尻上がりに世界に入って行けり」
(佐藤通雅『水の涯』より)
「駆けて逃げよわが血統は短距離馬かわされざまに詠むな過去形」
(小嵐九八郎『叙事がりらや小唄』より)
「空の樹の水の祈りを聴きとむるかなしみの瞳(め)のしづかなる耳」
(櫟原聰『光響』より)
「身のうちにみづかねといふ蝕あるを思ふゆふべの『テレーズ・ディケイルー』」
(有沢螢『朱を奪ふ』より)
「石段の段の高さに刻まれて降りてゆきたり手に抱え持ち」
(高橋みずほ『フルヘッヘンド』より)
「ぐじやぐじやの世界の上に日は照りて植物相(フロラ)は次なる時にそなふ」
(酒井佑子『矩形の空』より)
「右の手を夜にさし入れてひきいだすしたたる牡蠣のごとき時計を」
(鳴海宥『BARCAROLLE [舟唄]』より)
「真白の光を作るため青きセロファンを挿す この視界にも」
(中島裕介『Starving Stargazer』より)
「アボカドの種子に立てる刃 待つといふ時間はひとを透き通らせる」
(森井マスミ『ちろりに過ぐる』より)
「ししむらを借りてたましひ傷めるをさくらまばゆき闇に還さむ」
(関口ひろみ『あしたひらかむ』より)
「ゆふぐれの背にまたがりて駆けてゆくきのふの街に手をふりながら」
(鎌倉千和『ゆふぐれの背にまたがりて』より)
「おたがいの母語に訳して聴いてみるおのまとぺいあミュンヘンは雨」
(光森裕樹『鈴を産むひばり』より)
「影重く垂らしてきみに逢いにゆく花に牙ある夕暮れ時を」
(柳澤美晴『一匙の海』より)
「咲きみちて一枝の花も散らざれば手触れむほどに過ぎてゆく時」
(桜木由香『連祷』 より)
「羽ばたけるせつなひかりを零しけり天に属する若きかもめら」
(藤沢蛍『時間(クロノス)の矢に始まりはあるか』より)
「ゆふぐれの庭に佇つ犬尾を振れりわれに見えざるものに向ひて」
(徳高博子『ローリエの樹下に』より)
「少年はあをきサロンをたくしあげかち渡り行く日向(ひなた)の河を」
(前田透『漂流の季節』より)
「夕暮れが日暮れに変わる一瞬のあなたの薔薇色のあばら骨」
(堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』より)
「海沿いのちいさな町のミシン屋のシンガーミシンに砂ふりつもる」
(久野はすみ『シネマ・ルナティック』より)
「みぬちなる音盤(ディスク)は風にほどけゆき雪ふる空のあなたへ還る」
(紀水章生『風のむすびめ』より)
「あるときは斜めに生きておもしろし御笠の川みず浅く流れる」
(山中もとひ『〈理想語辞典〉』より)
「夏さびて知らぬふりする月の頃ピアスをもとな揺らす間夜(あひだよ)」
(廣庭由利子『ぬるく匂へる』より)
「秋はひとりまぶたをとじて耳を澄ます 雨のなかに隠した音楽」
(安井高志『サトゥルヌス菓子店』より)
「盆踊り同じ高さにそよぐ手の上(へ)をわたりゆく魂のあるべし」
(芹澤弘子『ハチドリの羽音』より)
「さるすべり炎天にひらく形にて暗くよぢれる臓物(わた)もつわれら」
(楠誓英『禽眼圖』より)
「はすかひに簷(のき)の花合歓(ねむ)うつしつつ化粧鏡は昏(く)れのこりたり」
(明石海人『明石海人歌集』より)
「星ひとつ滅びゆく音、プルタブをやさしく開けてくれる深爪」
(田丸まひる『ピース降る』より)
「約束はひとつもなくて日傘をささず帽子をかぶらずに行く炎天下」
(黒﨑聡美『つららと雉』より)
「みづの上(へ)に青鷺ひとつ歩めるを眼といふ水にうつすたまゆら」
(藪内亮輔『海蛇と珊瑚』より)
「ひと雨に花となりゆく六月の杳き眼をしたぼくのそれから」
(窪田政男『汀の時』より)
「失った時間をチャージするためにサービスエリアがあるたび止まる」
(九螺ささら『ゆめのほとり鳥』より)
「測量士冬に来たりかぎりなき雪上に紙上の文字を重ぬる」
(高石万千子『外側の声』より)
「花の名を封じ込めたるアドレスの@のみずたまり越ゆ」
(杉谷麻衣『青を泳ぐ。』より)
「人を待ち季節を待ちてわが住むは昼なお寂し駅舎ある町」
(阿部久美『ゆき、泥の舟にふる』より)
「大いなる今をゆっくり両肺に引き戻しつつのぼる坂道」
(五島諭『緑の祠』より)
「傘を盗まれても性善説信ず父親のような雨に打たれて」
(石井僚一「父親のような雨に打たれて」より)
「ピンホールカメラを覗くごと新国立美術館建つ夕暮れにうかびて」
(西五辻芳子『金魚歌へば』より)
「まぶしいものに近づいてみる近づいて舗道の上に柿はひしゃげる」
(阿波野巧也『ビギナーズラック』より)
「西の方角(かた)へ一滴ひかるあれは海掌(て)にひとかけらトパズのせゐて」
(浦上和子『根府川』より)
「目を閉じた人から順に夏になる光の中で君に出会った」
(木下侑介『君が走っていったんだろう』より)
「心とはそれより細きひかりなり柳がくれに流れにし蛍」
(増田まさ子、合同歌集『恋衣』より)
「さらさらとさみしき冬日 花の茎ゆはへて水にふかくふかく挿す」
(木下こう『体温と雨』より)
「出窓からこぼれるようにゆるやかに揺らめく冬の床の陽光」
(永井駿「迷信」『西瓜』第七号より)
「二塁手になるはずだったマスターがシェーカーを振る腕の残像」
(中井スピカ『ネクタリン』より)
「費やした年月だけがぼくならば ぶあついパンケーキを縦に裂く」
(からすまぁ「春風に備えて」より)
「白壁にあかく日の差す丁字路の突きあたりまであゆみつつをり」
(川本浩美『起伏と遠景』より)
「ドアを出づ、―― 秋風の街へ、 ぱつと開けたる巨人の口に飛び入るごとく。」
(土岐哀果『黄昏に』より)
「ぼくはぼくを生きるほかなく沸点を越えてゆらめく水を見つめる」
(西巻真『ダスビダーニャ』より)
「どこにでもある不安なりペンに書く文字をゆがめてブルーブラック」
(久我田鶴子『雀の帷子』より)
「今日の水は流れいるかと問う我に年々異なる者が答える」
(長谷川富市『水の容体』より)
「とりあへず「括弧」でくくりかなしみの方程式は解かずに置かう」
(豊島ゆきこ『りんご療法』より)
「身をひとつ左へゆるい坂道にめぐらせゆけばそこが海です」
(大久保春乃『まばたきのあわい』より)
「白き雲流れゆくなり 雲梯を這って渡ったこと一度ある」
(野田光介『半人半馬』より)
「ではなく雪は燃えるもの・ハッピー・バースデイ・あなたも傘も似たようなもの」
(瀬戸夏子『そのなかに心臓をつくって住みなさい』より)
「見ゆるもの見ゆるまま描け目から手はぢれったく月のごとく遠かり」
(笹谷潤子『夢宮』より)
「アラームの鳴る一分前に目覚めればその六十秒を抱きて眠る」
(和嶋勝利『天文航法』より)
「めだま焼き片目ながれて涙目の朝には軽い出社拒否症」
(大井学『サンクチュアリ』より)
「人を傷(いた)めぬよき子になれと中の子の広き額を撫でてをりたり」
(宮柊二『日本挽歌』より)
「真剣に聞くとき自分をぼくという君の背筋のあたたかい月」
(山内頌子『うさぎの鼻のようで抱きたい』よち)
「一斉にはばたく音に振り向けばいま満ちてゆく木蓮の花」
(樋口智子『幾つかは星』より)
「十代の自分を恋えりローリング・ストーンズ聞いて幸せだった」
(川本千栄『樹雨降る』より)
「新しく求めし傘がこの町に大きすぎたと思って歩く」
(吉村明美『HAFU』より)
「コロッケを肉屋に買ひて歩みつつ少年の日のよろこびを食ふ」
(柳宣宏『施無畏』より)
「うぬぼれていいよ わたしが踵までやわらかいのはあなたのためと」
(佐藤真由美『恋する歌音』より)
「一匹の孤狼であれば聴こえぬか風よ悲傷のマンドリンはや」
(福島泰樹『柘榴盃の歌』より)
「湯の中に塩振りながら ブロッコリーお前程いさぎよき緑になれたら」
(文屋亮『月ははるかな都』より)
「あせたる を ひと は よし とふ びんばくわ の ほとけ の くち は もゆ べき もの を」
(会津八一『鹿鳴集』より)
「燠のごときひかりと思うガラス戸に身をつけて見る闇の海の灯」
(武川忠一『秋照』より)
■第三章:新種四百人一首(+100首)
「いる筈のなきものたちを栗の木に呼びだして妹の意地っ張り」
(平井弘『顔をあげる』より)
「木曜の夕べわたしは倦怠を気根のように垂らしてやまず」
(早川志織『種の起源』より)
「形容詞過去形教へむとルーシーに「さびしかった」と二度言わせたり」
(大口玲子『海量(ハイリャン)』より)
「ポール・ニザンなんていうから笑われる娘のペディキュアはしろがねの星」
(小高賢『本所両国』より)
「酢のなかでゆっくりと死ぬ貝類の声聞く七月某日真昼」
(村上きわみ『fish』より)
「歳月は餐をつくして病むもののかたへに季節(とき)の花を置きたり」
(中山明『愛の挨拶』より)
「わたしたちはなんて遠くへきたのだろう四季の水辺に素足を浸し」
(佐藤りえ『フラジャイル』より)
「さまよえる夢のおわりを棄てるとき飛沫があがる砂嘴 (さし) の向こうに」
(小林久美子『恋愛譜』より)
「死者はうたふあかときの窓むらさきのそのむらさきの葡萄のしづく」
(寺井淳『聖なるものへ』より)
「罎の内側から見ると恋人は救世主(メシア)のやうに甘く爛れて」
(魚村晋太郎『銀耳』より)
「白壁の一本の罅たどりつついのちのやぶれ目を見てゐたる」
(林和清『木に縁りて魚を求めよ』より)
「昼つ方先祖の墓の苔むして瓶のなか万緑のみづ燃ゆ」
(田中富夫『曠野の柘榴』より)
「睾丸に似たる蘭の実脆ければスプーンで神を掬い難きか」
(菊池裕『アンダーグラウンド』より)
「ワン・タッチの傘をひろげてゆかむかな男の花道には遠けれど」
(吉岡生夫『勇怯篇 草食獣・そのIII』より)
「仄暗き骨のあいだを子は駆ける窓に桜の揺らす日を踏み」
(吉野亜矢『滴る木』より)
「きみの脚の骨をそろりと抜き取つてうすあおいろに染めたきゆふべ」
(大津仁昭『海を見にゆく』より)
「〈時〉翳る半球のかなた血のごとく鯉沈みゐる小さき国よ」
(米川千嘉子『一夏』より)
「暁(あけ) 死してねむるわが裡(うち)こうこつと霜ふれり霜ふりの牛肉(ビーフ)に」
(下村光男『少年伝』より)
「水鳥のつばさを奪ふ シャッターを切りて時空の網を放てり」
(目黒哲朗『CANNABIS』より)
「髣髴(ケシキ)顕(タ)つ。速吸(ハヤスヒ)の門(ト)の波の色。年の夜をすわる畳のうへに」
(釈迢空『海やまのあひだ』より)
「ずぶ濡れの俺の背中に夕星が輝くという嘘を悲しむ」
(吉田純『形状記憶ヤマトシダ類』より)
「とぶ鳥を視をれば不意に交じりあひわれらひとつの空のたそがれ」
(柏原千恵子『七曜』126号より)
「独房の闇なき夜の壁際に光源のごとカサブランカ咲く」
(重信房子『ジャスミンを銃口に』より)
「多武峰もみぢしづかに燃ゆるいろたまゆらあそべ父のいのち火」
(一ノ関忠人『群鳥』より)
「メスにより切り啓(ひら)かれた空間にきょうも漂う船は一艘」
(光栄堯夫『空景』より)
「廃されし管制塔まで書きに行き詩を放つとき世界は眠り」
(八木博信『フラミンゴ』より)
「ヤマト糊のたましひ失せて初恋の秘蔵写真が剥がれ落ちたり」
(小泉史昭『ミラクル・ボイス』より)
「ピカソ展見終えて濠に光あり静かに充ちてわが日々を撃て」
(大島史洋『時の雫』より)
「十指とふこの十全なかたちのゆゑにかなしみのくる秋の食卓」
(笹原玉子『われらみな神話の住人』より)
「文鳥の胸の真白をかきやれば暗紫(くらむらさき)の肉の色もつ」
(伊津野重美『紙ピアノ』より)
「くあとろとやわらかくなるキーボードぼくらの待っているのは津波」
(加藤治郎『ハレアカラ』より)
「腐りたるトマトを捨てし昨日のことふと思い出す地下鉄に乗り」
(吉野裕之『空間和音』より)
「今日よりは蝶の受胎の日に入りぬ寒青葱の水染む緑」
(佐竹彌生『天の螢』より)
「沈むとき上下にくらくゆれたりし飯の茶碗を思うときあり」
(上野久雄『夕鮎』より)
「腰のリボン蝶々結びにしてやれば夏の道へと攫われやすし」
(前田康子『色水』より)
「苦しみて花咲かすべし夕闇のなか垂直に木蓮光る」
(大谷雅彦『白き路』より)
「花々に/眼のある夜を晩年の/父あらはれて/川渉りゆく」
(辺見じゅん『闇の祝祭』より)
「わたくしの夕暮れてゆく街にある影といふ名の数多のimages(いまあじゆ)」
(中川宏子『いまあじゆ』より)
「あめつちはいちにんのため季(とき)を繋(と)めくろき扇に撒かれし雲母」
(須永朝彦『定本須永朝彦歌集』より)
「八月の雨てのひらに受けてゐる誰にも属してをらぬ冷たさ」
(黒田和美『六月挽歌』より)
「ブーストを立ち上がらせつつ走りゆく前にも後にも時間はなくて」
(永田淳『1/125秒』より)
「ああマトリョーシカ開ければ無上なる怖さ 人より出でてまた人となる」
(浦河奈々『マトリョーシカ』より)
「おごそかなダンスに雪は生まれおり輝きはあれ午後の世界に」
(田中濯『地球光』より)
「しろき円をたもちて皿は暮れなづみ卓は卓として四方へとがる」
(菊池孝彦『声霜』より)
「目をあけてみていたゆめに鳥の声流れこみ旅先のような朝」
(雪舟えま『たんぽるぽる』より)
「一滴の青を落としてわが画布にはばたく鳥の羽を弑(しい)する」
(寺島博子『王のテラス』より)
「あれは明日発つ鳥だろう 背をむけて異境の夕陽をついばんでいる」
(岩尾淳子『眠らない島』より)
「南北の極ありて東西の極なき星で煙草吸える少女の腋臭甘く」
(フラワーしげる「ビットとデシベル」より)
「驟雨ななめにまちを疾りて匂ひたつ魂ぞしとど〈歓喜(ジョイ)〉てふ」
(大和志保『アンスクリプシオン』より)
「姉であることを忘れるウエハースひとひら唇に運んでもらう間」
(天道なお『NR』より)
「箸茶碗こともなく持ち両の手の互に知らぬ左右の世界よ」
(照屋眞理子『恋』より)
「禽肉(とりにく)はすでに死屍たる冷(ひえ)持てばまばたきもせず銀の塩振る」
(山口雪香『白鳥姫』より)
「碧釉漣紋器(へきいうれんもんき) 青をたどればしづかなる縁の乱るるひとところあり」
(経塚朋子『カミツレを摘め』より)
「縦向きの見本見ながら横向きに落ちてくるのを待つ缶コーヒー」
(蒼井杏『瀬戸際レモン』より)
「歩道橋越えても踏切渡つてもだれかの家の前に行きつく」
(橋場悦子『静電気』より)
「もうここへやってきている夕映えの手首まで塗るハンドクリーム」
(笠木拓『はるかカーテンコールまで』より)
「透明になる過程が見たい紙一重というところが見たい」
(宮崎信義『地に長き』より)
「なだらかに底を見せたる泥の上を鷺は歩めり影揺らしつつ」
(西川啓子『ガラス越しの海』より)
「バス停がバスを迎えているような春の水辺に次、止まります」
(𠮷田恭大『光と私語』より)
「月までを数秒で行く君の名のひかりと呼べばはつ夏の空」
(五十子尚夏『The Moon Also Rises』より)
「本当に愛されてゐるかもしれず浅ければ夏の川輝けり」
(佐々木実之『日想』より)
「月草のうつろふ時間たぐり寄せたぐり寄せつつゆく京の町」
(黒田京子『揺籃歌』より)
「刻々と報道される事実より吾は信じる線路の勾配」
(勺禰子『月に射されたままのからだで』より)
「親指はかすかにしずみ月面を拓くここちで梨を剥く夜」
(國森晴野『いちまいの羊歯』より)
「日の落ちてわづかに残すあかねいろの千切れ雲見ゆ旅の車窓に」
(服部崇『ドードー鳥の骨』より)
「火の粉ふり払う消防夫の如く螢の夜から出でし少年」
(中山俊一『水銀飛行』より)
「生と死を量る二つの手のひらに同じ白さで雪は降りくる」
(中畑智江『同じ白さで雪は降りくる』より)
「目覚むればこの世の果てより曳ききたる光はよわく落花にのこる」
(三島麻亜子『水庭』より)
「天降(あも)りくる光の無量か載りてゐむ天秤かたむくガラス戸の内」
(永守恭子『夏の沼』より)
「開けっ放しのペットボトルを投げ渡し飛び散れたてがみのように水たち」
(近江瞬『飛び散れ、水たち』より)
「ここはしづかな夏の外側てのひらに小鳥をのせるやうな頬杖」
(荻原裕幸『リリカル・アンドロイド』より)
「水たまりに光はたまり信号の点滅の青それからの赤」
(宇都宮敦『ピクニック』より)
「琥珀色の宝石みたいな水ぶくれ 七回撫でたらちょっとだけ秋」
(上坂あゆ美『老人ホームで死ぬほどモテたい』より)
「ありうべき光をさがす放課後のあなたはたぶん詩の書架にいる」
(塩見佯「図書館の午後」『西瓜』第八号より)
「細やかに組み立てられたランドリーラックを壊す夏のゆふぐれ」
(岡本恵「結束」『西瓜』第六号より)
「透き至るものの綺麗さはなちつゝ立つ空き瓶のゆふぐれは あき」
(川﨑あんな『triste』より)
「ひそやかに語る女生徒ふたりいて渡り廊下は校舎の咽喉(のみど)」
(山田恵理『秋の助動詞』より)
「リヤドロの陶器人形たおやかに諫死しており書架のくらみに」
(吉村実紀恵『バベル』より)
「立つわたし、いきなり語り出すわたし ウラル=アルタイ語圏のわたし」
(田中槐『ギャザー』より)
「ふららこという語を知りてふららこを親しく漕げば春の夕暮」
(大下一真『月食』より)
「最後まで話さなくていいカーテンに染みこませておく君の悩みは」
(野村まさこ『夜のおはよう』より)
「あと何を買ったら僕の人生は面白くなり始めるのかな」
(辻井竜一『遊泳前夜の歌』より)
「救ひなき裸木と雪の景果てし地点よりわれは歩みゆくべし」
(中城ふみ子『乳房喪失』より)
「人として生れたる偶然を思ひをり青竹そよぎゐる碧き空」
(志垣澄幸『日月集』より)
「ひとり酌む新年の酒みづからに御慶(ぎよけい)を申す(すこしは休め)」
(岡井隆『神の仕事場』より)
「やさやと生存圏を拡げつつ浮かぶや宙に愛のピカチュウ」
(上條素山「外大短歌第7号」より)
「空の海にさらはれたりや飛行船 五月の空は底なしの青」
(竹内由枝『桃の坂』より)
「ああ、博士 まるでひとりの島みたいどこまでも心が浜になる」
(瀬口真司「天使給電篇」『いちばん有名な夜の想像にそなえて』)
「『「いい人」をやめると楽になる』…本を戻して書店を出づる」
(平林静代『雨水の橋』より)
「地湧の菩薩として僧俗和合で〔魔の所為〕を砕滅する」
(森山光章『句集〔法華折伏破権門理〕、喜悦のみがある』より)
「霞立つながき春日に子供らと手毬つきつつこの日暮らしつ」
(良寛『良寛歌集』より)
「ねむりつく方法みつけられなくてあるだけ莢の豆はじきだす」
(青柳守音『風ノカミ』より)
「花束を買ふよろこびに引きかえて渡す紙幣はわづかに二枚」
(北沢郁子『夢違』より)
「一年に十分の時を先に行く居間の時計にわれの従ふ」
(吉田直久『縄文の歌人』より)
「後ろより誰か来て背にやはらかき掌を置くやうな春となりゐつ」
(稲葉京子『宴』より)
「キッチンは逆立ちしてもいいところ君もケチャップ我もケチャップ」
(大谷ゆかり『ホライズン』より)
「パブロ・ピカソさんらんとして地に死ぬをありあけの馬は見て忘れけむ」
(坂井修一『群青層』より)
「桑の實數千(すせん)熟れつつ腐るすでにして踰(こ)ゆべき海も主(しゆ)もわれになし」
(塘健『出藍』より)
「口紅と座薬とジャムと練りからし冷ゆる冷蔵庫夏過ぎてより」
(浜名理香『風の小走り』より)
「石(いは)ばしる垂水(たるみ)の上のさわらびの萌(も)え出づる春になりにけるかも」
(志貴皇子『万葉集』巻8・1418より)
・
・
・
【短歌表現】序章:異種百人一首
https://note.com/bax36410/n/n3c9d55768021
【短歌表現】第一章:新種二百人一首
https://note.com/bax36410/n/nee908066d92b
【短歌表現】第二章:新種三百人一首
https://note.com/bax36410/n/n9dea0b13b06b
【短歌表現】第三章:新種四百人一首
https://note.com/bax36410/n/nb91f879cfc1f
【短歌表現】第四章:新種五百人一首
https://note.com/bax36410/n/n410ddabf4a3f
【短歌表現】第五章:新種六百人一首
https://note.com/bax36410/n/n4145e0af2db2
【短歌表現】第六章:新種七百人一首
https://note.com/bax36410/n/n3000a64f2fe6
【短歌表現】第七章:新種八百人一首
https://note.com/bax36410/n/n94849bae6e6d
【短歌表現】第八章:新種九百人一首
https://note.com/bax36410/n/nf7a84797a0bf
<今後の予定>
【短歌表現】終章:新種千人一首
【短歌表現】新第一章:新種千百人一首(行けるところまで!)
・
・
・
【予習:短歌表現】
4.短歌を詠む意義
短歌を作ってみたいと思ったこと、それが、何より大切である。
それは、短歌をつくることに価値があるか、ということを問うことからはじめるものではない。
短歌を詠むこと自体が大切なのであり、意義のあることなのである。
人間が生きていること自体が大切であるように、短歌とは、人生そのもの人間そのものなのである。
生活の実感を大切にし、自分の思うがままを述べていくことは、自分にとっての安らぎであるばかりでなく、人や物等と繋がっていく。
短歌を作る意味とは、人間らしさを求めていくことにつながる。
自分の外側は写真で写すことができる。
しかし、その写真は、内面までをも描くことはできない。
それだけに、短歌は、一人ひとりにとって大切なものである。
二つとないその人らしさや、その瞬間を残しておきたいと思うことは、人として、当然の要求であると考える。
人間らしさを求めるがゆえに短歌なのである。
したがって、手間暇かけて短歌を作ることに意味がある。
短歌を作っていくということは、 単に、趣味的なことなのではなく、その人の生き方を支えていくものである。
人間と言うのは、人と繋がりつつ、孤独なものを支えて生きている。
ただ、それを歌うことで、寂しい時も生きる意欲や張りを与えてくれる。
我々が、折に触れて短歌を作ろうという思いになる根底には、日本語、そのものの特色が生きている。
単に、鑑賞するということだけではなく、実作していくことが重要である。
[テキスト]
短歌表現―コミュニケーション技術における学習効果の検討―
【授業:短歌のことを考えました】
カテゴリー「短歌のことを考えました」の47件の記事
【復習:意外と知らない百人一首の世界を探求】
【参考記事】
【参照文献】
コレクション日本歌人選 源実朝 三木麻子 著(笠間書院)
コレクション日本歌人選 菅原道真 佐藤信一 著(笠間書院)
コレクション日本歌人選-紫式部 植田恭代 著(笠間書院)
伊勢物語・大鏡・古事談・徒然草 新編日本古典文学全集(小学館)
一条摂政御集注釈 平安文学輪読会(塙書房)
院政期政治史研究 元木泰雄 著(思文閣出版)
栄花物語・大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
王朝の映像 角田文衛 著(東京堂出版)
王朝の映像-平安時代史の研究 角田文衛 著(東京堂出版)
王朝の歌人9 乱世に華あり 藤原定家 久保田淳 著(集英社)
王朝の変容と武者:古代の人物6〈三条天皇 藤原道長との対立〉 中込律子 著(清文堂出版)
王朝歌壇の研究 桓武仁明光孝朝篇 山口博 著(桜楓社)
歌合集 日本古典文学大系(岩波書店)
季刊墨スペシャル 百人一首(芸術新聞社)
貴族社会と古典文化 目崎徳衛 著(吉川弘文館)
金槐和歌集 新潮日本古典集成(新潮社)
愚管抄 日本古典文学大系(岩波書店)
訓読 明月記 今川文雄著(河出書房)
古事談・保元物語 新編日本古典文学全集(小学館)
後撰和歌集・拾遺和歌集・後拾遺和歌集 新日本古典文学大系(岩波書店)
後鳥羽院御口伝・井蛙抄 歌論歌学集成(三弥井書店)
後鳥羽院御口伝・近代秀歌 日本古典文学大系 歌論集 能楽論集(岩波書店)
最勝四天王院障子和歌全釈 渡邉裕美子 著(風間書房)
三条天皇 倉本一宏 著(ミネルヴァ書房)
紫式部集全釈 笹川博司 著(風間書房)
人物叢書 菅原道真 坂本太郎 著(吉川弘文館)
崇徳院怨霊の研究 山田雄司 著 (思文閣出版)
袋草紙考証 雑談篇 藤岡忠美 他 著(和泉書院)
大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
大和物語 新編日本古典文学全集(小学館)
大和物語・栄花物語・大鏡 新編日本古典文学全集(小学館)
淡光ムック 百人一首入門 有吉保・神作光一 監修(淡光社)
藤原定家『明月記』の世界 村井康彦 著(岩波新書)
読み下し 日本三代実録 武田祐吉・佐藤謙三 訳(戎光祥出版)
悲境に生きる 源実朝 志村士郎 著(新典社)
百人一首 定家とカルタの文学史 松村雄二 著(平凡社)
百人一首 鈴木日出男(ちくま文庫)
百人一首(全) 谷 知子(角川ソフィア文庫)
百人一首に絵はあったか 定家が目指した秀歌撰 寺島恒世 著(平凡社)
百人一首の作者たち 目崎徳衛 著(角川書店)
百人一首の新考察 吉海直人 著(世界思想社)
百人一首研究必携 吉海直人 編(桜楓社)
扶桑略記 新訂増補国史大系(吉川弘文館)
平安朝 皇位継承の闇 倉本一宏 著(角川書店)
平安朝歌合大成 萩谷 朴 著(同朋社)
別冊太陽 百人一首への招待 吉海直人 監修(平凡社)
保元・平治の乱 元木泰雄 著 (角川ソフィア文庫)
枕草子・俊頼髄脳・袋草紙 新編日本古典文学全集(小学館)
訳注 藤原定家全歌集 上下 久保田淳 著(河出書房新社)
歴代宸記 増補史料大成(臨川書店)
蜻蛉日記ー新編日本古典文学全集(小学館)
近代秀歌 (岩波新書) 永田和宏(著)
現代秀歌 (岩波新書) 永田和宏(著)
人生の節目で読んでほしい短歌 (NHK出版新書) 永田和宏(著)
【参考図書】
「日本うたことば表現辞典 全15冊揃」
万葉から現代の和歌・短歌・俳句をテーマ別・表現手法の修辞別に分類した我が国文学史上最大規模の作品辞典。
「わたくしが『日本うたことば表現辞典』の第一期の最初の巻に監修のことばをよせたのは1997年のことであった。
そして第二期の最終巻に筆をとったのが2010年である。
この間、書肆の遊子館の辞典編集部は、とどまることなく編集作業を着実に積み上げてきたのである。
おそらく、日本の詩歌文学において、このような一つのテーマで、持続的に、しかも古代から現代の領域に及んで体系的に纏めた出版企画は少ないと思う。
第一期は「うたことば」の表現分野の構成であり、第二期は表現手法(修辞)の構成となっており、この二つの必然の組み合せにより、読者は日本の「うたことば」の全容を知ることができるであろう。」〔監修者序より〕
通巻1・2 日本うたことば表現辞典—植物編(上・下)
通巻3 日本うたことば表現辞典—動物編
通巻4 日本うたことば表現辞典—叙景編
通巻5 日本うたことば表現辞典—恋愛編
通巻6・7 日本うたことば表現辞典—生活編(上・下)
通巻8・9 日本うたことば表現辞典—狂歌・川柳編(上・下)
通巻10・11 日本うたことば表現辞典—枕詞編(上・下)
通巻12・13 日本うたことば表現辞典—歌枕編(上・下)
通巻14 日本うたことば表現辞典—掛詞編
通巻15 日本うたことば表現辞典—本歌・本説取編
【関連記事】
朝顔、蝉、蛍、時代の情操と音律。
https://note.com/bax36410/n/n2209933d507c
【雑考】幻想文学から幻想的な短歌への誘い(その1)
https://note.com/bax36410/n/n466753a43630
【雑考】幻想文学から幻想的な短歌への誘い(その2)
https://note.com/bax36410/n/n92ddf4c2ff7b
【一筆】絵と短歌と詩と
https://note.com/bax36410/n/n22eb1d3ec7ba
【新鋭短歌シリーズ】生きたことばを掬う短歌たち。生活に「うた」の彩りを。 「うた」のある暮らしのすすめ
https://note.com/bax36410/n/n2af562456d6f
【現代短歌クラシックス】星の林と遊び種
https://note.com/bax36410/n/n045a544ef068
【現代歌人シリーズ(その1)】青空の青ってどんな色?
https://note.com/bax36410/n/na61f3d32da4f
【現代歌人シリーズ(その2)】言葉に選ばれる
https://note.com/bax36410/n/nfbfd9fac438b
【現代歌人シリーズ(その3)】心で感じなければ
https://note.com/bax36410/n/n889688a247f8
【本日の思いつきバックナンバー】「百人一首(近代・現代短歌)ある世界」版バックナンバー
https://note.com/bax36410/n/n43ce9f06b3c9
【読書メモ】
「英詩訳・百人一首香り立つやまとごころ」(集英社新書)マックミラン・ピーター(著)佐々田雅子(訳)

[ 内容 ]
『小倉百人一首』はこれまでも英語で翻訳出版されたことがあるが、従来の翻訳では和歌の世界を充分に表現しえなかった。
この言葉の結晶の新訳に、アイルランド生まれの著者が挑戦。
かくして、まったく新しいアプローチによって和歌に重層的に折り込まれた“やまとごころ”を英語で表現してみせた。
その翻訳は、英語の詩としても通用する。
ドナルド・キーン博士の高評を得て、原著は二〇〇八年コロンビア大学出版より刊行。
同年度日本翻訳文化特別賞等を受賞し、学問的にも評価された。
本書は平易な英語による『小倉百人一首』翻訳の決定版である。
[ 目次 ]
マックミラン訳の魅力(ドナルド・キーン)
日本語版のための序論
英詩訳百人一首
原書版序論
マックミラン訳が解き放したもの(アイリーン加藤)
[ 問題提起 ]
「これやこの ゆくもかえるもやくしては しるもしらぬも ひゃくにんいっしゅ」
失礼。
英詩訳も凄いが、その至らぬところを通して、短歌という形式の凄さ、そして、それを可能にした日本語の凄さを、改めて感じることの出来る良著。
「ひさかたのひかりのどけき春の日に」ひもとくのに。最上の一冊だ。
本書は、日本一、すなわち、世界一読まれてきた日本語詩集の、最新にして、最良の英訳。
ドナルド・キーンが、こう太鼓判をおしているぐらいだ。
「五七五(七七)というのはどうやら人類的普遍性のあるリズムであるようで、注意すると欧米のポップスにもこれが登場しているのがよくわかるぐらいだ。
こういう「隠れた」五七五だけではなく、今や haiku の方は世界語になっている。
その証拠というわけではないが、OS X Leopard 内蔵のスペルチェカーは haiku を通す。
tanka を通さないのがいささか残念だ。」
それだけに、百人一首の訳者たちは、「五七五七七」の強い呪縛に、支配されてきた。
勢い、それを優先するがあまり、元の歌の意が失われてしまいがちであったのである。
[ 結論 ]
本書は、それを、敢えて捨てたところに、凄さがある。
たとえば、冒頭のパロディの元の句、
「これやこの ゆくもかへるも わかれては しるもしらぬも あふさかのせき」
が、訳者の手にかかるとこうなる。
So this is the place!
The crowds,
coming
going
meeting
parting
friends
strangers,
known
unknown---
The Osaka Barrier.
これほど「これやこの」感、「ゆくもかへるも」感、「しるもしらぬも」感に溢れた訳が、かつてあっただろうか。
そのために、あえて「逢坂の関」を「外だし」しているところは、たしかに、原作忠実派の格好の攻撃対象になりそうだが、もし、蝉丸が、英語を話せたら、蝉丸も、また、本首に、一票投じると、私は想像する。
しかし、である。
それでも、やはり、著者の訳は、文脈を補いすぎていると、感じてしまうのである。
例えば、これ。
おそらく百人一首の中でも最も「わかりやすい」一首。
「君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな」
I always thought
I would give my life
to meet you only once,
but now, having spent a night
with you, I wish that I may
go on living forever.
間違い、ではない。
確かに百人一首は、
「よくもまあこんな猥褻な詩を小学生に教えますね」
というほど色恋の歌(色恋の文脈でないと成立しない歌)が多いが、しかし、この一首は、そうでない文脈でも、成立するところに、その妙味があるのではないか。
"having spent a night with you"とは。
世阿弥がこれを見たら、
「ああ、花が散ってしまう」
と、憐れんだかも知れない。
私なら、こうするだろうか。
詩には、なってないかもしれないが。
I would die just to see you.
Now that I have seen you,
I wish to live forever with you.
なんと、これでも、"I have seen you"という文脈を補っている。
本当のところ、こういう文脈だったかどうかは、わからないのに。
短歌や俳句の魅力は、人それぞれ、いや、一首一句、それぞれにあるのだろうけど。
私にとってのそれは、
「異なった文脈で異なるように成立すること」
である。
その妙を楽しむには、本書の訳は、彩りが強すぎると感じた。
しかし、よくよく考えてみれば、対象読者にとって、ピンとこない文脈を、訳注などで補うのは、翻訳の常套手段であり、王道でもある。
異なる文脈で使いたいのであれば、自分で読み直せばいいのだし。
それにしても、百人一首というのは、
「門前の小僧習わぬ経を読む」
の格好の例ではないか。
百人一首は、高校時代に覚えたが、もちろん、その時には、ほとんどの首は、意味不明だった。
「世をうぢ山と人はひふなり」なんて、「蛆山」と解釈してたぐらいだ(^^;
年を追うごとに、その意味がつかめる(わかるとは、とてもいえない)なって、なんとすごいものを知らぬうちに、もらったのだと、感動することしきりである。
[ コメント ]
今日日の小学生は、百人一首を覚えたりするのだろうか。
「蛆山」でいいから、覚えておいてほしい。
後で、宝の山に化けるのは、私が、惜しからざりし命をかけて、お約束します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
