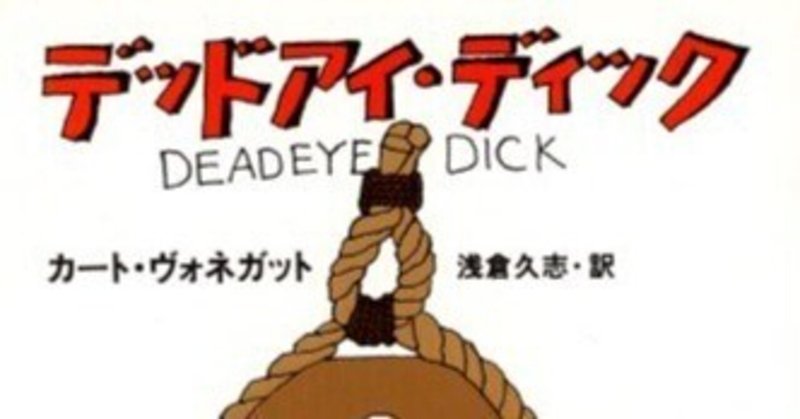
温もりのある小咄 -ヴォネガットの小説『デッドアイ・ディック』の魅力
アイロニーを突き詰めて、ヒューマンな温もりをもたらす作品。こうした作品の中でも、カート=ヴォネガットの小説はその最上級の素晴らしい成果でしょう。
『スローターハウス5』や、『プレイヤー・ピアノ』等、SFに分類される小説で、日本でも人気の作家です。そんな彼の作品の中でも、私が好きなのは『デッドアイ・ディック』という作品です。彼の中ではあまり有名な作品ではありませんが、肩肘張らずに面白く、軽い小咄を聞いているような楽しさがあるのです。
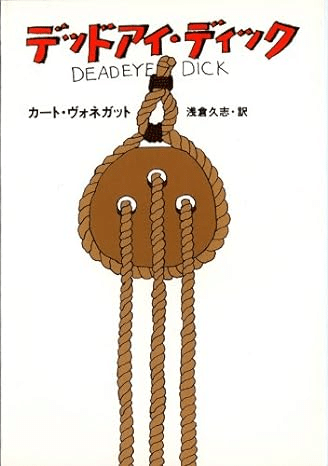
カート=ヴォネガットは、1922年アメリカのインディアナ州生まれ。このインディアナ州と、その州都インディアナポリスは、度々彼の作品にも登場します。

第二次大戦に徴兵されると、ドイツ軍の捕虜に。そして、1945年のアメリカ軍によるドレスデン爆撃(町の殆どが壊滅したと言われます)で、地下の屠畜場を使った捕虜収容所にいたために、偶然生き延びたという、数奇な運命の持ち主です。この経験は、代表作『スローターハウス5』で全面的に展開されることになります。
1950年に『プレイヤー・ピアノ』でデビュー。世界の終末と、新興宗教の教祖を描く1963年の『猫のゆりかご』がベストセラーになって、作家としての地位を確立します。『デッドアイ・ディック』は、1982年、円熟期の長篇小説です。
物語は、ルディ=ウォールツという男の回想録という形で進みます。ヴォネガットと同じ1922年にオハイオ州ミッドランド・シティという架空の都市に生まれ、ヨーロッパかぶれで道楽者の父や、善良だけど生活力のない母の間で育った男。
そんな彼がどうして、『デッドアイ・ディック』(俗語で「射撃の名手」の意味)と呼ばれるようになったのか。父と母はいかにして没落していったのか。ハンサムな兄はいかにして妻を失ったのか。ルディとカトマンズはいかなる関係があるのか。へんてこな家族を面白おかしく描きながら、どこか哀愁の漂う作品になっています。
結婚式で父の介添え人をつとめたジョン・フォーチューンは、父に一言も口をきかなくなり、父の耳に届いた確実な情報によると、町中にこんなことを言いふらしているようだった ーあいつは危険なあんぽんたんだ。
父がそうであったことはまちがいない。
どうしてこの作品が好きなのかと言うと、派手なSF的な仕掛けがなく、無理なくこの変わった家族の話に入って行けるというのがあります。そうすることで、真面目なようでちょっとふざけたユーモアやアイロニーが、薫り高く引き立ってきます。
そして、もう一つは、これはある意味、捨て子による語りの作品だからです。生活力がなく、ルディの起こした事件がきっかけとはいえ、彼を支えるどころか、彼を巻き添えにして没落していく両親。
「いい人」ではあるはずなのだが、何か大切なハートのようなものを失ってしまった人間(この主題は前作『ジェイルバード』でも展開されていました)によって育てられた悲哀のようなものを感じます。
両親を憎むことはできないけど、愛することも到底できないという、どこか痛ましい状態が、痛みなんてないよとでもいうように、何でもないように語られていく。それゆえに、逆に痛切な感情を覚えてしまいます。これは私の個人的な思いなのかもしれませんが。
それは、ある種の喪失感でもあります。この小説の前書きには、次のような一節があります。
この本に出てくる主要な象徴について説明しておこう。
球形をした、だれにもかえりみられない、空虚な芸術センター。これは、六〇歳の誕生日を間近に控えたわたしの頭である。
居住地域での中性子爆弾の爆発。これは、作家をこころざし始めたころの私が大切に思っていた、インディアナポリスの大ぜいの人たちの消失を表している。インディアナポリスはまだそこにあるが、その人たちはいなくなった。
勿論、象徴などと言っているのは、ギャグなのですが、まさに大切な人々の消失によって、取り残されてしまったような感覚というのは、本心だと思えます。
これは、全く自分を助けてくれない親にあたった子供や、何故かうまい具合に爆撃を避けられて生き延び、焦土と化した街を見た兵士が覚えるような感覚なのではないでしょうか。
ヴォネガットの作品には、こうした、自分はどこかに捨てられて一人ぼっちになってしまった人間だというような感覚がある。そこが、ユーモアの陰の苦いペーソスを出しているのです。
『スローターハウス5』だと、手の込んだ時間操作や、戦争体験、あるいは『猫のゆりかご』だと、世界の終末という、まあ、なかなか普通の人間には味わえない題材になっているため、どうしても、自分にとっての外側の話になってしまいます。
しかし、『デッドアイ・ディック』は、いつの時代、どこにでもありそうな平凡な都市を舞台にすることで、この「捨て子のアイロニーとユーモア」を、これは自分のことだ、と読者に感じせることに、成功しているように思えます。
この作品は、人生にご用心、という警句から始まり、ご存じですか、と読者に語り掛けて終わります。
それは、一つの読者への長い呼びかけ、つまり、人生への暗い影を持ちながらも、それでもユーモアとアイロニーを忘れずに生きるための呼びかけです。それこそが、この作品のヒューマンな温もりを表していると言えるのでしょう。
今回はここまで。
お読みいただきありがとうございます。
今日も明日も
読んでくださった皆さんにとって
善い一日でありますように。
次回のエッセイでまたお会いしましょう。
こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。
楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
