
言葉は世界を生成するー詩とインターフェースと外因性ー
これは3/6-11に行われた『東北芸術工科大学卒業制作展』で展示した「錯乱と閃光」を制作するにあたって研究した軌跡とその論考である。
詩は世界のポイエーシス
世界の生成であり
生成する世界である
───向井周太郎「かたちの詩学」より
序文
気づいたら22歳になっていた。大学4年の冬が過ぎようとしている。劇的に感じるのは自分の変化よりも世の中の変化の方で、むしろ自分の方が世界の変化に合わせているような感覚があった。テクノロジーを上手く使いこなし思想をアップデートしているつもりでも、それらは実は自分の意志で選び取ったり勝ち得ているものではなく、無理やりに「進化させられている」だけなのではないか。
今確認してみると、自分が普段肌身離さず持ち歩いているスマートフォンの中には、SNSアプリが5 つも入っていた。それぞれのアカウントがそれぞれ違う人格で、顔で、形態で、「自分」というものをアップロードしている。自分のポストした言葉や写真を見返してみると、そのどれもが確かに自分の投稿で、つまり切り取られた自分なのだろうけれど、どれも自分ではないような気がして気味が悪く感じる。でもやはり、何故かそうせざるを得なかった自分がここにはいる。突き詰めて考えてみれば、そういう行為に意味はない。やっぱり時代や環境に突き動かされているだけなのだ。もっと言えば、「自分」なんてどこにも存在しない、ともすれば「世界」なんていうものだって存在しないのではないか。
かつて「コンクリート・ポエトリー」を標榜しながら、「自分」や「世界」とは何か、という問いと対峙をした詩人たちの研究を進めながら、現代に生きる自分はそんな思いにとらわれた。ここから先に書かれていることは、作品制作と平行して進めた「詩」と「芸術表現」とはなにか。や、なぜ我々は芸術が必要なのかという研究の軌跡であり、備忘録であり、論考の道筋を確認するためのものである

創造する言葉
詩は言語表現を用いた芸術である、と一般的に定義できる。では、詩と、それ以外の言葉とを隔てることは出来るだろうか。
プラトンはポイエーシスを「あるものがまだそのものとして存在していない状態から存在へと移行することについてのいっさいの原因」と定義している。かつて「言葉」が無数に発生し、「言語」が生成された───そして現在もなお終わりなく生成を続けている───その大本の原因を「ポイエーシス」と呼ぶわけである。
ポイエーシスとは、「創造」を意味するギリシャ語であり、「詩(poem)」の語源でもある。つまり「詩」という言葉は、「創造(存在していないものが存在へと移行すること)の原因」を内包していることになる。
論考の冒頭、エピグラフに引いた向井の詩に表れているような「世界」と「詩」の「鶏が先か卵が先か」的な関係性は、ある意味なぞかけのように見えて、本来的な詩の在り様を的確に言い表している。「初めに言葉があった」という旧約聖書的な世界感を、現代の分析的方法に基づく世界感とを同じ俎上に載せ、一旦近代の過剰な合理主義的認知の在り様から外れ「世界は言葉に因って生成されているのではないか」と考えてみる余地はないだろうか。
それを考えるにあたってまず、そもそも「言葉」とは何か。我々が無意識のうちに会得し、扱っている「言葉」とは一体何であるかを考える必要がある。
現代を生きる我々は「言葉」を主に情報伝達の手段として使用する。意味を有し、時に意味以上のものすら含まれることがある故に、我々はそれを個々がコミュニケーションするにあたっての最も合理的な道具として扱ってきた。
しかし、旧約聖書や向井を始めとした詩人が考えるような「言葉」の原義に立ち返るならば、「言葉」を情報伝達の道具として使うということは、「言葉」の有する機能の部分的な利用でしかない、と理解するべきであろう。時に詩人というのは、言葉を、そうした「意味を構築する」「互いが意味を理解する」というような限定的な利用ではなく、「言葉そのもの」に眠っているエネルギーを解放することを目指しているのではないだろうか。
「私」を「私」という言葉で定義するとき、果たしてそれは本当に、私が言葉を使役しているとだけ認知していてよいものだろうか。「言葉」という型が、本来の「私の形」を歪めながら象っている可能性があると考えられないか。それらを暴くことが出来うる可能性を、詩は秘めている。

連続する道具
生物学者であるジョン・メイナード・スミスとエオルシュ・サトマーは、生命を「自己複製可能な情報システム」とした上で、生命進化の系譜を生物学的な組織の主要な遷移によって定義している。分子や細胞が分裂したり、生殖を行うことで、生命は自己複製を繰り返してきた。霊長類が「社会」を形成するまでを、八段階の閾値として定義している。
この変遷上でも「言葉」は重要な役割を果たしている。「言葉」が発明されて以降、人間自体は大きな変化をしない一方で、印刷技術や工業技術のテクノロジーによって「自己複製可能な情報システム」を段階的に成長させてきた。
ケヴィン・ケリーは、現代のテクノロジーが向かう情報化・非物質化への流れを踏まえつつ、生命における生態系と同等なものとして、テクノロジーの活動空間を「テクニウム」と名づけている。その上で、生命を1つの「進化する情報システム」と捉えた前述のスミスらの分類を持ち出すことによって、生命と「テクニウム」という概念を同一線上にある進化の系譜として説明し、未来を予測している。ケリーは同名の書の中で、 グラハム・ベルと同日に電話機の特許出願をしたエリシャ・グレイの例や、有史以前のイノベーションの多くが隔てた地域で同時多発的に発生していることを発見した考古学者ジョン・トロエンの研究を用いながら、 「テクニウム」も生命と同じく「進化(イノベーション)には固有の順番がある」と論じている。
私たちは物から意味を見出す。石の硬さや鋭利さから、例えばそれが草木を刈ることに適している、という意味性を見出すことで、物を道具化していく。ここで注意しておきたいのは、「意味性を見出す」こと自体には、言語的な要素は介在していないという点である。「言語によって何かを定義する」というのとはまた別のところで、「ものから意味性───意味ではなくあくまで意味性───を見出す」ということを、人間は連綿と続けた結果進化してきたわけだ。
つまり、我々は「言葉」を介さずとも、ものから意味性を「読み取る」ことが出来るのではないか。そして、そのように無意識的にものから意味性を読み取ってしまうことが、我々を道具の進化特性の補助的存在たらしめているのである。
ここに、言葉の意味───ここで言う「意味」は「意味性」でなく、あくまで「言葉としての意味」であることを強調しておく───を排除した「コンクリート・ポエトリー」の重要性を見出すことが出来る。形式・形態だけを際立たせて構築された表現からも、我々は鑑賞者個人の立場・時代性・環境に即して意味性を読み取る。それは道具の進化特性という、我々生命とは明らかに異なる、ある意味超越的な外在因の存在の示唆でもあるのだ。
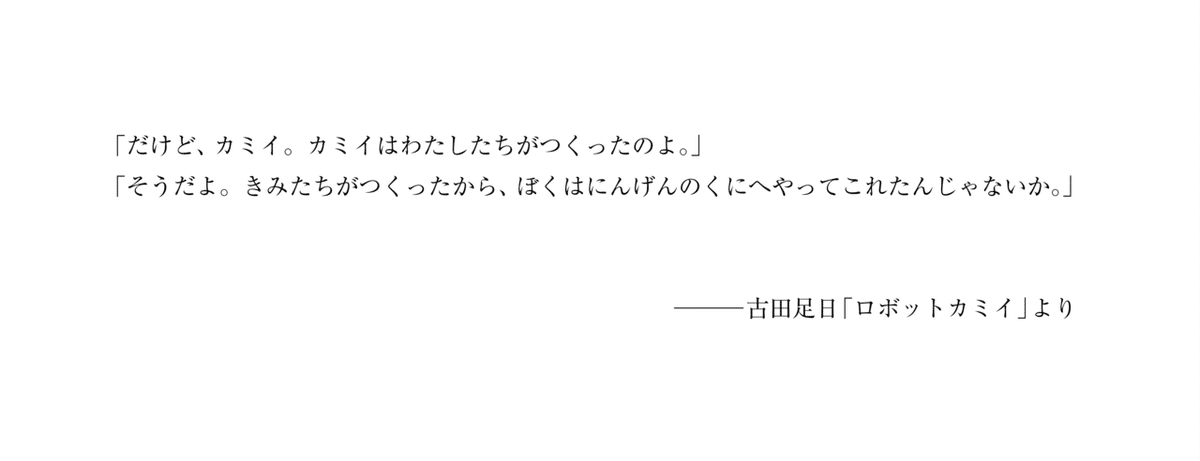
外在する神秘
デジタルインターフェースという「道具」の登場により、紙上の言語表現の在り様は大きく変わらざるを得なくなった。詩もまた同様である。元々紙面上でも動的な表現が多く採用されていた視覚詩だが、デジタルインターフェースに格納されることによって、実際に「言葉を動かす」ことが出来るようになった。また、DTP技術が発達することによって、制作者側が画面上で容易に文字表現を扱えるようになったことも、少なからぬ影響があるだろう。
前章で、「人間は言葉を介さず道具から意味性を読み取ることができる」可能性について触れた。意味性というのは、何もそのものの道具的特性───用法や効能など───だけを指すわけではない。章の冒頭に引用した絵本───子どもたちの手によってダンボールで作られたロボットの名前は、アイヌ語の高位の霊的存在を意味している───のように、人間の原初的な感覚は、その意味性の読み取りから神秘性、神の外在性を感じていたことが想像できる。
では、現代の私たちは、デジタルの道具やインターフェース、あるいはその内側にある事象や表現から、神秘性を感じることが出来るだろうか?
人が作ったものであっても、それを生かしているのは、どこか別のところからやってきた神秘的な力である、という感覚を、私は普段から感じています。何かを作っている時、実際に手を動かしているのは自分であっても、その作業において逐次なされる意思決定、無意識に選択されるデザインパターン、そして具象化されていく物の意味性を自己評価する目は、自分だけのものではなく、そのほとんど全てはどこか別のところから、おそらく長い歴史の中で様々な人が行ってきた膨大な工夫の蓄積として織り成されたアートの断片として、特殊な客観性を帯びながら現れるのです。
───プロレタリアデザイン/上野学
デジタルトランスフォーメーションをデザインによって支援するソシオメディアの中心人物である上野学は、インターネット上で公開したテキストの中で「ものの神秘性」について上記のように語っている。上野は、本テキストの中で「もの」に対する自身の役割を「鑑賞者」と「道具の使用者」の間で曖昧にしているように見える。
デジタルデバイスにおける「入力」と「出力」は、曖昧である。数値を入力したり、画面をなぞるだけで、その入力とは直接的に関連付けられない「出力」を反映することが、デジタルの世界では可能だ。それはソフトウェアやコンテンツの鑑賞者だけではなく、プログラムを組む人間にとっても同様である。インタラクションデザイナー/インターフェースデザイナーとしても活躍する上野のような人間「こそ」が、「神秘性」、つまり「自分が手を動かしているのに、特殊な客観性を帯びてあるデザインが現れる」と感じることはある意味必然的なことで、我々は自己主体感が薄れる───つまり、「入力」と「出力」が曖昧になる───ことを「神秘的」と呼び、「外在因」としての「神」のような高位的存在を感じるのである。

格納する世界
ヒューマンインターフェースとは本来、人間が触れる対象の界面や接触面のことを指す。指先で触れた石の鋭利さから、草木を刈るのに適しているという意味性を読み取ったのと同じように、例えば紙に印刷された小説であれば、我々は「物語」を享受する為に、「本」というヒューマンインターフェースに接してきたことになる。ヒューマンインターフェースとは、その内側に人間が直接触れることの出来ない「意味性」を格納する器であるとともに、その表面に人間が触れることで様々な反応を誘引することの出来る、「人間」と「意味性」の間に横たわるものとも定義することが出来る。
近代の合理主義的デザイン思考は、その「意味性」を人間が享受するにあたって、その内容や反応を恣意的に操作することを是として発展してきた。しかし、これはあくまで人間が人間に対して一定の反応───多くは消費を促すような───を促進させるためのものでしかない。
デジタルデバイスのような道具はある意味、近代までに発展してきた印刷技術───いわば紙の上に表現を「定着」させてしまう───による表現とは異なる表現を生み出すことが可能であると同時に、鑑賞者にとってもより「出力」と「入力」が曖昧な体験をもたらすことが可能だ。
そこに格納されている「意味性」を、上記のような合理主義的なデザインとは真逆の思想で、敢えて意味性のエントロピーを押し留めないまま表現しておくことによって、世界を格納すると同時にその解釈や広がりを無限に定着させるというような、二律背反的な世界の存在を示すことが出来るのではないか。
プログラムによってパッケージされ、境界線の引かれた詩の世界の中に、鑑賞者が無限の解釈をすることが出来うる。そこに筆者は、デジタルデバイスを使いインタラクティブ性を持たせた詩を表現する、ということに対する大きな意義を感じたわけである。

付与する意味
インターフェースを、「意味性」と「人間」の間に横たわるものと定義した。また、人間が道具が進化する際の補助的存在とも考えられる可能性についてもここまでに触れた。インターフェースという界面は、その内部/外部の両面に影響を及ぼす。デジタルデバイスに指を触れるというような恣意的な行為のみならず、そこに存在した時点で界面が生成され、同時に相互的に影響を及ぼしあうということを、道具の進化特性から省みねばなるまい。そして 我々は、科学や認知に関する研究を深め、意味性の存在を言語化し、一定の───あくまで一定の───「外在性」をコントロールする方法論を得た。「意味性」ではなく「意味」を伝える方法を平準化し───その多くは言語による力を介して───「テクニウム」以前まで進化してきたということになる。そうした方法論の確立と同時に、ここまでで論じたような「神秘性」や「意味性」の存在を認知する感覚を、我々は失いつつあるのではないか。美やアート、そしてそれが帯同するような神格性が極端に格上げされ、生活や人間社会における価値と隔絶してしまったのは、そうした結果に因るものではないだろうか。
この潮流の最先にある現在において、意味を付与するための中心的道具として進化してきた「言葉」を扱いながらもその意味性を排除したコンクリート・ポエトリーを再評価する必要がある、と筆者は考える。また、前章の結びに書いたように、鑑賞者と作品がインタラクションし、更にそのインタラクティブ性を視覚的に表現することが、我々が失いかけている原初的な感覚を呼び覚ます一助になることを願いながら作品制作を行った。
「意味性」は形を持たず、不確実なものである。「言葉」は意思疎通のための「道具」ではあるが、その言葉に格納されている「意味性」を完全な形のままで受け渡せるものというわけではない。結局言葉は、話者と受け手の間にしか存在し得ず、両者はそこに格納されている意味性を取り出すことでしか解釈しようのないものなのだ。そして、人間の進化において非常に重要な要素だった「言葉」の制御可能性の過信への問題定義を、意味性を排除した言葉に依って行うことで、ある種自己批判的な作品が浮かび上がってきたのではないか。と、こうして自身の作品について書くこともまた、自身がそこにある言葉から勝手に意味性を見出しているに過ぎないのである。そうして私は私自身をアップデートしていくのだ。

生成する世界
信仰すら、法話や聖書のような経典、つまり「言葉」の力に頼って紡いできた我々は、様々に希望を語り、未来を設計───デザイン───する。テクノロジーの発展によって「未来は予測可能」とするその未来の形を、我々は言葉によって記述する。その「予測可能性のある未来」すら、「未来は予測可能」と言葉で表現するしかないのだ。また、時にデザインは、そうして言葉だけでは想像出来ないようなイメージを可視化するために使われてきた。これまでにも、そうして未来を完全に設計しようとする───「意味性」が言葉によって象られていくのと同じように───ことに対しての批判が繰り返し行われてきた。アート・アンド・クラフツ運動、そしてそれを思想的に引き継いだバウハウス・ムーヴメント、コンクリート・ポエトリーなどがそうである。
「詩」というある意味非常に私的で小さな作品を制作しながら、ここまでに論じたのと同様の問題意識で「大きな物語」に抗った先人たちの跡を追った。思索とは何か、そして消費主義社会でそれを誰かに促すことが本当に可能なのかということを、自分もまた思索してきたつもりである。
近代合理主義的な思想は、道具の連続と同じように連続して生成されていく。それは繰り返される世界の生成の一部であり、逃れることは出来ないだろう。テクノロジーが進化していくことで人は大量生産を行い生活を便利にする「デザイン」を構築していった。そして反対の立ち位置にいた、上記の運動の主導者たちは、同じテクノロジーを扱いつつも、それらを批判するような、人間の生に語りかける方向へと向かっていく。
今回のメインの展示をデジタルデバイスによって制作したのも、彼らの歴史の変遷を辿り、現代の近代合理主義のあり方と対峙するためであった。普段デザインを生業としているものとしては終始ジレンマを抱えて制作をすることになったが、この両極端を一度に味わう行為は、現在の詩やアート、デザインを拡張するために必要な行為なのではないかと考える。これは自らの批判でもあり、肯定の作業とも言えるだろう。
序文で、『自分』なんてどこにも存在しない、ともすれば「世界」なんていうものだって存在しないのではないか」と記した。本研究において重要な示唆を与えてくれた向井周太郎は、感傷的な意味合いではなく、ここまでに論じた「道具の連続性(進化特性)」に紐づける形で、論理的にそれを示している。
模倣は人間固有の文化を形成するための本能的な能力であるが、人間による図像や手道具の外化にはじまる自然や自らの身体の模倣が今や急速に脳の内的組織や記憶の外在化あるいは遺伝子の外部操作に及んでいる事態を見れば、それは外化すべきもの、あるいは模倣すべきものの終焉として映るのであり、すなわちそれは自然や身体そのものの喪失を意味するだろう。 ───向井周太郎「かたちの詩学」
人間が、人間としての能力を延長し続けた───道具を進化させ続けた───その最終局面においてようやく、我々が自己を世界と切り離された立場から世界を認知し、恣意的に解釈するということの無意味さに気付き始めている。
私と世界の境界はより曖昧になり、結果として「自分を含む世界」を喪失するのではないか。
跋文
「私は言葉によって作られている」と理解するのには時間がかかった。普段使っている「言葉」という道具の本質に迫れば迫るほど、よくわからない。詩やアートの概念に触れれば触れるほど、目の前がぼやけて輪郭を失うような気がしていた。しかし今思えばそれがそのものの本質だったのかもしれない。今まで言葉を自由自在に使っていると勘違いしていた。そう勘違いしていたが故に、言葉というもののピントがあい、鮮明に輪郭を見えていた気になっていただけだったのだ。本当は、輪郭が失われるほどぼやけていて、いつだって正体不明のものが本当の姿だったのだ。常に変化を続け、理解される言葉も理解されない言葉も曖昧なゾーンの中で共存している。わからなくなればなるほど私はその本質に少しずつ近づき、普段ありふれている言葉の制約や、言葉のあり方との新しい距離を取ることができた。物心ついた頃から言葉に敏感だった私にとって、それはとても新鮮な体験であった。
この制作を機に、私自身のライフワークを発見できたこと、そして今後も言葉のあり方と対峙できることに喜びを感じる。言葉にすることを辞めず、言葉を疑うことも辞めず、そして永遠に言葉の魅力について囚われていたい。言葉とは何かを考えるときにすでにもう言葉を使い考えてしまう私は、この先もずっとまとわりつく言葉との距離の新しい取り方を模索するだろう。私にとってそれは詩であり、アートであり、大学で四年学んだデザインだった。

#詩 #コンクリートポエトリー #文学 #デザイン #アート #詩集 #小説 #映画 #インターフェース #インターフェースデザイン #UI #言葉 #視覚詩 #具体詩 #現代詩 #ポエトリー #ポエム #ポストポエム #アート #デジタル #メディアアート
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
