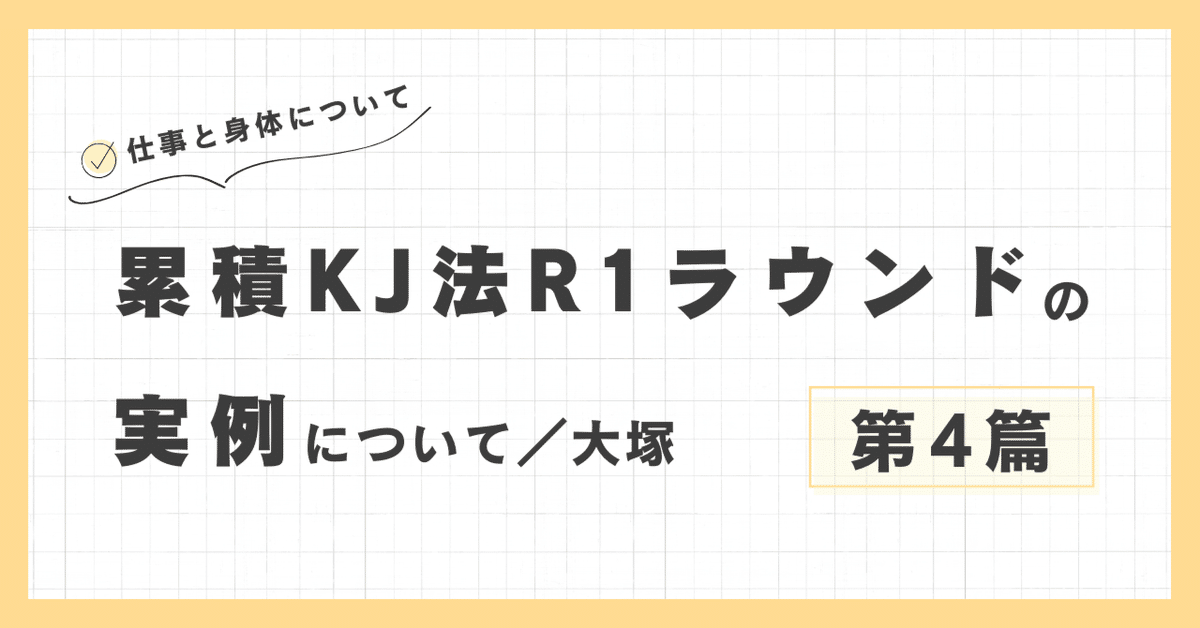
累積KJ法 R1ラウンド「何だか気にかかる問題点について」(第4篇)/大塚
累積KJ法 R1の最終回です。
前回はこちら(↓)。
前回をまとめると、「文章を書く力を磨いたのちに、他の芸術表現を組み合わせて悟りの領域までもっていく。そして、ひらめきを論理的に導くことができるKJ法を使って、直観とロジックの融合した本音の政治経済を実現したい」ということでした。
今回は、前回の仕事のことに関わる(7) 会社のお金は社員の共有財産となるだろうか、(8)観光の仕事はボランティアでなく利益につながるべき、の2点。働くことに関係しつつ、身体的な話題を扱った(9) 力仕事に精を出す両親の迫力が消えた、の1点を文章化します。

(7) 会社のお金は社員の共有財産となるだろうか
(人間らしい政治や経済を進めることで、お金はどのような意味を持つだろうか。貨幣は物の交換を割り切って行うために有意義だと本で読んだ。物々交換では介在する物品の価値がまちまちなので、お互いに心理的なしこりが残ってしまう。自分は多くもらいすぎじゃないのだろうか、または、こっちはこんな良いものをあげたのに、あいつはこんだけしかくれなかったなぁといったように。貨幣経済のない社会では、交換されるモノとヒトが強固に結びついている。)
メラネシアとポリネシアのいくつかの民族を考察することによって、贈与の体系に関する輪郭が浮かびあがってきた。そこでは、物質的、精神的生活と交換が打算的でない。義務的な形で行われている。さらにこの義務は、神話的、想像的、あるいは象徴的、集団的な方法で表現されている。しかもこの義務は交換される物に結びついた関心という形をとる。交換される物は、交換を行う者から完全に切り離されることはない。交換される物によって作られる人間の交わりや結合関係は比較的崩れない。実際に、社会生活におけるこのような象徴——交換される物に対する執着の持続——は、これらのアルカイックな類型に属する、文節化された諸社会の下位集団が互いに錯綜し、しかも、自分達が互いに義務づけられていると感じるその有様を明確に表している。
強調は引用者による
(それが継続的に交換を続ける要因であったのかもしれない。それが貨幣に変わってしまうと、等価交換が容易となった。その分、物の交換の体験に心情がなくなってしまい、どこか寂しい気もする。人間らしい経済におけるお金とはなんだろうか。貨幣経済はたしかに世界の発展を助けたが、人間根本のカオスさからは遠ざかっている。お金がなくとも、自分の創造性が社会に貢献できたら満足できるのでないか。)
そこで疑問に思うのが、いったい会社のお金は社員の共有財産となるのだろうか、ということ。(しっかり会社に一体感があれば、お金の使い道でとやかく揉めることはないだろう。それはほぼ共有財産ともいってよいか。給与として支払われたら、私有財産に変貌するが、それまでは輪郭の曖昧なお金として存在している。)
(8) 観光の仕事はボランティアでなく利益につながるべき
(そして、人間的な仕事というものは、ボランティアで行うよりも、しっかりした収益を得て対価を支払うことが必要であろう。その対価は金銭的なものだけでなく、やりがいなど心理的なものも含む。それは、ボランティアガイドなど稼ぎとは無縁に考えられがちな観光においても同様である。)例えば農家や陶芸家が副業として観光をする場合、観光は本業を潤すものであるべきだ。(直接には金銭的な報酬に結びつかずとも、心理的なやりがいは得やすい。そしてお金はあとから農作物や陶磁器を買ってもらうことで得る。観光は自分を知ってもらうきっかけにしてマネタイズポイントを後ろにずらすのである。)
また、直接的にも観光それ自体が事業として利益を出すべきだという意見もある。(ただし、赤字になっても未来の投資として確実な自信があればこの限りでない。)一方で、観光を進める会社の、社員の定着率が悪い原因はなんだろうか。観光を本業としており、給与が安いことは一因になりそうだが、それだけでなく、観光は多く感性の占める割合が高い仕事で、論理に結びつけるのは難しいことも関係しているかもしれない。そのように感性とロジックの齟齬に苦しむのか。もしくは、訪日外国人の急増や地方創生への要求などで中央官庁がむやみに事業を打ち出し、その現場における犠牲者となっているのかもしれない。
(9) 力仕事に精を出す両親の迫力が消えた
仕事の人間らしさが失われたのは、世界中の産業で機械化が進んでしまっていることと無関係ではないだろう。オフィスや工場だけでなく、家庭の仕事である家事も機械化しているものばかりである。一方で、昔は朝早くから大きな柴を抱えて親が帰ってきたものだと1940年代生まれの知り合いは回想していた。(それを見て、寝ぼけ眼をこすりながら親ってすごいんだなぁと感じていたらしい。)

都会では山菜採りも難しくなっている。人間の手でやる仕事がすたれている。迫力ある力仕事が消えてゆく。(同時に生活に密着した芸術のひとつである仕事唄や民謡もなくなってしまった。)そして、家庭でも泥臭く働く親の姿が見えなくなった。親の仕事の大きさが子供に伝わりにくくなっていると先ほどの知り合いは言っていた。
(それによって親を軽視してお金さえあれば自分でも生きていけるといったような驕りを子供に与えてしまう心配がある。また、以前は子供を作ることは家庭の労働力を増やすことであり、少子化の社会など考えられなかったであろう。それが機械化やモータリゼーションが始まったあたりから変わってきた。たとえば、昭和恐慌の直後に作られ、峠を走る乗合自動車を撮った次の映画の一コマでは、子どもが産まれることをブラックに皮肉っている。)
「この不景気に増えるものは赤ん坊ばっかりですねえ」
「どこの村へ行っても赤ん坊は増えましたねえ」
「そうですよ。そうして年頃になると、男の子はルンペン。女の子は女の子でまた、一束いくらで売られて行くんですよ」
「これからは、赤ん坊は生まれても、うっかり『おめでとう』も言われませんねえ」
「そうですねえ、へへ」
「まったくねえ」
「お悔やみが言いたいくらいですよ」
「ほんとうだよ」
(ここから時代が進んだ現代ではすでに、家庭における労働もほとんどを外部へ任せてしまい、労働の担い手としての子どもを必要としなくなった。人口減少もやむを得ないだろう。ただ、思想の労働としてKJ法をやる場合に、人数が増えた方が発想が豊かになるため、子供は多い方が良いという考えもあるのではないか。食料を得ることに直結するわけでないので熟考が必要だが、新たな少子化対策にならないだろうか。)
(ここで見てきたように、肉体労働や手作業が機械にとってかわられると、人間の本質として通底するムダや非合理性が見捨てられてしまう。手仕事をもって味わう肌感覚がうすれてしまい、パソコンや電卓のみに頼るビジネスは急速に情念を失い、論理ばかりを尊いものとして敬うようになる。人間らしい直観など非効率として顧みられない。日本人の人生の大半を占める仕事において、感情や創造性が失われるなど拷問に近いのでないか。進展目覚ましい人工知能を盲信するのは避けて、手計算や手書き資料にも味わいを感じながら仕事をしたい。)
来週は、このR1ラウンドをまとめます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
