
松下幸之助と『経営の技法』#108
6/2 自己認識と対比認識
~自己認識も対比認識もできていなければ、会社のためになるはずがない。~
絶えず松下電器の実力というものがどんなものであるか、競争力はどの程度であるかということを総合して、判定を誤ってはならない。これは社長の仕事である。皆さんは総合的な判定をすることは、仕事が多少違うとしても、その担当の部門の実績、実力というものがどんなものであるかということを絶えず認識して、それを一歩高めるにはどうしたらいいかということについて考える。具体的に実力を持つているのかどうかということですね。
この間、ある一つの器具を見たところ、なとこれはまずいなと思うたわけです。汚いし、なんだか素人がつくったようなものなんです。こんなものは信用を落とすと思うようなものなんです。ところがそこの技術担当者は、これを平気で出している。それは認識していないわけですね。つまり、自分の技術そのものを認識できているかどうか、あるいは自分の技術とよその技術的とを対比した場合に、どれだけ劣っていてどれだけ進んでいるか、という対比認識もできていない。こういう状態においてやっておれば、これはもう会社のためにならないことは決まっている。
(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

1.内部統制(下の正三角形)の問題
まず、社長が率いる会社の内部の問題から考えましょう。
「敵を知り、己を知る」という言葉の重要性は、説明するまでもないでしょう。優先順位はともかく、両方が必要なのです。松下幸之助氏が強調するのも、まさにこの2つです。
これは、言われてみれば当たり前のことで、自分自身も、自分の置かれた状況も、両方とも理解することが必要です。例えば資格試験を受けるにしても、自分の理解度や実力が分からなければ、「何を」勉強すべきかわかりません。また、他人に比べた場合の自分の相対的な実力が分からなければ、「どこまで」勉強すべきかわかりません。ところが、下手な苦労ばかり積み重ねた人に限って、自分の狭い信念を貫くことに夢中になり、これら2つのポイントを忘れてしまう傾向があるのです。
要は、自分を客観化できることが大事、ということにつきます。
そして、これは個人の問題ではなく、組織の問題です。
つまり、組織として、取りつかれたように何か特定の考え方に取りつかれ、柔軟な対応ができない状況になってしまえば、組織が社会から遊離してしまい、その存在すら危ぶまれてしまうことは、容易に理解できます。会社が社会の一員として受け入れられること(コンプライアンス)こそが、会社の永続的な利益につながる大事な要素です(一発当てて、無責任に逃げる、というビジネスモデルではない)から、会社が社会から遊離しないための仕組みづくりがとても重要です。個人の力量、つまり誰かバランス感覚の良い人がいるから何とか社会から見捨てられずに済んでいる、という情けない状態ではなく、社会に受け入れられるための情報や対応を、組織として永続的に入手し、実行できることが重要なのです。
この観点から具体化していくと、まずは従業員一人ひとりが「自己認識」「対比認識」を持たなければなりませんから、松下幸之助氏がこの点を訴えることの合理性も、理解できます。
さらに一歩踏み込むと、これを組織化しなければなりません。
すなわち、多少、従業員の認識にばらつきがあったとしても、結局、会社が組織として「自己認識」「対比認識」を持つことができれば良い(むしろ、従業員のばらつきを組織として吸収できる)ことになりますから、この感覚を会社組織として持ち合わせ、実行できるように、組織を作り上げ、それぞれに然るべき機能を与えるべきなのです。
2.ガバナンス(上の逆三角形)の問題
次に、ガバナンス上の問題を検討しましょう。
投資家である株主と経営者の関係で見た場合、組織のマネジメント、とりわけ戦略の設定と方向付けに関する、経営者の有すべき資質が見えてきます。
すなわち、会社が自分の位置や能力を理解できなければ危険であることは、個人の問題としてだけでなく、組織の問題としても重大な問題であることは、氏がコメントしているとおりです。
たしかに、組織を鼓舞するためには、わかりやすい目標を設定し、競争すべき領域を限定し、その限定された領域で競争させる方がいい場面があります。
けれども、そのことが会社自身の視野を狭めてしまっては、元も子もありません。視野を広く持つことは、特に現場の従業員にとって余計なことを考えることに繋がり、集中力を散漫にしたり、意欲を萎えさせたりしますが、会社が組織として歩むべき本来の道を踏み外すよりはましです。
このように、組織の意欲を高めつつ、大きな方向性を踏み外さない、という、両方に配慮した舵取りこそが、経営者に求められる資質なのです。
3.おわりに
従業員の意識の問題は、会社全体の方向性の問題と一体の問題です。特に、従業員に対して上司の指示したことだけやっていれば良い、というモデルではなく、従業員各自が主体的に活躍し、そのことで組織全体の活力が高まる、というモデルの場合には、従業員各自が、進む方向性を誤らないだけのセンサーと判断能力を兼ね備えなければなりません。
このようなモデルであればなおさら、従業員の意識が重要な課題となってくるのです。
どう思いますか?
※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。
冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

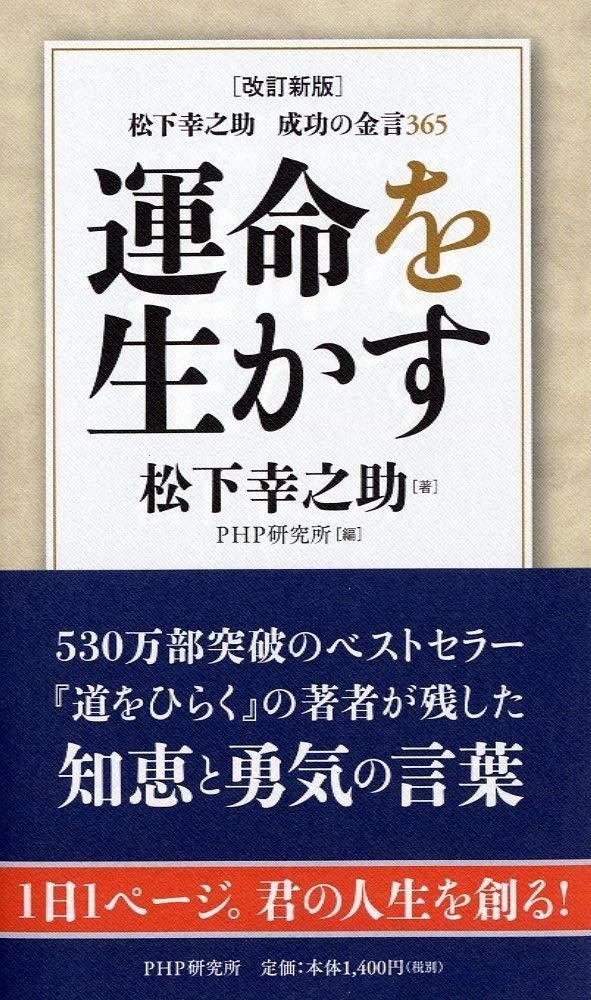


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
