
【教育ニュース最前線】国を支える研究力の危機/ 書くことで見えてくるもの
:::【教育ニュース最前線! 】:::
日々報じられる教育関連情報から、
教育業界への影響が大きいと思われる内容を、
代ゼミ教育総研 研究員が厳選してピックアップ。
それぞれの分析・私見を述べます。
今回のテーマは「国を支える研究力の危機、書くことで見えてくるもの」。
どちらも学校や大学を越え、その先の未来にも深くつながる内容です。
教育・学校・入試について関心がある方々の、
考えるヒントとなりましたら幸いです。
:::::::::::::::
🔽国を支える研究力の危機
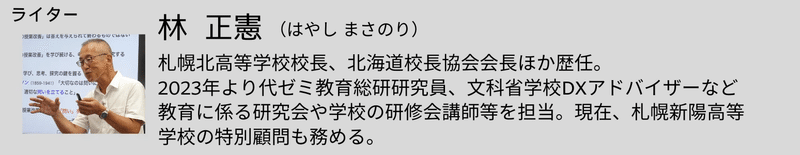
本日 1 つ目は、「科学技術の研究・開発」に係る深刻な問題についてご紹介します。
=====
文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が「科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP 定点調査 2023)」の報告書とデータ集を公表しました。
▼大学教員の 8 割が研究時間の不足を実感、文科省調べ(先端教育・5/16)
▽科学技術の状況に係る総合的意識調査 (NISTEP 定点調査 2023)報告書(文部科学省 科学技術・学術政策研究所ライブラリ・5/14)
NISTEPは、科学技術や学術振興に関する基礎的な事項を調査・研究する国立の試験研究機関です。
定点調査は、第一線で研究開発に取り組む研究者や有識者約 2,200 名を対象に継続的に行われています。
日本では、1995 年に「科学技術基本法」が制定され、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することになりました。
2021 年、急速に進展する科学技術・イノベーションと人間や社会の在り方が密接不可分になっていることを受け、法は「科学技術・イノベーション基本法」に変更されました。
法に基づき「第6期 科学技術・イノベーション基本計画( 2021 〜 2025 年度)」が策定され、今回の調査は 3 年目にあたる昨年 9 月から 12 月にかけて実施されました。
▽第6期科学技術・イノベーション基本計画(内閣府)
基本計画においては、国内外における情勢変化、新型コロナウイルス感染症の拡大、これまでの政策の振り返りについて認識を明らかにし、Society5.0の実現に向けた政策を示しています。
「国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革」「知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化」「一人ひとりの多様な幸せと課題への挑戦を実現する教育・人材育成」といった目的を掲げ、その実現のために「 5 年間で 120 兆円」の投資を目指すとしています。
しかし、残念ながら、今回の調査からは、時間の面でも環境の面でも、日本の研究が危機的な状態にあることがわかります。
NISTEPは、その後、研究開発費に係る調査の結果も公表しています。
▽大学教員レベルで見た研究開発費の時系列変化: 「科学技術研究調査」を用いた試行(NISTEP・6/7)
国立大学において、2000 年代中頃から 2010 年代初頭にかけての運営交付金の削減、研究開発費における「選択と集中」を背景に、仮説を立て調査・分析しています。
研究時間が足りない。
研究資金が足りない。
研究者の悲痛な声が聞こえてきます。
🎤 ・ 🎤 ・ 🎤
💡研究員はこう考える
▷社会のこと、個人のこと、そして子孫のこと
理想と現実が乖離していることはよくあることです。
日本は全体として国際社会における経済的地位を低下させ、研究や教育に十分な投資ができない厳しい状況にあります。
▼日本の去年1年間の名目GDP ドイツに抜かれ世界4位に後退(NHK・2/15)
しかし、少子化及び人口減少、生産労働人口の減少が深刻化する中、技術革新により労働生産性を高めること、組織改革や予算配分の改善などマネジメントの質を上げることの重要性は火を見るよりも明らかです。
▽労働生産性の国際比較2023~日本の時間当たり労働生産性は52.3ドル(5,099円)でOECD加盟38カ国中30位~(公益財団法人日本生産性本部)
日本が右肩上がりの成長を遂げている局面では、個人は全体を俯瞰し国の政策で頭を悩ませる必要はあまりなかったかもしれません。
量の増大を頼みにできるなら、自由な発想で、伸び伸びとやっているだけでよいかもしれません。
しかし、現在は危機的な状況であり、個人主義ではいられないと考えます。
国全体が、有限な時間と資本、エネルギーといった資源をどう配分するか、どう優先順位をつけるかを考える必要があります。
多岐に渡る分野の様々な課題解決のために必要な資源を全て満たすことは不可能だからです。
また、近視眼的に、自分の興味・関心や課題意識のみで判断することは危険です。
社会のことは、個人の生活に大きな影響を与えるからです。
研究やイノベーションに限らず、少子化、インフラ、介護、交通、環境etc.のことなど、どのような問題であれ、自分事として捉えざるを得ません。
日本の研究、研究者のこれからのことをどう考え、どうコミットするか。
自分から遠いことのように感じる人も多いかもしれませんが、世界には七世代先のことを考え、自分たちの行動を決めている人たちもいます。
▽『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』ローマン・クルツナリック著 松本紹圭訳 2021年 あすなろ書房
日本のことを、未来のことを、より真剣に考えたいものです。
🔽書くことで見えてくるもの

本日2つ目のテーマは、「ライティング」。
子どもから大人まで必須のこのスキル。
その重要性をあらためて考えさせられます。
=====
ソン・スッキは、韓国を代表するライティング・コーチです。
『150年ハーバード式ライティングの秘密』は、韓国で10万部のロングセラーになりました。
日本では、小学4年生から取り組めるエッセンシャル版が出版されています。
▽『作文宿題が30分で書ける! 秘密のハーバード作文』 – 2024/4/2 ソン・スッキ (著), 岡崎暢子 (翻訳) CCCメディアハウス
ソン氏は、毎日文章を書くか、書かないかで大きな差がつくと言います。
▼毎日「文章を書く子」と「書かない子」驚きの差(東洋経済・6/3)
一日に10分でよい、短い文章でよいから、毎日書くことを勧めています。
言葉をたくさん知っていても、国語の文章問題が解けても、書かなければ文章力はつきません。
また、タイピングに比べ、手書きの方が脳が活性化するというデータがあります。
したがって、ソン氏は「毎日手書きで10分」を勧めます。
🎤 ・ 🎤 ・ 🎤
さらに、息子との経験から、フィードバックの重要性を指摘しています。
▼塾に行かずに難関大合格した子「毎日10分したこと」、ハーバード流「論理思考を鍛える」ためのトレーニング(YAHOO/東洋経済・5/28)
息子が中学受験を迎えた頃、家族はソウルから半日離れた田舎町に住み、塾はありませんでした。
「勉強しなさい」とも言わず、ただ毎日10分文章を書かせ、それにフィードバックしました。
フィードバックは、「よい点を褒める」「気になった点を尋ねる」「肯定的な提案をする」の三点です。
彼は見事にハーバード大学に合格しました。
ソン氏は、YouTubeで 1 億 4500 万回視聴されたトロントの心理学者、ジョーダン・ピーターソンの本を引用しています。
▽『生き抜くための12のルール 人生というカオスのための解毒剤』– 2020/7/7 ジョーダン・ピーターソン (著)(朝日新聞出版)
・ ✍ ・ ✍ ・ ✍
💡研究員はこう考える
▷日常の中でどう感じ考えたかをアウトプットする訓練
言語活動には大きく「読む」「聞く」「書く」「話す」があり、後者の二つはより能動的な活動です。
書くことは、論理的思考力や構成力を鍛えます。
書くとき「何を書こうか」と考えます。
自分が学んだことを振り返ります。
自分が何を感じ考えたかにフォーカスします。
自分がどんな世界のどんな地点にいるのかを見定めようとします。
メタ認知をすると、過去から現在、未来に向かう時間の線が浮かび上がります。
学習指導要領で重視された「見通す」「振り返る」活動を、私も強調してきました。
行事や総合的な探究の時間では、できるだけリフレクションを行うようにしました。
手帳教育を推進したこともあります。時間管理、自己管理に有効です。
・ 📖 ・ 📖 ・ 📖
マッキンゼー出身でセンジュヒューマンデザインワークス代表取締役の大嶋祥誉氏は、2冊のノートを使い分ける方法を提案しています。
1冊は感情を書き殴る「クリアリング・ノート」。
もう一冊は出来事をベースに感情を掘り下げる「ロジカル分析ノート」です。
▼マッキンゼーで学んだ「2冊のノート」の感情コントロール術(THE21 online)
・ 📖 ・ 📖 ・ 📖
私は寝る前の3行日記(よかったこと・うまくいかなかったこと・明日への抱負)も度々勧めました。
▼自律神経が整う「3行日記」が最高。夜寝る前の “たった5分” で頭もスッキリ!(STUDY HACKER)
・ 📒 ・ 📒 ・ 📒
そして、私が重視するのは、学びのリフレクションです。
従来の「勉強観」では、学問的に正当な学習内容を正しく理解することが大事であり、学習者の主観的な感想や意見は二次的なものとして脇にやられていたと思います。
確かに正確な知識はテストで問われますが、個人的な思いは点数化されません。
しかし、私たちは学問の世界ではなく、現実の世界を生きています。
得られた情報が知識の観点から適切かどうかの判断は重要です。
その点を軽視するといわゆる「反知性主義」に陥ります。
しかし、現実の世界では、私たちの主観的な感想や意見が問われます。
したがって、日常的に学んで何を感じ考えたかをアウトプットする訓練が大切です。
表現し、それによって、自分を知る。
批判的に検討し、アップデートすることが可能になります。
今は生成AIがネット上の情報を集め、もっともらしい文章をつくってくれます。
しかし、生成AIはあくまで手段です。
人間は人間とコミュニケーションをとり、人間と生きていきます。
・ 🎬 ・ 🎬 ・ 🎬
生成AIと生きていこうとすると、大変なことになります。
孤独な主人公がAIとの恋に落ちて・・・
▽僕らの映愛(山崎貴監督✖️Hello,AI Lab)Vol.02 her/世界でひとつの彼女(三菱電機)
人の文章には、生成AIの文章にはない味わい、魅力があります。
書いて考え、考えて書き、自分の意見を表明し、対話をしながら、
よりよい社会をつくろうとすること。
それができるのは人間です。
よろしければ vol.06-2 もご覧ください📓
・ ・ ・

#代々木ゼミナール #代ゼミ教育総研 #教育総研note #文部科学省 #科学技術 #研究者 #研究開発費 #研究時間 #ライティングコーチ #ハーバード作文 #論理思考 #生き抜くための12のルール #手書き #受験 #大学受験 #大学入試 #大学
