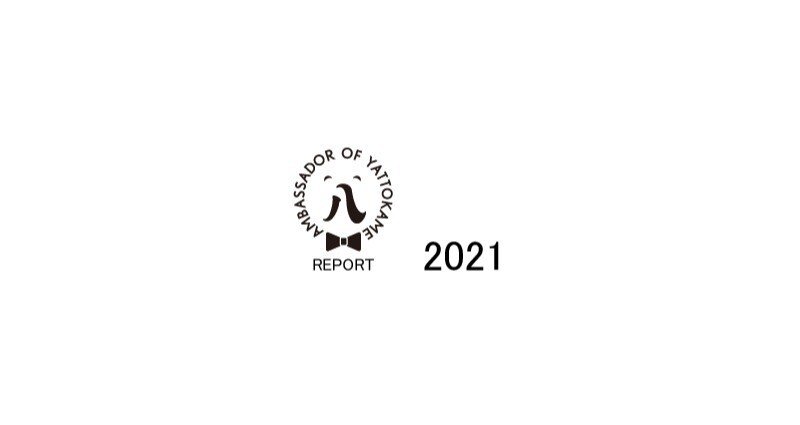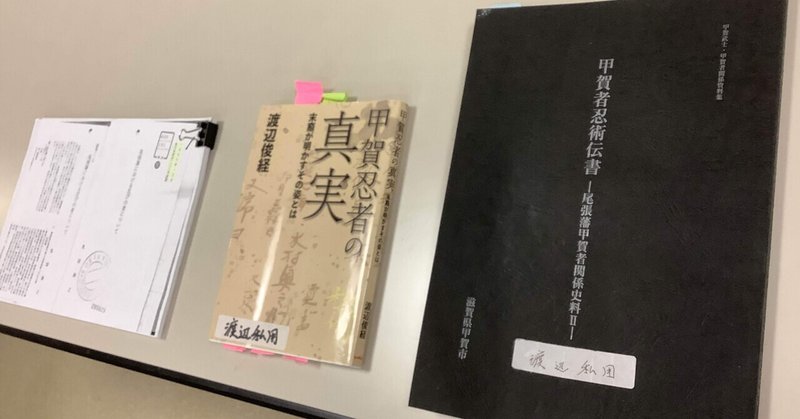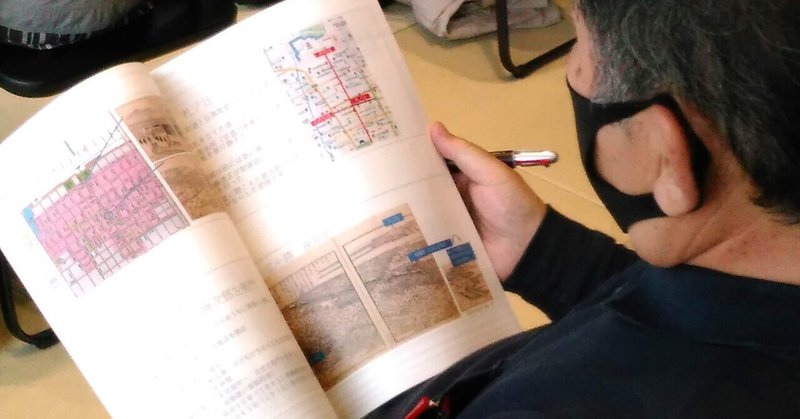#やっとかめ大使
お米トークと和菓子づくり体験②14:00〜16:00
「お米トークと和菓子づくり体験」午後の部も盛況でした!
まずは髙島屋の和菓子バイヤー畑主税さんと伏繁商店の鬼頭茂仁さんから,和菓子材料としてのお米についてのお話をうかがいます。道明寺や寒梅粉,上用粉など,お米由来のいろいろな粉の実物も見せていただきました。一口に「お米からつくった粉」といっても,粒の大きさや手触りが全然違うのですね。
つづいて和菓子づくり体験。名古屋生菓子組合青年会の職人さんた
お米トークと和菓子づくり体験①10:00〜12:00
お米トークと和菓子づくり体験に参加してきました。
前半は、高島屋和菓子バイヤーの畑主税さんと五つ星お米マイスターで伏繁商店(和菓子材料商)の鬼頭茂仁さんの対談で、[お米って凄いよね!和菓子の命のひとつ]の講座でした。
うるち米ともち米の色々なお菓子の種類や作り方等のお話がありました。
後半は、名古屋生菓子組合青年会の名古屋の和菓子屋さんの若旦那さん方の優しいご指導で、おはぎ、桜餅、練りきりでハ
名古屋の楽家「道年」の茶の湯10/30(土)⑤14:00〜14:45 ⑥15:00〜15:45
10月30日(土)に名古屋城茶庭書院にてやっとかめ文化祭『名古屋の楽家「道年」の茶の湯(14時~、15時~)』に参加してきました。
名古屋城茶庭は通常非公開、中部地区を代表する数寄者・森川如春庵の指図です。
前半・寄付(展観席)は初代道年から五代のご子息・崇壱さんの六世代の作品が飾られたお部屋で四代尼道年さんから道年家の歴史や楽焼について学んだ後、いよいよ本席(茶席)へ。五代道年さんが席主、崇
名古屋の楽家「道年」の茶の湯10/30(土)①10:00〜10:45 ②11:00〜11:45
10月30日(土)にやっとかめ文化祭まちなか寺子屋の講座『名古屋の楽家「道年」の茶の湯』(10時開始と11時開始)へ参加してきました。
名古屋八事窯五代の中村道年さんを講師にお迎えし、楽家「道年」の茶の湯と、道具を深く知れた45分。道具組の説明や道年家の歴史などの話を聞きながら、道具を鑑賞しました。その後茶の湯が行われました。
名古屋八事窯、歴代の道具が見られ、直接説明を聞けることがすごかった