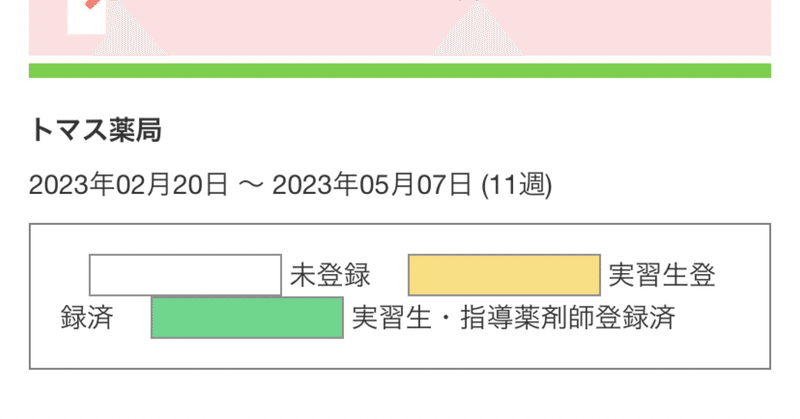2023年3月の記事一覧
3/08 便秘薬、種類
今日は便秘治療薬について教わった。
便秘治療薬は大きく非刺激性下剤と刺激性下剤に分けられる。
非刺激性下剤は酸化マグネシウムなど腸内の浸透圧を高めることで腸管内に水分が移動することにより便が柔らかくなる塩類下剤、カルメロースなど水や超下院愛の水分を吸収することで便を大きくし、帳に物理的な刺激を与えることで排便を促す膨張性下剤、DSSなど界面活性作用により便の表面張力を低下させて便中に水分を浸透させ
3/07 オピオイドローテーション
今日は昨日に引き続き麻薬について教わった。
以前の末期の癌で当初オピオイド鎮痛薬であるオキシコドン徐放錠が50 mg/day処方されていた患者がいた。この患者は病態が悪化するにつれ錠剤を飲むことが困難になり、テープ剤 (フェントステープ)への変更が検討された。オピオイドを変更する際は、力価表から同じ効果を得るための投与量を判断することが出来る。今回の場合オキシコドン徐放錠 50 mg/dayであっ
3/01ベンゾジアゼピン
今日来られた患者でベンゾジアゼピン系抗不安薬であるメイラックスを処方されていた方がいたので、今日はベンゾジアゼピン系抗不安薬について教わった。
ベンゾジアゼピン系薬はベンゾジアゼピン受容体に結合しGABA受容体を活性化することで、薬効を示す。このGABA受容体には5つのタイプがある。それぞれが活性化することによる作用はタイプ1が鎮静作用、タイプ2が抗不安・筋弛緩作用、タイプ3、5も筋弛緩作用、タイ