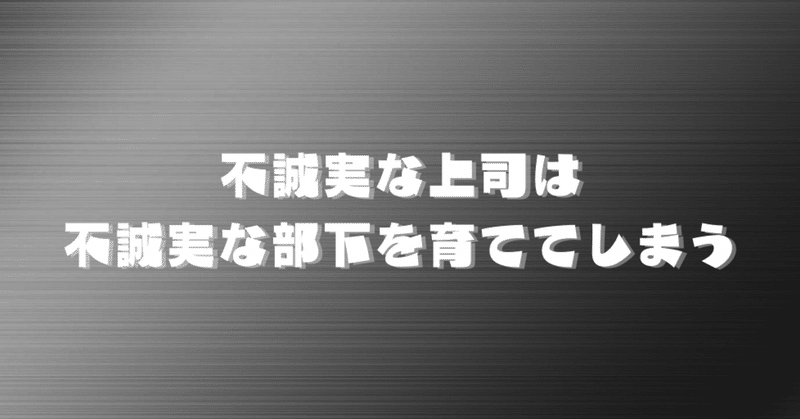
不誠実な上司は不誠実な部下を育ててしまう
はじめに(いつも書いてること)
このnoteでは、「仕事でも私生活でも心をラクにする(ワークライフハック)」をテーマに文章を書いています。
※「ラクする」というのは、「心身に苦痛などがなく快く安らかに過ごす」という意味で使っている言葉であり、シンプルに「サボる」という意味ではありません。
今回の内容
不誠実な上司は不誠実な部下を育てるなぁ・・・そう思い、少し前に読んだ本のことを思い出しました。
数字はファクトで、数字は嘘をつかない。
ただ、数字を扱う人が不誠実で、嘘の数字を出してしまったら、ファクトとして周囲は捉えるけど、実はファクトじゃないという事態になってしまう。
目的を見失った、良くない状態です。
「この数字を報告しとけばいいんでしょ?」という上司がいたら、そういう部下を育てることになります。
基礎に立ち返るつもりで、こちらの本を読みました。
組織の中に「数字をファクトとして押さえられるようになる」という課題があり、基礎に立ち返ろうと思いました。←「組織としてこの本を読んでみよう」と推奨していただいた背景もあります。
以前に、『短時間で理解できる数値化の鬼ブックガイド』という資料を読んだことがありました。
本をフルバージョンで読んだことはなかったので、丁寧にインプットしようと思い、読み進めました。
複数人で同じインプットをするので、組織としての業務改善に繋げていこうと思いました。
特に大切だと思った文章
目的さえ決めてしまえば、そこまでの行き方は自由。個人の能力によって試行錯誤してもらうことで、思わぬ近道を発見したり、自分にとって効率のいい交通手段を見つけることができる。自分で業務内容を改善して、初めて人は成長する。
著名なヒットメーカーや有名デザイナーも、話を聞いてみると、驚くほどの量をこなしていることがわかる。そのうちいくつかが圧倒的に成功すると、あたかも「それしかやってない」ように見えます。行動量は「見えない努力」だから。有名な作品を世に出している人ほど、圧倒的に多くの失敗作も生み出している。ホームランを打ちたければ、誰よりも多くバットを振る回数を増やすしかない。仕事とスポーツは違うように思うかもしれないが、構造は同じ。仕事ではスポーツのように練習がないから、より普段の行動量が大事になってくる。ホームランを打てば、その日の三振のことは観客の誰もが忘れてしまうように、大きな成功を生み出すと、それまでの失敗は誰も覚えていない。
※2023/05/05の日経新聞に大谷翔平選手の記事があり、そこにもこれに通ずるようなことが書かれていた。
・・・
試合がなかった1日にヌートバーから食事に誘われても「寝ている」と断った。10時間以上は睡眠に充て「寝れば寝るだけいい。まずは量。質はその次」という。快眠から覚醒し、日々の活躍につなげている。
・・・
とても大事なこと。
文章ではないですが、『変数』について書かれている一連の流れは、全て大切な部分だと思った。
識学の考え方では、社内の「人」による変数をなくすことを徹底する。つまり、どんな人が上司であろうと、部下にとっては平等でフェアな職場づくり、チームづくりが必要だということ。「どの上司に付けば成長できるのか」 「どのチームに入れば自分にとって有利なのか」 そういった変数によって個人の成績に明らかな偏りができるようでは、いい組織とは呼べない。私は経営者の立場ですが、その偏りがないかどうかを常にチェックしている。
5年後になっているべき姿になるため、まず1年後にどんな目標があり、この1週間に何をやるべきで、今日1日はどう過ごすべきなのか。 「5年後の姿」と「今日のKPI」はつながっている。
識学では、勝手に長期的な自己目標を立てることはあまり勧めていない。まずは行動量ファースト。とはいえ、「何歳までにどういったポジションになりたいか」くらいは、誰しもが考えることでしょう。「30歳までにマネジャーになる」 「35歳までに支店長になる」 そのために、逆算して毎年のノルマの達成度を考えたりする。大企業では会社が勝手にレールを敷いてくれますが、小さな企業などの場合では個人のキャリアを自分で考える必要がある。逆算して考えるようにしよう。
今後に向けて・・・アクションへ移す
解決策を策定するには、課題設定が必要。課題を設定するには、理想と現実のギャップ(問題)を明らかにすることが必要。問題を明らかにするには、理想と現実を数字として表すことが必要。→全チームの理想と現実を数値化する。
課題の話をしていたら、「捉えている問題は?」と問う。解決策の話をしていたら、「捉えている課題は?その背景にある問題は?」と問う。2018年まで率いていた採用チームでやっていたことを、再び実践する、うざったいと思われるくらい。
「この%は、何分の何ですか?」というのを口癖にする、チーム全体で。僕はよく、メンバーに聞いてきました。これホントに大事な問いです。
所感
客観的事実である数字。だからこそ、報告・共有する数字を捻じ曲げる事態が起こり得る。客観的事実として共有されるはずの数字が事実でなかった場合、それ以降の議論が無駄になるので、絶対にやってはいけないこと。これを、改めて実感した。
ビジネスの基本には、いくつかの流派があると思います。本を探せばいろんな種類があるし、これまでもいくつかの本を課題本として読んだことがありました。大切なのは、施策を点として完結させることなく、日々の業務に繋げていくこと。プラス、マネージャーやリーダーとプレーヤーが共通認識を持つこと。
例えばこれまでだと、『50の原理原則(仕事で成果を出す思考と行動)』という本を、多くの社員に配布したことがありました。あの本には、今回の『数値化の鬼』に書かれているようなことと同じようなことも含まれていました。どのような組織にしたいか、そこに向かうプロセスとしてどのような仕組みを構築したいか。ここを代表が舵を切り、幹部陣を巻き込みながら構築していく必要があると感じました。組織には、組織の目標を達成させるために役割があります。それぞれがそれぞれの役割を全うすることで、組織の目標が達成できるように、どんなチームにしたいか、そのチームにはどんな基礎が必要なのか、どんな仕組みが必要なのか、などを考えていく必要があると思いました。うちの場合、基本はコアバリューとクレドですが、「うちの会社に入ったらこれが仕事の基礎だ」というものを構築してもいいなと思った。教科書的な本として、『50の原理原則(仕事で成果を出す思考と行動)』も『数値化の鬼』も適しているかなと思ったので、そこは進めていきたい。←実際に今、『50の原理原則(仕事で成果を出す思考と行動)』という本を新卒向け研修プログラムの教科書にしようとしてます。
数字は嘘をつかない。
ただ、数字を扱う人が嘘をついてしまったら、数字が嘘をついているかのようになってしまう。
偽りの数字を伝えておきながら、あたかも数字が嘘をついているかのように報告する。・・・そんなことを上司がしていたら、それを見ている部下は、それが当たり前になりかねない。
「この上司おかしいよね」と思えればいいんですけど、上司を疑ったり、「それっておかしいです」と言える部下ってなかなか少ない。
子育てと同じだと思いました。・・・だから、人を育てる側の責任は重いです。
部下としても、学ばないといけません。
上司の言いなりになる必要なんてない。
立場や役職に拘らずに、ビジネスパーソンとしての自分なりの正義を持てるようになりましょう。←漫画『ONE PIECE』の海軍と同じです、『正義』を海軍として掲げているけど、個人として『◯◯の正義』を掲げているあの感じ。
「この人は素晴らしい、この人についていこう」と思えるような誰か(直属の上司じゃなくてもいいです)を見つけて、その人のようになることを目指すつもりで日々を過ごせば、自分の足りないことに気づき、それを埋めようとして行動するはずなので、自身で成長のレールを敷くことに繋がります。
そういう人の存在は、自身のブレない軸の確立を手助けし、その軸に自分を引き戻す自律も育みます。
自分の中に軸を確立できて、その軸に自分を引き戻せるようになれば(自立力と自律力が高い状態)、誰かに伴走してもらう必要性も薄れていきますから、自分で自分を導いていけばいい。
だから、軸の確立の時についていく人を間違えないでください。
誠実に物事を進めていく人についていけば、誠実なビジネスパーソンになっていくでしょう。
不誠実に物事を進めていく人についていけば、なり、嘘に嘘を重ねていくような不誠実なビジネスパーソンになっていくでしょう。
誠実さは、自分の心をラクにします。
感謝
今回も、読んでいただきありがとうございました。
他のnoteも読んでいただけると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
