
猿かに合戦で月を生成する深層の”心” -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(57_『神話論理3 食卓作法の起源』-8)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第57回目です。
これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
分離すべきところを結合し、結合すべきところを分離することと、親族構造の起源
前回の記事の最後にレヴィ=ストロース氏の友人であるジャック・ラカンの『精神分析の四基本概念』に記された一節を紹介した。
「原始的な科学の根は、陰陽、水火、寒暖といった対置と組み合わせを重視し、これらの組み合わせにダンスをリードさせようとするような思考様式の中にこそあった、ということです。ここでダンスという言葉はたんなる比喩以上の意味を持っています。なぜならこれらの組み合わせのダンスは、ある社会の中の性的分配に本質的に関わるダンスの儀式と密接不可分なものですから。」
陰/陽、火/水、寒/暖、男/女といった”経験的で感覚的な区別”の”対置と組み合わせ”に、”ダンスをリードさせようとする思考様式”こそが、「原始的な科学」つまり、人類の経験的で観察的で客観的な思考とその言語、あらゆる物事の”起源”を探求しようとする野生の思考の一番底で動いているのではないか。
そして、数ある経験的で感覚的な区別の中でも、特に男/女の分離と結合の謎こそが、人類の論理的・言語的思考の始まりを準備したのではないか。
人間もまた、他の動物と同じように雌/雄、男/女が、別々でありながら結合することで次世代に繋ぐ仕組みになっているが、人類の場合、この男女の分離と結合は、文化的な体系として、つまり誰が誰と結婚してよくて、誰がだれと結婚してはいけないか、という規則、タブーによって体系化される。
つまり、誰が誰とどう結ばれてもOKということではなく、規制された体系の中で、具体的な一組の男女の文化的な「結婚」ということが行われる。この辺りはレヴィ=ストロース氏が『神話論理』の前に取り組んだ仕事の中心である。

誰が誰と結婚してよくて、誰がだれと結婚してはいけないか、という人間ならではの文化。
ここで思い出すのは、神話にはよくインセスト・タブーの侵犯というモチーフが登場することである。すなわち、通常の社会においては結婚することが許されない者同士の結婚である。
新世界のあらゆる神話のうちで、太陽と月の起源をインセストから説明する神話ほど、極北の地から南アメリカにまで広く分布しているものはないだろう。インセストにより兄弟と姉妹は故意であろうとなかろうと[…]過度に近い距離で結ばれるということである。
兄弟姉妹での”結婚”などと言われるとびっくりしてしまう方もいらっしゃると思うが、ここは神話論理の世界である。
経験的現実としての具体的な兄弟姉妹の関係の話をしているのではなく、脈動するβ二項の一即二・二即一の関係を、身近な二項対立を組み合わせて考えてみようというところである。
そもそもなぜ神話は、わざわざインセスト・タブーの侵犯を話題に選ぶのだろうか。その答えは、経験的に「分離」されているはずの二項を”過度に結合する”ことで、両義的媒介的第三項を作ることができるから、ということになるのだが、詳しく分析してみよう。
結婚の起源
月の起源
転がる頭
『神話論理3 食卓作法の起源』に掲載されたM392「クニバ 転がる頭と月の起源」という神話を見てみよう。
この神話は結婚できる相手が文化的に規制された制度的結婚の始まりのはるか手前で、そもそも結婚する必要があるようになった(あるいは結婚できるようになった)ことの起源を語るものとも読める。
ある娘のもとに、毎晩見知らぬ男が訪ねてきた。
二人は愛し合った。
娘は男の正体を知りたくなり、ある夜、男の顔を青黒い樹液で擦っておいた。
明るくなってみると、なんと、娘の兄の顔に青黒い樹液の跡がついていた。
*
兄は村から追われた。
そして逃げる途中、敵対する部族の連中に見つかって、首を刎ねられた。
まずこの神話の冒頭、日本の三輪山の神話とそっくりである。
正体不明の恋人に、夜のうちにしるしをつけておく。
そして世が明けると、恋人の正体が明らかになり、二人は分離される。
この二人の結合は、相手が誰だかよく分からずに展開しているという点で、文化的に規制された結婚ではないものである。
*
経験的感覚的に分離されているべきところが過度に結合してしまったところから、一挙に逆に転じて、兄が村から追い出される、という分離が引き起こされる。
この分離は徹底していて、妹から、村から、分離された兄は、さらに追い打ちをかけるように、その頭と身体という通常はひとつに結合していないといけないはずのものが二つに分離されるというとんでもない悲劇に見舞われる。
とんでもないアニキだから罰が当たって当然だ、という方もいらっしゃると思うし、お兄さまがカワイソウ・・、と思う方もいらっしゃることだろうが、いずれにしてもここは神話である。
過度に分離された首は、そこで終わることなく、転がって憑いてきて、過度に結合しようとするのである。
喜んだり悲しんだりしている場合ではない。コワイ。
つづきを読んでみよう。

要素(項)ひとつひとつは「んん?」という感じだけれども、
全体の構造(関係)はうまく組まれている。
* *
娘にはもう一人、別の兄がいた。
この第二兄は、村から追われた第一兄(妹と結ばれた方の兄)を探し回り、そしてついに、兄の頭が転がっているのを発見した。
* * *
第一兄の”頭”は、ようやく助けが来たとよろこび、
弟に対して、飲み物や食べ物をよこせとせがみ続けた。
第二兄は困り、頭を置いて逃げることにした。
しかし、頭は転がって村まで追いかけてきて、家に押し入ろうとした。
しかし、家の扉は開かない。
頭は、水や石などにつぎつぎと変身してみせて、
最後は月になろうと、糸玉を繰り出しながら天に登って行った。
そして密告した妹への復讐だと言い、
兄は月に変身し、妹に月経を与え、悩ませることになった。
インセストの兄の首が刎ねられたところに、もう一人の兄というのが登場する。この主人公の娘(首の妹)には、兄が二人いたのである。
兄弟の接近→分離→接近→分離
兄弟二人のセットというのは神話によく出てくる組み合わせであるが、兄弟とのは、別々に異なるが同じ者である。即ち、兄弟とは、経験的には対立することが常套の二項(二人の男)でありながら、この二項が非同非異の両義的な状態に励起したものである。
この兄と弟という非同非異の関係にある二項が、結合し、そして分離し、そしてまた結合しようとする動きを演じる。まず弟が兄(首)を発見する、兄(首)は弟に自分の世話をするよう要求し(食べ物を分け共にするというのは結合のひとつの形である)、困った弟は兄(首)を放り出して逃げる(分離する)。しかし首は転がってついてくる!ここがおそろしいところである。分離したはずの兄弟が、まだ結合しようとする。
そして首兄はついに自分の家に、弟や妹たちが立てこもった家の前に辿り着き、中に入れろ、とうろうろごろごろする。
この、あわや、という急接近=結合から、神話は一挙に分離へと転じる。
神話においてβ脈動する(過度な結合と過度な分離を両極とする振幅を高速で描き続ける)β項のペアたちは、結合すれば分離するし、分離すれば結合する、と相場が決まっている。
*
家の中には入れてもらえないと悟った首兄は、意外と素直に、天体(この場合は月)に変身し、地上を遥かに離れた空へ空へと、分離されていく。
両義的媒介項も即自的には存在しない
この神話は過度な結合から過度な分離への急展開が四回重ねられて、図1のような二項対立関係の組み合わせを分節している。

a結合その1)まず、兄と妹の結婚という過度な結合がある。
二つのβ項が同じ座標を占めるような事態である。
b分離その1)次に、兄の体から頭が取れる。
これは過度な分離である。通常くっついているはずの頭と体が、別々に分離してしまう。しかもこの頭、生きているのである。
c結合その2)そして弟が兄を探しにやってきてうまいこと出会う。兄弟の結合あるいは接近と言える。そして兄(頭)は弟につきまとう。冒頭では兄妹がひとつになったが、ここで兄弟がひとつになる。ここに第二の過度な結合がある。
d)分離その2)そうして、第二の過度な分離へと物語は展開する。弟はせっかく見つけた兄の頭を放り出して逃げ出す。頭はころがって追いかけてくる。神話的な鬼ごっこである。そうして弟は家のなかに閉じこもり扉を閉ざす。兄(頭)はごろごろ転がるも、ついに諦めて、”糸玉”から伸びる糸を伝って天に昇り、月になる。
糸玉は、三輪山の神話にも登場する媒介項(過度な結合を過度な分離へと急転換させる媒介項)であるというのがおもしろい。

*
哲学者の清水高志氏が『空海論/仏教論』の「レヴィ=ストロースから三分結合説へ」という節で次のように書かれている。
「レヴィ=ストロースによる浩翰な神話の論理の研究は[…]神話的な思考がどのような展開を辿って世界を複雑に弁別し、意味づけるかについての豊富な事例をもたらしてくれる。厳密にいうと、二項対立はそこでは複数種のものが組み合わさったものとして与えられ、それらの組み合わせが変化することによって、ある二項対立を兼ねた第三項(媒介)が見いだされるのが常である。そうしてこうした第三項じたいが別種の二項対立の一つの項であって、このような第三項の位置はまんべんなく置き換わり、出発点がどこであると規定できないような、円環的な関係が描き出される(縮約)というのが、レヴィ=ストロースが取り組んだ神話の論理であった。」
第三項も(上の図でいえば、Δ二項に対するβ項)それ「じたいが別種の二項対立の一つの項」である。つまり第三項は、なにかスペシャルな項として、それ自体で単独孤立して即自的に自存して転がっているわけではなく、あくまでも二項対立関係の中で、それではないものーではないものとして区切り出される限りで「項」として観察されるのである。
上の神話の場合、兄/妹、首/体、兄/弟、(そして、弟/妹)という関係は、すべて図1で強いて表現するなら、β二項の、第三項と第三項の関係である。
第三項のペアは、過度に結合したかと思えば過度に分離し、過度に分離したかと思えば過度に結合する、という振幅を描く脈動をする。
第三項の分離と結合のあとに
経験的で感覚的な世界の
安定した分節体系が定まる
こうしてこの神話の最後には、まず天/地、あるいは地上の存在と天界の存在が分離され、この分離が確定される。つまり月が落ちてきて首の姿に戻ったりすることなく、月は月で、ずっと空にあるような束の間の(宇宙的にみれば)調和が訪れる。
そうしてやや唐突に、月になった兄が妹に月経を与える、というところで神話は終わる。
これについて、別の神話でははっきりと言及しているものがある。すなわち神話において、月経の起源は、人間の女性が子供を産むことができるということの起源であり、それゆえに、結婚の起源の前提であり、夫婦の起源、妻と夫という二項関係の起源の前提になるものである。
つまりこの神話は、最終的に
天 / 地
妻 / 夫
という極めて根源的な経験的二項対立を分離しつつも結びつけておくために、1)兄妹によるインセスト・タブーの侵犯、2)兄の体と頭の分離、3)兄の頭と弟の結合、4)兄の頭の昇天による分離という、過度な結合→過度な分離→過度な結合→過度な分離の振幅を描く脈動を振動させたのである。
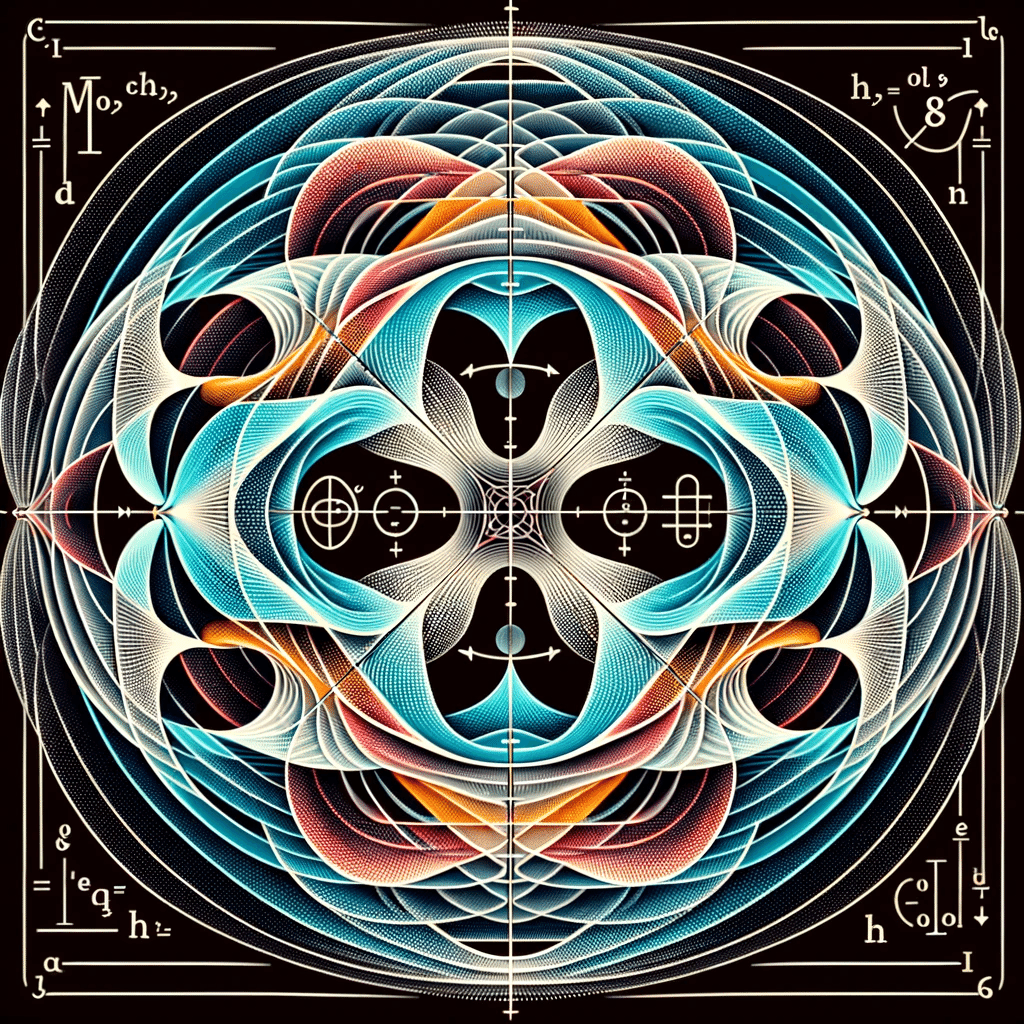
転がる頭/ 月の起源/ 結婚の起源 (2)
つぎの神話でも、頭が転がることから、月が生まれ、結婚が始まる。
”頭が転がることから、月が生まれ、結婚が始まる”なんて、日常生活の中で突然これを言われても訳がわからないとしか言いようがないことであるが、野生の思考の神話論理においては至極真っ当な常識に属する知見であるというのがおもしろい。
+ + + +
M393 「カシナワ 月の起源(一)」という神話を見てみよう。
戦争に明け暮れる二つの部族がいた。
ある日、ひとりの男が、狩をしていると、
不意に敵の部族の男に出会ってしまった。
狩の途中の男は逃げ出そうとした。
ところが敵の男は、大丈夫だ、攻撃しない、と言う。
そして自分の矢筒を差し出し、一緒に自分の村に行こう、としきりに誘ってきた。敵の男は「私の妻も、異国の客人をもてなすことができればさぞ喜ぶでしょう」などという。
M393 カシナワ 月の起源(一)を要約
まず戦いに明け暮れる二つの部族とある。
この二つの部族は、つまり過度に分離されているのである。
その過度に分離されているはずの二つの部族の者同士が出会ってしまう。
過度に分離されているはずのところが、いきなり短絡され、過度に結合する。
当然、その場で戦闘が始まるかとおもったら、どうも様子が違う。
敵の部族の男は、攻撃しないと言い、武器を手放し、自分の村に来てほしいと誘い、妻も異国の客人を歓迎する、などと言う。
主人公も、嘘だろう、騙すつもりだろう、と思っているようだが、いずれにしても現に目の前にいる敵は、攻撃をしかけてくることもなく、フレンドリーである。
まさに分離されているはずのところが突然結合する。
*
過度な分離から過度な結合への、第一の急展開である。
こうなると、つぎは過度な分離へと展開するはずである。
そして過度な分離といえば、いまこの文脈では「頭が取れる」であった。
展開が読めるとはまさにこのことである。
気をよくした男は、敵の男についていくことにした。
男はわざわざ身だしなみを整えたが、途中で食べた果物のせいで歯が真っ黒になってしまった。
敵の村に到着すると、男はやはり恐ろしくなり、たじろいだが、
敵に男にうながされて彼の家に入った。
敵の男の家では、たくさんの料理が用意され、男は満腹になった。
男が帰るというと、敵の男の妻は、土産の食べ物を包むという。
敵の男も、途中までお見送りしましょう、などという。
*
ところが、見送ると言いながら、敵の男が大ナイフを手にしていたので、主人公は心配になり、なにをするのかと尋ねた。
敵の男は、これは材木を切って掘り棒をつくるのだ、といった。
しかしこれは嘘であった。
帰路についてすぐ、敵の男がナイフを振り下ろし、
主人公の男は頭を切り落とされた。
敵の男は、刎ねた頭の目がまだ瞬きを続けているのをみて、山道の真ん中に棒杭を立ててその上に頭を引っ掛けて立ち去った。
M393 カシナワ 月の起源(一)を要約
主人公はのこのこ敵の男について行ってしまうが、これは過度な結合を表しているので仕方がない。そうして歓迎され、食事を共にするという、これまた結合の一つの形を演じたあと、主人公は首を刎ねられる。
体と頭という経験的にひとつに結合しているはずのところが、二つに分離される。
もちろん、この首は神話的な転がる首である。
体から切り離されたくらいでは死なない。
頭だけになって目が瞬きを続けているというのは、経験的に考えるととても恐ろしいが、神話的には自然なことに思えてくるから不思議である。
*
ちなみに、この過度な結合から過度な分離への急展開を媒介したのは「嘘」である。首を切るために用意した刃物のことを聞かれた犯人が、木材加工のためだ、と嘘をつく。
嘘というのは神話によく出てくるβ項である。
すなわち、嘘は、文字通りの記号と、その字義通りではない意味とが結合されたものであり、経験的にははっきりと対立するはずの意味内容(この場合なら、敵か味方か、武器か安全な道具か)の二項対立のどちらだかわからない状態の記号を作り出す。
分離(敵対)→結合(食事への誘い)→分離(首)→結合
さて、首が分離したところで、次はおそらく何らかの結合が生じるはずである。つづきをみてみよう。
棒杭に引っ掛けられた頭のもとへ、頭と同族の仲間が通りかかった。
頭は瞬きし、涙を流し、唇を動かしたが、喋ることはできなかった。
驚いた仲間は村に戻り、武装した戦士たちを連れて戻ってきた。
一方、頭を刎ねた犯人の男は、近くの木の上に登って隠れて、ことの成り行きを見ていた。
頭だけになった男の部族の戦士たちは、頭と一緒にひとしきり涙を流した後、頭を籠にいれて村へ連れて帰ることにした。
*
しかし、頭は自分で籠の底を食い破って、地面に落ちてしまう。
これをなん度も繰り返した。
仕方なく、戦士たちは頭を手に抱えて運ぶことにしたが、今度は頭が噛み付いてくる。
手に負えなくなった戦士たちは頭を置き去りにして逃げることにした。
ところが、頭は転がって追いかけてきて、戦士たちを罵倒した。
* *
M393 カシナワ 月の起源(一)を要約
盛りだくさんの内容で、どこから料理しようか迷うところだが、まず、頭が最初は喋れなかったというくだりに注目しよう。
喋れない?
あとの方では、頭は饒舌に喋り捲っている。
しかし、最初に発見された時には喋れなくなっている。
これはおそらく、敵の男の「嘘」と対立しているのである。
嘘 / 喋れないこと
この二つのなにが対立しているかといえば、まず嘘は、字義的な意味内容から分離された記号である。つまり記号だけが際立って、意味内容がなくなっている。一方、この神話の場合の頭が「喋れないこと」は、音声という記号が欠落しながらも、その喋りたいことの意味内容ははっきりと際立ってある。
嘘:
記号 / 意味内容
ある / ない
喋れない:
記号 / 意味内容
ない / ある
つまり上記のように、ある/ないの向きが逆になっている。
細かいなぁ、と呆れられるかもしれないが、これが神話の論理を分析するおもしろさである。
籠の底を食い破る
さて、次に注目したいのは、首が籠の底を食い破り、地面に落ちる、というくだりである。
籠や網というのは神話においては、分離的な媒介項としてよく登場する。例えば、水の中の魚を網によって地上へと取り出す。
この分離的媒介項である籠が、この神話のこの段階では、まだうまく機能しないのである。
籠のような分離的媒介項がうまくその分離作用を実現するのは、神話の語りの最終段階、経験的世界における二項対立を確定する場合である。
しかしこの神話のこのくだりは、まだ過度な分離と過度な結合の間を激しく振動している状態であり、籠で分離している場合ではない。
だから籠は底を食い破られる。
底抜けの籠になる。
そうして、籠の底から抜け落ちた頭は、同族の戦士たちに「噛み付く」。
この噛みつきはすなわち、過度な結合である。
これに参った戦士たちは、頭を捨てて逃げ出していく。
過度な結合からの過度な分離への急展開である。
そして案の定、頭が追いかけてくる。
*
一見すると、頭の振る舞いは不可解である。
同族の戦士たちに村へ連れて帰ってもらえるというのに(結合できるというのに)籠を破って落下する(戦士たちと頭が分離する)。そして戦士たちが頭を抱き抱えれば、噛みつくという形で過剰に結合しようとし、逆に戦士たちに振り払われ分離される。そうして置き去りにされそうになると、また追いかける(結合しようとする)。いったいぜんたい、結合したいのか、分離したいのか、どっちだ?、という感じがするが、分離と結合の区別もまた二項対立関係なのである。
対立する二極を振幅の最大値と最小値のようなものとして区切り出しつつある脈動する両義的媒介項たちの動きの相では、分離と結合という経験的な区別もまた、分離するでもなく結合するでもない、という状態に励起されている。
突然理路整然と喋り出す
ここで頭は、戦士たちを罵倒し始める。
喋れるやん。
*
戦士たちが川を渡れば、頭も川を渡る。
戦士たちが川の土手の上の大きな果樹によじ登ると、頭はその樹下に陣取った。そして頭は、樹上の果物をよこせとねだる。
戦士たちの誰かが、まだ青い実を投げ落としてやった。
しかし頭は、熟れた赤い実をよこせという。
仲間が赤い実を落とすと、頭はそれを飲み込んだが、切断された喉からすぐに漏れ出てしまった。
* * *
仲間たちは、頭を溺れさせようと、川の中へと実を落としてみたが、頭は騙されなかった。そこで戦士の一人が一計を案じ、実を遠いところへ放り投げた。頭はそれを追って転がって行った。
その隙に戦士たちは木を降りて村へと急いで戻った。
しかし、まだ頭が追いかけてくる。
そして戦士たちが村の家に閉じこもると、頭はその家の周りをごろごろと転がり「どうか私の面倒をみてくれ」という。
仲間の誰かがあわれんで、扉を少しだけ開けて、糸玉を投げてやった。
カシナワ 月の起源(一)を要約
ここでまさかの猿蟹合戦である。
猿蟹合戦
水辺の樹上と樹下の間で、青い実や、赤い実との過度な分離や、過度な結合が繰り広げられる。神話がβ脈動を引き越すかっこうの舞台が、赤い実と青い実が混在する果実の樹上なのである。
おもしろいのは転がる頭は体がないので、せっかくの熟れた赤い実を食べても、すぐに下から出てしまう、というくだりである。
先ほどの底抜けの籠そっくりであるが、ここでは食べたのに食べられていない、結合したはずなのに分離してしまう、という、食べたのか食べていないのか、結合したのか分離したのか、経験的に対立する二極のどちらにも安定的に投錨できない状態=β振動状態が動いている。
*
この神話では、日本昔ばなしの猿かに合戦にはない場面が描かれており、これもおもしろい。いや、猿かに合戦でも、カニが潰れて中身が出るような異文もあったように思う。小ガニが生まれるというのも考えてみれば親がにが二つに分りするということになろう。内臓が飛び出すというのは、神話では、頭が取れるのと同じように、経験的に結合しているところが分離することのひとつの例である。
+++
樹上の戦士たちは、転がる頭から分離するため、まず、赤い実を水中に投げ込む。しかし、首はこの手にはのらない。
次に戦士たちは、赤い実を「遠く」へ放り投げる。
首はこれを追いかけて、一時的に戦士たちのもとから遠ざかる=分離する。
ここに、
地上界 / 水界
人間の住む世界 / 人間が住むことのできない世界
遠/近
といった二極の間で「実」が振幅の片割れのような放物線を描く。
* *
遠くに放り投げられた実を頭が追っていく。
その隙に、戦士たちは樹上から降りて、人間の村に戻る。
しかし、頭もだまっていない。
村まで追いかけて転がってきて、戦士たちが立てこもる家の周りをごろごろ転がり続け、面倒を見てくれと言葉で訴えたりもする。
過度に結合しようとしていた頭と戦士たちは、束の間分離し、そしてまた結合へと向かう。
そしてここで、糸玉が登場する。転がる頭と同族たちをかろうじて分離する「扉」の隙間から「糸玉」が投げ渡される。
扉の隙間が、少しだけ開く、というのがいい。開いているとも、閉じているとも、どちらとも言えない中間的両義的状態がある。
転がる頭が四つに分かれる
さて、ここまでは過度な結合と過度な分離の間の脈動が展開されたが、ここから先は経験的世界の安定的な意味分節の体系が定まっていく。
まず、「頭」の長台詞が入る。
喋れなかったはずなのに、よくしゃべっている。
糸玉をもらった頭は、自問し始めた。
「今後私は何になろうか。野菜か果物になろうか、いやそうすると私は食べられてしまう。土になろうか、いやそうすると踏まれてしまう。畑になろうか。そうすれば穀物が熟れて皆が食べるのだ。水になろうか。そうすると飲まれてしまうな。魚になろうか。それでも食べられてしまう。毒流し漁の毒になろうか、そうすれば人々は魚を食べられるようになる。狩の獲物になろうか、そうするとやはり食べられてしまう。蛇になろうか、そうすると嫌われ、殺されるだろう。毒虫になろうか、それでも殺されてしまう。木になろうか、そうすれば薪にされ料理に使われるだろう。コウモリになろうか、そうすると人間を咬んで殺されるだろう。太陽になろうか、そうすれば人間たちを暖めてやれる。雨になろうか。そうすれば川の水を増やし、人は美味しい魚を食べられるようになるし、草を育てて美味しい獲物を増やせるだろう。夜になろうか、そうすれば人は眠ることができる。朝になろうか、そうすれば人は眼を覚ますことができる。
私は一体何になろう。
そうだ、私は、私の血を、敵の通り道となる虹にしよう。
私の両目を星々に変えよう。
そして頭を、月に変えよう。
そうすると、人間の娘たちは血を流すようになる。」
この自問を聞いて驚いた村の娘が「血が流れるとどうなるの」と尋ねたが、頭は答えなかった。
そして頭は、自分の血を杯に集めて、空に振り撒いた。
血は流れながら、よそ者たちが攻めてくる道を描き出した。
頭が自分の目玉を抜き取ると、それは無数の星々に変わった。
そして頭は、糸玉をコンドルに託してぶら下がり、天へと運ばせた。
人々が家から出ると、虹が空にかかっていた。
そして夜になると、はじめて、満月と星々が夜空に輝いた。
そして、女性は月経をもつようになり、人間は子供を産むようになった。
M393 カシナワ 月の起源(一)を要約
頭はあれこれと、Δ項の線形配列を試した挙句、そのどれもが不幸な因果の連鎖に尽きることを見定める。
因/果
因/果
因/果
因/果
こういうやり方をいくら重ねても抜業因種できないとばかり、頭は四つに分かれることを思いつく。
1)血 →虹
2)右目 →星
3)左目 →星
4)頭(目と血を除いた残余)→月
星々の安定的に見える付置と、昼/夜の区別と交代=星たちが見える夜と見えない昼=太陽の時間(虹は太陽のもとで見えるものである)、そして昼夜の対立を横切るように動く月。

このようにして、時間と空間の安定的な動的構造が分節されたことになる。
そしてこの時空の動的構造の中で、人間が子供を産むということが起源する。人間が子どもを産むことこそ、男/女の結婚、それも文化的な制度によって規制された結婚の始まりでもあるし、生/死(生まれるから死ぬ)の分節の始まりでもあるし、長い人生と短い人生の分節の始まりでもあるし、世代の差異の始まりでもある。
人間にとっての経験的世界における様々な事象の対立関係の「起源」を語ろうという場合、その手前で「人間が子どもを産むようになった」経緯を語ることになる。そしてこの”子どもを産む人間”という項と非同非異の二項対立関係にある項の位置を、これらの神話では「月」が占めている。月は、地上からはるかに遠くに分離されながら、しかし人間の体と結びつき、そのリズムを直接動かしてもいる。分離されているのに不可分であり、不可分であるのに分離されている。
男/女でも、生/死でも、人間にとっての経験的な意味分節体系が分節されてくるくだりでは、この分離と結合のあいだの分離と結合の振幅を描く脈動を語る必要があり、そこに「月」は適任なのである。
まとめ
「転がる頭」は、自分の体から分離して、他の人の体にくっつこうとする。本来(というか感覚的、経験的には)「同」「一」であるはずの「自分」の体とは分離して、逆に、本来「異」「他」であるはずの他人の体と結合しようと、追いかけ回したりする。感覚的経験的に結合しているはずのところと分離して、感覚的経験的に分離しているはずのところと結合しようとする。

冒頭の神話にあるような「非難される性的結合」(あるいは分離)は、共同体の掟において分離すべきところで結合したり、逆に、結合すべきところで分離したりすることである。インセストタブーの侵犯のような「近すぎる結合」は、分離すべきところが結合している=結合すべきでないところが結合している=分離すべきところが分離していない、ということである。
*
そして、敵の部族の男の言葉に易々と騙されてしまうこと、人を信用しすぎるというのも、分離すべきところが結合している=結合すべきでないところが結合している=分離すべきところが分離していない、ということである。
人を信用しすぎる / 警戒心が強すぎる
逆に、警戒心が強すぎるというのも、結合してもよいところが分離している=結合してもよいところが結合せず=分離しなくてもよいところが分離している、ということである。
* *
こうした過度な分離と過度な結合を両極とする、分離と結合の間の振幅を描く脈動を、安定した四極の波紋を浮かび上がらせる共鳴状態へと変換するのが、「転がる頭」の「月」への変身である。
月は、周期的に満ち欠けする、満月から新月へ、新月から満月へ、一方の極から他方の極へと、周期的に一定の速度で円を描いていくような、とても安定した振幅を描いていく。
次回、月の起源神話を詳しくみてみよう。
つづく
>>つづきはこちら
関連記事
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
