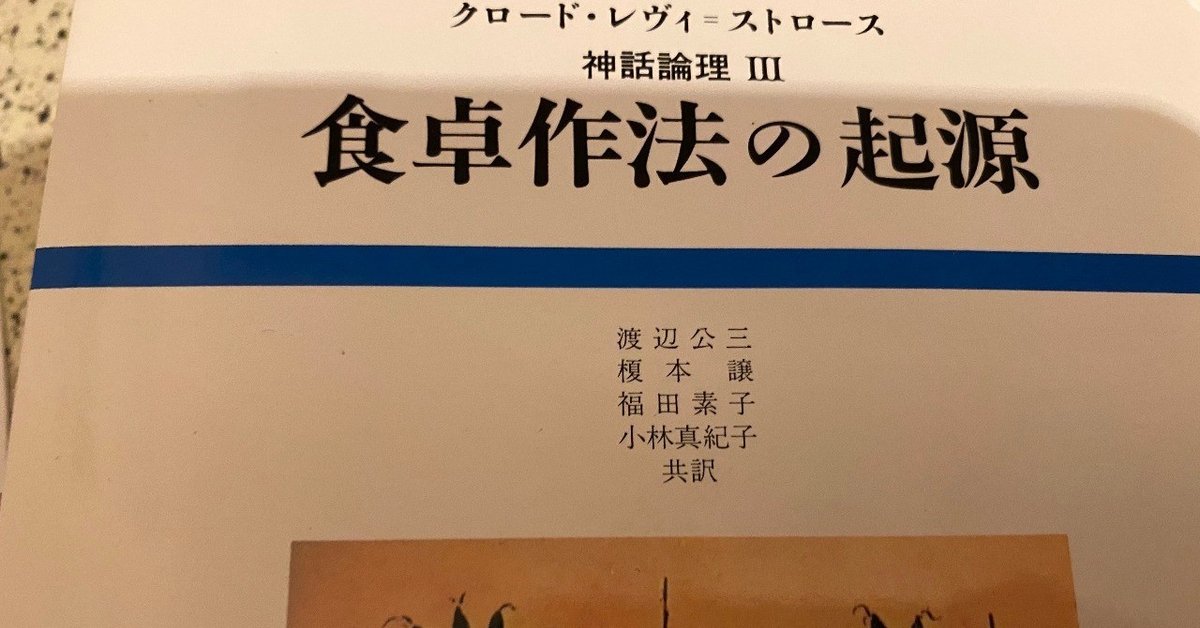
「意味する」のアルゴリズム −レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』「カヌーに乗った太陽と月の旅」を読む
(このnoteは有料に設定していますが、全文無料でお読み頂けます)
※
人類は長らく食べ物だった。
肉食動物に噛みつかれ捕食される祖先たち。
その遺伝子を受け継いだ私達は、いまでも捕食されることをおそれているのだろうか。
暗闇の中や藪の向こうに捕食者の姿を幻視すると同時に、瞬時に生理的な緊張状態に入るという性能を、私達の身体は受け継いでいるともいう。
そうした性能をもった身体は、人間だけで作った文化や言葉による真理や、身体を律する意識的な操作のはるか「以前」で、考えるまでもなく自動的に動き出す。
食べられてしまうかも知れない、そのことに戦慄するようにできている、食物連鎖の「中間あたり」の人類という「食べられる」運命にあるものたち。
◇
食べるもの / 食べられるもの
この「区別」は、長らく(ことばを喋るようになる遥か以前から)人類にとって大問題であった。
この区別は人間の経験を彩る意味の世界(意味分節体系)が織りなされる時の、もっとも基本的な分節(区別)のひとつ、分節の、区別する動きの最初の一撃といってもよいものかもしれない。
※
意味分節であり、存在分節であり、意識分節(分別)のはじまり。
その様子を、レヴィ=ストロースの『神話論理』そのⅢ『食卓作法の起源』に読むことができる。
『食卓作法の起源』の目次を眺めてみよう。

レヴィ=ストロースといえばおなじみの「構造」の最小単位とも言える、小さな「対立」がいくつも隠れ、互いに重なり合い、組み合わせのパターンを無数に増殖していく。
例えば、「カヌーに乗った月と太陽の旅」。
この部分は長大な神話論理の中でも、個人的に一番好きなところである。
太陽と月
カヌー
旅する
ここに、対立しながら一つであり、動きつつ静止し、ひとつでありながら多数であり、パターンを示しながらカオスであるという、レヴィストロース氏の考える動的でかつ静的な「構造」ということが、リニアであらざるを得ないという人類の言葉の桎梏からひらりと身をかわしつつ、その姿を垣間見せては消えようとする。
その一瞬のスナップショットを見ることができる。
もちろん、この場合の「見える」とは「見えない」ということでもあるけれども。
※
カヌーの先端と最後尾にそれぞれ座った月と太陽は、バランスを崩してカヌーをひっくり返してしまわないよう、それぞれのポジションを下手に動こうとはしない。
月と太陽は「止まっている」。そして「止まっている」からこそ、カヌーは全体として川を進む旅路を「動く」ことができる。止まっていることが、動くことなのである。
これこそ動きつつ止まり、止まりつつ動く、動と静の区別からしてそこから分節化する"動"、静と対立する限りでの動とは異なる区別以前の"動き"と、それが示すパターンとしての「構造」というビジョンの精髄ではないか。
◇ ◇ ◇
そして、臓物料理。
臓物の煮込みと、それをガツガツと、まるで「オオカミ」のように食べる人間。
オオカミは動物である。人間と対立する動物である。
そしてオオカミは、食べられるものである人間と対立する、食べるもの、である。
臓物を煮込む土器とは、身体外部に拡張された胃腸である。
土器は「食べる」身体の外部でありながら内部である。
そして、煮込まれたなにかの臓物は、食べられるものであると同時に、もうすでに「食べるもの」の一部である。
獲物は捕食者であり、捕食者が獲物である。オオカミにガツガツと食べられることもある人間が、いまオオカミのようにガツガツと食べる。
人間と動物
食物連鎖の上位者と下位者
食べ物と消化器官
これらは対立するとともに、一つである。
外部でありながら内部である煮込み用の土器は、止まりながら動くカヌーと同じである。
それは対立するふたつの事柄を、同時に一方でも有り他方でもあるという、一でありながらかつ二、という関係に絡め取る。これについて「カヌーに乗った月と太陽の旅」の最後(p.222)を読んでみよう。
対立という性格を維持していさえすれば、太陽と月の対立は何であれ意味しうるのである。(レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』)
意味とは、まず何かとなにかを異なるものとして区別すること。区別し対立関係に置くこと。そして複数の対立関係同士を重ね合わせることである。
神話的思考は…たえず新たな対立を発見していくが、そういう新たな対立により、別の対立を言い表す際にすでに用いていた用語同士の等価性を認めざるを得なくなる。(レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』)
対立は複数区切りだされる。
そしてある対立により、他の対立を「言い表す」。この言い表すということを可能にするのは「用語同士の透価性」、つまり対立関係1の第一項(あるいは第二項)となる語と、対立関係2の第一項(あるいは第二項)となる語のあいだに「等価性」をみること、つまり端的に「異なるが、同じだ」ということにすること。
内容が豊かになり複雑化するにつれ、形式的組み合わせは厳格さを失う、というかむしろ、簡略になっていくことによってのみ存続するようになる。太陽と月の場合、多くの神話が双方を交換可能としたり、当初太陽は月で月は太陽だったと語ったりすることで間に合わせようとしているような、深まりゆく内容の混乱は、もはや太陽と月が同じかあるいは別の意味を抽象的に表現できるような、いくつもの異なる様相によってしか埋め合わせできなくなる。(レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』)
何を何と置き換えて、何とは置き換えないのか。
その厳格なパターンは唖然とするほどあっさりと崩壊を開始する。
何が何と、という中身はどうでもよくなる。ただ、対立するということと、等価なものとして置き換わっていくこと、「異なる」ということと「同じ」ということが、「異なりながら同じ」にするという動きの純粋な姿としてのみ際立ってくる。
どちらもおそらく何であれ意味することができる。だが太陽の場合、慈しみ深い父か人肉を食らう怪物かというような、いっぽうか他方かという条件においてだ。(レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』)
太陽は、いっぽうか他方か、こちらでなければあちらであり、あちらでなければこちら、という関係とともにある。太陽は「なにかとなにかを区別すること」「なにかとなにかが対立関係にあること」を、先行する条件として要求した上で「どちらか」を務める。
ところが月といえば。
そして月が、当初の太陽との協調ないし対立関係を維持するのは、立法者かトリックスターたる造化の神のようにいっぽうでも他方でもある、または…いっぽうでも他方でもないという条件においてだけなのである。(レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』)
月は「いっぽうでも他方でもある」「いっぽうでも他方でもない」つまり、「異なるが、同じ」の「同じ」の方をその身に引き受ける。
異なること、と、同じであること
このふたつ自体を「異なりながらも同じである」とみること。
異なるとは、同じということである、と。
これこそが意味するということの精髄の作用であり、つまり人類が言葉によってなにかを「意味する」ということが許されるための最小のアルゴリズムなのである。
太陽は区別する。
月は同じにする。
ところが、太陽は月であって、月は太陽であり、つまりどちらでもよいのであった。
つまり異なるとは同じということであり、同じということは異なるということなのである。
最後に1ページさかのぼってみよう
カヌー…は、結合と分離を明確にし、双方をへだてておきながら、かつ交わらせている。((レヴィ=ストロース『神話論理Ⅲ 食卓作法の起源』 p.221)
隔てておきながら、交わらせる。
このミクロな運動が無数に増殖し続け消滅し続ける。
それが最高度に抽象的な生命ということであり、構造ということであり、変換あるいは写像としての「知性」ということである。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします。
関連note
◇
※
レンマ学、というのはこちらのことです。
※
ここから先は
¥ 150
この記事が参加している募集
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
