
母を殺す可能性の向こう側・オブジェクトの解体と再構築
先日、映画を観ました。グザヴィエ・ドラン監督主演、"I killed my mother"。日本語題ではマイ・マザー、となっています。
グザヴィエ演じるユベールの心情吐露から始まり、ユベールの深爪気味な指が映し出され、次のカットで母親の食事シーンが映し出されるところで二人の関係性を理解します。この点において、必要最低限かつ必要十分に描く彼の監督の才能は卓越していると感じます。詩的で、芸術的なメタファーを美しく散りばめていく技量には感嘆します。

さて、私は去年の10月ごろからずっと思考方法が行き詰まり、全てがシニシズム・生命の不可逆性に収斂していくのを感じながら、その思考の冷笑主義への傾倒を止めることができないでいました。詳しくは過去のnote記事などを参照していただければと思います。
かいつまんで述べれば、私が世界を認識し、意味を汲み取り、他者を理解しようとしている行為は、結局のところ「育った環境」「家庭の貧困さ・裕福さ」「幼少時に接した価値観」に依存していまうのではないか、という内容でしょうか。どこまで思考を練磨し、鋭敏化させようとも、カントの述べるような純粋理性はどこにもなく、影響を受けた、ドロドロに塗り潰されてしまったキャンバスのような感情の看取方法、感情の起毛細胞があるだけでした。私らしさがあるのは、感情や意味体系の「行使」「使用方法」のみであり、感情の構築には、皮肉にも私が関与できないことを、感じていました。この感情、「タブラ・ラサ」ではあれない悲しさは、言い換えれば生まれついた家庭そのものに対する悲しさでもあり、しかし、この家庭に生まれていなければ今の私は絶対に存在できないという捩れた、奇妙な偏執と接近の狭間で揺れていました。自己同一性の根源を、どこか別のフラットな地平に求めながらも、家族という温かな領域を同時に愛しく代え難いものとして認め、家族を嫌うことはしてはいけないと。
マイ・マザーに登場する、ユベールも、こうした反抗、そして偏執と接近を感じて悩んでいたように見えます。ユベールは深爪で、一方母親は長く伸ばした爪で口元の汚れも厭わずにガツガツと食事をする。ユベールに言わせれば「アルツハイマー」的な思い違いや、いい加減な相槌をする母親と、一度言ったことは一度で理解してほしいユベール。
「彼女のことは愛している。けれど、彼女の息子にだけはなれない」という言葉が何よりもユベールの心情を表しているように思います。
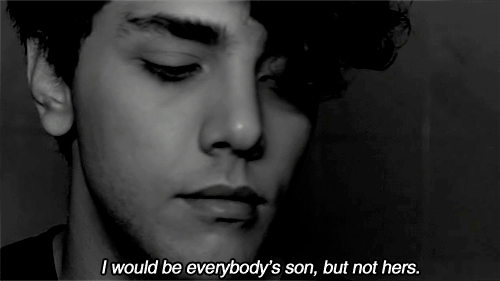
ヒステリックな気質のある母親と、同性愛者である息子の確執の結果、ユベールは寄宿学校へと通わせられることになります。その寄宿学校行きのバス乗り場に息子を送りにきた母親に、ユベールはこう言い放ちます。
僕を追い払ったくせに別れを惜しむの?
母さんは食べ方もガツガツして品がないし、物忘れは病気みたいにひどい
服のセンスも最悪だ 話し方も教養がない
僕を操ろうとするクソ女だよ
ユベールが母に対する感情を捲し立てたところで、母は背を向け、車へと歩いてゆきます。そこに、ユベールがこう問いかけ、立ち去ります。
今日 僕が死んだら?
そしてユベールは母の返答を待たずにバスに乗り込みます。
明日 私も死ぬわ
この母の言葉は、返答や投げかけではなく、むしろ独り言じみて、誰にも届かない独白として見えます。高速のテールランプの連なりや、車の輪郭だけが光って、母の視線が夜の空中を彷徨います。

我々は媒介的生物です。何かを媒介にしてしか、分かり合えず、伝えることすら愚か、自分の思考すらおぼつかない、そんな脆い存在です。
言語という、反応依存性を確かめる反応依存的なツールをもってしか、意思疎通を行えない。(反応依存性についてはリンクを参照ください。平たく言えば、「赤」という言葉は、個人の「赤い」印象を呼び起こし、リンゴやサンタクロースという多種多様の反応を引き起こす安定した傾向があるということです)
「あなたは〇〇のような人だ」という訴えは、〇〇に対する印象は個人によって異なるにもかかわらず、共通の明確な定義を持っているかのように行われますが、実際には〇〇に対する印象は各個人によって異なることを、思い起こさねばなりません。冷たい人だ、という言葉で、クールビューティを想起する人もいれば、意地悪な継母のような印象を持つ人がいるように、その反応依存性は個人によって大きく異なります。そんな不確定的で不安定な言語をもって感覚を確かめる、コミュニケーションは、なんと不確かなのでしょうか。表情やジェスチャーなどはよりその不明瞭さが高いことは言うまでもありません。
そうした言語・身振り手振りによってしかコミュニケーションを行えない我々には常に共約不可能性が付き纏います。決して開けられることのない、シュレディンガーの猫のような、我々の「本当の気持ち」。しかもその猫は、生死50%ではなく数多の可能性に分岐しています。さらに幾つもの「本当の気持ち」の中には、自分でさえ気づいていない気持ちがあることもしばしばでしょう。映画の中ではユベールはドラッグによってしか「本当の気持ち」を認識せず、かつ伝えることもできません。母親の前で、他社の前で、「僕はこう感じている」と伝えたその言葉の、一体どれほどが「本当の気持ち」かを、厳密に測定することは誰にも不可能なのです、自分でさえも。
そんな我々の現象の事実の上で、よくこうしたことが言われます。
母親と子供の間には血のつながりよりも、卓越した特別な絆がある
お腹を痛めて産んだ子供のことを何よりも理解しているのは母親だ
もはや無意識のレベルにまで敷衍されているように思えるこうした教義は間違っているのでしょうか。分かり合えている、親子には何よりも尊い絆があって然るべきだという不文律は、正しいでしょうか。実際には、我々は他者の誰とも「真に」分かり合うことはできない上、親子ならば尚更でしょう。むしろ、分かり合えていないことのほうが多いこともあるのではないでしょうか。全くもって他者であれば、共約不可能性を許すことが当たり前ですが、親子の間で「分かり合えない」ことはあってはならないという社会の不寛容によって引き裂かれる何かがあるように思います。他者であれば理解できない言動に出会っても「そういう人もいる」と認識できましょうが、特に、ユベールにとってクリームを口の端に付けたまま平気な顔をしている母親の行動は、度し難い。コトバを飲み込む、その引っ掛かりを許容することは、できない、なぜなら母親であるから。
もしかすると、この共約不可能性を許容する努力こそが、親子の愛情なのかもしれない。すべての人に対して発生しうる共約不可能性・意味のくらがり、届かない場所を許容し、容認し、受容すること、そして関係性を維持しようとする努力が、家族愛の、根幹的な要素なのか。かくも脆い、不認知な関係が、家族だろうか。
鬼束ちひろの曲に、こんなフレーズがあります。
分かり合えてるかどうかの答えは多分どこにもない
それなら 身体を寄せ合うだけでも
優しいものは怖いから泣いてしまう
あなたは優しいから
肉体的なつながりや、安易な「くっついている」ことに共約不可能性の埋め合わせを見つけることは、確かに可能です。取り急ぎ、とりあえず、付き合いましょうか、といった程度の愛のように思えます。インスタントラーメン的な愛。
また、はぐちさんという日常系四コマ漫画があります。他人丼のエピソードを思い出しました。

親子の、不確定性という確かさが、その揺れ合いが、拠所無い確かな柔らかさが、関係性のつなぎ目だとしたら。
もっと、我々親子はもっと別のあり方があったかもしれないという後悔は、しかし親子だからなのかもしれない。それはすでに等しく破綻していて、離れていて、緩やかな確かさがあるのみであって、故に、やり直したい・別の関係性であったかもしれないと思い起こすのでしょう。やり直すことはできなくとも、トレースすることはできるかもしれない。
我々の全ては、レプリカントではあるが、そこにある再現性、フィクション性は機械的なそれではなく、不確実な揺らぎ、意味のくらがりのなかにあるレプリカントであると信じることはできるのでしょうか。
私たちの生活は、今でこそ大部分を科学で説明可能です。母親という構成要素は認知心理学や人類学、脳科学によっても細分化され、厳密に近い形で語られうる。子供においてもそうであり、それは時計の部品を一つ一つ外し、説明するようなやり方でしょう。今や人間の全ては、生活の全ては、意味が明るみにあり、機械的です。故に、人間関係の「好ましい」あり方は認知心理学や応用心理学、脳科学、行動科学、文化比較人類学、医学、熱物理学、社会学、とあらゆる方法によって定義されるようになっています。エントロピーの増大、カオス理論、認知的不協和、エビングハウスの忘却曲線、マタイの原理。
そこに暗がりはなく、例外なく型にはめられます。親子の関係性において意味の暗がりは、犯罪予備軍扱いを受けるでしょう。「何をしでかすかわからない」という一点のみにおいて。それは非常に辞書的だと感じます。辞書の定義に収まりきらない、「わかりにくい」「わからない」ことの全ては「理解不能な、かつ理解するまでも無い原始的なもの」と捨象されることは、我々を鈍感にしてきたように思います。かのアインシュタインも、量子力学において「神はサイコロを振らない」として捨象しました。意味の暗がりは、現代において恐怖なのでしょう。アミニズムやシャーマニズムは、気持ちの悪いものと言われるように。
しかし、現代であるが故に、そのアミニズム的形態が、しなやかな余裕を生むのではないか、と思います。もはや我々は、というより私は、全てに厳密な説明を求めてはいません。自然派ママや狂信的なまでのオーガニック信仰、カルト宗教の再興は、世界の脱魔術化の弊害ではないでしょうか。宗教と科学を分離し、地動説を打ち立てたことは確かに大きな功績です。しかし、世界はもはや再魔術化の軌道を廻り始めています。
この脱魔術化と再魔術化の間で、ユベールとユベールの母、もとい我々は精神の貧困にあります。
ユベールが置かれている状況は物質的な貧困にはなく、むしろ美術品や嗜好品にあふれ、祖母の遺産を譲り受けた状況です。しかし精神においては不寛容性が増大し、挙措のいずれにも精神を磨耗しています。言い換えれば、コトバの共約不可能性、完全な他者理解の不可能性に対して寛容ではない。ガリレオ以降、説明可能な事柄に慣れすぎた彼らは、意味のくらがりに恐怖を覚える。ユベールの母がユベールが同性愛者だと知ったときの瞳のざらつき。それはユベールの母にとって説明不可能なのです。

この限りで、我々は物質化された精神状態にあるといえるでしょう。オブジェクト化された、《対象化》された事象に慣れてしまうことは、我々自体がオブジェクトと化することに鈍感になる。我々がモノとして扱われ、辞書記載内容化することを、当然のように受け入れてしまう、例えば「女性は生理のたびに機嫌が悪くなります」「教師は偉い」「勉強する人は出世する」など。固定化された世界に気づかないばかりか、精神の硬直化や目的の王国の崩壊にも気づかない。(精神の硬直についてはウェーバーを、目的の王国についてはカントを参照ください)ウェーバー的に述べれば「鋼鉄の檻」「絶対物象化」とも言えるでしょうか。H.アーレント的であれば「思考停止」であり、それは緩やかな悪への堕落、緩やかなアウシュヴィッツとでも言えましょう。緩やかに、我々は陳腐な罪悪人、平凡な、かつ大量複製されたアイヒマンになっているのではないでしょうか。
こうした事態はもはや既成の「事実」であり、それ以外は存在しないのです。「それ」は「それ」として働くべきであり、これを問うことは「赤色は何色ですか」「水曜日は何曜日ですか」と問うようなことなのでしょう。科学によってアウフヘーベンされ尽くしたと思われている限り、かつ科学の截然とした思考方法によって理解する限り、事実は絶対的な事実で、アンチテーゼは存在しません。実際のところ、認識しているすべての他に、アンチテーゼがあるかもしれないのに。詰まるところ、現状を打破するためには認識を、かつ世界を解体しないことにはどこにも行けないのではないか。そう思うようになりました。
しかし、世界の解体は私の解体を含み、家族の解体を含みます。母親から生まれ、父親から生まれ、愛情を受けたことを否定せねばなりません。
精神の貧困状態にあっては、生得的なもの、生得的な差異は批判の対象であり、罪ではありません。くらがりを許容できないことは、光を当てれば良いだけのことなのです。暴力的なまでの圧倒的深度を持ったメスでもって、くらがりを完膚なきまでに駆逐し、がらんどうのホワイトキューブにしてしまえば良いのです。
長谷川裕子は、金沢21世紀美術館研究紀要で、ホワイトキューブについて次のように言及します。
ホワイトキューブはマルローの「空想の美術館」以来、作品が生まれた場所の文脈と切断されたニュートラルな場所として考えられてきた。それは同時 に「時間」との切断でもある。
世界を見るとき、文化において全くの純血を保っているピュアランドなどなく、いずれも異種混交の不断のプロセスの中にある。ただその速度や開始の 時期にズレがあるだけなのだ。ホワイトキューブにおかれることで、還元される過程、異なった文脈の場所に移管(リプレイス)、移動されることによって行われる相対化は、言説化の過程と連結されている。これも記憶とその累積の問題とかかわっている。
そして、ボードリヤールを長谷川は引用します。
思想は真理に収束するのではなく、対象の複雑性に収束する。真理から逃れるには主体を信用してはならない。対象とそのストレンジアトラクターに、世界とその決定的な不確実性にすべてをまかせる必要があるのだ。
脱構築的な思考は、その感性は、不確実性に委ねる故に個人の独立した、しかし決定的に「個人ではない」「非主体的」「非媒介的」働きをなすだろう。そして、それは全く別種の、パラレルワールド的な第二の目的の王国を築く。しかしそこにはもはや、パルタージュされた生得的要因が潜んでいる。言語を、いかようにして排除するべきなのか。母親や父親から習得した、言語を(もとい「非自己」から習得した言語を)用いずに思考することは可能か。シンギュラリティにおいてはこうした思考方法をすることが可能になっているのかもしれない。完璧に機械的な言語習得が可能になった場合、その思考方法は限りなくフラットでニュートラルで、アクター間の諸要素を正しく捉えられるだろう。フッサールの現象学は、シンギュラリティ以降の言語によって解体されるかもしれない。フロイトはもはや現代では解体されていますが。
私は先天性高度難聴ですが、現在では訓練の甲斐あって何不自由なくコミュニケーションを取ることができています。それは殆どのところ母親のおかげであり、また、指導教授のおかげです。教授が確立した(ばかりの)指導方法に則り、母親が指導してくれたからに他なりません。私の言語能力の根幹は、おおよその部分において母親のそれとパルタージュ(分有)されているといって良いでしょう。通常の児童以上に、美的判断や感性的なそれは強くパルタージュされ、融合した意味体系を築いていたように思います。(従来の指導方法では高度難聴幼児は言語を獲得せず、意思疎通は手話のみでした。当時は聾者は筆記での意思疎通も不可能な場合が多く、完全に閉じられたコミュニティでした)
そのことが、私の問題を難しくしているようにも思います。
私が私として世界を認識することは、母なしにはできえないのではないか。当然、時間は逆行不可能・不可塑性であり、母のいない世界認識はすべての人にとって不可能ですが。しかし、そこには思考の尋常ならざる偏執と融合、分裂の繰り返しがあったように思います。
映画で、次のような詩が引用されていました。
お母さん、偽りの世界には罠がある
僕が幸福なのはあなたのおかげ
逆説的に、ここで私は次のようなことを感じました。
生得的なものに不満、むしろ嫌悪感を感じるのは、その他諸々のことが満たされているからなのではないか、と。
差異という差異が埋め尽くされ、障害者と健常者の差異が埋め尽くされた場合、問題は地平を一つ落とすのではないか。根源的な、意味の看取方法や世界の認識方法、フロイト的な無意識、肛門期などにあるような無意識的な過去のある地平への逆行。
しかし、その俎上では全ては無意味なのではないでしょうか。なぜなら、常に言葉を用いているから。言語という媒介を用いてどれほど思考しようとも、言語の魔力からは逃れられません。
ならば、この根源的地平を愛せるようになることが、全てを変えるのではないか。それは、真なる家族愛に似て、本当の意味での母を愛することなのではないか。かつ、その愛は選択可能で、愛することもできるし、愛さないでいることもできる。また別種の根源を愛することもできる。その限りにおいて、真に根源的な自由なのではないか……。
新約聖書、コリント人への手紙第十三章に次のような記載があります。
たとえ人間の不思議な言葉、
天使の不思議な言葉を話したとしても
愛がなければ 私はただの鳴るドラ、やかましいシンバル
たとえ予言する力があり、
あらゆる神秘、あらゆる知恵に通じたとしても
また、たとえ山を動かすほどの信仰があったとしても
愛がなければ 私は何者でもない
たとえ全財産を貧しい人々に与え、
誇るために自分の身を引き渡したとしても
愛がなければ 私には何の益もない
愛は寛容であり、愛は慈悲深い
愛は妬まず、高ぶらず、誇らない
愛は見苦しい振る舞いをせず、
自分の利益を求めず、怒らず、
人の悪事を数えたてない
愛は不義を喜ばず、真実を喜ぶ
愛はすべてを忍び、すべてを信じ、
すべてを望み、すべてに耐える
愛は決して滅び去ることはない
予言ならばすぐに忘れられるだろう
不思議な言葉ならいずれ止むだろう
知識ならば無用となる時も来るだろう
我々が知っているのは一部分、
また、予言するのも一部分であるがゆえに
完全なものが到来する時には 不完全なものは廃れ去る
私は幼い子どもの頃、
幼い子どものように語り、幼い子どものように考え
幼い子どものように思いを巡らした
しかし、大人になった時、
私は幼い子どものように振る舞うのをやめてしまった
我々が今 見ているのは鏡に映っているもの
しかし その時がやってきた時に見るものは
顔と顔を合わせてのものとなる
我々が知っているのは一部分、
しかし その時には自分が完全に知られていたように
私も完全に知るようになる
だから いつまでも残るのは「信仰」、「希望」、「愛」
このうち 最も大いなるものは「愛」
根源的な、生命への愛が、全てを可能にするのではないでしょうか。生命そのものというよりは、すべての、共約不可能性と意味のくらがり、揺らぎや、確かな不確実性を現象しうる生命を。
ヘーゲルは「人間的欲望の本質は自由」と言います。しかし、アクセル・ホネットは「自由であることの苦しみ」を述べます。自由は、それ自体で二項対立的であり、「自由か」「不自由か」のいずれかの状況を要請します。そのあいだはなく、厳密な区分法です。弁証法以降、我々の世界は命題的ですが、そこから地平を一つ落として、根源的な自由の不確定性と揺らぎに身を委ねることが、現代の本質的な自由であるように思えます。
その世界では意味の円環は閉じられなくなっており、意味が開放されているように見えます。ヘーゲルは弁証法の論理においてすべての終局的な地平は円環的な構造であると述べました。アウフヘーベンし尽くし、対偶をすべて列挙したとき、それは再び最初に戻るのです。ウロボロス的な寓話でしょうか。お互いの尻尾を噛む龍の像が重なります。全ては根源的な「何か」にぶつかり、それは神であり、親であり、宇宙であり、すべての構成要素である絶対的な「何か」なのでしょう。それを問い続けることは意味を為しません。素粒子の密度の間を問うても、量子力学的な可能性の特異点を求めても、それは円環的な思考です。
現代では思考や論理のドーナツ的円環はそれ自体オブジェクト化しつつあり、もっと超越的な領域・地平からその閉じた円環を解剖する時代になっているのではないでしょうか。内側からの視線は、内側のみしか彷徨いません。内部の論理では外部を措定することはできないのです。外部を否定することは、内部を措定することにつながりますが、内側の集合では全体集合を措定し切ることはできません。1、2、3、4、5、という内側の数字で外側の数字を措定することは、できるでしょうか。内側の意味体系に数字しかない場合、外側の世界は数字によってしか類推し得ません。実際には数字以外の何かがあったとしても。
これまでの二項対立が破綻し、外側からコトバや思考を見つめるとき、非媒介への開放が行われ、実存がこれまでにないほど再考を要請されるでしょう。「お前は何をもって思考しているのか?」と。言語が解体されたとき、「私」という存在を「わ・た・し」の音素以外でどう表すのでしょうか。宇宙人との邂逅が行われたとき、まさにこの問題に突き当たるように思います。人間は、どのように外部から措定されるべきか。あるいは多次元空間から人間はどのように説明されるべきか。三次元以下に生命は存在しませんが、二次元の思考がもし存在するとしたら、我々はその低次元思考を、低次元言語を理解できるでしょうか?宇宙人が我々を見つめる視線は、ちょうど我々三次元生物が二次元を見つめるときのそれと同じなのかもしれません。
ユベールの母が、日焼けサロンで息子が同性愛者であると告げられた時のあの乾いた目を想起します。

見ようとすれば、見えたのでしょうか。
円環の破綻は、意識しなければ認識することなどないでしょう。その意味で、円環の破綻を生きる人と、円環の中に生きる人という対立が生じてしまいます。なぜこの破綻は、意識せねば見えないのか?なぜなら、我々はすでにシミュラークル的生命であり、その生命を生きているからです。
私という存在は、生まれた時点で二つの生命を持ちます。一つは、地平を一つ落とした根源的な私であり、DNAによって表されるような、あるいは卵子と精子の受精によって起こるような生命です。一方は、シミュラークル的生命であり、何月何日に生まれた男/女であり、〇〇会社の課長である〇〇と〇〇の子供で、〇〇県では〇〇人目の子供である、といったような生命です。膨大なデータがそこには付され、説明可能なそれとなります。母親や父親についても同様で、それは有史以降の連綿たる集合体としての一個体です。
もはやそれはヴァーチャル的で、そっくりそのままクローン人間をすり替えても同じように世界は進行するでしょう。同様に、意味を知覚し、目的の王国を築くでしょう。

ヴァーチャルな世界でのシミュラークル的生命は、膨大なデータを持ち、他者との関わりを持ちます。故に、リアルそのもの・現実それ自体です。

シミュラークル的生命とシミュラークル的親、そして他者との関わり合いの中で形成される実存を第二の実存とここでは呼ぶことにします。
一方、根源的な生命を第一の実存とし、その二つの生命のありようは常に選択可能なものとします。
我々が(というより私が)肯定するのは、根源的な生命の過去であり、根源的な生命の続くだろう未来や現在です。それは取りもなおさず、歴史の肯定であり、私の肯定です。
ここでは親は非常に近く、かつ遠い存在として認識されます。シミュラークル的親、つまり第二の実存での親は確かに私と深く関わりますが、絶対的な他者です。その限りにおいて、第二の実存での親は分散可能で、脱構築可能です。言い換えれば、育ての親と言えましょうか。産みの親は第一の実存における親であり、否定不可能です。
ユベールの母も、これを否定不可能としました。「明日私も死ぬわ」というセリフは何よりも、ユベールの根源的母親としての態度だったように思えます。
第二の実存では、親や絶対的存在、例えば神や、高圧的態度を取る教師は、分散され、要素還元可能なオブジェクトとして捉えられます。Yahoo知恵袋を参照しましょう。こんな質問が散見されます。
・親って何ですか
・親になる資格は私にはあるのでしょうか
・私の親は親としての資格はないように思います
言い換えれば、親という存在は、還元可能なもの・細分可能なものとして、シミュラークル的生命においては捉えられます。つまり、「優しく」「義務感があり」「憲法上の義務を果たし」「子供のことを第一に考える」存在が、親であり、再現可能な実存です。また、子供である私も、「忠実で」「言うことを聞き」「自立した」存在であれば、再現可能です。もはや、そうした実存同士の関わり合いは機械的で乾燥しており、平板的です。くらがりはどこにもなく、強固な科学だけが支配しています。
しかし、第一の実存における親は、代替不可能でかけがえのないものです。二度と同じ子供は生まれず、また、その親も代替不可能な第一の実存であるが故に。我々は、親を、あるいは他者を、すべからく第二の実存上で愛さねばならないわけではないと考えます。彼らのキャラクターや第二の実存は、共約不可能で、絶対的な相互理解はそこにありません。許容し、くらがりを持ち、確かな不確実性をもって接することができるのみです。我々は、人間への尊厳として払うべきは第一の実存に対してであり、第二の実存は選択可能な事象に過ぎません。二つとも愛せる人は、強いですが、往々にして我々は「嫌悪感」を抱き、「喧嘩」をするものです。その揺らぎこそが、人間的なるものではないでしょうか。
MISIAのEverythingという歌を引用します。
You're eveything You're everything
あなたが想うより強く
やさしい嘘ならいらない
欲しいのはあなた
You're eveything You're everything
あなたと離れてる場所でも
会えばきっと許してしまう どんな夜でも
You're eveything You're everything
あなたの夢見るほど強く
愛せる力を勇気に 今かえていこう
いわば、やさしい嘘は、第二の実存における肉体的耽美や讃頌、上辺だけの言葉なのでしょう。欲しいのは、第一の実存における確かさ。
マイ・マザーでは次の言葉が冒頭に登場します。
On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne prend conscience de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. - GUY DE MAUPASSANT
母親への愛は無意識であり 親離れの時 初めてその根の深さを知る
原文では次のようになっています。
On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel comme de vivre ; et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière.
ひとはほとんど自分では知らずに、気がつかずに母親を愛しているものです。それは生きているのと同じくらい自然なことだからです。この愛の根の深さには最後の訣別の時でなければ気がつきません。
(モーパッサン『死の如く強し』杉捷夫訳、岩波文庫、1950年(1992年第18刷)、164頁)
第一の実存を生んだ、母親の第一の実存と、そして第二の実存を、お互いに愛し合うことが何よりも強い生命への肯定なのだろう、と考えます。
それは、選択可能で、母親が早くに亡くなられた方にとっては、育ての親・第二の実存における親を愛することになりましょう。また、ユベールのように「彼女の息子にだけはなれない」場合においては彼女の第一の実存のみを肯定することが、最大限の自己肯定であり、他者理解になるのではないでしょうか。
私にとって、他者理解とは、差し詰めこんなところだろう、と思います。
長くなりましたが…後ほどきっと加筆修正を加えるだろうことを付して末筆とします。参考文献などは以下に示します。コメントなどお気軽に!
エドムント・フッサール 「内的時間意識の現象学」
モリス・バーマン 「デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化」
M.フーコー 「知の考古学」
H.アーレント「人間の条件」
マックス・ウェーバー 「マックス・ウェーバー宗教社会学論選」
伊豫谷登士翁 「グローバリゼーションとは何か」
アンドレ・ゴルツ 「労働のメタモルフォーズ——働くことの意味を求めて 経済的理性批判」
テオドール・W・アドルノ、マックス・ホルクハイマー 「啓蒙の弁証法-哲学的断想」
藤野寛「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことだけが野蛮なのか―アドルノと“文化と野蛮の弁証法”」
廣松渉 「弁証法の論理」「弁証法の論理―弁証法における体系構成法」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
