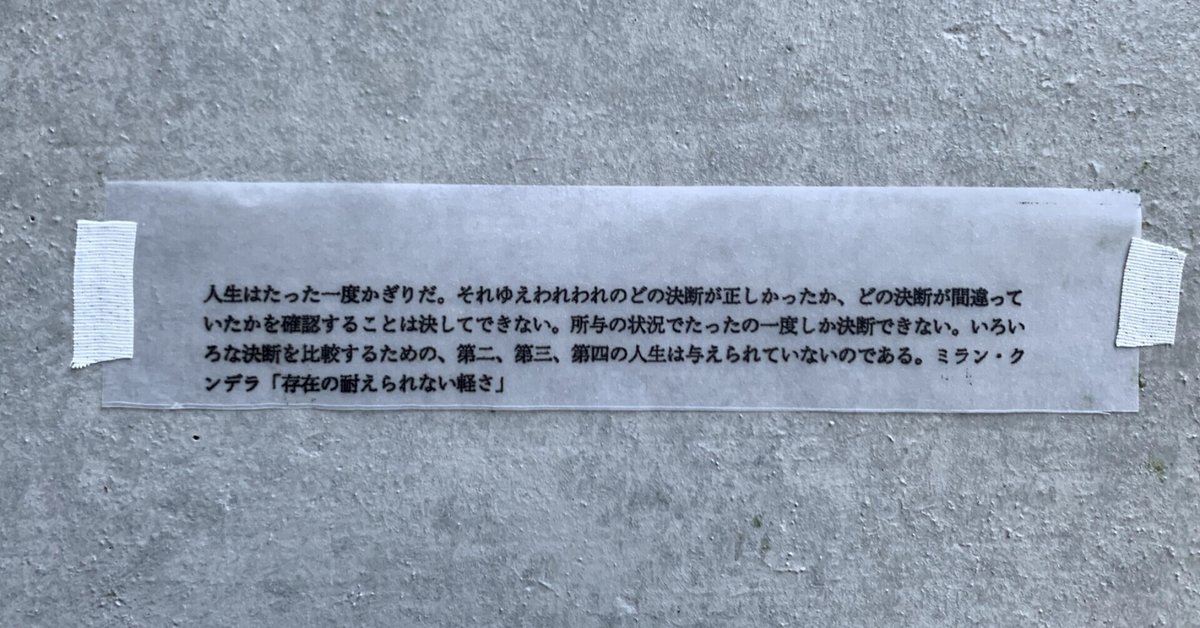
作品論・いくつかの感情・大岩雄典氏・砂山太一氏 《悪寒|Chill》 について
なすべきこと、事務作業、悩むべきこと、逡巡すべきこと、確定すべきこと、いくつもの必要事項が一気に雪崩れかかって、4月も目前にしながらようやく落ち着いてきた(もちろん落ち着いていないこと・片付いていないことも多々あるが)。
なすべきことをこなしていくときに、生活しているおのれの感情と、目の前にある事項を満たしていく感情とが分離する人と、しない人がいるような気がしている。これは事務作業に限定してしまうと概ね後者が正解のように思えてしまうが、しかし「創作」や「制作」というカテゴリのなかでは必ずしも単純に割り切れる問題ではない。作品をつくるときの感覚として、作者にとって、それは確かに作者の元から生まれいづるものでありながら同時に、作者のものではない状態を常に孕む。書くこともそうだ。確かにそれは作者の言語活動——ラングという地平からステイルやエクリチュールを選び取りながらある概念を顕現させていくこと——でありながら、常に作者自身から滑落していく危険性を孕んでいる。作者「の」状態と、「ではない」状態を往復、というより往復未然の状態として、それは在り続ける。
生活する私としての感情と、必要事項を満たすべき私としての感情。これらを容易に切り離すこととは、一体どういうことなのだろう。あるいは、逆方向から考えてみよう、生活する私としての感情と、必要事項を満たすべき感情が合一である状態とは、どのような状態なのだろうか。簡潔に表記するために(タイピングの労力を幾ばくか減らすために)、前者を「の」的感情、後者を労働的感情と措定しておこう。ここで「の」「労働」を付する理由は詳細に書くことはしないが、簡潔にいえば
・私「の」感情であり、私とそれは完全に癒着しているわけではないが、しかし見かけ上はほとんど同地平にあるように見える。いわば生来のものに見える(「の」的感情)。
・後天的。私たちはそれを好んで装用するわけではない。ある意味で、武器的であり、仮面的であり、脱皮的である(労働的感情)。
というわけである。さて、「の」的感情の強い現れとして何があるだろうか。例えば私の感覚では、次のようなものがそれの現れである。《リストカット・肛門期など小児性欲発達段階のそれ・一人で食べること・自分の過去を話すこと》など。慎重に検討していないが、大まかな感覚でいえば、「把持」しているかしていないか、ということであるかもしれない。もしくは、一つの連続体のなかで、確かに私とそれは地続きであると認めることができているかどうか。「の」とはそういうものだ。私のもの、私の感覚。自分の過去を話すということは、おのれが経験してきた(見かけ上は)、他人と通約することのできない何かを言語を用いて伝えようとする行為だ。それは、確実にその過去が私の経験したものであると自認することと不可分である。そして、自分で自分の身体を触ることや、そこで生じる感覚を、自分のものとして認めること。これもまた、「の」的感情だ。アプリオリにそれが紐づけられている…ことを判断材料としてしまう場合、いくつかの矛盾が生じる気がしているので、ここではアプリオリ性は含めない。なお、カントの議論で俎上にのぼるようなアプリオリなそれは、ここでは検討対象としない(単純に筆者が不勉強であり、それを我がごととして書くことができないからだ)。
次に、労働的感情である。《我慢・愛想笑い・テストを解くこと・社会的生活…》。もしかすると、おおよその感情がこの労働的感情に近しいのかもしれない。この意味で、アヴィニョンの娘たちやマティス、原始主義の絵画作品が「アート」的として週刊誌などでしたり顔の解説員を交えながら説明されることが多いのも、理解できるだろうか。つまり、労働的感情に塗れた現代社会から、しばらくの休息を取る意味で、プリミティブなそれらを見つめることが、高尚かつ良い趣味であると評されるのである。このようにして称揚された作品は、「発見される」「発掘される」などと揶揄されることが多いように思う。アウトサイダーアートは「発見」されるものなのか? そのとき注がれる眼差しは、かつて先進国が発展途上国に向けた憐れみ(という名の偽善)ではないか? あるいはチームラボを考えよう。そこで私たちが発見するものはなんなのだろうか。遊戯施設に幾ばくかのスペキュラティブ性が付属したに過ぎないそれを、私たちが見つめ、何かの訓示を得た気になるのは、私たちが発展途上国の偽善者に成り代わるための装置として、あの作品が機能していることの証左である。はっきり言おう、チームラボの作品は私たちを偽善者へと転化させるファシズム的装置であると。
話が逸れてしまった。労働的感情はプリミティブ性の反対(というよりかは向こう側)にあるものである。いわば、「そうせざるを得ない」ように思うこと、義務感、「べき」のそれ。We should... と定言するときの感情。バーンスタインやヤコブソン、シャノン&ウィーバーの言語情報理論で用いられるコード概念、ディシプリン。私たちがまさにそのコードに則って、意味のある(ように見える)発話内容を伝達しているならば、それらのすべては労働である。それはすぐに、「の」的感情の意味不明化を許容する論理にもつながるだろう。ここで(ように見える)と注を加えるのは、強い懐疑に基づくものであり、また、分析美学でいうところの反応依存性理論、もしくは強い主観性(メイヤスーの提示する「相関主義」)とも近しい理論を併用したいと考えているからである。
そして、本題に戻ろう。「の」的感情と労働的感情が併用されるパターン。ここでは創作行為や制作行為に焦点を当ててみよう。単純である。「自身のリストカット行為をモチーフにした作品を制作し、公募に応募。そしてその作品が選考を通過することを祈ること」などである。直裁かつ叩かれそうな言い方をするならば、「メンヘラっぽい」作品が評価されることを祈ることでもある。Twitterでのクソリプに例えるならば、あるツイートに「そうですか。でも、私ってこんなに大変で…」とクソリプしたものがバズることを願うことだろうか。作品の独自性、オリジナリティを自身の出生や「の」的それらに委ねるのである。それは閉じた円環であるが、しかし展示などを通して、開かれを獲得する。一般化された「の」的感情を利用し、あたかも「開かれ」ているように見せているのは、例えばアボカド6などだろうか。病み系歌い手などもそうかもしれない。そこにある作品像は、自己中心的で、痛みを抱えている。一応主張しておこう。あくまでも、ここでの主張はその善悪を判断するものではないことに留意されたい。
先の段落では「の」的感情の強いパターンを考えたが、もう少し穏当な例を考えるならば、「私はこう思う」ということをレポートにすること、アンケートに答えることなどもそうだ。このとき感じる負担、直裁に言えば「めんどくさい」と思うこと。これは、「の」的感情と労働的感情が分離されていないことに由来する(と思う)。もしくは、書いた文章の主張が首尾一貫せず、あれこれと寄り道しているように見える場合もそうだ。淡々とこなすべきことと、おのれの主張が綯交ぜになり、文章全体の構造が捩れる。むしろこの捩れが、作品の場合はよいアクセントとして作用することもあるだろうが、それは作者がその「捩れ」に意識が向いている場合に限る。無意識的な捩れは、作品や思想が未熟な印象を与えてしまいかねない。長い文章や大きな作品、シリーズものを制作する際に負担を感じるのは、この捩れが分量と比例するからだろう。巨視的な構造の理解を行いつつ、微細な部分の構造を理解しなければ、全体としての捩れを把握することはできない。プログラミングやコーディングでも同様である。
偉そうなことを言っておきながら、筆者自身は何も評価を得ていないので、ここで書いたことは自己満足の類である。が、そのことを棚にあげた上で、この巨視的構造と微細構造、あるいは「の」的感情と労働的感情の釣り合いがうまく取れていると感じる作品(アーティスト)をいくつかあげてみる。
梅原義幸氏
磯村暖氏 《左の鼻の音 無題の鍵盤曲 右の鼻の音》
大岩雄典氏・砂山太一氏 《悪寒|Chill》
単純に「の」的感情・労働的感情の側面から語るのも烏滸がましい・それだけではない良さがあると思うが、特に大岩雄典氏・砂山太一氏の《悪寒|Chill》について語るならば、当インスタレーション空間内で語られる「予感の感染症」というモチーフの秀逸さ。感染症という語句を用いることで瞬時に想起されるここ数年の状況。マスクをしている鑑賞者たちが一瞬にしてそのインスタレーションの装置に成り代わる演劇的状況。中央部分に配置された、演劇空間の模型、メタシアター的な状況。私たちが把持している、いくつもの予感や、個別具体的な恐怖(感染症へのそれ)が、公共の場としての「いま・ここ」で、演劇的振る舞いとともに交錯する。そこで語られる虚構(もしくは現実)(あるいはそのどちらでもあり、かつどちらでもない)で、時折差し挟まれる、痛々しいほどの指摘——「何だろうといいんです、人間はみんな自分のすることをしなくちゃいけないですし。私も私が感染しているかわからない」——。労働的身体として、日々を乗り越える私たちが同時に、「の」として経験するそれらが、そこで溶け合い、ある種の予感を得るその場は、まさに悪寒と呼ぶに相応しい、完璧な設計が敷かれている。それゆえ、私はあの展示場所で爛々と光っていた消火器の赤いライトさえも、展示の一部かと感じた。どれひとつとして欠けてはならないあの空間で(強いていうならば、建物の構造・部屋の構造が綺麗な長方形だったなら…?)、もたらされるアートの語りは、豊穣にすぎる。
昨今の感覚では、より透明な作品や展示、強いインパクトが好まれることがあるかもしれないが、上記のようなむしろ消化不良感を抱えそうな作品の方が私はよいと思う。というより、こうした作品に耐えうる批評の土壌がないことが問題か。作品が提示したものを、抱えきれないまま何も言わなくなってしまう批評家・観客たち。あるひとが叩けば一斉に立ち上がって総スカンを食らわせるSNSの有り様もどうかと思うが(ユージーン・スタジオ事件)、それも仕方のないことかもしれない。少なくとも私は、消化不良になりそうな作品の方を応援したいと思っている。無声音以上有声音未満、という表現を最近行うが、こうした曖昧な・しかし確実な発話行為としてのアート作品をしっかりと受け止めることのできる土壌づくり、支援が何よりも必須だ。行政レベルでこの認識ができるようになるのは果たして何年後だろうか。行政よりレベルを下げるならば、大学や学問機関だろうか。そうした場で、クリティカルな批評が生まれるためには、学府としてこれらの「役に立たない」と評される営巣行為を保護しなければならない。
こうしたことを考えるにつけ、「研究助成金」などの存在が脳裏をよぎるが、ここでまた「の」的感情と労働的感情の取っ組み合いが始まるのだ。助成金をこなすべき感情として淡々と書きつつ、しかし「の」的感情を完全に分離させることのないように(怒りを忘れないように)、粛々と進めなければならない。燃焼成分と空気がうまく混ざってはじめて、ガスは安定して燃えるのだ。半減期の短い元素のような存在にならず、息の長い批評・生活・制作・その他もろもろを行っていくためにも。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
