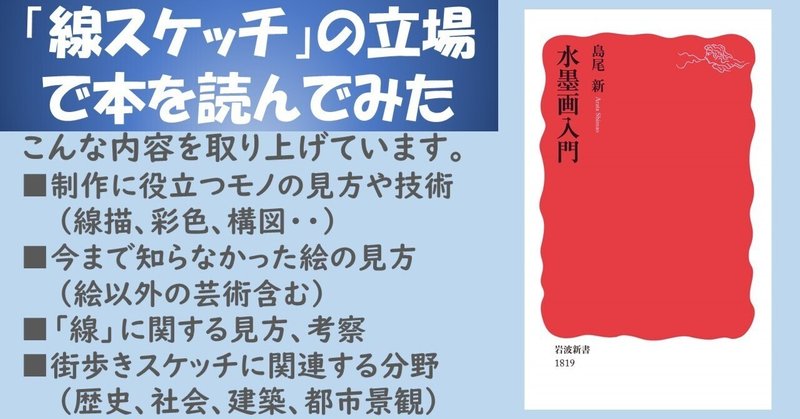
島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。その2
前回の記事、その1から続きます。
水墨画の存在様式
著者は、第2章「水墨の発見」で、「筆」と「墨」の基本的な性質とそれから生まれた「水墨」について、身体論や西洋絵画との対比も交え歴史的な経過を紹介してきました。
いよいよ、水墨画の説明に入るのかと思いきや、なんと文献や資料ではなく、直接画家のことば、すなわち「墨」「筆」「紙」の材料を用いて描く実作者の実感の紹介から始めるのです。
具体的には、著者も関わって2016年に開催された「SUMIの輝きー黒の表現者たち」展(筆の里工房)での実作者たちの問題意識と言葉を引用しながら話を進めます。(展覧会の内容は下記を参照ください)
1)磨墨
まず磨墨です。本格的な書道や水墨画の経験のない人間にとっては、「墨は単なる画材ではない」と云われてもピンときません。
実は「墨を磨る」とは次のような意味があるといいます。
よいものを使えば、墨は硯に吸い付くよう。端座して滑らかに硯の上に墨をすべらせれば、膠の香りーこの頃は香料を加えたものも多いがー漂ってくる。
ここでも「身体性」にかかわる意外なものが出てきました。「嗅覚」です。
著者は、しずかに磨墨を繰り返す時間は、単なる準備ではないと日本画家、福井江太郎氏の次の言葉を引用します。
「アトリエ中に墨の香りが広がり、心が整う。・・・・・無心で磨る墨は、感じるアンテナを育ててくれる」
すなわち、「「磨墨」はえがくこと・書くことに繋がりながら、それ自体で成り立つ営為でもあり、墨が単なる画材ではない」と教えてくれると。
2)「墨」の動き
さて、墨を磨れば次は筆に墨を含ませて紙に触れさせることになります。そうすると墨は紙の中に染み込んでいき、著者はこの墨の移動プロセスも他の画材と違う特別なものだといいます。
ここも鉛筆また油絵具とは異なるところで、インクの滲みとも感覚が違う。筆を動かして「線を引く」というよりは、筆から紙へと墨を「伝えてゆく」といえばいいだろうか。(中略)「潑墨」では「流し込む」といってもいいかも知れない。
ここでまた、実作者の言葉を引用します。
「墨には、自分の気持ちが筆の穂先と一体となり、そのすべてが静かに和紙の上から広がり沈んでいくような感覚がある。」(八木幾朗)
次にその「墨の動き」を書家日野楠雄氏の作品「純」(2012)を例にとり解説します。直接その作品を示すことが出来ないので、作品に用いた土佐の梼原和紙を漉いたオランダ人、ロギール・アウテンボーガルド氏のブログのURLと作品が載っている雑誌の写真のURLを下記に示しますのでまずはご覧ください。
https://kamikoya-washi.com/kamikoyawordpress/wp-content/uploads/2013/06/img058.jpg
https://kamikoya-washi.com/kamikoyawordpress/wp-content/uploads/2013/06/img059.jpg
「純」の字の旁を描いたということですが、花の部分は墨が広がって小さな円をえがいただけのシンプルなものです。どのようにしてこのような円が出来たのか、著者の解説が続きます。
墨は煤を膠で固めたもの。(中略)これを磨って作った墨液は、水の中に膠に包まれた煤の粒子が浮遊するコロイド状になる(図3-2)
これを筆に含ませて紙に触れると、まずは水がさーと広がってゆく。花の周囲に光のリングのように見えるのがその範囲。水に溶けた膠がエッジに溜まって、実際にはうすい黄色に見えている。その水の後を膠に包まれた煤が追っていく(図3-3)。
和紙の繊維に沿って墨が広がってゆくさまが見えるだろう。「墨の滲み」というけれど、むしろ「墨の拡散」「墨の動き」というのが相応しい。そしてこれがきれいなのである。この墨色と肌合いだけでも水墨ファンは感動できる。
まるで材料物性科学者、あるいは粒子工学研究者のような語り口が続いた後、最後の2行で「これがきれい」「墨色と肌合いだけでも感動」と、サイエンスとは真逆の感性、感情そのものの言葉が現れるので、それまでの文章との落差に驚きますが、「美」の感動を科学的に表現するすべがない現在しかたがないでしょう。
なお、引用中に記された図3-2の写真は直接出せないので、その写真をもとにイラストを作成しましたのでご覧ください(下記)

本書、図3-2の写真をもとに作成
著者は特に説明していませんが、煤の粒子の大きさは、油煙墨で15〜80ナノメ-トル、松煙墨は20〜400ナノメートルです。図の中に示した1μは1000ナノメートルになります。(ちなみに、墨の粒子はコロナウイルスの大きさと同じといえば読者にわかりやすいでしょうか)
3)墨は紙の中にも
次に墨が紙に染み込んだ後の、他の絵具との違いについて説明が移ります。
油画でも絵具はある程度は下地にあるいはカンヴァスに染み込むけれど、普通そこを「絵」とは呼ばない。絵は画面全体を覆う絵具の表面が見えるところで、カンヴァスまでは届かない。これに対して「水墨」の画は紙の「上」にもあるが「中」にもある。墨は「横」に滲むだけでなく紙の「奥」へも染み込んでゆき、そしてそれが「見える」のである。
この記述は、水墨と油彩との決定的な違いを指摘しています。水墨画を鑑賞する上で重要なポイントになりそうです。
著者は墨が染み込んだ紙の拡大写真で、墨の粒子が繊維にへばりついている様子を示します。その写真をもとに作成したイラストを下に示します。

本書の図3-4の写真を元に作成
注意したいのは、繊維の幅は数μから数十μあることです。ですから、ナノメートルサイズの墨の粒子は、それぞれの繊維の上に小さくへばりついているのです。ところが、粒子があまりにも小さいので、図3-4の写真では正直なところハッキリ見えていません。
墨の粒子が紙の繊維に小さくハッキリへばりついている写真がありましたので、参考までに下に示します。よろしければご覧ください。
さて、この状態では墨はどのように見えるでしょうか?
濃い墨ならば光を吸収して真っ黒に見えるが、(中略)薄い墨では、光の一部は墨を透過して裏打ちの紙に達し、そこで反射してまた墨を通って返ってくる。私たちが見ているのはそれで、「奥へ」の滲みも画の見え方に大きく作用する。(中略)光の強さは全体のコントラストに影響するから、特に微妙な墨のトーンで表現された画の見え方は、光によって大きく変わることになる。
これこそが、この節の冒頭で述べた油画との違いになるでしょう。
なお水墨画に限らず、江戸時代以前の日本の絵画の作品展示は、これまで美術館のガラスの箱の中で、人工の光に照らされてきたので、以上のような説明を頭に入れて鑑賞する必要がありそうです。
さらに話は「紙」そのものに移ります。
4)素地のモチーフ化
著者は「紙も画の一部」ということを、長谷川等伯の「松林図屏風」では雪山を、「柴門新月図」では月を、「外隈」の技法で描いている例で示します。

出典:共にwikimedia commons, public domain
それぞれの元の全体図を下記に示します。

出典:wikimedia commons, public domain

出典:wikimedia commons, public domain
「松林図屏風」の雪山の場合、
(前略)塗られた墨はそのままどんよりとした冬空になる。その冬空の墨は紙のなかに染み込んでいて、物理的には塗り残された山つまり紙と「同じところ」にある。ここでは墨が染み込むことによって、紙を画のなかへと取り込んでいるのである。
一方、「柴門新月」の月の場合は、「コーンスイート効果」の錯視により周りの空より明るく見え、「濃淡のくっきりした月の輪郭から、なだらかなグラデーションを空へとつけねばならないが、これを実現しているのも紙のなかへの滲みである」と。
さらに加えて「西洋絵画ではカンヴァスなどを「支持体(support)」と呼ぶようにあくまで顔料を支えるというイメージであり、絵はその上にある。ところが水墨の場合はそのありようは異なり、水墨の紙は支持体でありつつ画でもある」と西洋絵画違いを指摘します。
これにより、西洋絵画ではできない「裏からえがくやり方」も可能となり、この場合紙の裏から表へと「墨をうごかしてゆく」ことになります。
裏から描くと、「描き込むと墨色は鈍くなりますが、重なった部分は墨がしみ込まないので表側では鮮やかな墨色が保たれています」と日本画家の浅見貴子氏の言葉を引いたあと、「紙の中の空間は、画の空間としても発現することになる」と結論します。
このあと次節において日本の水墨における重要なトピック、「余白」についての議論が続くことになりますが、上で述べた「墨のもやもや」と「紙の白」とのまじりあいでその威力を発揮するのが霞や霧の描写について述べて、「霞や霧は、「水墨山水」の表現上の大きなテーマとなっていく」という言葉でこの節を閉じます。
なお、霞と霧の描写について、現代の水墨作家、呉一騏氏の「天光円鐸シリーズNo0555」をその作品例として挙げています。
「天光円鐸シリーズNo0555」は、ここでは示すことが出来ないので、下記の動画を代わりに示します。埋め尽くされた圧倒的な山と光り輝く「烟霞」をご覧ください。
5)水墨の画に「余白」などない(!?)
著者は、以上の「磨墨」、「墨液」、「墨の粒子の動き」、「紙における墨の動き」の順に材料科学的な記述と実作者の感覚を紹介した後、満を持して「余白」という節を設けます。
そして、のっけから「水墨の画に「余白」などない」と結論付けるのです。
これには驚きました。もともと水墨画のイメージとして紙の白を活かした空白が魅力で、日本の水墨ではさらにその空白を「余白の美」へ昇華したと勝手に思いこんでいたからです。
おそらくそれは、教科書などで若い頃からの長年の刷り込みがあったと思いますが、それにしても本当に驚きました。
けれど、前節の「素地のモチーフ化」を丁寧に読めば、おのずと著者の結論が得られることが理解できるのです。
そこで著者は、私のような思い込みを持つ読者に対し、またしても「西洋絵画」と対比させて分かりやすく説明します。
「余白」という見方は、絵についての「えがかれている部分」と「えがかれていない部分」の群別がベースになっている。油画では、基本的に絵具はカンヴァスの全体に塗られている。もし「余白」があったとすれば「塗り残し」ということになり、ふつうこれは「手抜き」だから、ルネサンス以来の伝統のなかにはまず見られない。「なんでもあり」となってからは別として、油画に「余白の美」はあり得なかった。
この部分を読んだ時に、私はセザンヌが自身の油彩の中で、日本の絵画の描き方を適用して、油絵具の薄ぬりと塗り残しにより余白の美を得ようとする試みを思い出しました。その作品はひろしま美術館の収蔵品、「座る農夫」です。

赤瀬川原平氏はこの作品を「美品」として誉めているのですが、私にはどうしても単なる塗り残しの未完成品としか見えませんでした。
この辺の事情は、下記に詳しく書きましたので、ご興味のある方はお読みください。
さて、この西洋の油画の絵具のあり様に対し、水墨では、
紙のなかにも画があって、紙も画の一部だから、すべてを塗りつくす方がむしろ不自然。「余白」はごく自然に生まれることになり、その境界はクリアーではない。「余白」と呼ばれるものは「えがかれないところ」ではなく、水墨の存在様式に由来するもので、あえて定義するならば「墨と紙との関係」なのである。
要するに、冒頭で著者は水墨画に「余白」はないと私を驚かしましたが、それは通常言われている、「えがかれないところ」の「余白」のことであって、水墨画では、水墨の存在様式にしたがった「余白」は自然に生まれると言っているのです。それは「墨と紙との関係」で定義される「余白」です。
ここで著者は長谷川等伯の「松林図」の「余白」に関する節を設けます。
6)「松林図」の「余白」
すでに左隻の図を示しましたがあらためて左隻、右隻の全体像を示します。

出典:wikimedia commons, public domain

出典:wikimedia commons, public domain
あまりに有名な作品なので、この絵についての多くの専門家が述べている鑑賞の内容についてはご存じだろうと思います。
ここでは、著者が「余白」について強調したいところを箇条書きにします。
●描かれているのはニ十本ほどの松(目立つのは5,6本)と左隻の右上に描かれた白い山だけで明らかに、松とともに「余白」が主役である。
●遠方から見ると、雪山の外隈の淡墨の面は曇り空のよう、淡墨の松は手前に霧が流れており、下の方では霧が濃くなって幹が消え、この濃い霧は紙の白で「余白」ということになる。
●「余白」に境界はなく、淡墨と紙の白の微妙なトーンで、柔らかな光を帯びた霧のイメージを作り上げている。
●「手前」と「奥」の関係も曖昧。濃墨の松と淡墨の松による前後関係、一方「余白」の霧は松の手前にも後にもあり、「余白」と淡い墨とは、その前にありながら後ろにも繋がって、幻想的な雰囲気を醸し出している。
以上の全体的な観点だけでなく、濃い松の筆さばきにも注目します。(下図)

出典:wikimedia commons, public domain
濃い松は、近づいて見ると荒々しい筆致でえがかれていますが、「画から離れると、その筆致は見えなくなって、静かな風景へと変化する」。これも「余白」のなせるわざだと言います。
結局観る人にとって大切なのは「えがかれたもの」と「えがかれないところ」の関係ではなく、「墨」と「紙」の織りなす関係だと結論づけます。
7)日本的水墨?
さらに続けて著者は、私がこの記事を書く動機になった「日本の水墨はどこに独自性があるのか?」という問いに、一気に踏み込みます。
まだ中国の水墨山水を紹介していないのに、先走ってしまえば、「松林図」のような画は、あちらにはまずありえない。このようなざざっとシンプルにえがかれる松は、近景ではなくやや遠いところにあるべきもの。水墨山水の原則からすればルール違反なのである。
著者は、この「松林図」は、水墨山水の原則から外れており、ルール違反とまで言い切っています。しかも、普通ならば先に中国の水墨山水の説明をしてから言うべきことを、あえて先走って紹介したと言っているのです。
この一言から見ても、著者がいかに従来の水墨画の入門書と異なる方法を目ざしたかが分かります。
さて問題は、以上のルール違反による水墨画は日本的かどうかです。正確には、長谷川等伯個人が創り出したと言えても、日本独自の水墨画とは言えないはずです。
しかし、著者は、ここで長谷川等伯が前代の画家や画跡、鑑賞方法について語った内容をまとめた「等伯画説」の中で、南宋の画家、梁楷の絵を表するにあたって「冷えたる」という言葉を使っていることに注目します。
長谷川等伯が生きた桃山時代より前、室町時代は現代につながる日本独自の文化が芽生えた時代として知られていますが、この「冷えたる」はまさにその室町時代に生まれた文化に共通する評語なのです(私は久しぶりにこの言葉を思い出しました)。
例として世阿弥では「さびさびとしたる」「冷えたる曲」、連歌師、心敬の「冷え寂たる方を悟り知れ」、茶の湯の祖、珠光の「冷え枯るる」「冷えやせる」を挙げ、漫画「へうげもの」(10巻)に登場する利休と等伯二人のの科白まで引用しながら「晩年の等伯のベースに「冷えたる」があり、「松林図」がそうだったとしても不思議ではない」と推測します。
以上から、確かに「松林図」は長谷川等伯本人が創り出したものですが、その背景には、日本独自の文化概念「冷えたる」があり、したがって日本独自の絵画様式とも言えるのです。
さて、第三章「水墨画の存在様式」のクライマックスが来て、ここで終わるのかと思うと、一転、最後に画家と水墨とのかかわり方について触れます。
7)水と紙による「墨の動き」の違い
これまで述べてきた「水墨の存在様式」に対して、画家はどのように向き合っているのか、今度は実作者の立場になっての記述が続きます。
まず、「墨の動き」でその作品を取り上げた書家の日野楠雄の「墨色の変化」についての膨大な実験結果を紹介します。物質としては炭素とゼラチンと少量の不純物・添加物というシンプルな構成にもかかわらず、水と和紙それぞれの種類ごとに滲みのパターンがすべて違うことが示されています。
(実験結果の写真そのものを示すことが出来ないので、「岩波新書編集部」のツイートに引用された下記の写真をご覧ください。)
この画像を初めて島尾新先生に見せていただいたとき、「雪の結晶みたいだ〜」と感動。日野楠雄先生の研究成果です。
— 岩波新書編集部 (@Iwanami_Shinsho) March 12, 2020
文中にある「月山和紙」は山形県西川町大井沢で三浦一之氏が伝承しています。大井沢は出羽三山信仰ゆかりの地。ここからは月山と湯殿山の雄大な山並みが一望できます。 https://t.co/0KXN4WYbiM
8)墨と紙との対話
以上の実験結果は何を意味するのか、紙と水だけでなく、画家が考慮しなければならない因子は箇条書きにすると次のようになります。
●煤の粒子の大きさや形状
●膠の性質や濃度
●硯の鋒鋩(表面のぎざぎざ)の形状
●磨るときの力の入れ方また気温や湿度
●加水分解する膠の経年変化
●下地の作り方
●
●
要は、パラメーターが多すぎて、「紙の繊維の中での墨や水の動きを含めて、完全に制御することは出来ない」のです。ですから
墨は支配するのではなく、付き合ってゆくもの
となります。これに対し、西洋絵画では画家が画面の全体を支配しているという幻想が成り立つとします。なぜなら、「絵具を重ねて、かたちや色を丁寧に調整して・・・・間違えたらえがき直すことが可能だから、すべては画家の意思に従ってなされたことと信じやすい」からです。
以上の西洋絵画に対し、水墨画家は上に述べた「様々な要素を組み合わせ、求める世界が得られるまで、実験を繰り返すしかない」とします。
そして実作者、中野嘉之氏の言葉、「墨は水に導かれ、紙も又水を導く」、そのなかで「墨、筆、紙、硯それぞれと深く対話が始まる」を引用し、次の言葉で第三章を締めくくります。
画家達は、不思議なダイアローグを千年以上ものあいだ繰り返し、さまざまに「墨を動かす」ことを試みてきたのである。
中間まとめ
以上で、記事その2を終えますが、実は本書全体の3分の1ほどを紹介したにすぎません。しかし、その1,その2を通じて私の最初の問題意識、
■水墨画はどこをどのように見て鑑賞したらよいのか?
■日本の水墨画は独自性はあるのか?
について手がかりを得たように思います。
すなわち、水墨山水の理念を知らなくても、現時点でも次のように鑑賞できると思うのです。
1)身体、五感を通じて作品と向き合うことで、インタラクティブに作品と向き合う
2)「墨を動かす」ための試行錯誤の取り組み、すなわち、画家たちの墨と紙と水のふるまいとの対話の結果として作品を味わう
以上のような味わい方は、「水墨山水」の専門家からすれば邪道かもしれません。しかし、私としては、この第三章までの知見だけでも、普段鑑賞している線スケッチや透明水彩画と同じように鑑賞できる気がしてきました。まずは初心者の鑑賞としてはそれでよいのではないでしょうか。
さてこれまでは、本書の特徴は、第二章「水墨の発見」、第三章「水墨読んだだけでも画の存在様式」の内容にあると考え、必要以上に丁寧に紹介してきました。
本書の第4章は、通常の水墨山水の一般的な紹介であり、第5章からは、具体的な作品を挙げて日本独自の水墨画が紹介されます。
次の記事、その3では、第4章はほぼ飛ばして、第5章以降の「日本の水墨画」の独自性に焦点をあてて記事を終えたいと思います。
その3につづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
