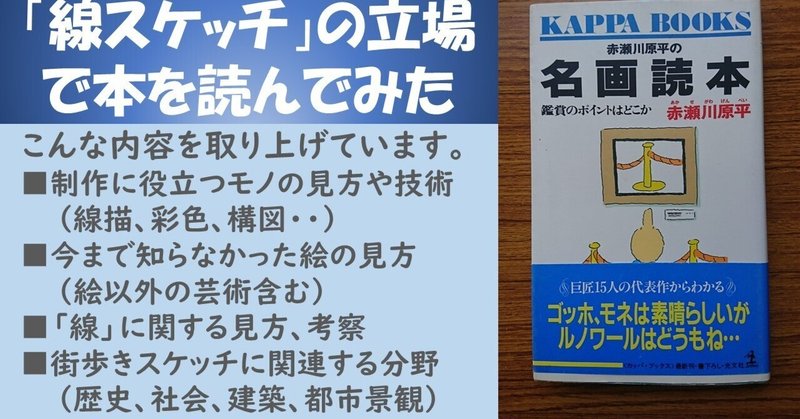
<赤瀬川原平の名画読本>鑑賞のポイントはどこか 赤瀬川原平 光文社(1992)その3
はじめに
赤瀬川原平の名画読本からの記事は今回で最後です。前回、前々回同様「線スケッチ」の立場から気になった文章を取り上げて、なぜそれが気になったのかを説明します。
シスレー【サン・マメス】・風景画を❘美味《おい》しく味わう

Saint-Mammès sur le Loing
著者は、広島美術館所蔵のシスレーの作品を取り上げています。著作権フリーとは思いますが、確実ではないので、広島美術館のHPの画像で見てください。
参考までに、描いた日時は違いますが全く同じ場所で同じ構図で描いたシスレーの別の作品を上に載せます(wikimedia commons パブリック ドメイン)。
シスレーの絵の描き方、筆さばきに対する画家ならでは見方を述べた後の、次のような文章が目を惹きました。
絵は鑑賞するものだけど、もとは描くものである。だから描いてみないと鑑賞し尽くせないところがある。上手い下手に関係なく、いちど絵具を扱ってみると、ああ、あの感触がここにある、というのでそれだけ画家の位置に近づける、というのでそれだけ画家の位置に近づける。感触だけではない。空の色を出す難しさ、樹木を生き生きとした感じを出す難しさ、といった体験があってはじめて絵の面白さがわかる。あれは好きこれは好きと自信をもって言える。(中略)
だから絵を見るのが好きだという人には、ちょっとだけ描いてみることを是非お勧めしたい。別に上手く描く必要もない。人に見せるためではないのだ。恥ずかしければこっそり押し入れの中で描いてみるといい。キャンバスの感触、油絵の具の感触、どんな名画もこうやって出来るのだという入り口が見えてくる。(後略)
「線スケッチ」を始めるまでは、絵の鑑賞に描く体験は必ずしも必要ないと思っていました。もちろん必要条件ではないと今も思います。けれど、著者が言うように、キャンバスの感触、絵具の感触、筆さばきの動き、感触を感じることで、頭だけの理解ではなく身体を通じてはじめて理解できることもあることを「線スケッチ」を始めて感じることができました。
著者は絵の鑑賞する人に絵を描く実体験してみたらと勧めていますが、スケッチを始めたいけれども始める決心がつかない人に、やってみてはじめてわかると私が勧めている趣旨と同じ内容です。
ここでは詳しく説明しませんが、絵を描く行為は、頭ではなくスポーツのように身体全体を動かすことと同じだと考えるとよいと思います。
ペンを動かす、絵筆を動かすときに、身体全体を動かすことに注意してください。そのためには、頭ではなく、身体の動きを通じて脳に神経回路を作るための練習が必要なのです。
初めからなめらかにペンや筆を動かすことが出来る人はいません。
ですから、絵を始めたばかりの人で、上手くならないのでやめてしまう人に対しても同じ趣旨の内容を声を高くして言いたいのです。
大人は頭で高い目標を持つのはよいのですが、その目標になかなか近づけないことに嫌気をさしてやめたいと思ってしまうのではないでしょうか。
高い目標を持つのは良いですが、身体を通じて体得するのに、時間がかかることを知ってほしいと思います。
セザンヌ【座る農夫】・画家の❘筆触《タッチ》が”自由”を求め始めた
著者が取りあげた絵は、シスレーの絵と同様にひろしま美術館の収蔵品です。(下の画像を参照)

A Seated Peasant
セザンヌの絵が薄塗りなのは、ジャポニスムの影響だという説を、最近どこかで読んだのですが、いくら薄塗でも、ここまで白いキャンバス地があちこちに出ているセザンヌの絵は見たことがありません。
著者は、実物を見てこの絵について「いいセザンヌだな」「ずいぶん良質なセザンヌである」と評価しているのですが、画像を見る限り、塗り残しだらけの絵にしか見えず、私自身の評価は保留にしたいと思います。
ただ、絵のあちらこちらに出ている白地部分についての著者の考察は、西洋と東洋の絵に関する本質的な問題を包含しています。私自身、線描に関する東西の違いについて関心があるので、内容を紹介することにしました。
さて、著者は実物を見て、この絵の評価をまるで「ライカ」の「美品」に出会ったように思ったと述べるのですが、さらにセザンヌのこの作品には「美品」からくる「緊張」を感じるというのです。
では、その緊張はどこからくるのかの考察に移ります。
でも、この緊張は何だろうかと思った。なんだか妙に生々しい。この作品の美品度というのが何か異常なほどで、まだできたばかりで一目にも触れていない、というほどの新鮮さがある。画家のアトリエから、まだできていないのに運ばれてきた、という生々しさである。
との印象を持つのですが、「絵を見るとあちこち塗り残されていることに気が付いた、まだできていないのだ、しかし「美品」としてもうできあがっている、できあがっているのを見て感動している、しかし塗り残しがあるからできあがっていない」と不安をかかえます。どちらなのかと。
ここから、実作者らしい長い考察に移ります。まず「絵というものは必ず絵具を塗り尽くされるものだろうか」と疑問を投げかけます。
つぎに、では「絵の出来上がりとはどこまでもをいうのだろうか」とたたみかけます。
以上の問いは、絵の鑑賞者は暗黙の前提で、美術館に掲げられている絵は、すでに出来上がったものを見ているが果たしてそうなのかと絵の鑑賞者になげかけた疑問なのですが、一度でも絵を描いたことのある人ならば「そうそうどこで止めたらよいだろうか、どこで最終にしようかといつも迷ってるよ」と頷くことでしょう。
実際、次はそれについての考察に移ります。
計算できるものだったら出来上がりは必ずある。でも芸術というのは計算が出来ない。出来上がりのラインというのは、本当はあるようでいて、ないようでいて、あるようでいて、ない。そこが製品と作品の違いである。
余白の問題から外れてしまいますが、この文の内容、「できあがりのラインがあるのは製品、ないのが作品」という文を読んだとたん、これまでもやもやとして分からなかった工芸品と芸術作品の違いについての明快な説明になると私は思いました。
すなわち、職人が作った美しい工芸品と創作作家が作った作品と何が違うのかに対する答えになっていると思うのです。
職人が作るものには計算された出来上がりのラインがある「製品」であり、創作作家のものは、計算できない出来上がりの「作品」であると。
誤解のないように断りますが、両者どちらかが上といっているのではありません、「美」は同じなのになぜ名前が違うのか、なぜ区別しているのかという疑問です。
さて、脱線したので著者の考察に戻ります。
ではこのセザンヌの絵はどうする。すでに感動してしまっているこの感動の値打ちはどうする。
あらためて画家の筆先について考えてしまった。とくにセザンヌの絵の筆触である。タッチという。何か明らかに確信をもってタッチを重ねていると見えるのに、その確信がどこにあるのかぜんぜんわからない。そしてこのようにあちこちがばらばらに塗り残されている。
いよいよ筆のタッチに注目した実作者ならではの考察に入りました。著者は、余白について「絵の具の塗り残し」はよくあることだと言っています。特に小品の絵のときに。
たとえば、肖像画の場合「肖像部分はきちんと描いて、周辺に行くにつれタッチが大まかになり、衣服の肩口のあたりでタッチがきれて筆をおく。なので余白の部分はキャンバスの白地がそのまま出ている」というスタイルです。
そして著者自身は、そのようなスタイルの作品は好きだと述べています。
その理由は次のように述べています。
顔の中心部の密なところよりも、そこを離れてタッチの大まかになったところのほうに、その画家の息づかいのようなものがじかに感じられる。画家の方もそれを知っていて、そこのところで自分の筆使いの達者さを見せようとしているふしがある。
画家の息づかいを感じる、最後は達者さをみせようとする作家の心理までも加えています。
さらに、印象派以前の古典的な絵では、筆のタッチを見せることは禁じられていた。それは法律ではなく、不文律として。昔の画家はあくまで依頼主の使用人の立場にあったので個人の表現は無用だった。絵が表現よりも「製品」に近かった。だから画家としてはせいぜい周辺に余白をつくる程度の自由度しかなかったと続けます。
ここでようやくセザンヌの余白の考察に入ります。
しかしセザンヌのこの絵にあるのは、そういう塗り残しとは違うのである。密に描いた中心を離れて、その周辺が塗り残される、というのではない。塗り残しはこの絵の各所に散らばっている。むしろ腕や胸や、顔面などという中心部に、塗り残されたキャンバス地があらわれている。中心部に余白があるのだ。
としてこの絵に感動しながら不安にかられる原因はそこらしいと推測します。それを受けて東洋と西洋の余白の議論に移ります。
東洋の絵ではよくあることである。水墨画など、中心はほとんど余白そのものである。空虚といってもいい。その空虚をあらわすために、ほんの少し松の枝を添えたり、人物を点在させたりする。塗り残しというより、それがもとから逆転している。まずベースとして空虚があるのだ。
西洋の絵で、描くことといえば絵具を塗りこんでいくことである。画面の隅々まで、そこに見えるものを描きこんでいく。分析的合理主義の充填である。
セザンヌの絵から、東洋の絵の余白、空虚と西洋の絵の塗り方の話が出てくるとは思いませんでした。
東洋の絵は塗り残しではなく、まずベースとして空虚がある。西洋の絵では見えるものを隅々まで描き込んでいくとの指摘です。
余白のことを間といったりするが、私たちはそれに慣れ親しんでいる。だからとりわけてそのことを考えたりしない。そういう自分の性質を忘れて、西洋のぎっしり描き込まれた絵を見る。自分と違う異文化に憧れたりしながら、そこに突然出てきた空虚に驚く。
ここから著者は「セザンヌはなぜ”近代絵画の父”といわれるのか」と小みだしをたてて、この絵の余白をベースに論旨を展開していきます。
それについては直接この本を読んでいただくことにして、ここではなぜ私が東洋の絵の空白と西洋の絵の余白のあり方についての著者の言葉に反応したのかを述べたいと思います。
「線スケッチ」ではペンで形を描き、その線を活かすように透明水彩絵具で彩色します。「ペン画」のジャンルに入るのですが、常々欧米人が描くペン画とはずいぶん違うと感じてきました。
欧米人のペン画では、ペンの線で紙を埋め尽くす感じとなります。輪郭や模様だけでなく陰影までも描き込みます。時代を遡ってデューラーの銅版画を思い出せばお分かりになるでしょう。
一方、東洋、例えば韓国、中国、台湾のペン画の作品は、かつて中国の水墨画の影響を受けたためか、線で埋め尽くすよりも、最小限の線でその物を表そうと意識しているように思えます。
このペン画の国による違いについて、別の機会に述べてみたいと思います。
私の場合は、往々にして線で細かく描き込み過ぎる傾向があり、そのときは意識的に描き込まないよう、自分自身に言い聞かせます。
西洋、東洋どちらのスタイルがよいかというのはまったく意味がないと思いますが、個人的には、この線に自分の気持ちを込めるという書のような東洋スタイルのペン画の方を好ましいと感じてしまいます。
やはり、生まれ育った地の文化の影響はつくづく大きいと感じます。
その意味では、著者が言うように、欧米人のセザンヌがこのような塗り残しだらけの絵を意識的に描いたということは革命的なことだと思います。
おわりに
今回で、「<赤瀬川原平の名画読本>鑑賞のポイントはどこか」の中で「線スケッチ」に関連して私が興味を持った部分についてのご紹介を終わります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
