
【勉強系14】社会人の勉強法とストレス対処法
【SYNCAオープン!】
経営管理部門・バックオフィス特化型の転職サイト「SYNCA」(シンカ)がオープンしました😁
皆様是非ご活用ください!
はじめに
所属する組織の文化にもよりますが、通常は、社会人になると勉強をする人は激減します。
大学に入った段階で文系の8割くらいの人は勉強をしなくなると思いますが、社会人になると残りの2割もほとんど勉強をしなくなって、勉強をし続ける人なんて滅多に出会えないという状況に陥ると思います🙄
それくらいが普通です。
社会人大学院ならばほぼ全員が勉強をしているはずだ!と思って行ってみると、最初の数ヶ月が過ぎた頃には勉強をし続けている人は半分以下になっていました。
修論の頃には、真面目に学んでいる人は1~2割まで減っていて、大半の人は何を学ぶわけでもなく2年間を過ごして卒業していきます。
なぜ社会人の勉強継続はここまで難しいのか🤔
勉強法に問題があるのか?
精神や意志の強さの差か?
おそらく、精神・意志の強さは、勉強継続に強い影響を及ぼすと思います。
ここで半分くらいは決定する気がします。
ただ、残りの半分は、勉強法やストレスへの対処法でなんとかなる部分もあるのでは🙄タブン
そこで今日は、社会人の勉強法とストレスへの対処法を考えてみたいと思います。

1.勉強法について
社会人で勉強を3年以上継続できている人たちには、ある程度共通点があると思っています。
それは、あまり手を広げないという共通点です🤔
一つのことをじっくり学んで、クリアにしてから次に行くという人が多いです。
これはシングルタスク・マルチタスクの議論に直結しています。
スタンフォード大学でClifford Nass(クリフォード・ナス)教授が行った研究では、日頃からマルチタスクを実行している人は、稀にしかマルチタスクを実行しない人と比べて、集中力が低く、生産性も低いという結果が出ています。
勉強もこれと同じで、同時に複数のことを処理するのは限界があるのです。
どれもが中途半端になってしまいがちで、勉強の成果が出にくくなります。
その結果、モチベーションも下がります😨
私が知る限りの人たちは、一見すると複数同時に学んでいるように見えることもありますが、内実を分析していくと、彼らは常に一つのことに集中しています。
一つの科目、一つの試験、一つの論文に一気に集中し、それを処理した後でなければ他のことをしようとしません。
同時にいくつものことをこなしているように見えるのは、彼らが極めてスムーズな流れでそれらを処理していっているからです。
社会人で勉強が続かない人の多くは、複数のことを同時に処理しようとしてしまい、勉強の途中で別のことを始めてしまいます。
例えば他の科目のテキストに手を出したり、皿洗いが始まったり、掃除をし始めたり、テレビやYouTubeを閲覧しはじめたりします😨
その段階で集中が一度途切れるので、戻ってくるまでに長い時間を要します。
結果的に、勉強の成果が出ない構造ができあがっていきます🤔
これを防ぐために、まずは一個のことしかやらないというルールを自分に課しましょう。
机の上には1つの科目のテキスト or 問題集しか置かない。
他のものはすべて別の部屋に移動させ、目に入らないようにする。
一瞬でも気が散るものはすべて排除する。
集中できる空間を作り出すことが重要です。
部屋が集中できないのであれば、個室をレンタルしても良いでしょう。
耳栓なども効果的です。
入ってくる情報を極限まで遮断して、勉強だけに集中できる状態を作り出すのです。

集中できる環境が整ったら、是非やってみてほしいことがもう一つあります!
それは、まとめノートの作成です😁
これは非常に有名な勉強法で、いろいろな書籍で紹介されていますし、実践している方も多いでしょう。
具体的な方法としては、その日一日で学んだことを、勉強終了時にまとめてノートに書くだけです!
できる限り短い言葉で、箇条書き程度で書くのがコツです。
それを次の日の朝、もう一度見直して、復習する。
たったこれだけの習慣で、記憶の定着率が倍以上変わってきます。
どういうメカニズムなのかを説明します。
まず、人間の脳は、記憶を2種類に分類して保存する機能があります。
それが、短期記憶と長期記憶です。
この分類基準は様々ですが、一つの基準として「繰り返し思い出したか」という点があります。
何度も繰り返し思い出した出来事、情報は、重要なものである可能性が高いので、脳が長期記憶として保存しようとするのです😁
また、痛みや強い感情の起伏を伴った情報も長期記憶に保存されます。
そのため、昔の忍者は、一瞬で記憶するためにわざと自分の手を針で刺して、物事を瞬時に記憶する記憶術を使っていました。
我々はさすがに針で刺すわけにいかないので、繰り返し思い出す工夫をする方で対処しましょう。
毎日まとめノートを作ることで、その日のうちに一度読んだところを思い出す作業が発生します。
これによって少なくとも1回は思い出す機会が生まれます。
そして、次の日の朝にもう一度そのノートを読み返して、昨日やった内容を思い出します。
これで最低2回は思い出す作業が発生します。
もし、毎週末、その一週間分のまとめノートを読み返すと、そこでさらに思い出す作業が入ります。
ここまでやれば相当な記憶定着を生み出すので、試験にもかなり合格しやすくなります。
勉強で結果が出にくい人の多くは、思い出すまでの周期が長すぎるのです🙄
問題集やテキストを一回全部読み通してからやっと2周目に入るというやり方をする人が多い。
これだと、下手すると思い出す作業1回目のときには全部忘れているということが起こります。
その結果、長期記憶として殆ど残らないので、成果が出ません。
繰り返す周期を上手にコントロールすることが勉強成功の鍵です。
私の感覚では、
・1~3時間後(その日の勉強終わり)
・6~12時間後(次の日の朝)
・数日後(週末)
・1ヶ月後(月末)
・数カ月後(3~6ヶ月)
くらいのペースで繰り返しておけば、ほぼ長期記憶として定着する実感があります。
上記のペースでまとめノートを見直していくと、最低でも5回繰り返すことになるので、記憶できている情報量が通常の勉強のときと比べて、実感ベースで3~4倍になります😁
簡単な資格ならこれで十分合格できてしまいます。
是非お試しください。
ちなみに、私はノートを持ち歩きたくないので、Evernoteに全部書きためていくようにしています。
Evernoteは非常に便利です!
スマホと同期しておけば、いつでもどこでも見直しができます😁
ただ、実際に手書きで残す場合と比べると、記憶効率は落ちます!
タイピングより、手書きの方が脳に残りやすいようですね🤔


2.ストレスへの対処法について
続きまして、ストレスへの対処法についてお話していきましょう。
私は日頃から勉強ばかりしているので、周りの人間から見ると「単に勉強が好きな人」というイメージを持たれています。
酷いときは、
「あぁ、あいつは勉強がストレスにならないやつなんだよ」
という誤解をされます😒
いや、待ってくれと。
おそらく、勉強で最もストレスを感じているのは私だと思うんですよ。
元々勉強なんて大の苦手です。
物覚えも悪い。
そんな人間が、毎日noteを書くために文献を読み漁り、論理を分解して再構築する作業を延々と繰り返し、それ以外の時間はずっと法務として大量の契約書を読んで、書いて、日々を過ごします。
休みの日も大学院で研究している分野の文献を読んだり、レポートを書いたりします。
こういう生活が一年中続いています。
ストレスが溜まらないわけがないでしょうがぁぁぁああああ😭
長いことそういう生活をしているので、ストレスに対処する機会が多くございました。
そんな私が勉強系のストレスに対処する方法をご紹介しましょう👍
日頃は絶対に表に出ない(出せない)ストレス発散法を今日はご紹介しましょう😏
(1)テキストをスパーキンっ!
まずはこれですね。
私の経験上、ストレスの原因の9割は、出来の悪いテキスト・問題集にあるんですよ。
見たくもないし、読みたくもないし、難しいし、イライラする😱
文章が下手くそなテキストなんて読んだ日にはストレスマックスですわ。
そう。
全部、ダメなテキスト(問題集)が悪い。
そんなやつはスパーキンっしてやればいいのです。

このとき、手加減をしてはいけません。
渾身の力を振り絞って、堅いザラザラした壁に思いっ切りスパーキンっしましょう。
神社の石垣やザラザラの砂壁などがいいですね。
日頃の鬱憤を言葉にして叫ぶとより効果的です。
テキストが汚れる?🙄
それがなにか?
どうせ勉強していけば汚れる!
マーカーも入れるでしょうし、書き込みもするでしょう。
たかがスパーキンっ。
そんなこと気にする必要ありません。
ストレスを抱え続ける方が問題です。
思いっ切りスパーキンしましょう。
素晴らしいテキスト・問題集ならイライラなんかしませんから、どうせスパーキンっされるのはダメな本だけです。
(2)水攻めの刑
まずは、水攻めのために、水がヒタヒタに入った窯を用意します。

あえて熱して熱湯にしても構いませんよ😁
ダチョウ倶楽部が入る以上の熱湯に仕上げてあげましょう。
そこにポーンです。

もちろん書籍はブヨブヨになります。
でも、大丈夫です。
ストレスの原因となるような書籍なら、十中八九いらないやつだと思うので、無問題です。
どうしても必要ならまた買えばいいだけの話です🙄サイコ
絶対に許せない書籍が出てきたら、水攻めの刑に処してやってください。
若干スッとすると思います(笑)
(3)市中引き回しの刑
江戸時代に行われた「市中引き回しの刑」を参考にして、書籍を引き回してやりましょう😊
もっとも、江戸時代と違うのは、引きずり回してやるという点です。
イメージはこんな感じ。

アスファルトの上を100mほど引き回してやればそこそこのダメージを負わせられるので、若干スッキリするでしょう😁
試験会場にそのボロボロの書籍を持っていけば、周りから見れば
「あの人、ガチ勢だわ!あんなにボロボロになるまで勉強してるぅ!」
というプレッシャーをかけられるのでおすすめです。
ただ、実際に私がやってみたところ、ハードカバーの書籍だとダメージは限定的でしたね🙄
普通の書籍だと300mくらい引き回してやれば、表紙や角の部分に致命傷を与えられるので効果的でした。
500m超えてくると、一瞬「あれ?俺、何やってんだっけ」という虚無感に襲われるので、300m程度が限界かなと思います。
(4)ゴミ箱ポイポイ選手権の開催
ダメなテキストでイライラさせられたら、もう家族全員でゴミ箱ポイポイ選手権の開催です!
テキストを破って、丸めて、ゴミ箱にポーイ!
入れば1ポイント。
入らなければ-1ポイント。
家族の中で最初に10ポイント獲った者が優勝です!
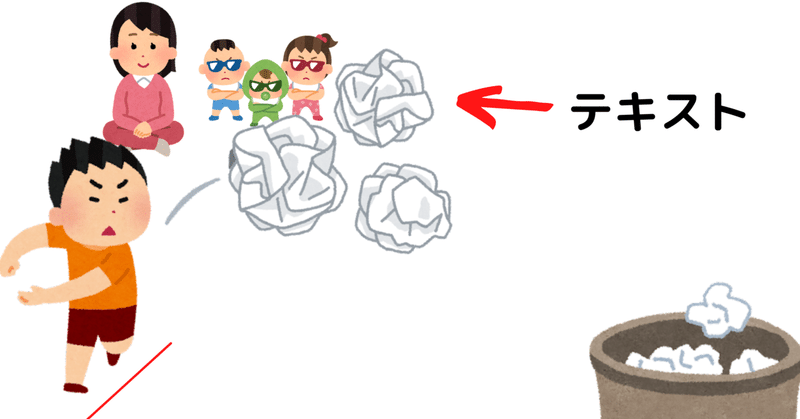
どうしようもない書籍も、家族で使えばHAPPYツールに生まれ変わりますし、皆で楽しめるのでストレス発散にもなります🤣
テキストは尊いものだという認識を捨て去り、ビリッビリに破いてやればいいんですよ👍
子どもたちも楽しい、おっさんも楽しい。
ストレス発散にもなる。
一石三鳥です。
おわりに
今日は社会人の勉強法とストレス対処についてご紹介しました。
勉強法については一点集中方式とまとめノートを。
ストレス発散法については、スパーキンっを始め、日頃他人には言わない発散法をご紹介しました(笑)
勉強でストレスが溜まらない方法なんてものはありません😱
どんなに頑張ってメンタルケアをしても、勉強という行為によって、少なからずストレスは溜まっていきます。
その分、合格したり、学位を手にしたりしたときに嬉しさがこみ上げてきます😁
そこまでの辛抱ではありますが、どうしてもしんどいときは、スパーキンっしましょう👍
ではまた次回の記事で(^_^)/~
【お問い合わせ】
この記事は、株式会社WARCの瀧田が担当させていただいております。
読者の皆様の中で、WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方がいらっしゃったら、以下のメールアドレスにメールを送ってください😁
内容に応じて担当者がお返事させていただきます♫
この記事に対する感想等もぜひぜひ😍
recruit@warc.jp
【WARCで募集中の求人一覧】
【次の記事】
【著者情報】
著者:瀧田 桜司(たきた はるかず)
役職:株式会社WARC メディア編集長
専門:法学、経営学、投資
経歴:営業系商社→大手生保→独立→法律の勉強→上場ベンチャー法務部長→FinTech系ベンチャー執行役員→投資家 / ベンチャー役員 / WARCで記事書くおじさん等の兼務😵
その他:いつでも気軽に友達申請送ってください😍
Facebook:https://www.facebook.com/harukazutakita
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
