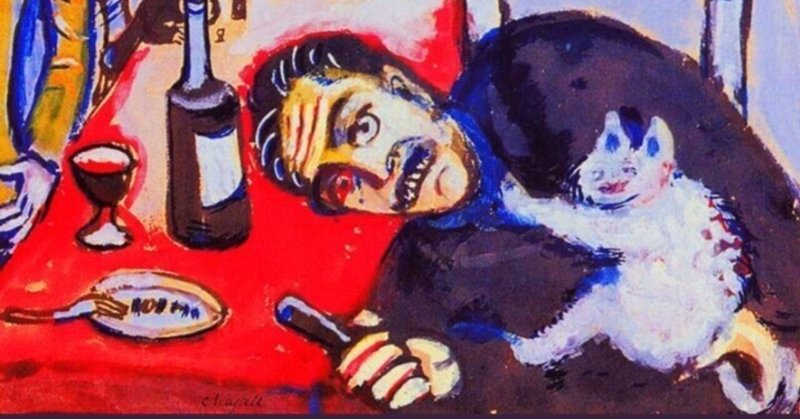
狂気ってなに? 〜世界一わかりやすい映画理論入門第2講・精神分析理論入門〜
・初級編はこちら!(読み飛ばし可)
https://note.com/waganugeru/n/nefc7f97da558
・はじめに
初級編を読み終えたあなたは、既に“映画を見る”ことから卒業し、“映画を読む”ための新たな道具を手にしているはずだ。
そこで、この文章では、より実践的かつ強力な第2の武器を提供したい。
それはズバリ、“精神分析理論”という名の道具だ。
おっと、身構える必要はない。いつも通り、世界一わかりやすく、最短距離だけを通っていく。
ひょっとすると、最初はムズかしく感じられるかもしれないが、心ってなんだろう?狂気ってなんだろう?という好奇心から読み進めてみてほしい。
そうすればきっと、新しい発見と出会えるはずだから。
それでは、スタート!
・意識は言葉の関数である
かつてブッダが到達した悟りの境地とはどのようなものだったのだろう?
それは例えば、ひとつを入れたらすべてが出てくる特殊な関数が、通常の脳の働きに取って代わった状態だと言える。
われわれは世界の諸相をまずイメージとして捉え、言葉によって具体化した上で、論理に従って並べ替える。
これらのピースが互いにくっついたり離れたりしながら形作られるパズルの全体が、おのおのの思考のベースになっていることは言うまでもない。
例えば、リンゴという言葉を聞けば、赤い、丸い、おいしい、果物、青森、農家などの言葉が思い浮かぶだろう。
もちろんこれらの語句には無限のバリエーションが考えられようが、いずれにせよ、それぞれの頭の中でリンゴと結びついた〈既に論理化が完了したイメージ〉の範囲を超え出ることはない。
というのは、本来あいまいで無関係なイメージ同士が関わりを持つためには、必ずなんらかの論理が必要になってくるからだ。
先ほどの例に沿って言えば、リンゴで“あるから”~色は赤い、形は丸い、味はおいしい、種類は果物、産地は青森、生産者は農家、といったように。
つまり、ある言葉=aの刺激に対する反応は、通常必ず、aが入れられているイメージの袋=Aの中から出てくる。
これを反射する言葉=a’とした場合、aなる入力に対してはa’、bに対してはb’、cに対してはc’が出力される・・・
このような関数こそ、われわれが〈意識〉と呼ぶシステムを動かしている仕組みなのである。
・狂気は意識のシステムエラーである
ところが、われわれの経験には、aという言葉を聞いて、なぜかAではなくBに関係するイメージや、Cの袋に入っている言葉が連想されるケースが容易に含まれる。
リンゴという言葉を聞いて、赤い、丸い、の代わりに、泥棒、映画館などの一見無関係な言葉が想起される場合がそれだ。
このような経験の多くにおいて、当事者は自身の反応を上手く説明することができない。
つまり、なぜ赤いではなく泥棒が、丸いではなく映画館が浮かんできてしまうのか、それらのイメージが自己の内部においてどのようにリンゴという言葉と結びついているのか、その論理性を明らかにすることができないのだ。
こうしたイメージの混在は特に珍しいものではないが、生活の全般に及び始めると狂気へ近づいてゆく。
意識の関数にならって言えば、aの入力に対してa'だけではなくb'やc'も出力される、というのが通常のエラー。これに対し、〈狂気〉とは、いつも必ず無関係なb'やc'だけが出力されてしまう、という重大なシステムエラーを指す。
つまり、赤い、丸い、とともに泥棒、映画館が連想される状態は正常だが、泥棒、映画館だけが連想される状態は狂気だというわけだ。
「昨日リンゴ食べたらさー」という切り出しに、「ああ、あの映画館ね〜」とか「この泥棒!」などと受け答えする人間の姿を想像してみるといい。
近代的な医療倫理が浸透する以前、同性愛は精神疾患の一種と考えられていたが、これは、男性に対して女性、女性に対して男性が出力される恋愛関数が正常とされた時代における、“間違った意識の関数”であったためだろう。
狂気が指し示す内容は歴史によって様々に移り変わるが、それを、〈システム化したエラー/入力に対する出力がねじれた関数〉として扱う大枠には、ほとんど変化がない。
・精神分析はストーリーを繋ぎ直す
だがそもそも、些細であれ重大であれ、システムエラー/出力のねじれはなぜ起きるのだろう?
a→a'式の意識の関数が正常に機能するのは、関連するイメージが言葉の袋で仕分けされ、論理のひもでしっかりと結び合わされているからだ。
とすれば、a→b’のようなねじれが発生してしまうのは、言葉と論理のいずれか、もしくは両方に問題が起きているからではないだろうか?袋が破れていたり、ひもが途中で切れていたり・・・
19世紀末、ジグムント・フロイトによって創始された精神分析学は、こうした破れや切断の理由を、意識に対する無意識の働きのなかに探り、言葉と論理を通じて形成される個人の物語=〈ストーリー〉に着目するに至った。
われわれが普段利用しているクリアな意識は、実は意識全体のわずかな陸地面に過ぎず、その周囲には真っ暗な無意識の大海が広がっている。
クリアな意識の中から自在に言葉を取り出すことができるのは、それが〈既に物語化が完了したイメージ〉によってできているためだ。
一方、なんらかの抵抗にあったせいで物語化を完了できなかったイメージは、無意識の底へと沈んでいき、やがて言葉にならぬ声を発し始める。
この声を無視し続けていると、最悪の場合、訴えは心身の不調となって現れ出る。「んもー!ぼくの言うことをちゃんと聞いてよ!」と、ダダをこね始めるわけだ。
したがって、精神分析における治療とは、患者自身から発されている無言の叫びに、声を与える=言葉と論理によって名付け直す試みにほかならない。
こうした名付け直しの過程において、物語化を阻んでいた患者の抵抗が徐々に明らかになり、破れや切断が修復され、ちぎれたストーリーが繋ぎ合わされた瞬間、症状はひとりでに治癒する。
治るのではなく、役目を終えてホッとした症状が、自ら立ち去るわけだ。
・二つの物語化、精神分析と宗教
一見するとこれは、「うっかりAの袋の中に迷い込んでしまったb'が、Bの袋の中へ戻ることによって、a→b’のねじれが見事に解消された」という事態を指すようにも思える。
だが、より正確には、まさにそのようなキレイでわかりやすいお話を、患者の意識内部に作り出す手助けをするのが、精神分析の役割なのだ。
なぜなら、嘘だろうと本当だろうと、ストーリーが完成しさえすれば症状は回復するのであって、そもそも当の本人が忘れ去っている事柄の真偽を判定することなど誰にも不可能だからだ。
逆に言えば分析医は、誰しものうちに自然と備わっている〈物語化の機能〉を促進する補助役、サブのドクターであるに過ぎない。
では、優秀なメインドクターである物語化をわざわざ阻む患者の抵抗は、どこから生まれて来るのだろう?
それは、意識関数の範囲内ではとても処理しきれない、理不尽な経験によって生まれる。
「廊下を走り回っていたら怒られた」「ある人の悪口を言いふらしていたら殴られた」できれば避けたいような出来事だが、これらの経験は言葉と論理を使って一応ストーリー化できるため、無意識の症状の出る幕ではない。
ところが、あまりにも理不尽な出来事「道を歩いていたら見知らぬ人にナイフで刺された」「突然の事故により最愛の息子を失った」などの悲惨な経験においては、意味や論理を見出すことが困難であり、むしろそれをしようとすると意識が深手を負う公算が高いため、無意識があえてストーリーを未了のままに留めておくのだ。
つまり無意識の症状は、患者を傷つけるためではなく、患者を守るためにこそ出現してくる。
一方、未了のままのストーリーを、より大きな物語のピースの中にはめ込むことで、完了を肩代わりする方法も存在する。
「わたしがナイフで刺されたのは罪を浄化するためだった」「事故で息子を失ったのは神による試練だった」・・・
もうおわかりだろう、宗教だ。
精神分析を個人の物語の再インストールだとすれば、宗教はより大きな物語=世界観のインストールである。
したがってもちろん、信仰者に神の不在を説いても意味がない。彼は神がいる世界ではなく、神がいる世界のストーリーを生きているからだ。
いずれにせよ物語化は、「世の中はそもそも理不尽なものである!」というナマの現実から、われわれの身を守ってくれる武器なのである。
・最初のフィクションは自分である
程度の差こそあれ、 人はみななにかしらの物語の中を生きている。
そもそも自分というストーリーが未了のままなら、今ここにいるわたしを過去に遡って語り起こせないとしたら、その人物は始終不安に苛まれるだろう。
自分を物語化する経験を通してはじめて、われわれは、自分であったかもしれないものや、反対に自分ではないものを、別なるストーリーとして楽しむことができるようになるのだ。
この通り、フィクションは可能性としての世界の物語化だから、二つの物語化=宗教と精神分析と相性がいい。
物語の素を生み出す神話や宗教が創作における霊感を刺激し、物語を語り直す(繋ぎ直す)精神分析がしばしば批評の道具として利用されるのは、そのためである。
現実もフィクションも、物語化の手続きなしに読み解くことはできない。逆に言えば、ストーリーとして読み解く限りにおいて、同じ臨床上の知恵を使えるというわけだ。
しかし、実のところ、あらゆる種類のどんな物語も生きていない人間も存在する。
物語る機能が完全に失われてしまった、エラーもシステムもすべてが区別なくごちゃ混ぜになってしまった、そんな人間の姿をぜひ想像してみてほしい。
・ヒント(読み飛ばし可)
ヒントとして、ここまでの流れを関数にして整理してみよう。
意識(クリアな意識)・・・a→a'、b→b’(※これはもちろんc→c'~z→z’を含み持つが、以下省略する)
無意識(の作用による一般的なねじれ)・・・a⇢b’
よって、いわゆる正常な意識は上記二つを統合した形態だと言える・・・a→a' or b'
狂気(ねじれの固定化/エラーのシステム化)・・・a→b'
無意識の訴えが症状として現れ出た状態(ねじれの常態化/エラーの頻繁化)・・・症状の程度や種類に従い、a⇢b’からa→b’に至るまで、矢印が濃淡を描く
・精神分析は完全な狂気の前に敗れ去る
精神分析の功績は、無意識の概念を使って出力のねじれを構造化することによって、人間の知られざる内面のドラマを、まるで絵のように観察可能な対象に変えたことだ。(今敏のアニメーション映画『パプリカ』を想起せよ!)
ねじれは、ただでたらめにねじれているわけではない。
あるひとつのねじれa→b'が、出現するごとに、a→c'、a→d’・・・とランダムに変化していくなどということはあり得ない。
そこには必ずなんらかの法則、無意識による操作のクセが存在する。
こうした発見により、もし仮に狂気の正体がシステム化したエラーだったとしても、そのエラーはけっして修復不可能なものではないことが、希望をもって示されたわけだ。
ただし、これはあくまで精神分析が用いるメスと縫合糸=言葉と論理が及ぶ範囲の事柄に限られる。
逆に言えば、あらゆる法則性を欠いたランダムな出力や、好き放題にねじれまくる矢印の存在が確認された場合、精神分析ではたちうちできない。
論理的に言って、これこそが〈完全な狂気〉と呼べるなにかだろう。
一行目を思い出してほしい。
『かつてブッダが到達した悟りの境地とはどのようなものだったのだろう?
それは例えば、ひとつを入れたらすべてが出てくる特殊な関数が、通常の脳の働きに取って代わった状態だと言える。』
そう、完全な狂気とはおそらく、悟りに近いものである。
ひとつの言葉aを入力すれば、A~Zのすべてに関わるイメージがランダムに、しかも複数同時に出力されるムチャクチャな関数。
ブッダ=お釈迦様が万物に慈愛をもって接することができるのも当然だろう。
なにしろ彼にとっては、人も虫も花も蛇もみな等しく価値がある=ないのだから。
今この瞬間、目に映るなにもかもが同じものであると“同時に”違うものでもある。
しかし考えてみるとこれは、単に平等と呼ぶにはなまやさしい、渾沌に満ちた恐ろしい世界ではないだろうか?
言葉はイメージを区別するために、論理は区別されたイメージを繋ぎ直すためにあるから、あらかじめいっさいの区別が失われた世界の暴力性の前にあっては無力だ。同様の理由から、精神分析もまた〈完全な狂気〉の前に敗れ去る。
人間を救済する理論としての精神分析が宗教に及ばないのは、まさにこの点だ。宗教の強みは、言葉の限界を沈黙の言葉=信仰と祈りによって、論理の行き詰まりを絶対者に保証された論理=教義によって乗り越えるところにある。
したがって、完全な狂気の関数はこうなる。
完全な狂気(≒悟りの境地)・・・a→a'~z’
・完全な狂気の正体は「ありのままの現実」である
ところが、ここにある恐るべき問いが浮上してくる。
完全な狂気が、いかなる種類の物語化をも利用することなく、直接に世界を経験した場合にのみ感じられるものだとすれば、われわれが普段なにげなく口にする「ありのままの現実」とは、まさにこうした狂気の世界を指し示しているのではないだろうか?
そもそも、ありのままの現実、人間の手が加えられていない世界のイメージは、ご丁寧に言葉の袋で仕分けされたり論理のひもで結び合わされたりしていない。
それらはすべて論理化が完了していないイメージ=凶暴な断片の集積であり、われわれを傷つけかねない理不尽な出来事の親玉である。つまり、物語化を阻む理不尽さそのものを産む母体、〈ありのままの現実〉こそが〈完全な狂気〉の正体なのだ。
実を言えば、われわれ人類が言葉と論理に頼って文明を築き上げてきたのは、普段現実の外側をコーティングしている物語の保護材が剥がれ落ち、露出した現実がふたたび狂気へと逆戻りする危険を防ぐためだったのである。
無意識の症状は、いわばこうした人類規模における防衛形成の、個人的なレベルでの現れにほかならない。
このように考えてみた場合、われわれは永久に現実そのものには触れることができない、という残酷な結論が出てくる。
その過酷さに耐えうるのはせいぜい、あらかじめ狂気を受け入れた者か、悟りを開いた聖人だけだろう。
いやむしろ、こう言った方が正確か。
それぞれが信じるストーリーをクッションにして現実を遠ざける努力を通じてのみ、われわれはようやく現実を生きることが可能になるのだ、と。
一度は〈完全な狂気〉の前に敗れ去った精神分析は、この点に希望を見出すことによって、何度でもその輝きを取り戻そうとするだろう。
・まとめ
改めて全体を整理してみよう。
狂気とは関数のねじれのことだった。
したがって・・・
意識(ねじれなし)・・・a→a'
無意識(ねじれ)・・・a⇢b’
症状(ねじれの発生)・・・a⇢b’~a→b’
狂気(ねじれの固定化)・・・a→b'
完全な狂気(ねじれのランダム化)・・・a→a'~z’ = ありのままの危険な現実
たったこれだけ!
精神分析理論を理解するための最短距離は、まずこの公式をしっかり頭に叩きこんでおくことだ。
とはいえ、使えない理論に意味はない。
続いて、この理論を実際に“使う”ーー精神分析を道具として利用し、“映画を読む”ーーに当たって、忘れないよう復習しておこう。
※実践編
覚えたらさっそく使ってみよう!
精神分析理論を使って、マッツ・ミケルセン主演の名作映画『アダムズ・アップル』をわかりやすく読み解いていくぞ!
https://note.com/waganugeru/n/nd1743a88235b
野生動物の保護にご協力をお願いします!当方、のらです。
