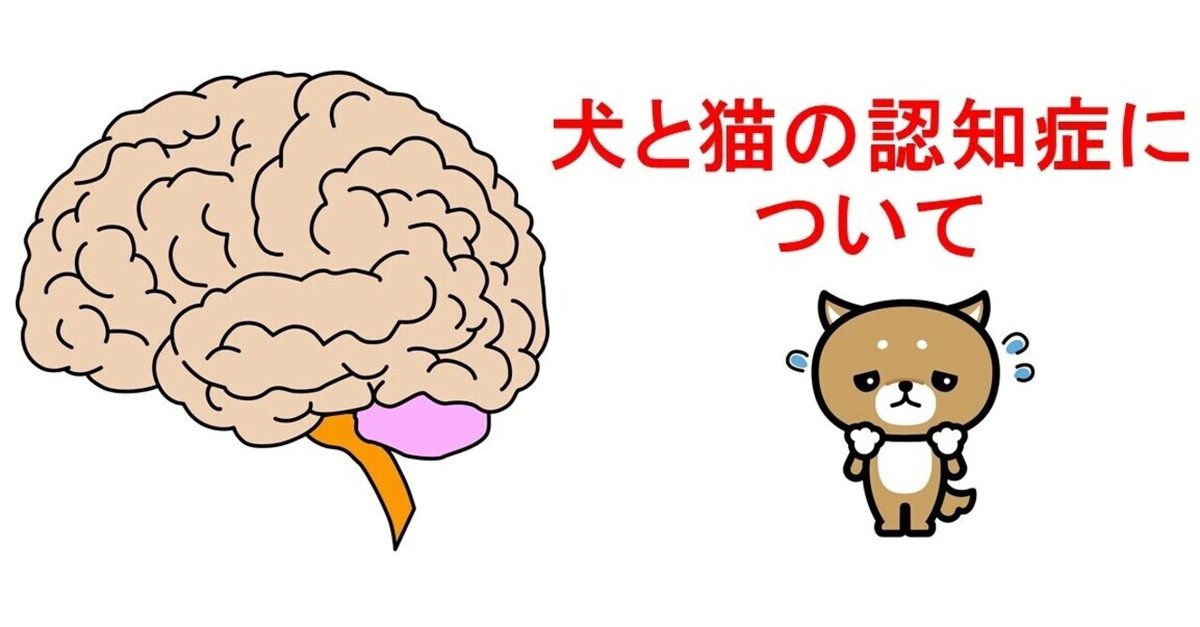
犬と猫の認知症について④
獣医師ゴリです。
前回は認知症の発生年齢についてお話ししました。↓
今回は、犬の認知症の具体的な症状についてお話ししたいと思います。
セミナーの中では以下のようなデータが示されていました。↓
DISHAAの徴候
1.見当識障害(Disorientation)
2.相互反応変化(Interaction Changes)
3.睡眠あるいは行動の変化(Sleep or Activity Changes)
4.トイレトレーニングを忘れる(Housetraining is Forgotten)
5.活動の変化(Activity changes)
6.不安(Anxiety)
それぞれ簡単に解説していきます。
1.見当識障害(Disorientation)
見当識障害とは、自分が現在置かれている環境が理解できなくなる障害のことです。
犬や猫では、
・自宅のドアを間違える。
・ウロウロと徘徊する。
・部屋の角や家具の裏に入り込む。
・散歩に行って自宅に戻れなくなる。
などの行動が当てはまります。
2.相互反応変化(Interaction Changes)
相互反応変化とは、ご家族や同居の動物に対する態度の変化として観察されます。
・ご家族を認識できなくなる。
・周囲からの呼びかけにほとんど反応しなくなる。
・食事の要求を繰り返す。
などの行動が当てはまります。
3.睡眠あるいは行動の変化(Sleep or Activity Changes)
・昼間はずっと寝ていて、夜になると活発になる。
・夜鳴きや夜の徘徊がはじまる。
などの行動が当てはまります。
4.トイレトレーニングを忘れる(Housetraining is Forgotten)
トイレトレーニングを忘れ、歩きながら排便をしたり、尿を垂れ流すようになります。
5.活動の変化(Activity changes)
特定の活動が異常に活発もしくは減退するようになります。
<活発の例>
・円を描くように歩き続ける。(旋回運動)
・過度に舐める。
・空中を凝視する。
・攻撃性が増加する。
<減退の例>
・寝てばかりいて活動しない。
・無気力
などの行動が当てはまります。
6.不安(Anxiety)
・ご家族が近くにいないと鳴き、ご家族が近くにいくと鳴きやむ。
・これまで大丈夫だったものに対して怖がる。
などの行動が当てはまります。

今回のセミナーで言われていたのが、上記に挙げた行動の変化は、血液検査やMRIなどの検査で獣医師が発見できるようなものでなく、
あくまでもご家族が愛犬愛猫の行動の変化に気づくことによって発見できることが多いです。
そのため認知症の早期発見早期治療には、ご家族がいかに今回挙げたような行動の変化に気づくことが出来るかがポイントとなってきます!
ご家族が愛犬愛猫の行動を「老い」によるものと思っていたことも実は認知症の症状が隠れていることも多いです。
今回のnoteを読んで
『もしかしたらうちの子も認知症なのかもしれない!?』
と思われた方は今度動物病院に行くことがあれば、主治医の先生にぜひ相談してみてください。
もし主治医の先生に聞きづらい、主治医が決まっていないという方は私に相談いただいても構いません。
行動の詳細を教えて頂ければできる限りのアドバイスをさせていただきます。
興味ある方はぜひご相談ください。↓
今回のnoteは以上です。
次回は認知症の病態についてお話ししたいと思います。
つづく
<参考文献>
・ヒルズセミナー「先生、眠らせてください」にどう対処しますか?
認知機能不全症候群のアップデート
・一般診療にとりいれたい犬と猫の行動学
<お知らせ>
この度私が初めて有料記事を書かせていただきました。↓
愛犬愛猫の認知症も含めたさまざまな病気のサインにいち早く気づくにはどうすればよいのか!?
そのような内容も書かせていただいています。
興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。
そしてコメントで読んだ感想などをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
