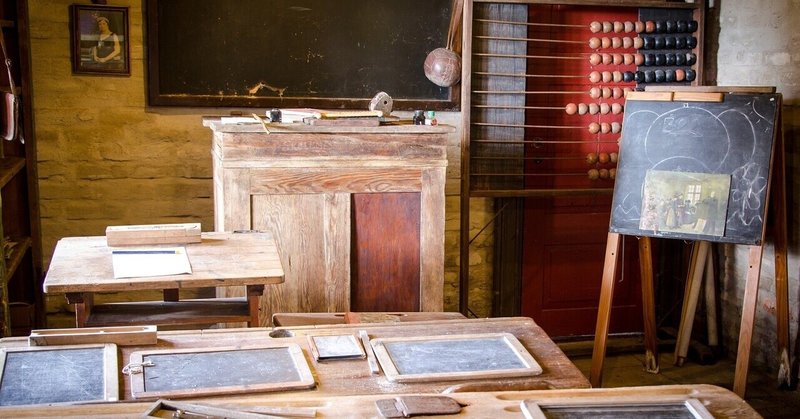
相手の立場で考えるのは難しい【私が岸田さんをすごいと思ったわけ】
相手の立場に立って考える、相手の目線で考えるというけれど、それって簡単なことじゃないと思う。
目線を合わせるなんて、実際の行動しかりじゃないか。
目線の低い子供に物を渡すときに腰を落とす人は、大体子供がいるか子供と接する機会が多い人だ。
わかっていてもできるかどうかは違う。
第100代内閣総理大臣に岸田文雄氏が選出された。
先月末の総裁選は、1年以上使用していないテレビをつけ、在宅での仕事をしながら見守った。
私は政治についてそこまで詳しくない。
総裁選は国民投票も無いため、正直これまではあまり興味がなかった。
が、面白いニュースが流れてきた。
学校でSDGsについて学んだ小学一年生が、「将来虫を食べることになってしまうのか」と質問したそうだ。
これに対する4者の回答が面白かった。
●河野氏「そうならないように努力をしています。お肉すきかな。大豆からお肉が食べられるように、実験進めています」
● 岸田氏「皆で努力すれば虫を食べなくて済む。水や自然を守っていかなければなりません」
● 高市氏「今でも伝統的に虫が好きな方がいます。栄養もありますよ。工場の中で野菜や果物が育てる仕組み進めています」
●野田氏「おばちゃんは昔から虫を食べています。しょうゆと砂糖で煮るとおいしいです。肉や野菜を作る人が増えるよう願っています」
(上記リンク日刊スポーツより引用)
この中で私が一番良く知っているのは、Twitterでも度々話題になる河野さんなのだが、いかにも河野さんらしい論調だなと思った。
言葉を濁したりせずスパッと改善策を出してくれるところは、賛否両論あれど、いてほしい存在だなと思う。
高市さんと野田さんに関しては、地域によっては現在も昆虫食の文化があることを説明していることに好感を持った。
ただ、高市さんの話は小学一年生にするにしては少々難しいのではないかと思うし(食糧問題を社会科で扱うのは第5学年)、野田さんは「願っています」の表現が引っ掛かる。なんとなく他人事のように感じてしまうからだ。
正直、岸田さんが一番ふわふわしたことを言っている。
最初に見たときは「なんか具体性に欠けるな」という印象だった。
ただ今回考慮すべきなのは、伝える相手は小学一年生ということだ。
私は小学校を卒業して10年以上経っているが、当時よく年間のクラス目標や行事のスローガンとしてあげられていたのが、「one for all, all for one」「みんなで協力」「心をひとつに」などだ。
あれからゆとり教育は廃止され、今の教育の現場は変化しているだろう。
ただ学校に通うということは、単なる学習だけでなく、他人と関わることも目的に含まれるのは変わらないはずだ。
「皆で努力すれば」
この発言、もしかしたら一番小学生相手に刺さる言葉ではなかろうか。
上記は私の推論なので、現代の教育現場と相違があるかもしれない。
しかし、もしこれが実情と合っているならば、岸田さんは共感でも改善策の提示でもなく、自発的に行動するよう促しているのではないだろうか。
国を動かすのは個人の行動だと指し示していることにならないだろうか。
違う環境で違う人生を生きている私たちは、完全に共感し合うことはできない。
しかし、相手の心を動かすことは不可能ではない。
私たちはわかり合うことだけを目的にしちゃいないだろうか。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
