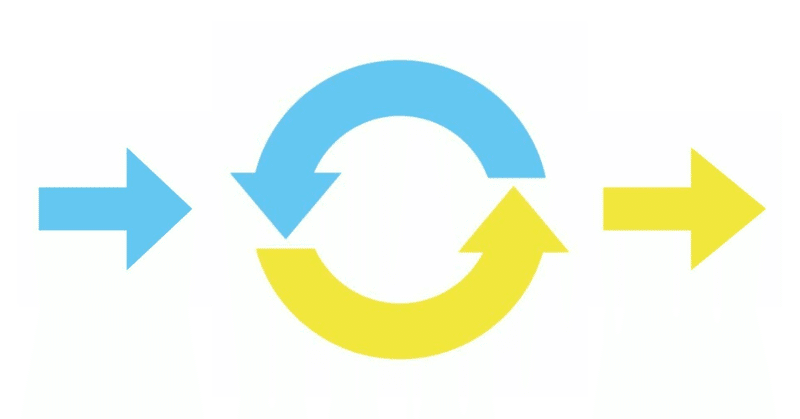
28."サイクル"がなければ、事業は伸びない.
▼誰に読んでほしいテーマか
・起業準備中で、アイディアを固めている起業家
・新規事業開発の事業責任者
・事業を大きくしたいと考えている経営者
今回は、事業を前進させる上で重要な要素となる、
「循環(サイクル)」について書きたいと思います。
▶物事を「循環」でとらえることの重要性
事業に限った話ではないですが、
物事には、「原因」と「結果」があります。
これらは「原因」→「結果」のように
二元的にとらえられがちです。
ただ僕はこれを「循環の一部」だと捉えること大事だと思っています。
つまり
【原因①】 →【原因②】 →【原因③】 →【結果】→【原因①】に戻る
のようなサイクルが回っているということです。
この循環を具体的にイメージするものとして、
特に有名なのはジェフ・ベソスがAmazonの創業前に書いた、
「グロースサイクル」ではないでしょうか。

アマゾンがここまで大きく成長した理由を、
単一的な要因で説明することは、中々困難です。
しかし
「特定領域の品揃えに注力する」→「顧客体験が良くなる・・・」
といった具合で、
果たして創業者がどんなことに重きを置いていたのか?
は、誰にでも説明はできますし、理解もしやすくなると思います。
何が言いたいのかというと、
成長するサービスを分析してみると、必ず相乗効果を生む循環
「正の成長サイクル」が存在していて、それが一目瞭然になっている
ということです。
成長サイクルを描くことの重要性については、
過去のエントリーでも触れておりすので
ここで同じ内容を展開することは控えますが、
今回のエントリーでお伝えしたいのは、もう少し事業運営の現場に即して、
発展的・実践的に、捉えておいて損がないはずだと思っていることを
共有したいのです。
▶ 「成長が、さらに新しい成長を生む」ことをベースに置く。
▶ 調子が悪いなと思う時は、まず「不のサイクル」を捕捉する。
それがこの2つです。
▶成長がさらに成長を生む循環を考える
上の図でも、真ん中(コア)にある
「Growth(成長)」から矢印が伸びて、
「Customer Experience(顧客体験)」に戻る
という流れがあります。
これがどんなことを示唆しているのかを考えると、
事業は、成長すればするほど、「顧客の体験」に還元される
という再成長のループを描かねばいけない
ということだと思います。
言葉にすると、「当たり前じゃん」なのですが、
一般的に、組織を作り、事業を大きくしたいと考えるときには、
要素を分解してKPI(重要な評価指標)を設定する
という手法を取ります。
一番わかりやすいのは
「売上」=「顧客単価」×「顧客数」という図式です。
ここで
「顧客単価をいかにあげるか」
「リピート率をいかに増やすか」
「解約率をいかに下げるか」
「新規顧客をいかに増やすか」
「高単価の案件獲得を強化する」
といった具合に、テーマ別に施策を考え、各部門ごと、
もしくは小規模な内は、社長自らが考えて、動くこともあります。
どの施策も、とても重要であり、やるべきことですが、
(特に事業初期の場合は)限定されたリソースで、
かつ状況や数値も逐一変わる中では、朝令暮改が当たり前になり、
PDCAも回しづらいということも、間々あるのではないでしょうか。
なので、
あるKPIを改善したいというミクロ視点で
施策を回すことも短期目線では効果的ですが、
経営者や事業の責任者のレイヤーであれば、
それに加えてマクロ的な目線。
つまりこの循環モデルを成長に組み込む必要があります。
つまり、「業績目標とKPIだけを設定して追えばOK」ではなく
「顧客体験の向上(ユーザーが喜ぶ)」を
重要な事業成長の要素として含めたうえで、
成長循環モデルを図式化してみること。
事業の規模拡大が、どのように顧客の体験や価値の向上に、つながるか?
これを明確にしてみることが必要なのです。
▶「調子が悪い」ときもループにハマっている
2つ目です。
循環の考え方は、逆に調子が悪いという時にも当てはまります。
事業運営上、順風満帆な状態がずっと続くことはありません。
むしろ、「下がり調子」「悪い」と思う時のほうが多いかもしれません
赤字が続いている、営業の契約が取れない、集客が思うようにいかない。
など。調子が悪い時ほど、人は損失への痛みを感じやすくなります。
そうすると、焦燥感にかられて視野が狭まり、
周りが順調に見えたりして、気分や気力も低下し、
各々が苦悶の時間を過ごしてしまいがちです。
ここを抜け出す糸口として、一つ有効なのは
「負のサイクル」に陥っていることを分析してみることだと思います。
なぜなら、人は答えが中々出ないときほど、苦しみますが
サイクルで考えることで、「今の不調がどこから始まっているのか」
その起点が整理されやすく、見つかりやすいからです。
例えば、営業不調の原因が
「商談がうまくいかないこと(商談からの受注率が低い)」
だと認識している場合を想定してみましょう。
ロープレなどを通じてトークや切り替えしの練習などを行うと思いますが、
なかなか短期的に功を奏さないこともあります。
以下は、例として簡略的なものを上げますが、
営業のキモとなるのは
「顧客が求めていることを、キャッチできる力」です。
そこを起点として考えてみると、その先の行動によって
正と負のサイクル、どちらにも陥ります。

ここではわかりやすいように、かなり単純化していますが、
現在地とループがどこを起点に起こっているかを見極めていきます。
これで分析できてくると、とるべきアクションが
おのずと変わっていきます。
・顧客の業界課題や志向が別のところに移っていないか・・・?
・競合他社は、新たな打ち出しをしていないか・・・?
・営業している担当や相手は本当に適切なのか・・・?
・顧客からみて、どの分野で専門家になるべきなのか・・?
こんな具合に、視野が自然と多角的になり、論点が明確になっていきます。
何か上手くいかないなというときには、
負のループ、つまり根本的な「起点」が必ずあります。
そこを見極めることができれば、
逆の行動をとることで、正のループに突入することがしやすくなり、
暗中模索のような状態から抜け出すヒントが得られるのです。
▶「循環」を止めないのは、当たり前を当たり前にやる力
まとめです。
今回は「事業を成長させるサイクル」について深堀をしてみましたが、
人によっては、こういう話は、コンサルタントが説明に使うときの
理想形のように思えてしまい、
「現場は、もっと泥臭い活動の連続なんだよ」
と思う方もいると思います。
結論、僕もそうだと思います。
というのも、一番大事なことは、
正のサイクルを経営者だけがわかってることではありません。
事業を運営する組織自体が、ここを浸透・理解しているかどうかです。
現実では、「風が吹けば桶屋が儲かる」のように、
勝手に良いサイクルが回って結果が出るということは余りありません。
結局、成長には劇的な近道はないのだということを理解することだと
思っているからです。
もちろん目新しく、一気に注目を浴びて、メディアに取り上げられる
スタートアップや新規事業なども稀に存在しますが、
そこが、ずっと支持を得て続けられるかどうかは
結局、顧客と組織、両面に向かい合って
地道に成長を回そうと努力しているか。
経営陣が、そういう運営をしているかどうかだと思うのです。
言い換えれば、「顧客に喜ばれることをする」といった
当たり前なことを当たり前にやろうよという活動理念が
最終的な成長を生む原動力になるのだと思います。
もちろん「サイクル」に固執する必要はありませんが
事業を大きく導くための、字引きにはなってくれるものなので
あまりきちんと考えたことないなという方は
是非、取り入れてみていただくのをお勧めします。
今回はここまでとなります。
最後までお読みいただきありがとうございました!
【僕の自己紹介です】
【僕の活動について】
事業の立ち上げや、起業、もしくは起業について関心のある方、
是非是非、カジュアルにお話しませんか?
こちらよりお気軽にどうぞ!(※日程調整ツールが開きます)
★facebookやLinkedinからDMも歓迎です。
・facebook
・Linkedin
【↓↓↓良ければこちらも読んでみてください↓↓↓】
★起業・経営について
★組織づくりについて
