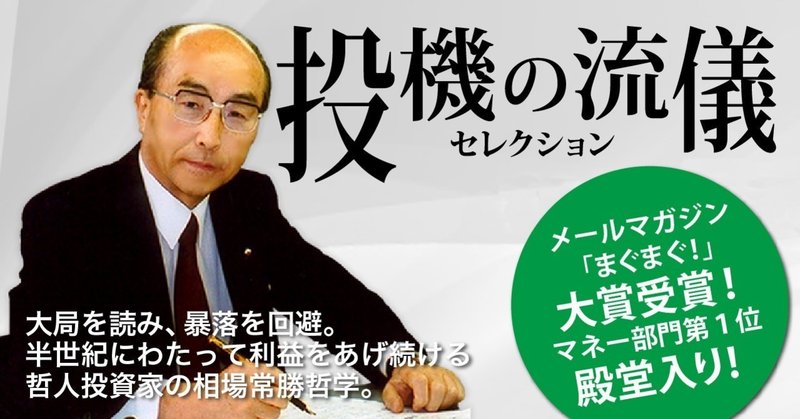メールマガジン配信大手の「まぐまぐ」で好評を博し、堀江貴文氏(ホリエモン)と並んで2年連続「メルマガ大賞」を受賞、殿堂入りした週報「投機の流儀」。
人生の前場をセルサイドとして、…
- 運営しているクリエイター
#コラム

【投機の流儀 セレクション】株は「将来の期待を買い」「将来の不安を売る」ものだが、「実証を伴う現状の実勢」に惑わされる
日銀は10月31日の金融政策決定会合で、金融緩和の現状維持を決めた。 2%の物価目標達成が遅れ、金融緩和は長期化する方向である。 日銀は7月の決定会合で副作用に配慮して長期金利の上振れを容認するような政策を調整した。 緩和の効果と副作用を両方とも見ながら政策の方向性を慎重に判断していく。 故に日銀の決定会合は市場に対しては無風状態となる。 日銀は現状を追認して「総じてみれば着実な成長を続けている」と言うが、これは現状の追認である。 株は「現状」を買うのではなく「将来の期待」を