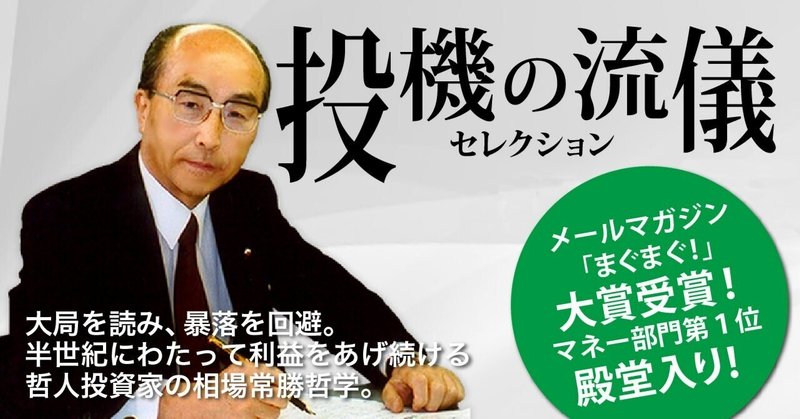メールマガジン配信大手の「まぐまぐ」で好評を博し、堀江貴文氏(ホリエモン)と並んで2年連続「メルマガ大賞」を受賞、殿堂入りした週報「投機の流儀」。
人生の前場をセルサイドとして、…
- 運営しているクリエイター
記事一覧

【投機の流儀 セレクション】世間をナメた自民党の浅知恵──石破総理は自民党の中で一人浮いていた「異端児」であり「党内野党」であった。こういうのを代表にして、自民党観の一新を図った自民党の浅知恵
石破総理は、総理になる前から自民党の中で一人浮いていた。異端児であり、党内野党ではあったが、具体的に石破氏が総裁選前から自民党の中で浮いていた原因は二つある。 1.2004年の鳩山の大醜態と似たようなことをやり出した。鳩山氏は米国と打ち合わせもなく、唐突に普天間基地移設は「最低でも県外」と発言して、混乱を招いて、オバマにもバカにされた。子供が大人に売った喧嘩のようなものだが、オバマは相手にしないで笑っていた。石破総理は日米地位協定の見直しに着手すると言い出した。こういうこと

【投機の流儀 セレクション】大相場の終焉の大底にせよ、中間反落にせよ、底値の付け方には一定のパターンがある。AIがあろうが、なかろうが、人間の思考法に古今大きな変化はないからだろう
「動画」で底値の付け方についてのご質問があった。実際の実例をパネルで示して説明したが、ここでまとめておきたい。 人間の思考能力は2000年前からほとんど変わっていない。2000年前に1人のユダヤ人のことが「聖書」として世界のロングセラーとなり、2500年前の一中国人の日常の言動が「論語」としてロングセラーになっている。2500年前からヒトの思考法に大差はない。 ところで、大相場の終焉の大底、または中間反落の底値、いずれにも四つの型がある。この四つ以外にはない。頑固にこのよ