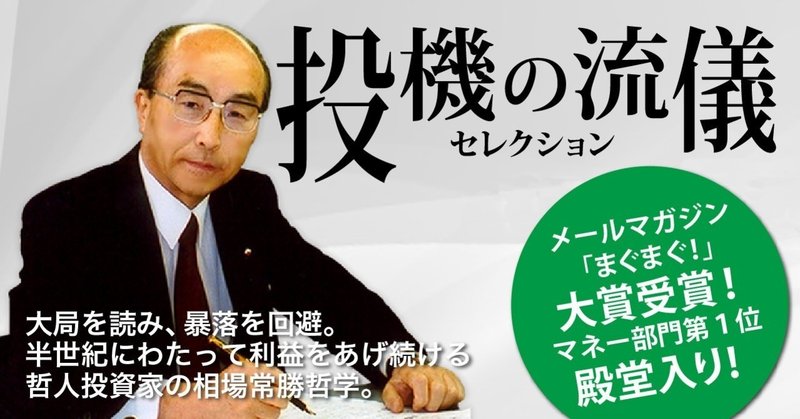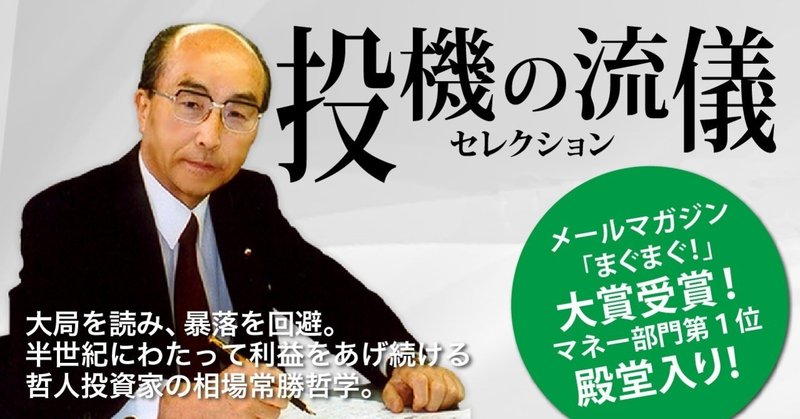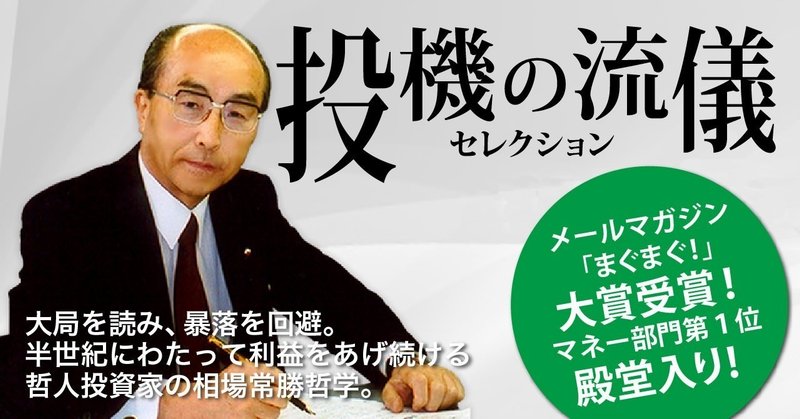メールマガジン配信大手の「まぐまぐ」で好評を博し、堀江貴文氏(ホリエモン)と並んで2年連続「メルマガ大賞」を受賞、殿堂入りした週報「投機の流儀」。
人生の前場をセルサイドとして、…
- 運営しているクリエイター
#暴落

【投機の流儀 セレクション】大手銀行・大手証券の強引営業が引き起こした仕組み債のロックインの危険性――それが現実化すれば再び「阿鼻叫喚相場」
大手銀行・大手証券の強引営業が引き起こした仕組み債のロックインの危険性――それが現実化すれば再び「阿鼻叫喚相場」 既報で述べたが、大手銀行と大手証券が仕組み債というものを販売していた。十数年前、リーマンショック以前にメリルリンチ証券から勧められて筆者も考えたことがあったが、仕組みが複雑でリスクが大きいので筆者は乗らなかった。それ以降仕組み債についてはその将来性に関心は持って眺めてきた。日経平均が2万2000円~2万3000円の頃に1万6000円を割ったならば「ロックインする」