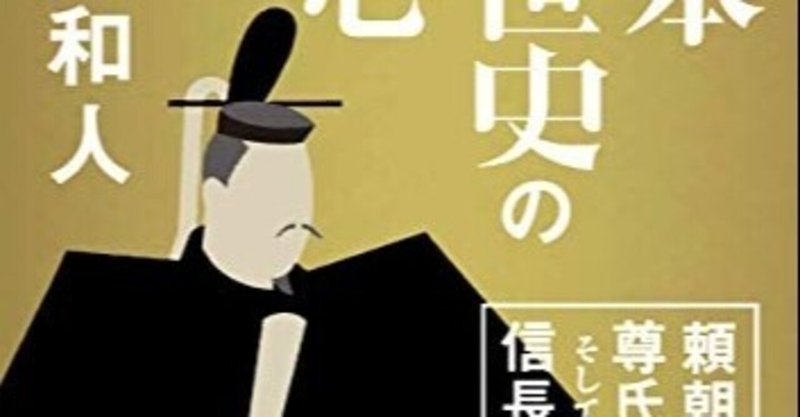
【書評】本郷和人「日本中世史の核心」
中世史の専門家である本郷和人氏の著作。日本の中世史(鎌倉・室町・戦国時代)を概観するための8人のキーパーソンが並べられている。
その内訳は以下の通り。
源頼朝、法然、九条道家、北条重時、足利尊氏、三宝院満済、細川政元、織田信長。
源頼朝と足利尊氏、織田信長はわかる。法然は中学、細川政元は高校の日本史教科書に載っている。が、九条道家・北条重時・三宝院満済というメンバーは知名度も低いし、なかなか面白いラインナップだ。
著者はあとがきで語っている。
人間一人では歴史は変えられない。たしかにそうなのです。しかし、時代の要請が、一人の人格に集約されて現れる、ということはある。
その言葉通り、本書では「人物」に焦点を当てすぎず、歴史の大きな変化がわかるように叙述している。だから、人物そのものの解説に割かれた字数は意外と少ない。
一般向けに分かりやすく書かれているが、一般人を馬鹿にしてレベルを下げているわけではない。例えば、「北条重時」の章では鎌倉時代の訴訟のあり方を2種類に分けている。
A:理非弁別型…統治者がルールを定めて、それに基づいて判決を下す。
B:理非追認型…社会通念としての善悪が最初にあり、統治者がそれを後追いして(追認して)判決を下す。
北条泰時が御成敗式目を定めた鎌倉幕府はA型で、京都の朝廷はB型というふうに違いがあったのだそうだ。
「織田信長」の章で古い学説を述べていたり(松永久秀が足利義輝を殺した、など)気になる点もある。しかし、鎌倉時代から室町時代にかけて、政治が何を争点に変わっていったかをつかむには良い入門書だと感じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
