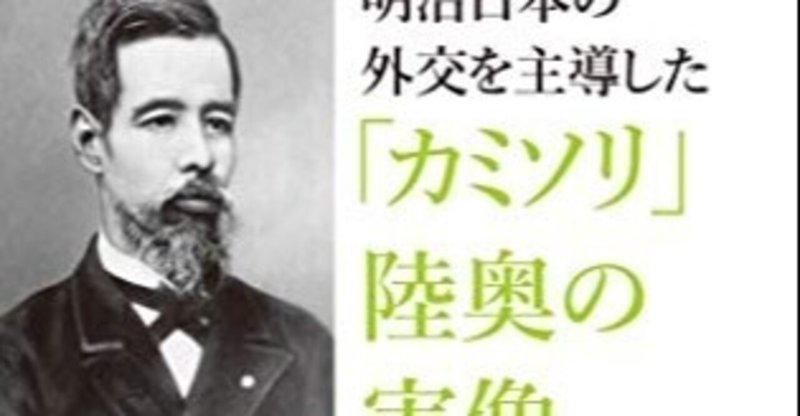
【書評】佐々木雄一『陸奥宗光』(中公新書)
陸奥宗光といえば、近代日本の悲願であった条約改正(領事裁判権の撤廃)を成し遂げた人物です。「カミソリ」のあだ名をつけられた切れ者で、優れた外交官として知られています。
しかし、陸奥の実像はその説明にとどまるものではありません。本書は陸奥の生涯を簡潔にたどりながら、彼の実像を明らかにしています。
外交にとどまらない業績
陸奥宗光は、条約改正・日清戦争・下関条約・三国干渉という明治日本の激動期に活躍しました。本書でも半分近いページ数が割かれています。
しかし、年表を見ればわかるように、陸奥が外務大臣に就任したのは1892年、49歳の時。彼は1896年に病気で外務大臣を辞任し、翌年亡くなります。つまり、一般に知られる彼の事績は、晩年の3~4年のできごとであり、陸奥の活動のごく一部分なのです。本書は、以下に述べる内政面での事績も詳述されています。
藩閥か、民権か
陸奥宗光は、紀州藩(和歌山県)の出身で、薩長中心の藩閥政府の中では傍流でした。優れた才知を生かしてのし上がった陸奥は、伊藤博文など元勲と協力しつつも、「出身ではなく実力で登用される政府」を目指していました。
そのため、同様に薩長に批判的な自由民権運動の側にも好意的に関わっていきます。しかし、陸奥は「反藩閥、民権派」と単純化できる政治家ではありませんでした。
頭の良すぎる陸奥は、清濁併せ吞む必要のある政党のリーダーには、必ずしも向いていませんでした。そのため、藩閥政府と民権派政党の双方のパイプを生かし、調停役のように暗躍する役目を負ったのです。
原敬、西園寺公望、小村寿太郎、星亨、内田康哉など、多くの政治家・外交官が陸奥の影響を受けました。これもまた、陸奥の遺産といえます。
外交官・陸奥宗光が本当に戦った相手
陸奥宗光は外相としてイギリスとの困難な交渉にあたり、見事領事裁判権の撤廃を引き出した――教科書的な理解ではこうなるでしょう。
しかし、実態はこれと異なっています。陸奥が外相となる以前にも、井上馨・大隈重信・青木周蔵らが欧米と交渉を進めていました。彼らが失敗したのは、外国との交渉で合意できなかったからではありません。外国と合意ができそうだったのに、より有利な条件を求める国内の反対にあったからです。
陸奥外相の時代に行われた交渉の内容も、前任者たちの延長線上にありました。彼が巧みだったのは、国内の対外強硬派を納得させた手腕でした。外交で厄介なのは相手国よりもむしろ国内の強硬派、というのは現代にも当てはまる現象ではないでしょうか。
教科書的な知識にとどまらず、より深く近代史を知りたい人におすすめの一冊です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
