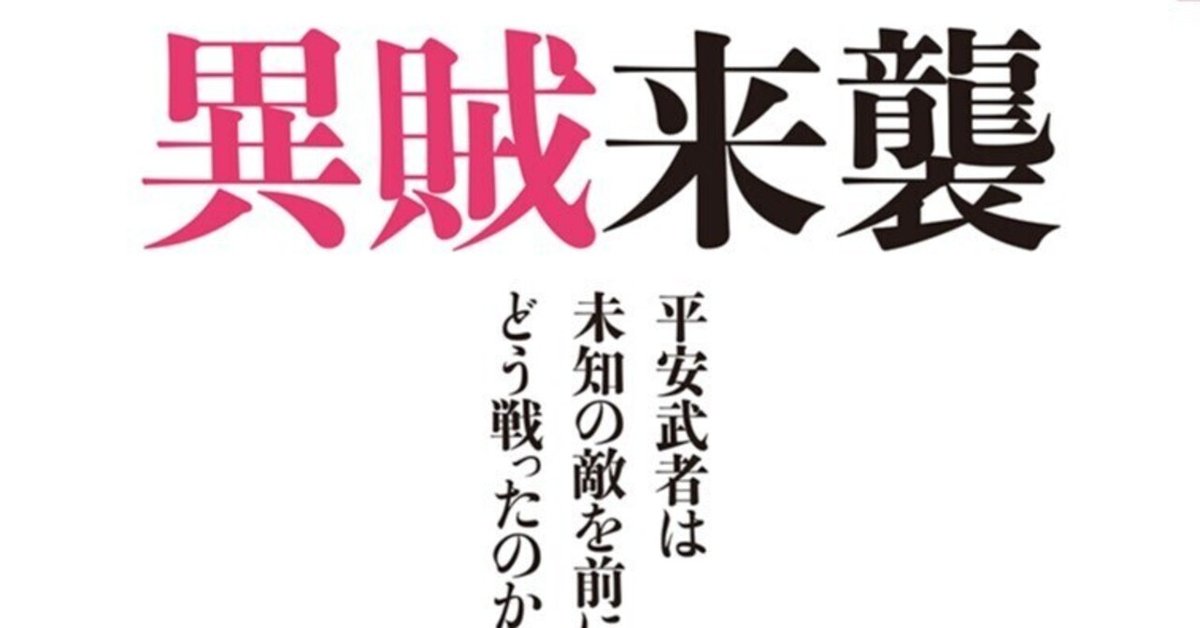
【書評】関幸彦『刀伊の入寇』(中公新書)
近代以前の日本の対外危機といえば、鎌倉時代に起きたモンゴルの襲来(元寇、蒙古襲来)が挙げられるでしょう。
しかし、平安時代後期の1019年に起きた異民族襲来事件である「刀伊の入寇」の一般的知名度は高くありません。
「刀伊の入寇」のあらまし
「刀伊」とは現在の中国東北部~ロシア沿海州に住んでいた狩猟民族・女真人を指すと考えられています。
刀伊の賊が50隻余りの船団で対馬・壱岐・北九州を襲撃し、約400人が殺害され、約1300人が拉致されました。しかし、太宰府に赴任していた貴族・藤原隆家の指導や地元の武士たちの奮戦によって撃退されたという事件です。
襲撃を受けた住民にとっては悲劇に違いありません。しかし、刀伊の賊は半月ほどで日本を退去しており、歴史的影響という点ではそこまでのインパクトを与えません。そのため山川の日本史教科書でも欄外の注で触れられる程度の扱いで、一般の知名度は低いのです。
「刀伊の入寇」を読む2つの視点
言うまでもなく、本書はこの事件についての概説書です。ただできごとを追うだけでなく、2つの大きな流れの中に、「刀伊の入寇」というあまり大きくない事件を位置付けているのが特徴です。
①世界史の中で位置づける
視点の一つは、「東アジア全体の動乱の中で事件が起きた」としていることです。10世紀以降、東アジアでは唐が滅亡して政治的な不安定が生じました。朝鮮半島では新羅が高麗に交代するなど、各地に変動が波及したのです。
その関連で女真人の動きも活発になりました。女真人の中には、沿岸部を南下して海賊行為を働く者もあらわれ、その一部が日本に襲来したと考えられます。
②日本史の中で位置づける
もう一つの視点は、「日本の軍事システムがどう変わったか」という国内的な観点です。古代の律令制では徴兵制が敷かれますが、やがて崩壊に向かいます。平安時代の末期には武士が台頭するわけですが、この間の過程は、まだはっきりとは解明されていません。
朝廷は、「刀伊の入寇」という対外的危機にどう対処したのか。それを探ると、古代から中世の過渡期にあった武士たちの実像が見えてくる、という趣旨です。
戦いに参加した武士の中には、かつて功績を挙げた者の子孫(「ヤムゴトナキ武者」)や、「住人」として記録される土着の戦士などが含まれていました。彼らが成長していき、中世の「武士」になったと推察されます。
まとめ
本書は200ページ程度の薄めの新書ですが、非常に読み応えのある良書でした。世界史・日本史両方の視点から、一つの事件を立体的に見ることができるからです。一つの事件を様々な視点から見ることは、歴史について学ぶ際、忘れてはいけない態度だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
