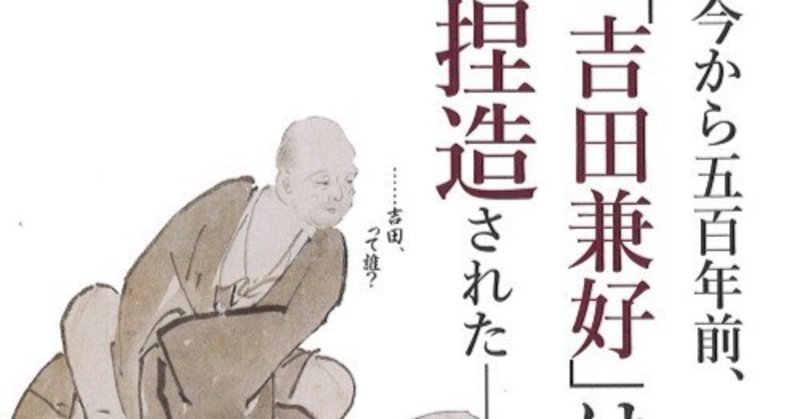
【書評】小川剛生『兼好法師』(中公新書)
”今から五百年前、「兼好法師」は捏造された――”
帯に書かれていたセンセーショナルな文言に惹かれて購入しました。
兼好法師(吉田兼好)といえば、鎌倉時代末期の随筆『徒然草』の作者として有名です。しかし、よく知られた彼の生涯については同時代史料の裏付けが乏しく、実態は違っていた、というのが本書の主張です。
吉田兼好? 卜部兼好? 兼好法師?
そもそも、なぜ彼は「吉田兼好」と呼ばれるのか。兼好は、古代から朝廷の卜占を担当した卜部氏(うらべし)の出身です。各地の卜部氏のうち、吉田神社の神官の家系が室町時代に「吉田」を名乗るようになり、やがて吉田神道を大成します。
通説では、兼好は吉田流卜部氏の系譜のため「吉田兼好」と通称されています。しかし、吉田姓を名乗り始めたのは兼好より後の時代なので、厳密には正しくありません。「吉田兼好」の呼び名は、教科書など学術的な場では使用が避けられるようになり、「卜部兼好(うらべのかねよし)」や「兼好法師(けんこうほうし」の表記が主流になりました。
経歴や系図は捏造だった?
通説では、兼好は公家の堀川家の加勢を担当する家司(けいし)で、若くして六位蔵人の官位を得たとされます。
しかし、卜部氏の他の人物の位階は低く、兼好の地位だけが突出しています。先例を重視する貴族社会では不自然です。
その他諸々の根拠をもとに、筆者は「兼好の系図や経歴は捏造である」と結論付けます。若き日の兼好は侍で、鎌倉幕府執権・北条氏の庶流である金沢氏に仕えていたようです。
なぜ捏造が起きた?
兼好の事績が捻じ曲げられたのは、室町時代の後期、吉田兼倶が登場してからです。兼倶は、「仏は仮の姿で、日本古来の神が本来の姿である」(反本地垂迹説)などの教義を持つ吉田神道を創始しました。
しかし、吉田流卜部氏は業績が乏しく、華々しい歴史を持っていません。兼倶は、過去の著名人と吉田流卜部氏との縁を捏造して自家の権威を高めようとしました。
『徒然草』の作者として有名だった兼好法師も、そのターゲットになります。兼好が「卜部」を名乗ったのは事実ですが、兼好が吉田流卜部氏につながっているのは、兼倶による系図捏造です。後世の学者らもこれを信じたため、「吉田兼好」が誕生してしまったのです。
歴史では、これまで信じられていた通説が研究によって覆ることがあります。常識が書き換えられる知的刺激に満ちた一冊です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
