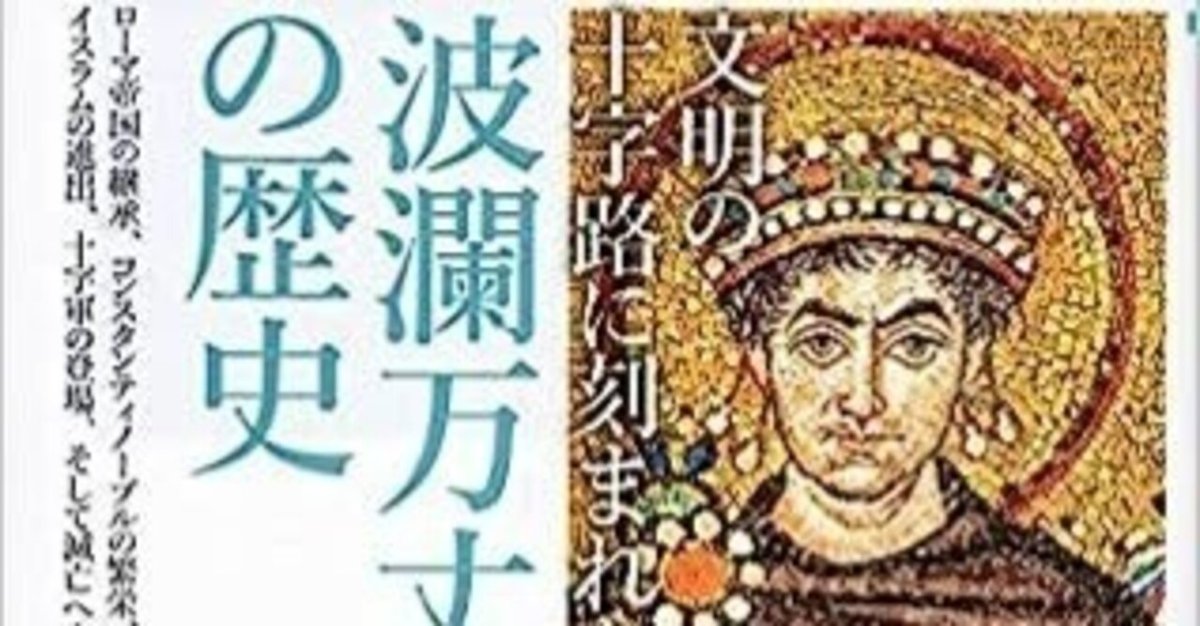
【書評】中谷功治『ビザンツ帝国』(中公新書)
ビザンツ帝国(東ローマ帝国)について、一般的な日本人が知っていることはほとんどないでしょう。コンスタンティノープル(現イスタンブール)を首都として、現在のギリシャやトルコのあたりにあった国です。
本書の冒頭では、ビザンツ帝国を次のように定義しています。「コンスタンティノープルを首都とし、キリスト教を国教とする、ローマ帝国の継承国家」。
ビザンツ帝国の扱いは不当に軽い?
日本の歴史教育では西欧が中心であるため、東欧にあたるビザンツ帝国の扱いは軽いのが現状です。
しかし、中世におけるビザンツ帝国の影響力は非常に大きいものでした。ローマ帝国以来の伝統を持ち、文化や建築の面では西欧を圧倒していました。ビザンツ帝国から見ると、フランスやイギリスといった国家は歴史が浅く、野蛮人に見えていたのです(P.217)。
下記のできごとでも、ビザンツ帝国が関わっているにもかかわらず、高校の歴史教科書では触れられていません。
ビザンツ帝国の滅亡はいつ?
一般的に、ビザンツ帝国の滅亡は1453年、オスマン帝国の攻撃で首都コンスタンティノープルが陥落した時とされています。しかし、本書では異なる解釈がなされています。
「帝国」とは、異なる民族を強大な力で束ねた国家と定義できます。1204年、ビザンツ帝国は第4回十字軍の攻撃で首都を失い、滅亡しました。その後、パライオロゴス朝がビザンツ国家を復興させるのですが、支配域はコンスタンティノープル周辺のわずかな地域にとどまり、「帝国」と呼べる体裁ではありませんでした。
そのため、同書では「ビザンツ帝国」の滅亡を1204年としていますが、パライオロゴス朝も「ビザンツ世界の残照」という章立てで扱われています。
千年間続いた帝国
ビザンツ国家が成立してから滅亡するまで、約1000年にも及ぶ歴史があります。その間、ユスティニアヌス1世やバシレイオス1世、アレクシオス1世などの多くの英邁な君主が登場しました。また、滅亡の危機を何度も乗り越えたタフな国家でもありました。
最近では、ビザンツ帝国を舞台とした漫画「アンナ・コムネナ」など、徐々に魅力が広まりつつあるようです。新書一冊では語り切れない豊饒な歴史を、もっと勉強してみたいと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
