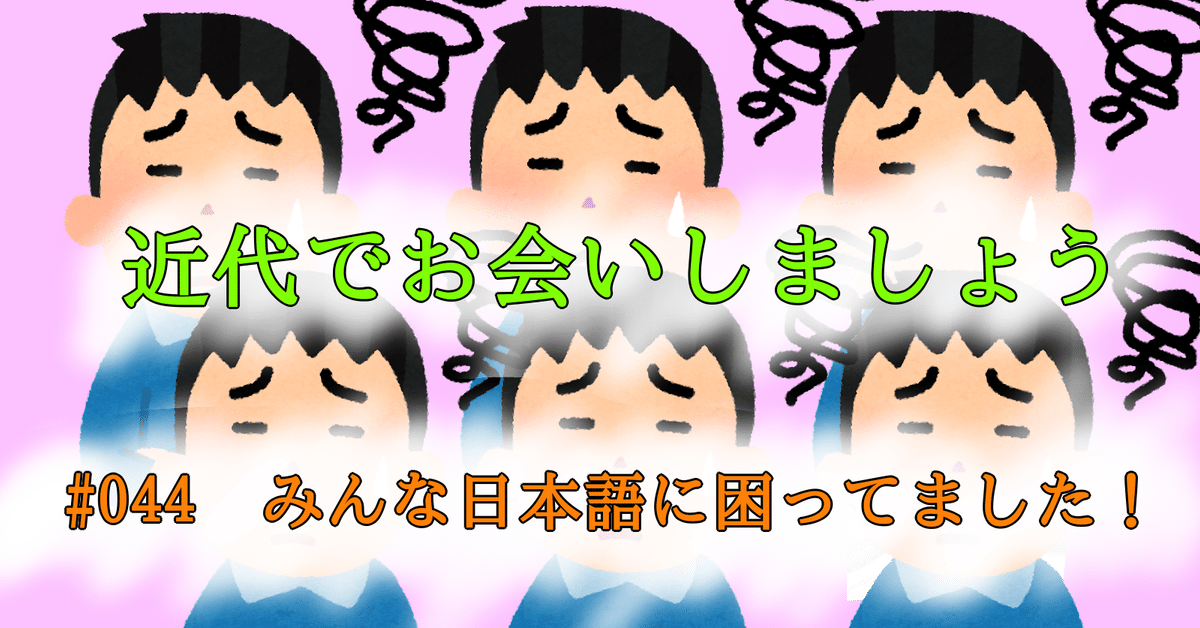
#044 みんな日本語に困ってました!
福沢諭吉(1835-1901)は、『学問のすゝめ』(1872)で、こんなことを言っています。
学問とは、ただむつかしき字を知り、解し難き古文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るなど、世上に実[ジツ]のなき文学を言うにあらず。
ここで言う「むつかしき字」とは漢字のことで、当時は、漢文を学んで、漢文を書いて、補助的な役回りでカタカナを使うことがアカデミックな文章作法となっていました。
坪内逍遥(1859-1935)の『小説神髄』(1885)には、こんな文章があります。
いにしへの人は質朴にて、その情合[ジョウアイ]も単純なるから、僅かに三十一文字もてその胸懐[キョウカイ]を吐きたりしかど、けふこの頃の人情をばわづかに数十の言語をもて述べ尽すべうもあらざるなり。よしや感情のみは数十字もていひ尽すことを得たればとて、他の情態を写し得ざれば、いはゆる完全の詩歌にあらねば、彼の泰西の詩歌と共に美術壇上に立ち難かるべし。是れ豈にあたらしきことならずや。さればこそ過[スギ]にしころ外山、矢田部、井上の大人[ウシ]たちが、ここに遺憾を抱かれつつ、『新体詩抄』一部をあらはし、世に公けにせられたりき。
1882(明治15)年、外山正一(1848-1900)、矢田部良吉(1851-1899)、井上哲次郎(1856-1944)が、和歌の5・7・5・7・7の31文字に囚われず、漢字とひらがなで七五調の詩集『新体詩抄』を刊行したのは、『学問のすゝめ』から10年後のことです。それまでは、「詩を作る」といったら、漢詩を作ることを指していました。
また、#040で紹介した本居宣長(1730-1801)の『源氏物語玉の小櫛』(1799)のように、儒教的観点を取っ払って古典を読み直す「国学」という学問がありましたが、このような「解し難き古文を読」むことも、福沢諭吉は、これからの学問ではない!と言っています。
『学問のすゝめ』の先進的なところは、これまでの学問を否定することの体現として、「漢字+ひらがな」で書かれていることなんです!
福地桜痴が勤めていた東京日日新聞の1874(明治7)年11月12日付の記事には、アカデミックな文章に対して、こんな投書が寄せられています。
昨日或る商人の処に行きしに、その主人小さき紙に活字にて摺りたる物を手に持て考へ居たり。何ぞと尋ぬれば御触なりと云ふ。何事の御布告ぞと尋ぬれば、イヤ夫れがどうも解りません。此節の御役人様はみな学者で困る。私どもは皆学校の無い時に生れた人間だから読めません。子供は有ても忙しくて、中々こんな六かしい字ばかり稽古されては置かれませず、誠に面倒な世の中なりと嘆息せり、此数語大に味はひあり。当時の諸君宜しく察し玉へ。
これが当時の庶民の素直な思いであり、福沢諭吉が『学問のすゝめ』を「漢字+ひらがな」で書き、ベストセラーにもなった根本的な原因ですよね!だって、言いたいことが理解される前に、そもそも「読めない」となったら、どうしようもないわけですからね!w
福地桜痴も、当時の日本語の状況については、ほとほと困っていたようで、1875(明治8)年8月29日付の東京日日新聞紙上の社説にて、日本語に関する状況と、今後の日本語について論じているのですが…
それはまた明日、近代でお会いしましょう!
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
