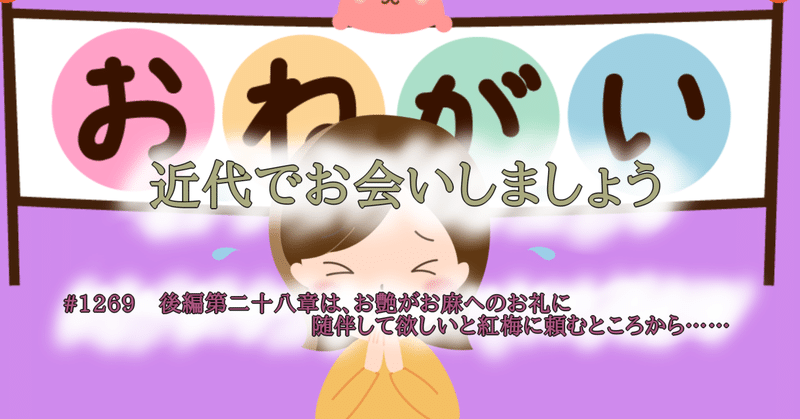
#1269 後編第二十八章は、お艶がお麻へのお礼に随伴して欲しいと紅梅に頼むところから……
それでは今日も尾崎紅葉の『三人妻』を読んでいきたいと思います。
今日から「後編その二十八」に入ります!それでは早速読んでいきましょう!
(ニ十八)我[ワガ]筆[フデ]の書きける文[フミ]ながら
設[タト]ひ此[コノ]身を苛[サイナ]まむとのお意[ココロ]なりとも、表面[オモテムキ]は御深切[ゴシンセツ]に、興津からお人を下されし事なれば、一寸[チョット]なりともお礼に上がらでは済むまじけれど、色々様子をも承まはれば、行[ユ]きたうも無けれど、思ひきりて、近い内に一日[イチニチ]御本家へ伺[ウカガ]はねばならぬ、此様[コノヨウ]な恐ろしい事はござりませぬ。
御迷惑でも其日[ソノヒ]には、貴嬢[アナタ]も御一処[ゴイッショ]にお出[イ]でなされて下さりまし。せめて貴嬢[アナタ]お一人でも側[ソバ]にゐて下さらば、それぞ私[ワタクシ]には百人の味方、どれほど気強[キツヨ]いことか知れませぬ。頼みますると思入[オモイイ]りたる気色[ケシキ]に、十五六の少女[ムスメ]でも、これほどに意気地無きは鮮[スクナ]きに、ニ十四五の暁[アカツキ]まで、女一人で世帯張[ハッ]てゐたといふ女[ヒト]にも似ず、然[サ]りとは世間慣れぬ根性。米屋の言訳[イイワケ]はどの口でした事やら、と紅梅は心に可笑[オカシ]く、御迷惑の頼むのと、これしきの事に他人がましく何をおつしやるやら。御一処[ゴイッショ]に上がるはいと易[ヤス]ければ、何日[イツ]なりとも御都合の好[ヨ]い日をおつしやりまし。然[サ]れども、奥方が例の御了簡ならば、何として私[ワタクシ]をお側におかるゝものぞ。屹度[キット]何とか謂[イ]はれて、先へ私[ワタクシ]を還[カエ]さるゝやうにしたまふべし。
落語の演目に「言い訳座頭」というものがあります。
江戸時代、日頃の商売はツケが基本、清算は大晦日に行ないます。ところが、長屋の甚兵衛はツケがたまりすぎてどうしようもない。そこで、なけなしの金を使って、口達者な座頭の富の市に「言い訳」を代理してもらうように頼みます。富の市は、米屋の大和屋では「清算を延ばして欲しい。ウンと言うまで帰らねえ」と言って店先に座り込んで許してもらい、薪屋の和泉屋では「延ばしてくれないから、私をここで殺せ。殺しやがれ」と往来に向かって喚き散らして許してもらい、魚屋の魚金では「甚兵衛が貧乏で飢え死にかかっている。返すまでは死んでも死にきれない」と泣き落としで許してもらいます。ここで除夜の鐘が鳴ったので富の市が帰ろうとすると、甚兵衛は「まだ三軒ばかりあるんだ」。すると富の市は「そうはいかねえ。これから自分の家に帰って、自分の言い訳をしなくちゃならねえ」という話です。
跡にて貴嬢[アナタ]の御難儀とは知りながら、還さるゝものを剛情に還らずにも居難[イニク]ければ、夫[ソレ]から後[アト]はお一人にて、何とあそばす御心[オココロ]ぞや。よしや責殺[セメコロ]されむほど苛[サイナ]まれても、逭[ノガ]るゝ路[ミチ]はあるまじく、其[ソノ]憂目[ウキメ]を見るが否[イヤ]さに、遠き処からわざ/\人まで寄来[ヨコ]されて、呼ばれしをも断りいうて逃げられしに、呼ばれもせぬに此方[コナタ]から出懸けて行[ユ]かれうとは、什麼[イカ]なる御了簡か、私[ワタクシ]にはちと解りかねました。義理の済まぬものとは、今おつしやることではござりませぬ。
というところで、この続きは……
また明日、近代でお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
