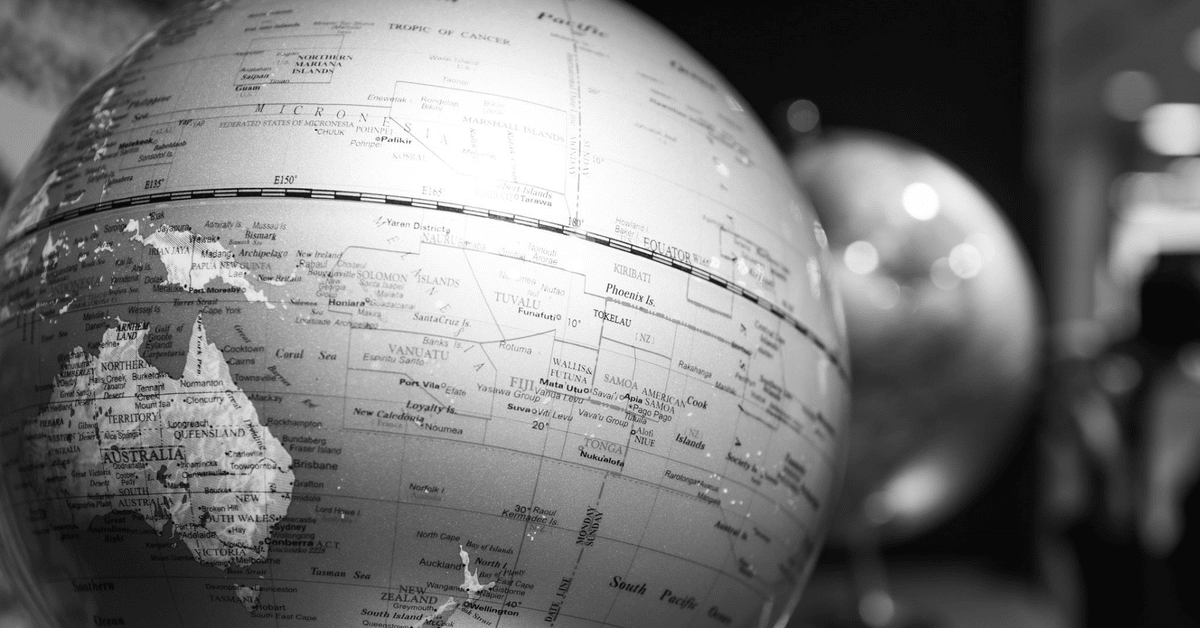
東京大学2018年国語第1問 『歴史を哲学する―七日間の集中講義』野家啓一
筆者の野家啓一は、つねに論理にもとづく地道な文章を書く哲学者である。歴史を題材とする本問題文でも、丁寧すぎるくらい、論拠がくりかえし述べられているため、理解しやすく、解答もしやすいといえるだろう。
(一)「その痕跡が素粒子の『実在』を示す証拠であることを保証しているのは、量子力学を基盤とする現代の物理学理論にほかなりません」(傍線部ア)とはどういうことか、説明せよ。
傍線部アは、素粒子の実在と物理学理論の関係を述べたものである。まず、素粒子については、「知覚できないにも拘らず、われわれがその『実在』を確信して疑わないもの」としている一方で、「われわれが見ることができるのは、霧箱や泡箱によって捉えられた素粒子の飛跡にすぎません」としている。
そして、傍線部に続いて、「素粒子の『実在』の意味は直接的な観察によってではなく、間接的証拠を支えている物理学理論によって与えられている」としている。
以上のことから、素粒子そのものは知覚できないが実在していること、素粒子の飛跡は実験によって直接的に観察できること、素粒子の実在を証拠づける物理学理論は間接的証拠であること、の3点が傍線部の骨子であることがわかる。
よって、「実験によって直接観察できる痕跡が、知覚できない素粒子の実在の証拠であることは、間接的証拠としての物理学理論により導かれるということ。」(66字)という解答例ができる。
(二)「『理論的虚構』という意味はまったく含まれていない」(傍線部イ)とはどういうことか、説明せよ。
傍線部に続いて、「それは知覚的に観察できないというだけで、れっきとした「存在」であり、少なくとも現在のところ素粒子のような理論的存在の実在性を疑う人はおりません」とある一方で、「しかし、その『実在』を確かめるためには、サイクロトロンを始めとする巨大な実験装置と一連の理論的手続きが要求されます」とある。
上記の「サイクロトロンを始めとする巨大な実験装置と一連の理論的手続き」を抽象化したものが、第2段落中の「物理学理論の支えと実験的証拠の裏づけ」である。
傍線部の主語は「理論的存在」なので、「理論的存在は、知覚的に観察できないものの、物理学理論の支えと実験的証拠の裏づけがあるため、その実在性は疑いようがないということ。」(64字)という解答例ができる。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
