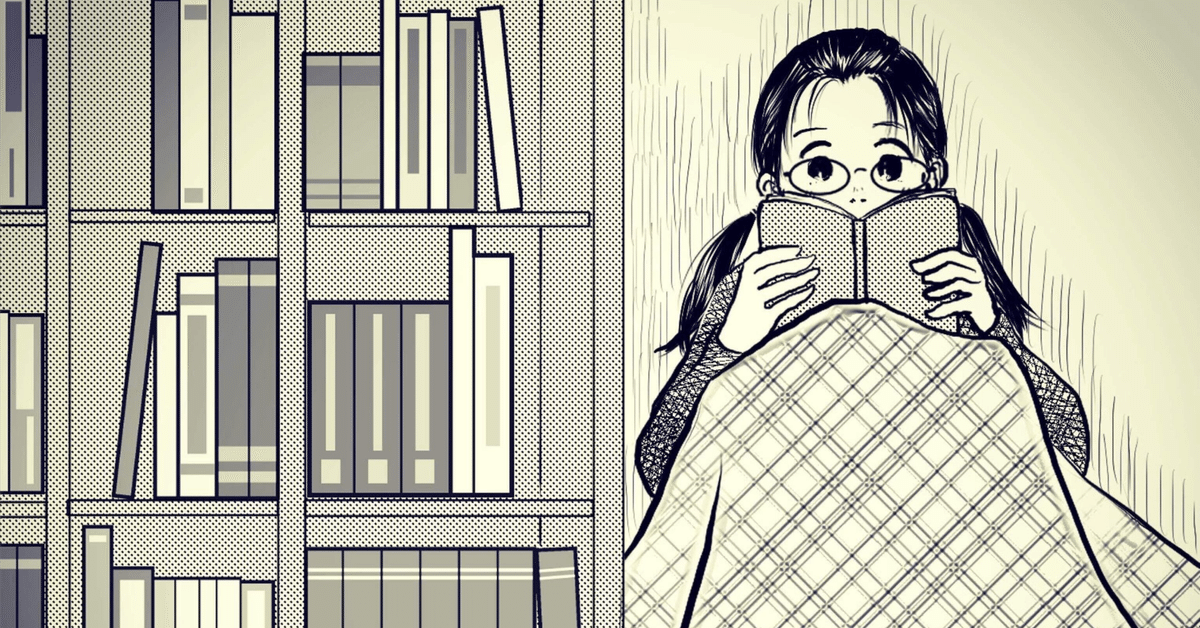
連載【短編小説】「わたしの『片腕』」第一話
「片腕を一晩お貸ししてもいいわ。」と娘は言った。
という書き出しではじまる、川端康成さんの『片腕』というお話を、はじめて読んだ時のことは今でもよく覚えています。
まだあげ初めし前髪の、中学二年生の秋の暮れ。なにひとつ波風の立たない退屈な日常に、どっどどどどうどと、一陣の風を巻き起こしてくれるような刺激を求めて、週に一度の割合で学校の図書室に通い詰めていた頃のことでした。
木造の旧校舎二階の廊下の突き当りに、図書室はひっそりと深い森の奥のようにたたずんでいました。丸眼鏡を掛け、一言も私語を発することのない、まるで図書館の器物の一部ででもあるかのような司書さんを除けば、まるで人気はなく、訪れる生徒はわたしのような物好きだけでした。当時、義務としては本を開いても、自ら進んで手に取る生徒は数えるほどだったように記憶しています。
わたしは、ハードカバーの単行本のような、内容を含めて胃もたれがしたり、持ち重りのしたりするお話は好まず、片手に収まるそれこそlightな、綿あめのような軽やかなお話ばかりを間食のようにつまんでばかりいました。自分の体重に百グラム単位で一喜一憂するようになったのも、その頃からだったかもしれません。それはともかく、星の数ほどもある作品の中でどのお話を選ぶかは、ずばり直感でした。スマートフォンもパソコンもなく、作者にもタイトルにも詳しくはなかった当時は、いかに一目で惹かれるか。それが全てでした。異性または同性も、そういうものでしょう。人は見た目が九割はさすがに極端だと思いますが、実感としては分かるような気がします。
図書室の大きな書架に寒さを堪えるように、きゅっと身を縮こませて収まっていた数多の文庫本は、みな子どものようで可愛らしいものでした。見れば「窮屈」と、イルカのようにうめき声を上げているのがすぐにわかりました。本当はもっと余裕をもって、木の香りのする本棚の中でくつろぎながら眠りたいのに、これではまだ深夜バスの座席の方がましなくらいです。
そう言えば、文庫本と言うものは出版社や作者ごとに、まるで絵の具のように背表紙の色が分かれていますね。――白、黒、赤、緑、水色、青、橙などと。新潮文庫の太宰治がなぜ黒なのか、もし新潮社の方にお会いしたらぜひ一度聞いてみたいです。
わたしが見つけたそれは、まるで私のことは見つけないでほしいと訴えているかのように、とても濃い藍色をしていて、逆にわたしの目には目立って映りました。タイトルは白字で『眠れる美女』。素敵、だと思いました。わたしのすっぴんは美女とは程遠く、毎日鏡を見るのも嫌に思うような年頃でしたが、「眠れる」という言葉に何よりも惹かれました。何故なら、当時のわたしは常に眠っていたかったからです。後にある病気から来る症状だと判明するのですが、そんなことも知らず、時間さえあれば場所を問わず眠っていたわたしは、まさに「眠れるこっくりさん」でした。ちなみにこの「こっくりさん」は、あの占いのコックリさんとは関係ありません。舟を漕ぐという意味での、こっくりです。あしからず。
『眠れる美女』の文庫本は痩身で、うらやましい限りでしたが、わたしの人差し指の釣り針に抵抗なく引っかかり、難なく釣り上げることができました。手のひらに収め、この中に眠れる美女が眠っているかと思うと、まだ見ぬ愛おしい親友に出会ったような気持ちになりました。
本来、手に取った本はその場で開き、自己紹介代わりの目次やあらすじに目を通すのが通例でしたが、みだりに美女を起こしてしまってはいけないと思い、わたしはいっさいの物音を立てないように、慎重に司書さんのいるカウンターに本を運び、借りる手続きを行いました。帰りはまるで赤子を抱いているかのように、揺り起こさないよう心を配りました。
家に帰ってすぐ鞄から本を取り出し、学習机の上に寝かせました。木の机は冷たくはないだろうかと思いましたが、感情移入もそこまでくると、先ほどまでの熱の入れ方が嘘でもあるかのように、不思議と冷めていくものです。夜に再び自分の部屋に戻ってくるまで、「待っていてね」と言葉だけを掛け、子どものままごとのように、布団代わりに何かを掛けるような真似はしませんでした。
しかし、夕食の時もお風呂の時も、眠れる美女のことは常に頭の片隅にありました。――いったい、どのような顔をしているのだろう、と。日本の小説家の作品ながら、思い浮かぶのは何故か西洋の女性ばかり。わたしたちの美女に対するイメージは知らず知らず、海外から輸入されたものなのかもしれません。
さあ。いよいよ、ご対面です。わたしは文庫本を手に、布団の上に横たわりました(行儀が悪いなどとは言わないでください。これがわたしの読書のスタイルなのです)。まだ美女の顔は見えません。当然です。本を開いてもいないのですから。まずは改めて、その表紙を眺めます。闇夜に沈む山杉でしょうか。装画は日本画家の大家、平山郁夫さんが手掛けたようです。もしかしてこの山杉の奥に、眠れる美女が住んでいるのでしょうか。それではまるで、かぐや姫です。いまは昔。竹取の翁といふもの有けり。物は試し、翁に成り代わり、竹林ではないですが、山杉の奥に分け入ってみましょう。分け入っても、分け入ってもの種田山頭火。
――ぺらり。
目 次
眠れる美女…………………………七
片 腕……………………一一七
散りぬるを……………………一五一
解説 三島由紀夫
な、何と、眠れる美女の傍らに、「片腕」が横たわっていました。これ以上の予想外はありません。わたしは浮気者ではないはずですが、「片腕」という文字を目にした途端、あれほどまでに恋焦がれた眠れる美女のことは、すっかり興味関心の系外に。薄情なものです。「片腕」の生々しい存在感を前に、ごくりと唾を呑みこみました。わたしは何かに急き立てられるように、鼻先をくすぐる程度のそよ風を起こしながらページを飛ばし、一一七の住所へと一目散に駆け付けました。
表札には、「片腕」の文字。
わたしは胸に手を当て深呼吸をした後、「ごめんください」と声を掛けました。そして、日本家屋の玄関の戸を、ガラガラガラと音を立てながら引き、あの冒頭の文章に出会ったのです。
つづく
※この物語は未完です。後に加筆修正する場合があります。
#小説 #短編 #連載 #川端康成 #片腕 #島崎藤村 #初恋 #図書室 #新潮社 #新潮文庫 #一人称 #平山郁夫 #北山杉 #竹取物語 #かぐや姫 #種田山頭火
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
