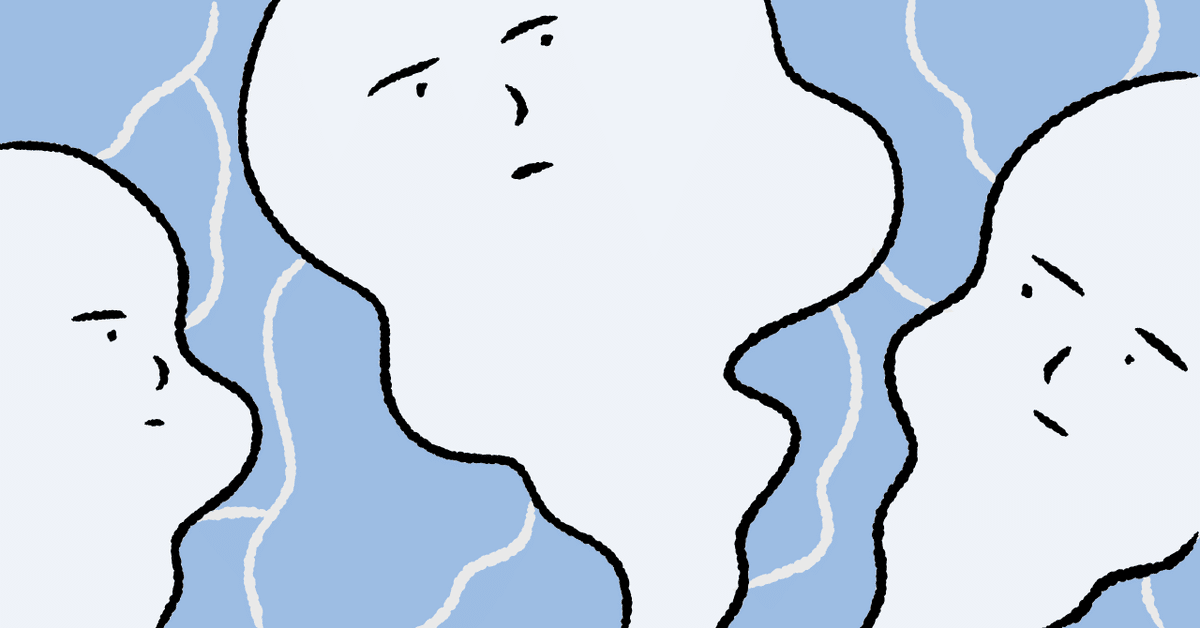
【読書】『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力』(谷川嘉浩・朱喜哲・杉谷和哉)
ネガティブ・ケイパビリティ。これは、詩人のジョン・キーツが「不確実なものや未解決のものを受容する能力」として用いた言葉だが、この概念自体が本人によって仔細に論じられている訳ではない。
この本は「ネガティブ・ケイパビリティ」を書名に冠しているが、その概念自体に触れることは数回程度に留まり、紙幅の大半を様々なテーマを多面的に検討する三人の哲学者の鼎談に割いている。書名の通り、それは性急に何かを片付ける訳ではなく、そもそも結論を出す訳でもない。「結局、何が言いたいの?」という態度でこの本を読むと面を食らう可能性が高いだろうが、そのモヤモヤこそがネガティブ・ケイパビリティへの入り口なのだろう。
個人的に昨今のポラリゼーションや単純化・効率化の加速に警戒感を感じていたためか、とても多くの含蓄や示唆を得られた本だった。網羅的ではないが、特に気になった点をいくつかピックアップしてみたい。
ファクトやエビデンスを手放しに称揚する危うさ
「それ、エビデンスないですよね」
ドヤるひろゆきと、"完全論破"。ここまで極端ではないにしても、どこか否定しきれない側面もあると感じてしまう。特にリベラルな人たちは「科学的なもの」を手放しに信じてしまいがちだ。かく言う私も、どちらかと言えば「そっち」寄りである。
本書の序盤では、ロジックが成立していないもの、事実に基づいていないもの、科学的でない主張を、"ひろゆきのように" 切り捨てるこの危うさを、「陰謀論」を取り上げながら検討している。
「なんでそんなことを信じてしまうのか、気がしれない」「なんて愚かなんだ」と、陰謀論の怪しさを手短に切り捨てることは簡単だろう。
でも、少し考えてみて欲しいが、「どうして陰謀論を信じるようになったのだろう」と、当事者に思いを馳せてみたことは、これまでにあっただろうか──。
マジョリティの安全地帯にいると、そうした想像力はなかなか働きにくい。包摂とまでは行かずとも、社会から疎外された感覚のままでは余裕など生まれない。その疎外感を適切に言葉で言い表すことが難しい場合もある。
物事の妥当性を論理で考えるだけでは、見落としてしまうものがある。それに、誰しもが弁証法的な西洋的価値観を持っている訳でもない。(その価値観に優劣関係はない。)
論理という自分の価値観だけで物事を早計に判断してはいけない。当事者の事情や渇望に焦点を当てること、そのためには「観察」が重要だという。
わかりあえなくてもいい。でも、少しだけでも目を向けて、じっと観てみることが大切だ。
アテンションエコノミーからのデタッチメント
インスタや Facebook の「いいね」を気にする。この note の「スキ」も同様だろう。
インターネットによる情報量の増大と能力主義の加速は、必然的に「アテンション」の必要性を高めてきた。インターネット空間、特に SNS では多様性・複雑性やコンテキストが低下するために、これに拍車をかけている。
本書内では触れられていないが、グローバル化もこの要因の一つなのだろうと、外資系企業で働いてきて肌で感じるところだ。日系企業の場合は、昇進や査定は能力云々よりも、その会社や上司の配慮でなされることがまだまだ多いのではないだろうか。加点方式よりも減点方式だと言った方がわかりやすいかもしれない。
一方で、グローバル企業の場合は昇進や査定は最終的にグローバル本社側で決定されるから、会社や上司の配慮を期待していても何も起こらない。各国で言語や背景が異なる中で、英語で明瞭に言語化してアピールする必要がある。
そのためには「キャラ」付けをし、自分のブランドを確立する必要がある。「私はこの成果にこんなに貢献した」のだと声高に叫ばなければ生存できないが、私はこれが苦手だ。
ある意味、アテンションの獲得は現代における生存本能の発露なのかもしれない。
簡潔なナラティブによってアテンションを集めなければ大きなうねりや成果は生み出しにくい。一方で、単純化によって複雑性はそこから失われてしまう。
複雑なものを、複雑なままにしておけないものだろうか。
観察と自己相対化によるナラティブからの解放
本書で最も印象に残ったのが「自分のナラティブに振り回されるのではなく、自分のものにした方がいい。」という言葉だった。
私たちは、原体験や問題意識が言語化された「自分に都合のいいナラティブ」に安易に飛びつきがちだ。そしてそれを「正しい」ものだとして信じ込んでしまう。それがエビデンスや社会倫理など、「正しい」とされている側のナラティブであれば尚更であり、リベラルこそ過信の危うさを孕んでいるとも言えるだろう。
安易にこれに飛びつく(振り回される)のではなく、身の回りをその目で観察して世界の解像度を上げることが大切だ。そして、対話を通じて互いが観察した世界のズレを認識し合い、どちらかの極へと偏るのではなく均衡を取り続けることが健全な状態とも言える。
著者の一人、朱喜哲氏の下記のインタビュー記事ではジョン・ロールズの「正義」の考え方が紹介されているが、常にこうした視点に意識的でありたいと、切に思う。
ロールズの画期的な主張として「コンセプション オブ グッド=善の構想」というものがあります。噛み砕いてお伝えすると「何が好きか嫌いか、どんなものをいいって思うかは、それぞれ違うよね。」ということです。社会はこういった多種多様な「善の構想」を持った人が寄せ集まって作られていますよね。
「正義」という言葉について、きちんと考えることで「バランスを取っている状態そのものを「正義」と呼ぶべきではないか?」と提案が導けますよね。そう考えたならば、個々人の抱く「善」レベルのものとは区別した「正義」という言葉づかいが重要になってきます。「正義の反対は悪ではなく別の正義」みたいなネットミームもありますが、それは単に「それぞれの善の構想は対立することもあるよね」という当たり前のことに「正義」という大切に扱うべき言葉を使ってしまっているわけです。
何でも自分ごと化しなくていい
本書の終盤では、自分に都合のいい既存のナラティブに安易に絡め取られないようにするためには、パブリックとプライベートの間のコミュニティが重要である、という議論が進んでいく。ネットと SNS への接続が常態化したことで、パブリックとプライベートの境界線が曖昧となった世界で私たちは生活している。
日々触れているメディアから報じられる凄惨な事件やニュースの数々、SNS で目にする綺羅びやかな事々物々は、私たちの生活にダイレクトに踏み込んでくる。スマホのロックを解除した瞬間に、そこは様々な情報が飛び交うパブリックな空間なのだ。
そこからは嫌でも無意識的にでも影響を受けてしまうし、常に何かしらの意見やスタンスを求められているように錯覚する。けれども、物事を安易に自分に接続せずに、問題を問題としてクールに扱うことも大切だと、著者たちは鼎談する。
過激な情報からは一歩距離を置いて、自分の言葉で翻訳する。そのためには、パブリックとプライベートの中間となるコミュニティが必要だ。それは、ここなら安心できると思えるアジールなのだろう。
ニュースや SNS で "バエる"「イベント」だけでなく、寧ろ日常の些細な「エピソード」を大切にしながら毎日を暮らしたい。だって、他の人が気がついていなかったり、全く関係がない・気にも留めないような小さなことを、自分だけが愉しめたり、愛おしく思えることができるなんて、素敵じゃなことじゃないですか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
