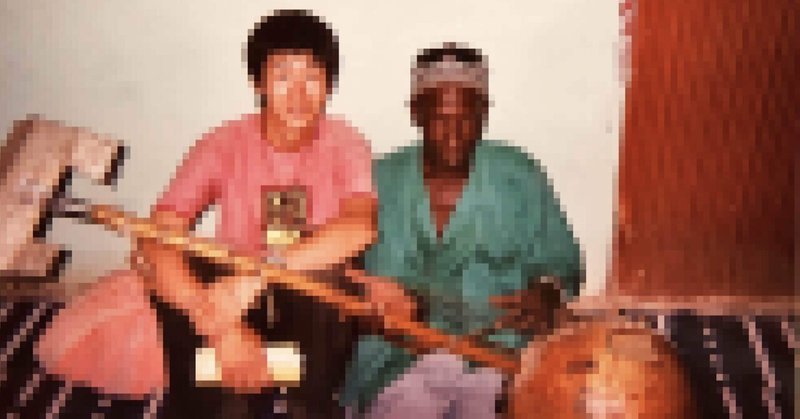
アフリカの旅 ⑤ (セネガル②)
5度目のアフリカの国への旅は、前回と同じセネガルのタンバクンダへの太鼓 (Djembe) 修行の旅でした。
前回とは逆に、日本のツアーの仲間よりも少し早くに現地に行きました。前回一緒だったアメリカ人のJ君も来ていました。
今回は日本やアメリカからの生徒達を受け入れる為の合宿所が出来ていて、そこで太鼓とダンスと歌を習う事ができると聞いていました。
ところが着いてみると、もうすぐ日本人のツアーが来るというのに、合宿所はまだ完成していませんでした。
僕と J君が前入りするというので、その分の部屋は出来ているのですが、いくつかの部屋の屋根がまだ出来ていない。いろいろ話をしてみると、大工さん達とAbdoulaye Diakite (Abdouli Diakite)先生とJ君とで、侃侃諤諤の議論があってなかなか進まないらしい。J君はこの時には、Diakite先生に信頼され、いろいろな事を任される様になっていたのですが、今回の事には、アメリカ人とセネガル人との価値観の相違も絡んでいるようでした。お互いに「アメリカ人は話が分からん!」「セネガル人は分からん!」という感じになっていたから弱ってしまった。
しかももう1人来ていたジェリー・ガルシアを崇拝するアメリカ人のおばちゃんが、ヒッピー文化丸出しで「国や文化が違っても分かり合えると思っていたのに!」と怒っているから「まあまあ、外野までカッカしたらまずいよ、冷静になろう!」と元来は短気な僕が、いつのまにか間に入る立場になっていました。
J君の話を聞くと、それは一理あるし、僕はアメリカで暮らした事もあるから、彼の感覚もなんとなく分かる。だけど僕のじいちゃんだったらどうだろう? Diakite 先生の言う事がよく飲み込めるのではないか?などと思って、心情的にも間に入る感じになって来た。そこへ滅多に来ることのない先生が僕の部屋へ来て「相談がある」と。「来たか!」と思ってじっくり話を聞いて、「それで頼みがある」と言われたので、平静さを装いながら、頭の中では「そんなこと受けて大丈夫かな?" 」と計算をして、「大丈夫! 」と腹をくくって、あたかもなんでもない事かの様に「いいっすよ!」と受けてしまった。それが功を奏したのか、何とか事は動き出し、はじまると屋根の骨組みを組むのも茅を葺くのもあっという間に終わった。実に見事な協働作業で感心しました。
夏の朝草屋根を葺く速さかな

そうして出来上がった部屋の1つが写真のものです。この様な完成した小屋が、敷地の中にダンスと太鼓の練習場を囲んで立ち並ぶのを見て、なんとも嬉しく思いました。
皮が張られぬままに置かれてあった幾つかの太鼓も、ほっとしたのか J君があっという間に張ってくれ、何事もなかったかのように皆を迎えました。Diakite 先生の相談事については、日本人ツアーを引き連れて来たダンスの柳田先生に「こんな事受けちゃったんだけど...」と言うと、「何だ、大丈夫よ。分かったわ。」と何とも太っ腹なお答えで、ほっと胸をなでおろしました。
僕も悩んだが、J君も相当煩悶した事と思います。僕にとっても彼にとっても、この時の事は成長するいい機会になったと思っています。
そんな中でも太鼓の練習はしていました。皆に「短期間ですごい上達したねぇ」なんて言われましたが、こんな風にバタバタしていた事を皆は知らない。僕は喜ぶ余裕はなく、苦笑いをするしかなかった。しかしいろいろとあったとしても、身近に名人達がいて、自由に太鼓を叩けるっていうのは、とても恵まれた環境だったと思います。本当に感謝しています。
この旅では上に書いた事以外にも、本当にさまざまな事がありました。とても語り尽くせませんが、少し俳句にして詠んでみましたので、以下に紹介します。
(この旅も昔の事で、記憶違いの点があるかもしれません。1回目と2回目の旅の記憶が混ざってしまっているところもあるかもしれない。その点はどうぞご容赦ください。)
月天心祭の帰り野路の伴
Abdoulaye Diakite 先生のアルバム『Tambacounda Dunun ni Don』と「Manden Foli』で Dunun を叩いている若いスス人の太鼓の名人 Adama Camara が、ギニアから来ていました。
彼が祭りで叩くというので一緒に行き、帰り道、月が照らす中、祭りで叩いて疲れている名人に「君は疲れてるから持つよ」と言って僕が太鼓を担ぎ、舗装されていない道を数人で歩いて帰りました。その時の事を詠んだ句がこれです。野路は少し大袈裟だったかもしれない。僕が子供の頃には、舗装されてない道が日本にもだいぶあったなと思いながら、その感慨も込めて、そう詠んでみた次第です。

酒二人身振りで語る夜長かな
タンバクンダのバンバラ人のドラマーと2人、酒を呑んで語り明かした夜もありました。それを詠んだ句です。昼間はとても熱いのですが、日が沈むと途端に涼しくなり、何か秋の夜長の風情がします。それで夜長と詠んでみた訳です。身振り手振りで愚痴まで聞いた、そんな夜でした。
犠牲祭や恩人を訪うマンデ人
ツアーの間に、犠牲祭(タバスキ)を迎えました。羊を煮込んだ料理を作り、一張羅を着て、訪ねて来た人をもてなします。親しい人の家を訪ねる風習で、僕も手土産と一緒に世話になった人の家をまわりました。その事を詠んだ句がこれです。
タンバクンダには、師匠と同じバンバラ人(バマナ)やマラカ人、ソウルウバを演奏する Mandingo (タンバクンダではそう呼ばれていました)などマンデの諸民族が一緒に暮らしています。それでマンデ人と詠んだ訳です。フラニ人、セネガルで一番多いウォロフ人も住んでいましたし、ジョラ人の若いダンサーが訪ねてきたりもしました。どこまでが"マンデ"と呼べるのかは、僕も正直自信がありません。

白い服が私
初嵐旅居の匂い運びけり
このツアーでは、師匠たちが、途絶えていたバラの祭りを復活させました。僕は友人の看病で病院にいて、祭りには参加できなかったのですが。
この祭りの前日まで数日、空は分厚い黒い雲で覆われ、とても強い風が吹いていました。ところが祭りが終わった途端にカラッと晴れ上がり、雲一つない。驚きました。そんな事もあって、暑い季節に強い風が吹くと、何かタンバクンダの匂いや人々の仕草までも、運んて来る様な気がするのです。その事を詠んだ句がこれです。
タンバクンダで受けた太鼓のレッスンについては、前回書いた事以上のことはありませんので、そちらを見ていただければと思います。
(以前にinstagram(philosophysflattail)に書いた記事を手直ししたものです。)
見出し画像は、西アフリカの弦楽器ドンソンゴニの名人Samba Traore翁と私です。
ドンソンゴニと Samba Traore翁については、こちらの記事でも触れています。↓
ツアーを企画して下さった柳田知子先生のHP
Djembe 奏者 Yaya Diallo の生涯を描いた名著 (柳田知子訳) 西アフリカのバンバラ人の生活と文化がよく分かります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

