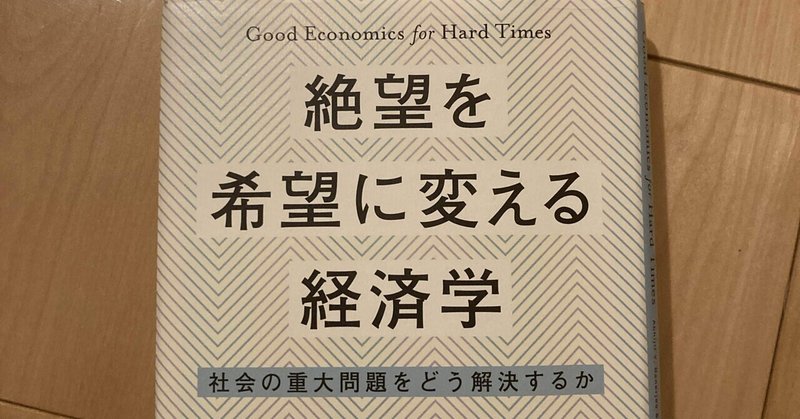
【絶望を希望に変える経済学】凝り固まった負の常識を破り、建設的な議論を
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆☆
〜何冊分もの価値がある一冊〜
ビルゲイツが「読むべき5冊」に選出していた1冊。
経済学、と銘打っているものの、実際のところは経済学者の視点から語られる「世界の危機に対する問いかけ」である。
世界は多くの問題に悩まされている。貧困、成長、不平等、貿易、移民、新技術…。そして、それらの問題は日々議論されているように見えながらも、実際には膠着状態であり、政治家は人々の怒りを煽り、人々は不信感を蔓延させ、建設的な議論は出来ない状態になっている。世界の二分化はますます拡大していく。
そんな世界に対して著者である2人の経済学者、バナジーとデュフロは経済学の観点からいかにして危機を克服し乗り越えていくかを解説する。
断言するが、本書はそこらのビジネス書や新書の10冊分以上の知識量と価値がある1冊である。読み終えた頃には間違いなく世界の見え方が変わる。
〜誤った常識を破る〜
さて、世の中には社会を語る上で常識とされているような定説がいくつもある。
自由な貿易は富裕国も貧困国も豊かにする。移民の流入は国の資本や文化に悪影響を与える。富裕層の減税を実施すれば国全体の経済が活性化し、結果として貧困層も豊かになる。過剰な給付は人の働く意欲を低下させ、経済が悪くなる。
こんな話は誰でもどこかしらで聞いたことあるだろうが、これらの定説を著者たちはことごとく疑って否定していく。
例えば第二章では主に移民に関する話が展開される。
移民は移住先の国の資本と職のパイを奪っていく、貧困国の人々は富裕国の資本を狙ってやってくる、などなど、移民に関しては世界中どこにおいてもネガティブな印象をもつ人が多い。
日本でも、外国人に対して良い印象を持っていない人は多い。経済が悪くなったり、治安が悪くなると外国人のせいにする風潮があるように思う。
世界のニュースを見ると、移民を排除することを高々と宣言する政治家はよく見るし、それに賛同する人々も多い。
しかし、移民はそんなにも迫害するほどの存在なのだろうか?著者たちはそこに疑問を持つ。
まず、移民は世界において一国の経済や文化に影響を与えるほど多くはない。国連の推計では全世界の移民の割合は3%ほどだそうだ。
次に、移民が来ることで経済が悪くなるというデータは無い。移民は移住先の国で稼いだお金を移住先の国で消費する。移民がいることでその国のGDPを下げる要因とはならない。
そして、いくら自国が貧困だからといって、稼ぎを求めて外国に移住する人はほとんどいない。自分に置き換えて想像すればすぐ気づくことなのだが、自分の国が貧しくなったからといって、豊かだが行ったこともない国に移住する決断を果たしてするだろうか?実際の調査では、貧困国の人は貧しいからといって豊かな国に行こうとはせず、住み慣れた地で家族と飢え死にすることを選ぶ。そして、現実は逆で、外国に移住して仕事をする人はバイタリティに溢れた優秀な人が多い。つまるところ、移民となる人はその国の経済に寄与する人の方が実際には多い。
このように、多くの人が常識と考えている社会の「負の常識」を著者は次々と覆していく。そして、そのテーマは幅広い。
〜膠着した議論を前に進めるために〜
世界が二分化していき、議論が膠着状態になっているのは、こうした誤った常識が原因である、と著者は語る。
著者たちは本書で、データに基づく事実と少しの想像力で誤った常識を否定して、世界の危機について建設的な議論が出来るようになるための土台を作ったに思える。
本書を読むと、常識だと思っていた社会の見え方が変わるはずだ。少なくとも、僕は大きく変わった。そして、いかに自分が発言力の強い政治家や富裕層、または(エセ)専門家や(エセ)文化人の言葉に毒されていたかに、気付かされた。
世界の危機に立ち向かうために、建設的な議論をするために、真正面から問いかけた1冊。たしかに多くの人が読むべき1冊である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
