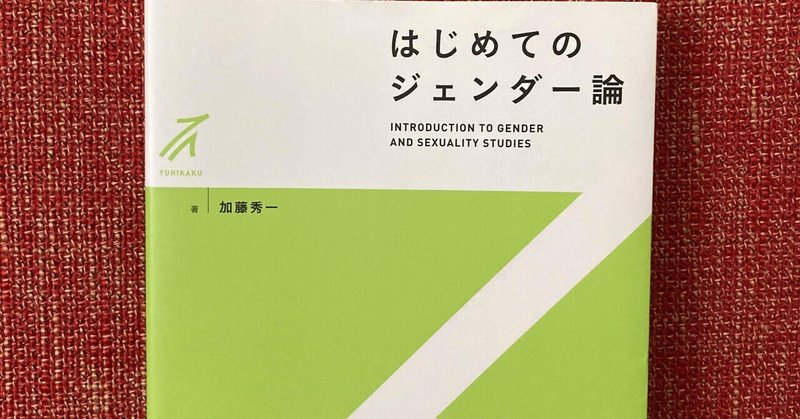
【はじめてのジェンダー論】不安な話題に対して無知な僕が思うこと
オススメ度(最大☆3つ)
☆☆☆
〜口にする事自体が不安な話〜
過去の記事で「ビーガン」に関する本についての書評を書かなかった事をお伝えしたことあるのだが、その理由として「ビーガンになる気がない自分が何を書いてもビーガン批判に捉えられかねない」事が不安なのだと述べた。
日常生活の中でも「ビーガン」に関して話す事はほぼない。
「ビーガン」と同じぐらい口にしたり文章に起こしたりするのに不安になる題材が「ジェンダー」「フェミニズム」に関する事だ。
個人的には日常において「男」「女」という言葉を使うことすら慎重になっている。
他にも、日常生活で口にするのが不安な話はあるが、いずれも共通しているのが、話の流れで制度やルール的なものよりも、文化や思想など、人の内面や感情的な部分に焦点が当たりやすい話題である事だ。内面や感情的な部分を否定したりすると、理屈や理論で否定する以上に人の怒りを買ってしまう事は容易に想像できる。それが理由で日常会話で持ち出す事が不安なのである。
しかしながら、他の内面的な話題に比べて、「ジェンダー」については、僕自身にも直接関わる事だという意識がある。このことについての話題を避けるわけにはいかないだろう。
というわけで、前置きが長くなったが、これから書く記事は、そんな不安な気持ちの中で勇気を出して書いた記事である、という事をご承知いただきたい。ついては、充分に言葉には気をつけて書いていくつもりだが、本文中に何か読んだ方が不快になる、または気に触るような表現があった場合は、それは決して悪意のものではなく僕の無知からの失言である事をご理解いただきたい(「無知である事が悪だ!」なんていう論理をお持ちの方は、これ以上この記事は読まないでいただきたい)。
〜「男」だとか「女」だとか〜
さて、本書は「はじめての〜」というタイトルからも分かるとおり、はじめてのジェンダー論を勉強しようという人のために書かれたもので、社会をとりまくジェンダーに関する諸問題を幅広く取り上げている(著者曰く、ジェンダーの問題は多岐に渡り、本書だけで網羅出来てはいない、そうだが)。
現状、男女の格差がデータとして現れていたり、現代の生活様式に合わない法整備がされていたり、まだまだ「女性差別」が社会から無くなったとは決して言えない状況である事がよくわかる。
しかし、やはり、本書で書かれている事のほとんどは、人々の内面にある「男」と「女」の分類に対する事だ。
余談だが、僕自身、幼い頃運動嫌いだった僕を母と姉が「男なのにスポーツしないなんて情けない」と言ってきた事が今でも嫌な記憶として残っている。また、姉は「私は女だから専業主婦になりたい」「あんた(僕のこと)は男なんだから、勉強してちゃんと稼がないとダメ」と兼ねてから言っており、「女だから」という理由で様々な努力や責任を兄弟の中で僕に押しつけてきた。母も同じ論理で姉よりも僕に対して教育熱心だった。その頃から僕はジェンダー被害の一端を受けていたのだろうと思う。今でも姉と母にはそんな意識が残っている。
しかし、そんな「男なんだから」という論調で家庭内で嫌な思いをしてきた僕でも「男っていうのは…」「女っていうのは…」という意識が全くない、とは言い切れない。
「男」「女」という単語を使う事で、誰の逆鱗に触れるかわからない。だから僕は「男」や「女」という単語を日常で使わない事を決めたのだ。
話を戻すと、本書において、人々の内面的な感覚・感情・思考に対して著者は時折強い言葉で批判する場面も見られる。
男は○○が普通だ、女は○○が普通だ、なんて誰が決めたのでしょう。普通の恋愛、とは誰が決めた事なのでしょう。男性にはこれが向いていて女性にはこれが向いている、なんてどんな根拠があるのでしょう。
社会に蔓延る男女の誤った"常識"や"普通"の認識に対して強く反論する著者の理論理屈は非常に分かる(そんな著者が時折「こんな性癖を持つ人は例外としますが…」等、ジェンダー以外の点で"普通"or"普通ではない"の観点を持ち出すのが、非常に気になったのだが…)のだが、やっぱり内面的・感情的にこびりついた感覚を否定されると人は疲れてしまうし、その感覚はなかなか変わらないだろう、と僕は思うのだ。
おそらく、今から母と姉に対して、過去に僕に対して「男らしさ」を強要されて嫌な思いをした事を伝えたとしても、反省どころかなぜ僕が嫌な思いをしたのか理解さえしてもらえないと思う。
〜制度や仕組みが人々の意識を変えるのでは?〜
さて、男女の分類に関する人々の意識や感情は根深く、それを変える事は容易ではない。また、そこについて議論をすると、人は感情的になってしまい解決に向けた冷静な議論は出来ない。
その点がこのジェンダー問題の難しい点だと思うのだ。
この問題を解決する糸口として(決してジェンダー論について知識が豊富とは言えない)僕が思うのは、社会の仕組みや制度などのハード面と人々の意識や感情などのソフト面を切り分けて考えて、ハード面から解決していく方向に舵を切る事だ。
本書においても、諸問題を語る上で制度と人々の意識をごちゃ混ぜにして書いているので、非常に解決が難しく感じてしまう。
もちろん理想は人々の意識が変わる事なのだが、前述の通り人々の意識を変える事は難しいと思う。
しかし、著者の言うように、過去の男性優位の法整備や社会の仕組みが、今の女性差別的な思考・文化につながっているというのであれば、逆に仕組みを無理矢理にでも変えてしまえば、人々の意識もそれに追従して変わっていくのではないかと思うのだ。
著者の書いているような「性犯罪に関する法律を"被害者"目線で考えたものに改正していく」「女性が働き続けられるような育児をしやすい労働環境を整えるために、育休制度や児童手当を充実させていく」「職場内での男女差別を無くすため"総合職"、"一般職"のような不透明な区分を規制する」などなど、明らかに女性差別になっていたり、男女平等になっていない事実がわかるデータや法律があるのなら、そこをまず解決すべき課題として人々が理解すべきだ。
もちろん、ソフト面を蔑ろにしていいわけではない。しかし、問題を切り分ける事で複雑さが無くなり、個々が何をすべきか見えてくるハズだ。
法律を変える、なんて大層な事が出来ない僕のようなサラリーマンでもやれる事はある。
それは、今ある制度をキチンと知って大いに活用する事だ。
例えば、男性の育休取得率が現状そこまで高くないのはよく知られていると思うが、性別に関係なく育児のために育児休暇や時短勤務が出来るのだからどんどん使う事だ。
ちなみに僕は、子供が産まれた時に育休をとり、今保育園への送り迎えのために時短勤務にしている。僕より上の世代ではあまりいなかったそうなのだが、僕が当然のように育休・時短を取る事で後輩たち(男性)は自分に子供が産まれた時に備えて、制度について調べ出している。育休を取った事を同年代の女性に話したら「へぇー、父親なのにすごいねー」と言われたが、そこで別に反論したりするつもりは無かった。制度があるのであれば、それをみんなが利用して、利用する人が増えればさらに制度が充実し、それに伴い人々の意識も変わるだろう、と思ったからだ。
ジェンダー問題は社会的に大きな問題ではあるけど、小さく切り分ければ身近なところで自分が問題解決に向けて行動出来る部分はあると思う。言葉の上で他人を説得するのが難しい問題であれば、個々人がそれぞれできる事をやる事で社会は良い方向に向かっていくと思う。
僕はそう思うのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
