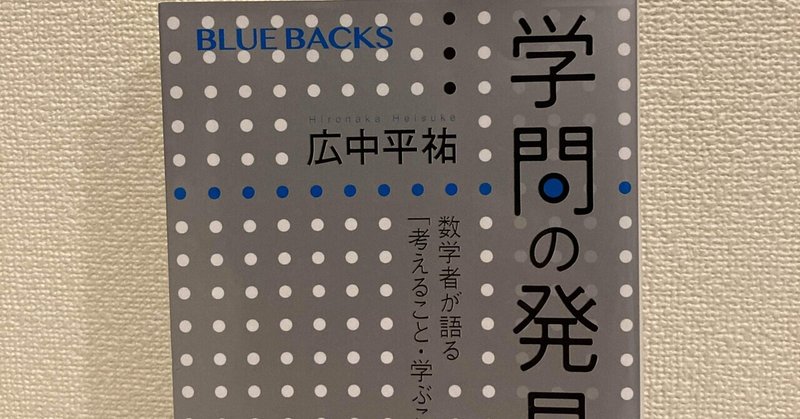
【学問の発見】時間をかけて多くを学ぶ人生を
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆☆
〜天才数学者が語る「学問」との向き合い方〜
30代にしてこの本に出会えて良かった。
勉強とは学生だけのものではなく、人生を通してやっていくものなのだと、襟を正された気分である。
本書の著者は広中 平祐さんという方であり、数学界では名誉あるフィールズ賞を日本人で2人目に受賞された方である。
そして、本書はそのフィールズ賞を受賞するまでの経緯に触れつつ、「学ぶ」事に対する大切な基本姿勢が語られている。
大学生や研究者だけでなく、僕のようなサラリーマンにも刺さる「学ぶ意義」。老若男女問わず全ての人が読むべき一冊だと思う。
〜なぜ、勉強するのか?〜
特に、第1章と第2章は子供が「何で勉強なんかしなきゃいけないの?」と言い出したら、聞かせてやりたい内容だ。
なぜ、学校ではあんなにも色んな科目を勉強しなければいけないのだろうか?
まず一つは「知恵をつけるため」である。
学校で学んだことは、テストや試験が終われば忘れてしまう事がほとんどだ。覚えもしない事を学んでも意味がないと思うかもしれないが、学んだことは実は記憶の奥底に眠っていて、何かの折に引き出す事が可能なのである。例えば、生活や仕事の中で世界史の知識が必要になった場合、学んだ経験があれば少しの学び直しで思い出す事が可能だが、全くやったことのない事を一から学ぶのはかなりの時間と労力がかかる。そうして、少しのきっかけで引き出した事が「知恵」として、生活の中で役に立つのだ。
そして、二つめは「成功体験を得られる」こと。
ここでいう「成功体験」とは「わからない事が理解できるようになった」という体験である。
「学べばわかる」「勉強すれば理解できる」という体験をたくさんすればするほど、何か課題や問題に直面した時に、簡単に諦めるような事にならず、勉強する気力を出す事が出来る。
もちろん、現状の教育現場で問題視されている「試験のための勉強」では、この体験は得られない。「理解する」という勉強が必要となるのだ。
〜何が役に立つのかは、わからない〜
昨今「学校で学ぶ事なんて、実生活では役に立たない」と言って、プログラミングや経済・金融など、現代において実践的な教育カリキュラムを組み込む動きが見られる。
たしかに、情報教育やお金の教育は大切だし、"今の社会"では重要な知識だろう。
しかし、生きていく上で何が直接的に役に立つかなんて、一人ひとりの人生が違うんだから、わかるはずが無いのだ。
決して、情報教育やお金の教育に反対しているわけではない。けれども、「この科目は実生活では使わない」「こんな勉強役に立たない」と切り捨ててしまうのは、あまりにも安直だ。
著者が成し遂げた数学の難題「特異点の解消」は数学者たちの中でも「こんな問題解いても無駄だ」と言われていた。しかし、いざその問題を解き論文を発表すると、その手法を応用して様々な実践的手法が生み出されたという。
何が役に立つかなんて誰にも決められない。
最短でゴールを目指すのでは無く、色んな事を学んで幅広い知識を持つことで新たなアイデアを生み出せるのだろう。
著者は「人生の喜びは創造から生まれる」という。そして、その創造は、世の中が求めるニーズでは無く、自分の中にあるウォントから生まれるのだ。
そして、その創造のためには「学ぶ」事が大事なのである。
著者は「学ぶ」事に人の倍の時間をかける事を意識しているという。フィールズ賞をとるまでにも、何度もまわり道をしてきたそうだ。
なんでも、スピード重視で合理性ばかり追求している現代は、誰の目から見てもオーバーヒートしている。少し立ち止まり、時間をかけて色んな事を学ぶ、ということを多くの人が考えるべきだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
