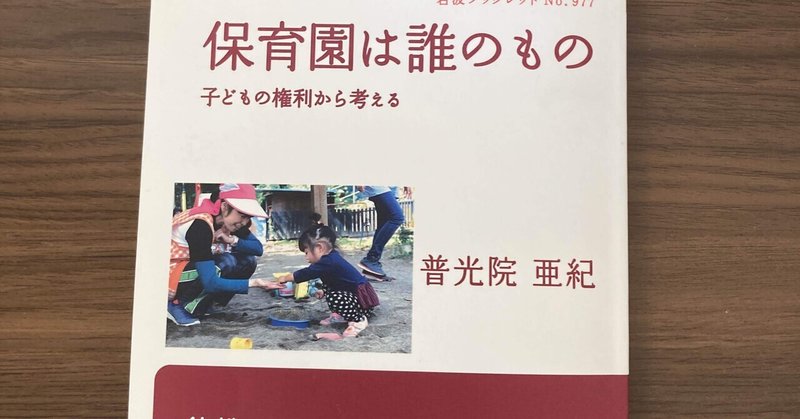
【保育園は誰のもの】改めて「子ども」や「母親」だけのものではない事を考えたい
オススメ度(最大☆5つ)
☆☆☆☆
〜保育園に関する諸問題〜
娘の行っている保育園は、子どもたちが非常に楽しそうにしており、保育士さんも園長さんも良い方たちだ。保育士さんたちが子どもたちに真摯に向き合ってくれており、毎日送り迎えの時に園での様子を教えてくれる。感謝しかない。
その一方で、まだ記憶に新しい静岡県の保育園で起こった「不適切保育」、いわゆる園児への虐待事件。実際に保育園に娘を預けている僕としては聞くだけで辛い事件だった。この事件から、保育士の労働環境の劣悪さや保育士不足の問題が改めて問われることとなった。
また、保育園に入れない、いわゆる待機児童が問題になって久しい。待機児童数は減少傾向にあると厚労省は発表しているものの、本書によれば、その集計方法は1997年から変わっており、もともとは「認可保育園に申込した児童ー認可保育園に入園・継続できた児童」という単純な算出方法だったのだが、昨今の算出方法では「保護者が育休中」や「自治体が関与する認可外施設を利用」や「特定の保育所を希望している」児童は待機児童としてカウントされない。
「潜在的な待機児童」がいる中で、本当に待機児童数が減少しているかどうかは定かではない。
保育園に対する不安や問題は尽きない。
本書では、こういった保育園の問題について改めて問うものである。
〜質よりも量を重視してきたツケ〜
保育園を取り巻く不安な現状を作り出したのは、主に"質"よりも"量"を重視してきた結果であると、本書は述べている。
例えば、認可の基準となる児童1人に対する保育園の最低面積はスウェーデンの3分の1である。さらには、条件付きで最低基準を越えた児童を入園させられるように「定員越え受入」の弾力化を図った。また、非正規雇用の保育士の上限人数もこの二十数年で緩和された。
とにかく、保育園に児童を「詰め込む」形で量的な規制緩和がなされ、待機児童の数こそ減ったが(前述した、算出方法の疑問は残るが)、そこに"質"の問題が出てきた。保育士1人で見切れないほどの子どもが園に詰め込まれ、当然保育士の責任と業務は増えた。広々と遊ぶことができない空間は子どもの心身の発達にとっても好ましくない。
待機児童問題は、単に待機児童の数が減ればOKというだけでは無くなっているのが現状なのだ。
〜社会全体のための"保育"という仕組み〜
"質"の問題が表面化した以上、保育園の問題は「国や自治体が保育施設をもっと増やせば良い」とか「保育士の給料をもっと上げれば良い」とか、それだけで済む問題ではない。
もっと、社会全体、地域全体で考えなければいけない事なんだと思う。
この本の内容からは外れるが、「保育園の騒音がうるさい」「上の階の子どもの足音がうるさい」など、子どもが「騒音」「公害」扱いされるケースをメディアやネットで頻繁に目にする。
僕個人としては、子供が産まれる前から、子どもとはそういうものだと思っているので、電車で喚こうが外で騒ごうが「子どもがうるさい」と感じた事は無い。しかし、世の中的には「言論の自由」を理由に「そういう意見を否定してはいけない」という風潮になっている事に、正直戸惑いを隠せない。
以前読んだ「誰のための排除アート?」に通じるが、不寛容から子どもが街から排除されているような感覚になってしまう。
そうした声のある中で、「空いてるところに保育園をどんどん作れば良い」という単純な話でもないだろう。
子どもに対しては大人が寛容さを持って欲しい、と思う。
大人の寛容さが、保育環境を改善する事につながるはずだ、と僕は考えている。
当然、この僕の意見に反対意見を持つ人もいるだろうし、妥当な妥協点を見つけることも難しい議論だと思うが、目を逸らしてはいけない話だと思う。
話が逸れてしまったが、
保育園、というのは子どもや親だけのものではない、と改めて全ての人が考えるべきである。
保育が充実すれば、子育てとは関係ない人も含めて、社会全体が豊かになっていく。
子どもや親のために必要なのは当然として、少子化や貧困の問題も幾許かは改善されるし、先進国として男女平等の社会を築き、社会保障を持続させ、企業として育休中の社員を確保して将来の消費者を育て、あらゆる世代が活力に満ちた地域社会を作るために必要なのである。
保育園とは。保育とは。
全ての人が真摯に向き合うべき議論なのだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
